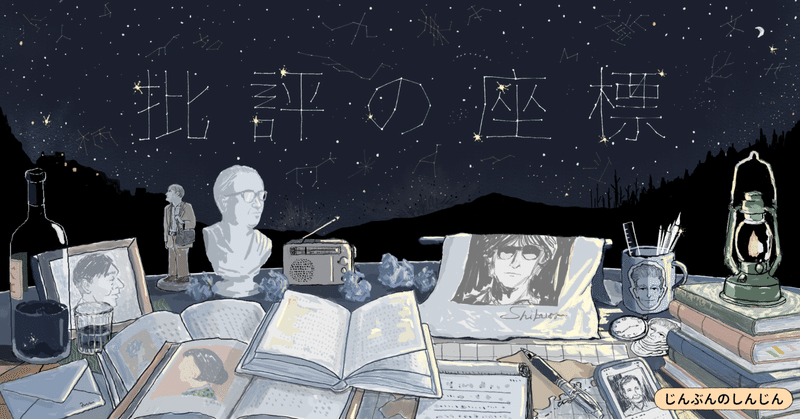
【批評の座標 第8回】妖怪演義――花田清輝について、あるいは「どうして批評は面白くなければならないか?」(袴田渥美)
アヴァンギャルド芸術に伴走する批評と文体の華麗さで名を馳せた花田清輝。マルクス主義者としての彼が過剰なまでのレトリックを必要としたのはなぜか。同人誌『ラッキーストライク』を運営する袴田渥美が、花田の語り口から批評という言語活動に宿る独自の快楽について論じます。
――批評の地勢図を引き直す
妖怪演義
――花田清輝について、あるいは「どうして批評は面白くなければならないか?」
袴田渥美
はじめに
この連載シリーズは、かつての批評家たちの紹介をはじめに企図したものなのであり、批評と名指されるジャンルに属する文章に初めて触れようとする誰かに宛てられたものでもあるのだから、批評を読むことの面白さをこそ指し示さなければならないだろう。しかしそれはいささか難しい要請でもある。単なる作品の「考察」としては異様に難解で、高度な文学研究における「論文」としてはきわめてルーズな批評ジャンルの文章を読むことが、どのように誰かを誘惑し、いかにして読む者に快楽をあたえうるのかを伝えることはいつも難しい。そのうえさらに、いままさに書かれているこの文章もまた、きっと批評と呼ばれてしまうはずなのだから、私はその批評の面白さなるものを私の手によっても上演しなければならないにちがいない。
そんな厄介な要請を突きつけられた私には、花田清輝について書くことがもっともふさわしいと思われた。ときに嘘をつき、しばしばはぐらかし、すぐには理解しがたいレトリックを駆使する彼の文章を読むことはいつも楽しい。その面白さはたしかに、数日前に観たばかりの映画の「考察」を首をかしげながら読むときのそれとも、論集に収められた立派な「論文」を頭をひねりながら読むときのそれとも異なっている。その面白さとはすなわち、斬新なアイデアでも刺激的なコンセプトでもなく、「考察」にも「論文」にも見いだしえない言葉の具体的な運動からやってくるものであるはずだが、それを誰かに伝えることができたのであれば、この文章のささやかな目的は叶えられたことになるだろう。
1. サルバドール・ダリかく語りき?
花田清輝(1909-1974)の批評家としてのキャリアのメルクマールでもありシンボルでもあるマルクス主義者としての戦時下抵抗や戦後のいくつかの論争についての詳細は、ここでは措く。というのもそれらについては、この記事のほかに花田を初めて読む読者の案内となりうる仕事がいくらもあり、かつこの記事ではそれらを整理するに紙幅が足りないからだ。
この記事から花田に興味をもってくれた読者は、まず『社会評論』に1997年3月から12月にかけて連載された「花田清輝 その芸術と思想」シリーズを読んでほしい。『社会評論』のバックナンバーはいまでは入手しにくいが、ありがたいことに、菅本康之の立ちあげた花田清輝ルネッサンスプロジェクトのウェブサイトで第四回を除く記事を読むことができる。生前の花田とも親交のあった武井昭夫の証言を含むこの連載は、初読者にとりたしかに貴重な手引きである。あるいは、花田が50年代を通じて『近代文学』同人や吉本隆明と繰りひろげた論争を同時代の状況とあわせて解説した仕事としては、好村富士彦『真昼の決闘 花田清輝・吉本隆明論争』[1]を挙げることができる[2]。
花田にかんする人目を惹きやすいトピックについてはこれらの仕事に譲ることにして、さてそれでは私は、花田の批評の面白さを、メルクマールにもシンボルにも頼らずに、まずは書かれた言葉から具体的に示してみることにしよう。書かれたものの集合のどこかに目印や道標を打ちこむことで可能になる読みもたしかにあろうが、そのような読みとは別の方法を示すのでなければ、批評なるものの独自の快楽を語ったことにはならないのだから。
*
1950年8月から51年1月にかけて、花田清輝は「マザーグース・メロディー」、「林檎に関する一考察」、「鏡の国の風景」、「機械と薔薇」と題されて54年の『アヴァンギャルド芸術』に収録される文章において、サルバドール・ダリに対する批判を連続的に展開するのだが、このなかの一篇である「鏡の国の風景」には、たとえばこんな一節を読むことができる。
とはいえ、この二十世紀のトラキアの女[=ダリ]は、右にかかげた一文によっても、あきらかにみとめうるように、外部の世界に対する素朴な、あまりにも素朴な信仰によって支配されているのではあるまいか。かつてトラキアの女は、内部の世界へはいってゆき、穴に落ちてしまったタレースを笑ったが――しかし、どうやらこの二十世紀のかの女の後裔は、逆に、内部の世界から外部の世界へ出てゆき、同様に穴に落ちてしまう二十世紀のかれの後裔に、無遠慮な嘲笑を浴びせかけるのではなかろうか。どうしてかの女は、外部の世界に、客観的な証明力と、密度と、継続性と、説得力と、認識力と、伝達力とがあると思い込んでいるのであろうか。それにしてもなんというたくさんの美徳で、外部の世界を飾りたてたものであろう! これはまるで恋愛をしている女が、かの女の恋人をほめたたえながら、しかし、あたしだって、あなたに負けないくらい、いいひとよ、と自慢するようなものではないか。抽象派の作品と同様、かれの作品もまた、今日の知的懊悩からみれば、いかにも甘ったるいものにみえる。内部の世界と同様、外部の世界もまた、ダリのみたような具象的な非合理性の影像で溢れており、現在、われわれは、その物質のもつ非合理的な側面を、ダリにならっていうならば、もっとも熾烈厳格な精密さをもって――想像的な精密さをもって、精神化する段階に立っているのではあるまいか[3]。
ここで「二十世紀のトラキアの女」と呼ばれているのはダリなのであり、花田の言わんとしていることは要するに、内部の非合理な現実をレアリスムの手法をもちいて外部の現実と同等の確かさのもとで捉えるのだとダリは言うが、どうして外部の現実をそんなに確かなものだと思えてしまうのか、ということであるわけだが、この批判の妥当性はここでは問わない。問題は、それだけのことを言うのにこんな――異様におおげさで回りくどい――語り方をすることの意味とはなにか、ということである。このことを考えるための補助線として、上の一節で「右にかかげた一文」と言われている花田によるダリの引用を検討してみよう。
ダリは、かれの『非合理の征服』のなかで、抽象派の作品を、今日の知的懊悩からみれば、いかにも甘ったるいものとして、おのれの心境を、大凡、次のように告白している。
絵画的な領域におけるわたしの野心は、すべて具体的な非合理性の影像を、もっとも熾烈厳格な精密さをもって物質化することにある。想像的な精密さをもって物質化することにある。想像的な、あるいは、具体的な非合理性の世界は、現象的な現実の外的世界にくらべて決して劣らない客観的な証明力と、密度と、継続性とをもつのみならず、同じ強さの説得力、認識力、伝達力をもつものである。重要なことは、非合理的な具象性の主題を伝達することであって、絵画上の種々な手段が、この主題のために使用されるのである。――具象的な非合理性の影像が、現象的な現実に接近し、あるいは、それに応ずる表現手段が、偉大なレアリストたち――ヴェラスケスやウェルメエル・ド・デルフト等のそれに近づくことである[4]。
この花田の引用を典拠であるダリの『非合理の征服 La Conquête de l'irrationnel』と突き合わせてみると、奇妙なことがわかる。たしかにダリのテクストには、「私の絵画的な平面についての野心はすべて、精密さのもっとも帝国主義的な猛烈さをもって、具体的な非合理のイマージュを物質化することにあるToute mon ambition sur le plan pictural consiste à matérialiser avec la plus impérialiste rage de précision les images de l'irrationalité concrète」という花田の訳文の最初の一文に対応するセンテンスを発見することができるのだが、その後につづく「想像的な精密さをもって物質化することにある」という一文に対応するセンテンスはどこにも見当たらないのである[5]。これはいかなることか。
ここで花田が遂行している戦術が厄介なのは、「想像的な精密さをもって物質化することにある」というたった一文の書きくわえが、ダリの言わんとしていることをおおいに歪めているわけではないことである。そうであるならば、歪められた真実を自身の語りの真実らしさに奉仕させる操作であると理解することも可能であろうが、嘘ではないが本当でもない、この曖昧な操作をそのように理解することはできない。
こういうことではないだろうか。「……もっとも熾烈厳格な精密さをもって物質化することにある」とダリは意気込むのだが、花田はその身振りを誇張してしまう。勢いあまって「想像的な精密さをもって物質化することにある」とまで言ってしまうといい。おおげさに演出されたダリの身振りを指して花田は言う。あなたはまるで「二十世紀のトラキアの女」のようではないか。内部の現実は外部の現実とおなじくらい確かなのだとダリがつづける。対して花田は、「まるで恋愛をしている女が、かの女の恋人をほめたたえながら、しかし、あたしだって、あなたに負けないくらい、いいひとよ、と自慢」しているかのようだと応じる。ついには、誇張されたダリの身振りを鏡写しに真似てみせて、いま必要なこととは、「もっとも熾烈厳格な精密さをもって――想像的な精密さをもって、精神化する」ことではないのか?
だとすれば花田がここで遂行してみせていることとは、ダリの告げ知らせる真理の単純な否定でもないのだろう。真理の否定はつねに別の真理を呼びだすが、そうではなく、観客に対して真理の振るまいを過剰におおきく見せながら、それをさかしまに真似てみせるのならどうだろう。誇張された真理は滑稽さをおびて失効しているが、同時に、大仰なモノマネがなにか本当のことを語りうるはずもない。だからこのとき、私たち読者に要求されているのは、語られていることの正しさを判断することではなく、わざとらしく演出されたダリの身振りと、それを逆向きに真似ていっそうわざとらしい花田の身振りに笑ったり白けたりしてみせることであるにちがいない。あるいはダリと花田のアクションが心から素晴らしいと思うのであれば、あなたは感嘆してみせても――もしくは興をひかれたのであれば、あなたも演技に乗ってしまっても――よい。
2. 帝国に妖怪が出る
通常、論文や考察と呼ばれるすでに書かれたものについての二次的な言説の価値は、その対象において真であることを言い当てえているかどうかによって測られる。しかしダリを批判する花田にあっては、その対象の真実性がさきんじてわずかに毀損されている。そのうえ語り手は、代わって自己自身の考えだした真理を語ろうともせず、鏡のように相手の振るまいを真似るだけである。ではそんな不安定な言説の空間にはなにが残されているのかと言えば、真理を導出する論証の手続きに対しても、言われていることの真偽判断に対しても過剰な、ただ効果をしかもたない言葉の運動、言い換えればレトリックであるだろう。
では、花田においてこのような言語活動がどうして要請されるのかについて考えてみよう。花田自身がレトリックについて語ったもっとも有名な文章として、国家主義政治結社・東方会を主宰する中野正剛の資金援助によって創刊された『文化組織』に1941年に掲載され、46年に『復興期の精神』に収録された「女の論理」を挙げることができるだろう。
まず修辞の目的とするところは、説得ということであった。我々は修辞を用いることによって、我々の相手に信頼の念をおこさせようとする。修辞的な証明、すなわち、エンテュメーマは、論理的な証明、すなわち、シュロギスモスとは異り、話される事物によって規定されることなく、もっぱら話す相手の気分や感情によって規定されるところの証明だ。それ故に修辞は、話す相手がないと存在しないであろう。それは絶えず人と人との関係を予想するものであった。しかもその人と人との関係は、ピスティスが問題である以上、相互の感情の交流の上に成立していなければならず、したがってその対話は、本質的な意味において、一人称と二人称とをもって発展してゆくであろう。そうして、そこでは、たくさんの暗喩や直喩がつかわれるであろう[6]。
ここで言われている「修辞」すなわちレトリックの特性とは、そのまま花田の批評のそれとして読むことができるにちがいない。花田の言説の空間には、論及されている「事物」すなわち対象における真理に拘束されない言葉の運動、転義法やたとえ話、あるいは「話す相手」に呼びかけようとするおおげさな身振りばかりが横溢しているのであり、そこでは語りを聴きとる誰かの――笑ったり白けたりするあなたの――感情的な反応、たとえば「信頼」を引き出すことができるかどうかだけが問題となる。
他方で、私たちはそのような言語活動の在り方を容易に批判することもできる。語られていることの真偽など一顧だにせず、巧妙な言い回しや声調に訴えて相手を説得しようとするその言語活動は、デマゴーグのそれとよく似ている、と「女の論理」の花田自身さえもが言う[7]。しかしつづけて、「イエスはレトリックの達人であった。そうして、ロジックのみをあやつるパリサイの徒を、いかにあざやかに論破したことであろう」、「もしも修辞的であることが、イエスの美点であるとするなら、それはイエスが、あくまで修辞をもって武器と見做し、これをふるって、現実の変革のために果敢な闘争を試みたからであった」はずだ、とも[8]。
私たちが花田のレトリカルな批評の必然性を理解しはじめるのは、この地点においてのことである。レトリックは実践的に使うことができる。ではなぜ花田にとり手に取られるべき方法は、論証や真偽判断のために捧げられた論理ではなく、レトリカルなそれでなくてはならなかったのだろうか。このことは、花田の歴史的な状況認識にこそかかわる。
ファシズム体制下、『文化組織』に1940年に掲載され、41年の『自明の理』にともに収録された「錯乱の論理」と「童話考」は、当時の花田による状況認識を語ったドキュメントでもある。「錯乱の論理」の花田によれば、生産技術の発展が現実を捉えうる論理の形態を変容させていくのだという。たとえば生産技術の中心が手工業的技術から機械工業的技術へと移りゆくとき、「形式論理」に代わって「弁証法」がようやく現れる[9]。機械が人間の思考を組み換えてゆく。
あるいはそのとき、「童話考」の花田にとり、世界は「童話」のように見えた。
それまでに転換は徐々に行われつつあったのだが、戦後、ヨーロッパの若い作家達は、かれらの周囲が、不意に現実の世界から童話の世界に変わっているのに気付いた。新しい環境にあっては、すべてが定かでない。絶えずすべてが動揺している。見馴れた顔ですらが、なぜか妖怪じみてみえる。信用のできるのは静物だけらしいが、それらの静物もまた、じっと見詰めていると、わざとひっそり静まり返って、身じろぎもしないもののように思われてくる。しかもこの童話の世界が、いっそう気味の悪い印象を与えるのは、それがあまりにも明るい二十世紀の人工的な光によって、煌々と照らし出されていることである[10]。
「ヨーロッパの若い作家たち」とは、ピカソやキリコ、あるいはダリやエルンストのようなシュルレアリスムの圏域に属する作家たちなのだが、40年の花田は彼らの童話的でありかつ人工的なタブローを、現実からの逃避によってなされたものではなく、いつのまにか童話のように変貌してしまった現実を捉えようとしたものとみなす[11]。童話になってしまった世界とは、第一次大戦を越え、近代がひとつの臨界を迎えたヨーロッパであり、ファシズム体制下の大日本帝国でもあろう。

またここで言われている「童話」とは、形式的かつ科学的な因果律に規定された「小説」の対概念でもあるわけだが、「たしかに今日の現実の童話性は、御粗末な形式論理の因果律によってとらえられるには、あまりに錯綜しすぎているよう」なのであり、それはもはや「現実の表面をなでまわすにすぎない」だろうと花田は考える[12]。だからここでもういちど、すでに歴史的な役割を終えた、通常、論理と呼ばれてきたものを手に取りなおすことはできない。いまいちど具体的な現実を掴みなおすために手に取られるのは、童話の、言い換えれば誰かに語り聞かせるおはなしの論理であり、レトリックである。花田清輝の選択とは、およそそのようなものではなかっただろうか。
花田のレトリカルな語りの方法は、通説の通り、たしかに治安維持法下の言論統制を回避するために編み出されたものでもあるだろう。しかし同時に、そのような戦術の選択を彼自身の状況認識が裏づけていることも見落とすことはできない。あるいは彼が戦後、繰りかえし主張することになる「対立を、対立のまま、統一する」奇妙な弁証法[13]とは、この意味において、対話、あるいはおはなしの論理として理解されるべきものでもあるにちがいない。
3. かぐや姫は月に帰る
このような花田の状況認識と戦術の選択は、戦後、柳田民俗学におけるフォークロアの発見へと連なっていく――この態度決定の連続性は、1957年の「砂のような大衆」において仄めかされているような、大衆社会がいちど現出してしまえば状況は不可逆であるという判断に裏打ちされてもいよう[14]。59年の『近代の超克』に収録された「柳田国男について」に代表される花田による柳田の再評価が問題含みなものであることもまた確か[15]だが、私たちにとり、花田がフォークロアの語り口にこそ可能性を見いだしてもいたことはやはり見逃せない。
「柳田国男について」の花田は、フォークロアの語り手がときに、かぐや姫が最後にはかならず月に帰ってしまうというような大筋は決まっているとしても、部分的に語られる内容を変更してしまうことがありえたとする柳田の記述に注目する。それはたとえば、子どもに語りきかせるために「近所のあの川のような橋のうえで……」であるとか、「隣の……さんのような金持ちが……」といった喩えをもちいるような他愛のないものでさえあったわけだが、その語り口に花田は即興や声調の変化をともなったコミュニケーションの具体的な効果を見る[16]。そこに見いだされている可能性とはおそらく、「女の論理」で素描されていたレトリックのそれとほぼおなじものであるにちがいない。あるいは、54年の「笑い猫」における記述などに触れるのであれば、ダリやエルンストの「童話」のようなイマージュから出発した花田の思考が、このフォークロアの発見においても持続していることを理解できる。
化猫にしてもそうだが、ちょっとわが国の化物の種類の豊富なことを考えてみただけでも、いかにわれわれ日本人が、アヴァンギャルド芸術家としてのゆたかな素質をもっているかがわかるはずである。犬、猫、鼠、狐、狸の化物はいうまでもなく、すっぽんの化物さえいる。海坊主や、一つ目入道や、のっぺらぼうを知っているわれわれにとっては、キリコやピカソの絵など子供だましみたいなものだ[17]。
以降、花田はフォークロアや童話の語り口や非合理なイマージュの具体的な効果をもって近代的な小説を越え、映画やラジオにおける新たなマスコミュニケーションを発明することを企図するのだが、このことにかんしてはここでは措く。
さて、では、もうひとつだけ、ここまで追跡してきたような花田の態度決定が条件づけた批評の面白さを紹介することにしよう。童話や妖怪譚に可能性を見いだした彼の批評は、おはなしとしてどのような形態をとっただろうか。ここで私が取り上げたいのは、1950年に初出の日付をもち、54年の『アヴァンギャルド芸術』に収録された「サルトビ・レゲンデ」という文章である。
*
この文章の冒頭で、花田は「わたしもまた、「猿飛伝説」の粉砕にあたり、劈頭、まず、真田幸村に関するさまざまな伝説を、完膚なきまでに破壊してしまう必要があるのだ。馬を射んと欲すれば、まず将を射よ、と諺にもいうではないか」と意気込む。ナポレオンや真田幸村のような英雄が「一度もこの世に実在したことがなく、かれらの赫奕たる戦果にかがやく歴史が、ことごとく一片の絵空事にすぎなかったことは、太平洋戦争を経験し、その「赤裸々な」報告や「掛値なし」の記録の氾濫に食傷している今日のわれわれにとっては、ほとんど証明する必要のない、自明の事実に属しているからだ」[18]。なにか意味ありげではある。
しかしすぐに雲行きが怪しくなる。花田はここで、ジャン・バチスト・ぺレスなる人物に倣うべきだと主張する。彼は1817年にナポレオンが太陽の人格化であり、本当は実在しなかったことを証明したらしいのだが、その方法がいかにもいかがわしく、アポロンとナポレオンの綴り字が似ていることを自説の根拠としていたという。「なるほど、そう指摘されてみると、両者の差は、きわめて小さい」[19]。ペレスの名を初めて書きつけたつぎの段落で花田は言う。
しかし、いまだにナポレオンの実在を信じているおめでたい人間が跡を絶たないのは、この論文のあらわれた一八一七年が、ワーテルロー戦争後、二年目にあたり、物情騒然たる時期であって、一見、悠長な閑文字にみえないこともないこういう言語学的研究に耳を傾ける余裕が、たぶん、大衆のあいだに失われていたためであろう[20]。
2年前までヨーロッパ中を大戦争に巻きこんでいたナポレオンが実在しなかったと誰が信じるだろうか。悪びれる様子もなく花田はつづける。真田幸村は星の人格化であったのではないだろうか。しかしつぎの段落では、「真田幸村という名はナポレオンやアーサーというような名とちがって、容易に天体の名とは結びつかないらしい。やはり、この手の採用は、中止した方が無難なようだ」[21]。
ここですべてを解説することは避けるが、このあとにも数ページに渡って、くねくねと蛇行する花田の語りはつづく。青髭や猿飛のような庶民の実在に作家たちは拘るが、そうしなければいけないほど彼らは庶民を知らないのだ、であるとか、猿飛がスパイだと考えることはやはり彼を指揮する真田幸村の実在を前提にしている、であるとか[22]。しかしある地点で急速に、語りはひとつの結末へと収斂していく。
要するに、わたしは、実在していた「猿飛」を行商人であったと考えているにすぎないのだ。その頃は、戦国時代の末期にあたり、生産力が増大し、農業と手工業のある程度の分離がおこり、貨幣経済が発展し、商品の全国的規模における流通が、ようやくはじまったばかりであった。おそらく「猿飛」は若干の小間物を背負いながら、全国を行商して歩いたのであろう。もしもかれの身辺に、多少の妖気がただよっていたとすれば、それは、かれの担っていた商品の魔術性のためだったにちがいない。したがって、さきにわたしは、真田幸村を、星の人格化だときめたようだが、あるいは、かれは、星などとは関係のない商業資本の人格化かもしれない。そういえば、かれの旗じるしには、たしか貨幣が描かれていたようである[23]。
花田の説明によれば、そういうわけで、「商業資本の人格化」である真田幸村は「絶対主義の人格化」である徳川家康と対立したのであり、「行商人」である猿飛の魔法のような侵入を封建領主たちは防ぎえなかったのだという。ところで、猿飛の同時代人であった九条植通という貴族も、猿飛とおなじように魔力をもっていて、彼が寝るときにはかならず屋根のうえでフクロウが鳴いたそうだが、これは「時代の終焉を告知するミネルバの梟」だった[24]、とも。あれほど際限なく行使されていた自由な語りは、どうしてかほとんど教科書的とも言えるような唯物史観に収束する。これはいかなることか。
こんなふうに考えることはできないだろうか。「サルトビ・レゲンデ」において、マルクス主義とはおはなしのフレームである。比喩やたとえ話、あるいは怪しげな逸話やおおげさな調子に満ちた語りを無際限に解放してしまえば、おはなしはシナリオを失って無秩序で効果のない――聴衆をひきつけない――独りよがりなモノローグと化してしまうだろう。だからフォークロアが部分的には自由な語りの変更を許したとしても大筋は決定されていたように、ここにはおはなしの収まるべきフレームがなくてはならない。ならば唯物史観という定点をあらかじめ結末に置いて、語りを他律させればよいのではないだろうか。かぐや姫がかならず月に帰るように、共産主義とは必然である。
ここにはおそらく、単なる原則論的なマルクス主義者のそれとして理解するにはあまりに過剰なものを帯びた花田の批評を理解するための導きの糸があるにちがいない。理論に他律させることによって、無制限に駆動しかねないフォークロアや童話のような語りを制御すること。この視座に立つとき私たちは、彼の奇妙な批評言語を説明することができるのではないだろうか。
おわりに
可能な限り丁寧に、花田清輝の批評の魅力を伝えようと努力してきたつもりだ。しかし最後に、応答しておかなければならない要請がひとつだけ残されている。私たちは私たち自身に、自分たちが座標軸のどこにいて、誰とのどのような緊張関係のもとに語っているのかを示すよう求めたのだった。
花田清輝を読むことで私に突きつけられる問いとは、あなたはどのように語るのか――あるいは、あなたのその語り口はいったい何なのか?――という問いである。私がここで追跡してきたような花田の批評の方法は、21世紀の現在にそのまま再現しうるものではきっとありえない。けれども、20世紀の人工の光のなかに、妖しく照らしだされた童話の世界を見いだした彼の眼に相当するものを私たちがもちえているのか否かを問うことは依然として可能である。彼は生産技術の発展と帝国という資本主義の臨界に、それまで「論理」と呼ばれてきたものの歴史的な終焉を見抜いたが、では私たちは、過激なまでの情報技術の進歩と、前世紀以前のような侵略戦争をふたたび召喚しさえする資本主義の持続になにを見るのだろうか。私たちもまた、かつて通用したはずの思考と語りの方法――そこにはこれまで批評と呼ばれてきた方法も、啓蒙主義的な学知の方法もまた含まれることは言うまでもない――がいつしか限界を迎えていく光景をずいぶん前から目の当たりにしているのではなかったか。
問われなければならないのは、記事を書き終えてもなお、はじめに掲げた「批評の面白さなるものを私の手によっても上演」してみせるという目標をついに叶えられなかった、私の語り口のこの白けたつまらなさである。母音の色を発明し、沈黙や夜を書き留めてしまう言葉の錬金術からはいまや遠く隔てられてしまった私たちのための言葉とは、いったいどのようなフォルムをとりうるだろうか。こう問うときに私たちは、批評なるものの再発明をようやく思考しうるはずである。
[1] 好村富士彦『真昼の決闘 花田清輝・吉本隆明論争』、東京、晶文社、1986.
[2] 花田の論争についての比較的に近年の仕事として、乾口達司『花田清輝論――吉本隆明/戦争責任/コミュニズム』(京都、柳原出版、2003)も挙げることができる。好村の著作とあわせて読むことを勧めたい。また言い添えておくと、本連載シリーズの韻踏み夫による記事にタイトルのみ挙げられていた絓秀実『花田清輝 砂のペルソナ』(東京、講談社、1982)をはじめに読むことはあまり勧められない。難解であることもそうだが、花田についての一般的なディスクールを理解したうえで読んだほうが、そこに批評的に介入してみせる絓の狡知により鮮やかに感動することができるからだ。
[3] 花田清輝「鏡の国の風景」、『花田清輝全集』第四巻所収、東京、講談社、1977、p. 161.
[4] 同書、p. 160.
[5] Salvador Dali, La Conquête de l'irrationnel, dans Oui, Paris, Denoël, 2004, p. 259. 花田によって書きくわえられた一文に前後する箇所の原文は以下の通り。「Toute mon ambition sur le plan pictural consiste à matérialiser avec la plus impérialiste rage de précision les images de l'irrationalité concrète. Que le monde imaginatif et de l'irrationalité concrète soit de la même évidence objective, de la même consistance, de la même dureté, de la même épaisseur persuasive, cognoscitive et communicable, que celle du monde extérieur de la réalité phénoménique(私の絵画的な平面についての野心はすべて、精密さのもっとも帝国主義的な猛烈さをもって、具体的な非合理のイマージュを物質化することにある。想像的な具体的非合理性の世界が、現象的現実の外的世界のそれとおなじ、客観的な明白さ、確実性、硬度と、説得的で認識的かつ伝達可能な厚みをもつように)」
[6] 花田清輝「女の論理」、『花田清輝全集』第二巻所収、東京、講談社、1977、pp. 229-230.
[7] 同書、pp. 230-231.
[8] 同書、pp. 231-232.
[9] 花田清輝「錯乱の論理」、『花田清輝全集』第二巻所収、東京、講談社、1977、pp. 22-27.
[10] 花田清輝「童話考」、『花田清輝全集』第二巻所収、東京、講談社、1977、pp. 74-75.
[11] 同書、pp. 70-71.
[12] 同書、p. 74.
[13] たとえば、「二十世紀における芸術家の宿命――太宰治」(『花田清輝全集』第三巻所収、東京、講談社、1977)や「沙漠について」(『花田清輝全集』第三巻所収、東京、講談社、1977)、あるいは全集四巻に収録されている『アヴァンギャルド芸術』の諸篇などを参照せよ。
[14] 花田清輝「砂のような大衆」、『花田清輝全集』第六巻所収、東京、講談社、1978、pp. 477-481.
[15] 絓秀実「花田清輝の党」、『群像』、no 77(3)、2022、pp. 186-219. を参照せよ。
[16] 花田清輝「柳田国男について」、『花田清輝全集』第八巻所収、東京、講談社、pp. 350-352.
[17] 花田清輝「笑い猫」、『花田清輝全集』第四巻所収、東京、講談社、1977、p. 236.
[18] 花田清輝「サルトビ・レゲンデ」、『花田清輝全集』第四巻、東京、講談社、1977、p. 58.
[19] 同書、p. 59. ここで花田が取りあげているペレスの仕事とは、« Comme quoi Napoléon n’a jamais existé ou Grand Erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe siècle »と題されたパンフレットであるはずだが、このパンフレットが出版されたのは1827年であり、おそらくここにも花田による典拠の書き換えが施されている。なお、
Albert Sonnenfeld, « Napoleon as sun myth », Yale French Studies, no 26, 1960によれば、このパンフレットは風刺あるいは論争的な意図のために書かれたものである。
[20] 同書、pp. 59-60.
[21]同書、p. 60.
[22] 同書、pp. 61-64.
[23] 同書、p. 65.
[24] 同書、pp. 65-66.
人文書院関連書籍
その他関連書籍
著者プロフィール
袴田渥美(はかまだ・あつみ)シュルレアリスム/文芸批評。批評誌『ラッキーストライク』運営。過去の仕事は以下。「象徴詩的身体に抗して――ジュリエット物語、あるいは思考のレッスン――」(『大失敗』2号掲載、2020年5月)、「理論が書きかえる/理論を書きかえる――子を食う母についての覚書、あるいはブラックユーモアのレッスン――」(『ラッキーストライク』創刊号掲載、2021年9月)、「薔薇の弁証法、あるいはグラディーヴァに出会うためのいくらか不可思議なある実験についてのレポート――ジグムント・フロイトとアンドレ・ブルトンにおいて現実的なものの発明とは何か?」(『ラッキーストライク』二号掲載、2022年10月)。
次回は8月後半更新予定です。七草繭子さんが澁澤龍彦を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
