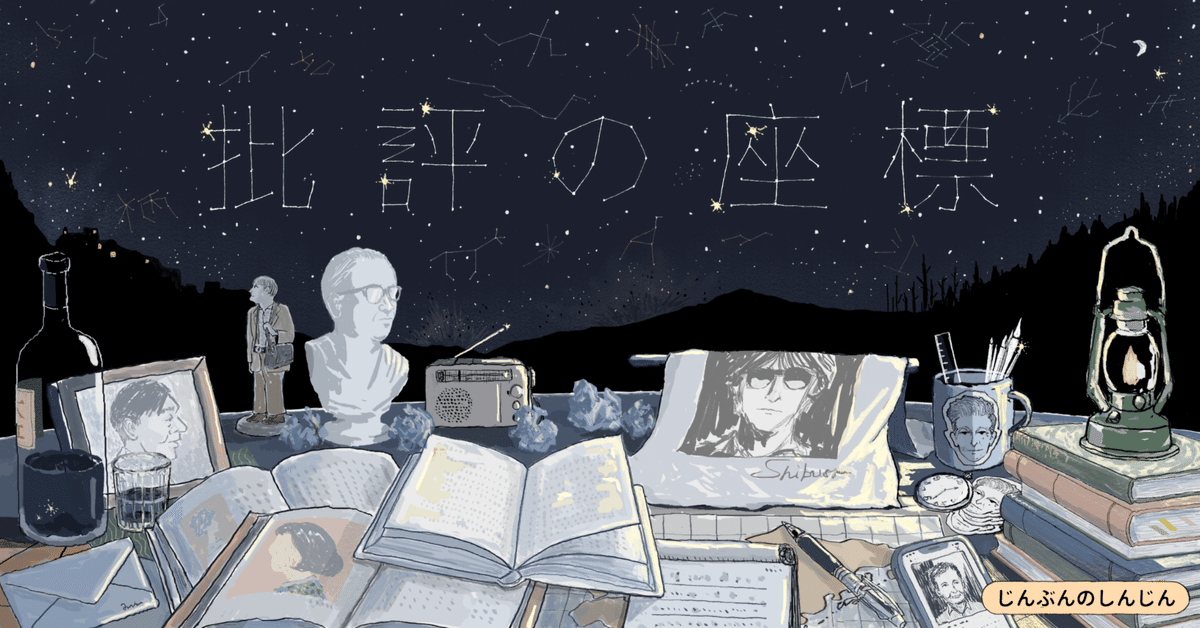
【批評の座標 第23回】「あなた」をなかったことにしないために――竹村和子論(長濵よし野)
「批評の座標」最終回の本論考で取り上げるのは、英米文学者でありフェミニズムの思想家、ジュディス・バトラーの訳者としても著名な竹村和子。日本のフェミニズムに功績を残しながらも早世した彼女の思想を読み解き、その呼びかけに応えるのは、大庭みな子を研究する傍ら在野の編集者・ライターとしても活躍する、長濵よし野です。
――批評の地勢図を引き直す
「あなた」をなかったことにしないために
――竹村和子論
長濵よし野
アイデンティティの概念を「差異化」という言葉で言い換えれば、一方で、周縁を見えなくして均一化する抑圧操作を、差異化という戦略を使って可視のものとしながらも、他方で、差異が固定して新たな階層秩序に陥らないように、無限に差異化を押し進める、そのような二重の作業が、ぜひとも必要だということになる。[1]
ここにわたしがいる。脳裏には――今遠くでたしかに呼吸をしている――さまざまな「あなた」(たち)が浮かぶ。それぞれを今、個別具体的な「あなた」として思う。わたしはわたしのことを「わたし」だと思う。そしてあなたもまた、あなた自身を「わたし」と思い、わたしのことを「あなた」と呼ぶだろう。
これからはじめるのは、ジュディス・バトラーの訳者で知られる竹村和子(1954-2011)という人物とその言説についての批評であり、話題は主に、性にまつわるアイデンティティの政治と倫理のことになる。そのような文章を書くにあたり、わたしは「わたし」のこと、そしてわたしが確かに知る「あなた」(たち)のことを思いながら書こうと思う。その理由は、この社会をとりまく抑圧と差別について考えるとき、「わたし/あなた」がどのようなアイデンティティや立場であれ、このわたし(たち)こそが一人も洩らすことなくその抑圧をうむ構造にとりこまれているからというのがひとつ、そしてもう一つ重要なのは、わたしがその抑圧構造に抗したいと思うとき、最初の手がかりとして、少なくともわたしにとって最も確かなのは「わたし」が感じたあらゆる苦悩や傷や喜び、この抑圧の構造を要因のひとつとしてうまれた「わたし」の感情や悩みだと思うからである。
だからこそわたしは、この先を書く前に、いわば半径1メートル以内でわたしが感じたこと、あるいは出会ってきたすべての「あなた」を思い出すことからはじめる。大きな構造を今の状態から変えようと思う時、最初に必要なのは、そのような近距離からはじめることであり、それこそが大きな構造をも変えていくことにつながるとわたしは信じている。そしてこれから論じようとする竹村和子もまた、多くの人のもとにその言葉を届けつつも、後に詳述するようにそのような近距離の「わたし/あなた」からフェミニズムをはじめとするセクシュアル・アイデンティティの政治と倫理について思索を深めていった人であった。むしろそうした竹村の言説の姿勢が、個別具体的な「わたし/あなた」を思うということに、わたしを向かわせる。そのように言うのが正しい。
冒頭の引用はトリン・T・ミンハ『女性・ネイティヴ・他者』の訳者あとがきで竹村が書いたものだ。英米(/英語圏)文学、批評理論、フェミニズム、セクシュアリティ研究を専門としつつそれらの横断的な研究者でもあった竹村和子の言説を端的に説明するとすれば、わたしはこの一文を選ぶ。ここにみえるのはすなわち、抑圧構造に向き合う上で、二項対立/二項対立ではとりこぼしてしまうものの往還が必要であるということだ。
たとえば女性差別や同性愛差別といった差別と抵抗の歴史を考えるとき、まずそこで考えうるのは、そうした差別が、「男性ではないもの」とされてきた「女性」というカテゴリーに対する差別、「異性愛者ではないもの」とされてきた「同性愛者」に対する差別として、考えられてきたということだ。これは、抑圧構造の一側面を二項対立的にとらえたものであり、そのような二項対立のもとで発生している権力勾配は是正していく必要があるのは言うまでもない。とはいえ抑圧構造の「一側面」であると書いたように、単純な「男/女」「異性愛/同性愛」という二項対立を持ち出すだけでは、トランスジェンダー・ノンバイナリーのライツや、「女性」「同性愛者」とカテゴライズされる中で発生する権力勾配を無視しかねない側面があるのも事実である。
構造的な問題に抗しようという時、そこでは二分法によって可視化されるべき差別の現状が一方ではあり、もう一方では、単純な二分法であらゆる声を抹消してしまわないように、「無限の差異化」つまり、カテゴリーの外縁そのものをとらえ直し続ける必要がある。竹村が想定しているのはそうした往還であり、その双方の間に矛盾を抱えているとしても、抑圧の構造に立ち向かうという意味では目指す先は一致する。そうした無限の往還に向き合ったのが竹村和子という人であった。
いま、女性差別や同性愛差別、トランスジェンダーやノンバイナリー、アセクシュアル、アロマンティックに対する差別、人種による差別、その他ありとあらゆる「正しくない」として排斥され、抑圧され、棄却されてきたアイデンティティに対する差別について考え、抗しようというとき、なぜ竹村を読み直す必要があるのか。それは、おそらく単に二項対立的なものとしてとらえられがちなこのアイデンティティの政治について、そして二項対立だけでは取りこぼしてしまうものがあまりに多すぎる「倫理」の問題について、竹村の言説は「無限の差異化」、境界の絶え間ない引き直し、という往還的思考法を実践として提示してくれるからだ。またそれを「わたし/あなた」の距離からはじめていく竹村の言説は、それぞれの「わたし」から、一歩踏み出していけるということを示してくれる。
一、それでも「フェミニ・ズム」を手放さない
*トランス差別反対を示すべく、トランス差別的言動に言及する箇所があります。
竹村和子が世に文章を発表するようになったのは90年代後半であった。1997~2001年まで雑誌『思想』に連載された5つの論文は、代表作『愛について アイデンティティと欲望の政治学』として2002年に刊行される[2]。上野はこれを「鮮烈」な「デビュー」[3]としており、竹村は『愛について』をきっかけとして、英語圏文学・フェミニズム・セクシュアリティの研究者として知られるようになった。また、この時期には岩波書店の『思考のフロンティア』シリーズより、竹村が担当執筆したフェミニズムの概説書『思考のフロンティア フェミニズム』も刊行される。
フェミニズムの歴史は4つの波で表わされることが多い。清水晶子は19世紀末~20世紀前半の第1波を「女性の相続権、財産権そして参政権を求めた運動」、1960年代からの第2波を「政治や経済活動などの公的な領域を担うのは男性、私的領域である家庭は女性、という性別化された活動領域」への異議申し立てをした運動と位置付けた。また続けて清水は1980~90年代の第3波は、第2波を引き受けつつ「人種やセクシュアリティ、ポスト植民地主義などの問題」や「ダイバーシティやインターセクショナリティという観点」が重視されたこと、つまり「性別以外の属性に基づく女性たちの差異や多様性により一層の注意を払おう」としたことを特徴としてあげ、また「ガールパワー」が言われ出したのもこの時期だと述べる。そして今は、2010年代からそこに「オンライン・アクティビズム」の性質が備わって来た第4波だと清水は言う[4]。
もちろんこの4つの波は世界的なフェミニズムの思想や運動の歴史をとらえる上で重要な指標だ。竹村はここでいえば、第3波の時期にその出発を位置づけることが可能である。しかし日本国内のフェミニズムの動向をみていくときには、10年単位でフェミニズムがどのような状況にあったか確認していくことで、はじめて理解できることも多い。竹村がおかれていた1990~2000年代は特に慰安婦問題等のなかでフェミニズムへのバックラッシュが強まった時期ともいわれる[5]。上野千鶴子は当時について「ジェンダー平等に関して一定の前進があったからこそ起きた反動[6]」だったと回想していた。ではここで竹村が発信した言説はどのようなものであったか。
竹村は『思考のフロンティア フェミニズム』の冒頭[7]で、フェミニズムに対する社会的イメージはおそらく大抵の場合「権利を奪われている女」が「権利を過剰に付与されている男」に対する異議申し立てという図式であろうと述べる。またそうしたイメージのもとでは、男性が「この性の不均衡はもしかしたら自分自身を呪縛しているのではないか」と感じても、フェミニズムという語では居心地の悪さを感じて「男性学」「ジェンダー研究」という語を選択するかもしれない、また女性であってもそのなかにはあらゆる個人の差異を含む以上、「女」とひとくくりに語られることに疑念を感じて「セクシュアリティ研究」や「カルチュラル・スタディーズ」の方へ向かうかもしれないと、竹村は続けて書く。そしてそれはフェミニズムが「フェミナ(女)」という語を母体にした造語である限り避けがたい事態であること、フェミニズムの実践が歴史的に背負ってきた限界でもあることを竹村は指摘したうえで、性の抑圧のあらゆる制度に抵抗する手法としてフェミニズムという語を使用することは「かならずしも最適な選択ではない」とまで言いきってしまう。
しかしその上で重要なのはその後だ。
それでもなおわたしは、少なくとも現在では、フェミニズムという言葉を手放したくはない。その理由は、けっしてフェミニズムを「女の権利の主張」という枠に閉じこめて、「女」を理論の基盤、あるいは解放されるべき主体として、保持したいと願っているためではない。わたしがフェミニズムという用語のもとにしばらくは思考を進めようと思っている理由は、「女」であることはたやすく身体的な次元に回収され、そして身体は還元不可能な与件だと理解されているので、もっとも根源的な本質的属性とされている「女」というカテゴリーを根本的に解体することなく、「男」に対する抑圧も、「非異性愛者」に対する抑圧も、また性に関連して稼働している国籍や民族や職業や地域性などの抑圧も、説明できないのではないかと危惧しているからである。[8]
竹村はフェミニズムの限界を感じつつも、「それでも」フェミニズムを手放さないと力強く述べる。そしてそれは、フェミニズムが歴史的に見れば「女性の権利の主張」を起点にしていることは事実でありそのことはもちろん軽視しないとしても、それは最終目的ではなく、あくまで「女」という語を入口としてあらゆる差別と抑圧について考えること、またその抑圧を生みだし再生産するシステムを考えることが、竹村にとってのフェミニズムであるということだ。そして竹村は、最終的には「女」というカテゴリー自体を「無効化」し、「現在女と位置づけられている者以外に開いていくこと」、さらに「フェミニズムという批評枠を必要としなくなるとき」をめざしている[9]。
竹村が文章を発表しはじめた1990年代後半、すでにバックラッシュが強まりを見せていた。そうした逆風のなか竹村のフェミニズム観は、逆風そのものに立ち向かうというよりも、逆風とフェミニズムの位置関係を俯瞰して観察し、フェミニズムという言葉と歴史の限界性を見つめつつも、しかしその上で改めてフェミニズムを諦めない、というものだ。
フェミニズムが二項対立的異議申し立てであるという認識はいまなお一般的に定着しているものだと思う。たとえば上野千鶴子は「論争好きで「ケンカにつよい」というレッテルをちょうだいした」と自身の社会的イメージが喧嘩腰的なものであると認識している[10]。上野は「わたしはたしかに論争的だが、ケンカ好きなわけではな」く、「ふりかかった火の粉」[11]を払うべく論争にあたっているのだと述べている。しかし上野はここで「ケンカをしている」という点は否定しない。
もちろん、こうした喧嘩腰ゆえにきりひらかれてきた女性の人権は多くあり、わたしは今その政治によってきりひらかれてきた地平の上にたっている。しかしながら竹村がここで、真向からの喧嘩をするのではなく、フェミニズムの立場に立ったうえで、女性のみならず男性、同性愛者、またあらゆるアイデンティティの人々を想定し、その全員をとりまく抑圧構造に抗するフェミニズムという像を提示していたことは重要だ。
わたしがフェミニズムにしっかりと向き合い始めたのはちょうど20歳になったころだった。それまでフェミニズムという言葉を知っていたにもかかわらず、その頃になってようやく、わたしの日頃の悩みや葛藤がフェミニズムと分かちがたく結びついていることに気が付いたのだった。しかしそこでフェミニズムについて学んでいこうと思ったとき最初に抱いたのは、単純な二項対立(にみえる)形で、女性を抑圧される側・男性を抑圧する側と分離する事への違和感であった。女性は常に「被害者」なのだろうか、男性もまた抑圧をうけているのではないか(であるとすればそれは一体何か)、そもそも男女という枠組みだけではとらえきれないものが多いのではないか、そして、フェミニズムに対する反動やそれに伴う人々の分離は、どうしたら解消することができるのだろうか、主張の仕方は今のままで解消は可能なのだろうか、こうした思いがフェミニズムの学びの入口にたったときにわたしにうかんだものであった。
しかしこれは、そもそもわたしがフェミニズムを二項対立的な政治としてとらえていたことが間違っていたのだ、と今は分かる。竹村の想定するフェミニズムは、あらゆる差別・抑圧とそれを稼働させているシステムをとらえる入口として「女性性」をとらえている。フェミニズムの目的地は単に「女性の権利向上」ではなく、女性性を入口としてあらゆる差別構造をとらえ、その構造を瓦解し、また「女性」というカテゴリーすら解体・無効化し、最終的に「フェミニズム」という語が「使命を終える[12]」地点なのだ。
また、こうしたフェミニズムにてらせば、「女性の危険」を「恐怖」として煽るTERF言説はフェミニズムとはよべないと言わなくてはならない。昨年末「LGBT理解増進法」の制定をめぐって、トランスヘイト言説が一部SNSを中心に流布したことは、非常にネガティブな意味合いでよく知られている。その時持ち出されたのは、シス女性が更衣室やトイレや公衆浴場で不安を抱えるのは問題であるため、性的マイノリティはマジョリティに対する「配慮」をすべきであるという唾棄すべき意見であった[13]。竹村のフェミニズムはこうした言説に対して抗する力も持つ。竹村が提示するフェミニズムとは、あらゆる差別に抗すべく、その入り口として女性性という言葉をとらえるものであり、シス女性が被っている抑圧は、トランスジェンダーを抑圧する言説やシステムとも連動する構造的問題であり、むろん後者の方が幾重にも抑圧を受けているのだが、そのすべてに抗するべく思索を進めていく必要があるからだ。
また竹村の言説は、フェミニズムの立場からバックラッシュに喧嘩腰で向き合うというよりも、フェミニズムそのものの限界性をまずとらえ、そのうえで決してフェミニズムを手放さず、あらゆるアイデンティティをもつそれぞれの個人が、これからいかなる思索を進めていくことが可能かをさぐるものであった。こうした姿勢は、竹村の言説内容のみならず、文体にもあらわれている。
二、言語/物語に投企された者として
それら(「世界の出来事」「政治のアリーナ」:引用者注)は、〈わたし〉から遠く隔たったどこかべつの場所で、あるいは〈わたし〉にときたま到来するべつの機会に、起こるものではない。それらはつねにいまここで、〈わたし〉と〈あなた(たち)〉のあいだで、つまりはその「あいだ」を再生産し、「あいだ」によって再生産されている〈わたし〉の「なかで」起こっていることである。[14]
わたしは、あなたとわたしを同質性という囲いのなかに閉じ込め、その囲いのなかでわたしとあなたを引き裂くすべての言語に抵抗する。
(中略)
だからわたしは忘れない、あなたの身体を、あなたへの愛を、愛がもたらす諧調のすべてを私が感じていたことを。忘却は記憶を呼びよせ、記憶は過去を現在の物語に変える。記憶は、現在刻々の「行為」であり、そのなかで新しくよみがえるあなたは、幾重にも増幅し幾多のかたちに姿を変えて、「母なるもの」「女なるもの」の名前を無効にしていく。[15]
竹村和子の代表作『愛について』の文体の特徴をひとつあげるならば、こうした「わたし」「あなた」の二人称の語りだろう。
『愛について』の「マスター・テクスト」は、文庫版巻末の解説で新田啓子が言うように「セクシュアリティ」と「アイデンティティ」という「それぞれに多面性を内包した二つの観念/言説」についてである[16]。第1章~第3章 は主に前者が主題であり、両輪として合わせて稼働する性差別と異性愛主義の「〔ヘテロ〕セクシズム」をはじめとして絡み合うあらゆる規範/物語が唯一正統とされて、異端や病理、狂気とされた愛のあり様を幾重にも抑圧/棄却していく仕組みやプロセスを系譜学的に分析するものだ。そして第4・5章はそこから、性差別や植民地主義に抗するためのアプローチ/政治/倫理の問題として「アイデンティティ」やそのアイデンティファイの現場において重要である個別の「語り」をいかに聴く/語るかについて問い直していくものである。その論理的な分析は緻密に、そして慎重に行われていく。その一方で、その緻密な論理的分析の合間にはさまれるこうした文体は、論理的というよりも、むしろ。いや、いったいこれをどんな言語と呼べるだろうか。
その補助線となるかもしれないテクストに、コロナ禍を挟んで赤坂憲雄・藤原辰史によって交わされた往復書簡『言葉をもみほぐす』(写真:新井卓・岩波書店・2021)がある。本書は、人災を含む災害や、為政者による抑圧が繰り返されるなか、すぐれた人文学者たちの言葉をもってさえも現実が暗くありつづけていることを問題意識とし、しかしそれでもなお言葉になにが出来ると信じうるか、という藤原の問いを出発点としていた。それに対する民俗学者・赤坂憲雄の一通目の応答のキーワードは、「臨床」というものだ。
わたしはいつしか、とても具体的な人や物や場所に繋がり、そのやわらかな裏付けを受けながら言葉をくりだすことを、自らの知の作法とするようになっていました。
(中略)
荒れている言葉を鎮めて、言葉の力を、それゆえ言葉への信頼をとりもどすことは、いかにして可能か。それはあくまで、臨床的なフィールドにねざしてこそ可能となるにちがいない、そう、わたしは信じています。[17]
ここでいう言葉の「臨床」とは、具体的な人や物や場所を「裏付け」として言葉をくりだすことだった。藤原もまたそれに「具体的な人間の顔なり足なり手なり、その肌理を思い浮かべつつ言葉を紡げば、どんなに抽象的な内容でもきっと力を持つでしょう」と返す。それは藤原が『分解の哲学』執筆にあたり、「一人の人間のことを思い、その人のために書いて」いたという記憶に裏打ちされたものだ[18]。
竹村がその分析に伴走させるように、「わたし」として「あなた」へ呼びかけ語るとき、そこに力が宿っているとしたら、それは言語が「臨床」性を帯びるからではないだろうか。
ここで、『愛について』序で竹村が「物語」と「比喩」という言葉から議論をはじめていることも思い出したい。
わたしたちは何らかの「物語」なしに、自分の感情を感じることも、自分を把握することも、行動することも、何かを理解することも、他の人々との同意を得ることも、あるいは誤解、決裂することもできない[19]
竹村はわたし(たち)が、そのような物語や比喩を必要としながらもそれらにからめとられながら生きているということを示している。本書においてこの物語とは、異性愛主義、性差別、ドメスティック・イデオロギー、生殖イデオロギー、ロマンティック・ラブ・イデオロギー、モノガミー規範など、本来あらゆる「諧調」をもつ愛を、ペニスを中心とした形で序列化して解釈する力学といったそれぞれの規範、またそれらの絡み合いのことだとひとまずはいえるだろう。竹村は、わたし(たち)が具体的に生きる「個別的な物語」は社会に流通する「集合的な物語」(≒社会規範)のもとで理解され、それゆえ誰一人、「個別的な物語」を生きながらも「集合的な物語」から完全に切り離されてはいないと言う。そしてハイデガーの言う意味で「既存の言語のなかに」「「投企」されている」わたし(たち)は、いつも「「事実」と価値づけられた「比喩」」としての「集合的な物語」をいつしか受け取らされ、それが錯覚であるにもかかわらず、「わたしたちに、遡及的な事実性を生産していく」のだと竹村は書いている[20]。
しかし竹村はここで「個別的な物語」はたえず、「集合的な物語」からの「ずれ」をもち、それこそが「物語」が「事実」ではなく単に「比喩」であることを「気づかせてくれる」ともいう[21]。竹村はわたし(たち)をからめとっているものが、「物語」であり、そしてそれが「言語」の問題であるということを痛切に感じている。
だからこそ竹村は、論じる対象としてのみならず、自らの言葉の実践からはじめていこうとしていたのではないか。臨床性とはすなわち、「個別的な物語」が「集合的な物語」からずれていく瞬間のあり様だ。藤原の言葉を借りれば、それは「わたし」と「あなた」の「肌理」ともいえるものだろう。そして具体的な個人を思いながら発される「わたし」と「あなた」の語りは、テクスト内のみならず、読者をもその語りの内側へと巻き込んでいく。
三、アイデンティティの倫理のために――「わたし」の解体からはじめること、あるいは「鬼」として
『愛について』第4章の題は「アイデンティティの倫理――差異と平等の政治的パラドックスへ」であった。続く第5章「〈普遍〉ではなく〈正義〉を――翻訳の残余が求めるもの」とともに、ポストコロニアル批評をひきうけたアイデンティティの政治/倫理の問題を取り扱っている。まずここで思い出したいのは、竹村が差別の構造をとらえるとき、たとえば同性愛差別を稼働させている〔ヘテロ〕セクシズムが抑圧するのは、同性愛だけではなく異性愛者もまた同じシステムの中に抑圧されるようにして捉えこまれていると考えていた点である。
また、上野千鶴子や新田啓子が指摘するように[22]、竹村の目的は、アイデンティティという概念やそれに付随して稼働する認識そのものの解体であり、竹村にとって既存の権力秩序の下での見かけだけの平等や承認は決してゴールではない。たとえば竹村は、語りえぬとされたものを語り手が語ろうとし、聞き手がそれを聞くことで理解し、同情したとしても権力付置は変わっていないことを指摘する。上野はこうした姿勢について、「彼女の目的は、(中略)異性愛制度のもとで性的マイノリティの「人権」や「承認」を確保することではない[23]」と書くが、これは第一節でみてきた竹村のフェミニズムにおける姿勢とも一致する。
その意味であらゆるアイデンティティの人々が、「語り」を語ること/聴くことを通してアイデンティティの倫理を実践するには、そしてゆくゆくは既存の権力付置を温存した言語の中で構築された「アイデンティティ」なるものを解体するためには、どうしたらよいのか。そこで提示されているのが、自己と他者の間主体的な政治と、「自己の位置をずらし、自己のなかに差異を生じさせていく[24]」自己内部の内主体的な倫理、その往還である。
竹村はここで「「わたし」を同定するアイデンティティが、「わたしでない」ものを生みだし、それとの差異化をはかる」としたうえで、「人と人の〈あいだ〉」でのアイデンティティの「政治」から「自己のなかの〈あいだ〉」 をあつかうアイデンティティの「倫理」へ接続する必要があると説く[25]。つまり、既存の言語/体制の中での見かけだけの平等、マジョリティと構造的他者/マイノリティの間での見かけだけの平等にとどまらないために、他者と他者の間ではなく、まずは自己の内側の差異に目を向けよ、ということである。
語りえぬとされた語り手とその語りの聞き手。その互いがそれぞれに「自己を引き裂き、還元不可能な他者性を双方の身体と精神に呼び込むことが可能になったとき[26]」、アイデンティティの倫理はその入り口を見せる。つまり竹村がアイデンティティの倫理において重要だと考えているのは、他者と自己との間での政治だけではなく、まず自己のアイデンティティを解体するところからはじめなくてはいけないということだ。竹村はこれをデリダの「アイデンティティ(自己同一性)の中断」とかさね、そして「自己同一性の中断の不断の実践こそが、差異を表面的な平等に取り込まないアイデンティティの政治的実践だと言えるだろう[27]」と述べている。
これはいわばアイデンティティの「瓦解」である。それが恐怖と不安を伴う状態であることは容易に想像されるだろう。『愛について』序で竹村は同書の執筆が「いかに自分と向き合い、自分をある意味で危機に陥れるものか」と気づいて愕然とし、また「自分が粉々に砕けるような気がして、恐ろしくて身がすくむ思いがした」と書いている[28]。規範に対し疑念を抱き、思考の上で対象化し、抵抗を試みようとしても、その解体はその規範を内面化した自己の破壊を伴う。私自身もまた、その破壊を前にして「恐ろしくて身がすく」み続けている一人だ。しかしその一方で、私がその地点に立ってはじめて、わたしに重なるかたちで見えてくる像が一つある。それが「鬼」である。わたしは今、自分が20歳前後でフェミニズムに出会ったとき、同時に「鬼」という言葉にも出会っていたことを思い出している。
三従の美徳に生きるはずの中世の女が、鬼(般若:引用者注)となるということのなかに、もっとも弱く、もっとも複雑に屈折せざるを得なかった時代の心や、苦悶の表情をよみとることができる
(中略)
世阿弥は〈鬼の能〉にふれて、「形は鬼なれども、心は人なるがゆへに」という一風を想定している。私が〈鬼〉とよばれたものの無残について述べようと思うのも、このような人間的な心を捨てかねて持つ鬼に対する心寄せからである[29]
馬場あき子『鬼の研究』は、主に中世までの「鬼」にまつわる言及や表象について分析するものであり、決して現代について考察するものではない。しかしながら、里に定住せず生きる山の盗賊や、能の鬼女、あるいは「まつろわぬ」とされた民の表象に私がこの本のなかで出会う時、わたしは、現代の不均衡な社会構造のなかで懸命にいきようとし、また声をあげようとする(私を含む)無数の鬼たちのことを思う。馬場は「累々と屍を積み、土に帰したであろう鬼」について、それは「王朝繁栄の暗黒部に生きた人びとであり、反体制的破滅者ともいうべき人びと」だと述べていた[30]。そして、馬場は「われわれ自身が、孤独な現代の鬼である」かもしれぬとも書いている[31]。
あまりに不均衡にできたこの社会のなかで、構造的に抑圧された者が声をあげようとすること、あるいはそれを聞こうとすること。竹村は、そうした「聞きえない」とされてしまう「声を語る」こと、「語りえない」とされた「声を聞く」ことを「〈正義への訴えかけ〉」と言い換えていた[32]。そしてそうした声は、「語るものにさえ制御」できずに「溢れでる」ものであり、それはまた「語る者にも聞く者にも」「不安と不確かさを否応なくもたらす苦悶の言葉、狂気の声」として現れると竹村は言う[33]。竹村がここで「狂気」という言葉を出したのは、竹村自身が後述するように、9.11同時多発テロ事件が念頭に置かれたものであった。「狂気が、本来は聞き取られない声をなんとか届けようとする絶望的な試みであるならば、それを聞くものは、その声を不条理の暴力として[34]」まず聴くだろうと竹村が言うように、今にも抹消されようとする声が発露するとき、時にそれは狂気として受け取られる。それは馬場がまなざした、中世の鬼女や、「反体制的破滅者」としての「鬼」たちと重なる像なのではあるまいか。
しかしここで言わなければならないのは、私は、聞きえぬ声≒狂気を発する者たちを、アイコンとしての「鬼」としてまつりあげたくはないということだ。そんなことは絶対にしない。なぜなら、馬場もまた、先ほどまとめて引用した箇所で世阿弥の言葉を引いて言うように、「鬼」とはまさに「人」のことにほかならないからだ。「あなた」や、「わたし」と同じだ。
だから、わたしはわたしを鬼だと思ったことがあった。今でもそう思う。あなたももしかしたら、「鬼」であるかもしれない。「わたし」の目に映る「わたし/あなた」は「鬼」であり、そしてまぎれもなくあたたかい血の流れる「人」だ。悲しみや喜びを感じ、風にふれ、黙ったり、しゃべったり、笑ったり、泣いたり、そして時に怒ったりする「人」だ。
しかし、やはり鬼とは、いわば(構造的)他者の表象である。鬼とは、狂気の表象である。「聞きえぬ」「語りえぬ」とされた声、時に狂気として受け取られてしまう声。竹村はそうした声を、「語る者にも聞く者にも、何を語っているのか、何が語られているのかわから」ないものだとしていた[35]。そして竹村はそうした、怒りや悲しみや、なにかさえ定かでない、狂気≒声を聞こうとする/語ろうとする、「挫折」も伴う政治と倫理の場から「目をそむけないでいること」が重要であると述べる[36]。
それは言い換えるとすれば、あるいはまずわたしに出来ることがあるとすれば、ほかならぬ「わたし」や「あなた」を“なかったことにしない”ということなのではないか。
「わたし」が「わたし」を「鬼」だと思うとき、それは「わたし」のなかに「鬼」という他者をもつということだ。わたしを「わたし」と思うわたしは、わたしのなかにいる「わたし」とおもえない「鬼」と目を合わせる。そして「鬼」である「わたし」はあゆみをはじめ、ときに「鬼」をもつ「あなた」に出会う。そのすべてを、わたしは今、なかったことにしたくないと思う。
「わたし」は、今思う。「あなた」を思う。これまで出会ったすべての人を、景色を、出来事を、作品を、そして目を合わせたわけではないけれど、遠い過去の人々の息遣いを、そのすべてを、「あなた」として思う。そしてまだ出会ったことのない、これから出会うかもしれないし、出会わないかもしれないすべての「あなた」を出来る限り思う。
「わたし」は、だれのこともなかったことにしたくない。これからもしない。そしてそれを、言葉だけにしたくない。わたしには限界があり、傷つけられる可能性と同時に傷つけることも可能性としてもち、また沢山の間違いをすでにしている。だから信じなくてもいい。わたしさえ、欺瞞かもしれないと思う。それでもなお、わたしは、すべての「あなた」をなかったことにしたくない。「あなた」に出会うわたしのことも、なかったことにしたくない。わたしは、ときに「狂気」として人々の目に映り、ときに簡単になかったことにされてしまう「あなた」や「わたし」を、なかったことにしない。
「あなた」と「わたし」をなかったことにしないために、この声が、そして竹村和子の言葉が、今「あなた」のもとに届いていくことを願う。
[1] トリン・T・ミンハ『女性・ネイティヴ・他者』竹村和子訳 (岩波書店・1995)「訳者あとがき」p243
[2] 竹村和子『愛について アイデンティティと欲望の政治学』(岩波現代文庫・2021)参照
[3] 上野千鶴子「あなたをわすれない」(竹村和子『境界を攪乱する――性・生・暴力』(岩波書店・2013))p409
[4] 清水晶子『フェミニズムってなんですか?』(文春新書・2022)p19~23
[5] 西川祐子・上野千鶴子・荻野美穂『フェミニズムの時代を生きて』(岩波現代文庫・2011)p219~229参照
[6] 注5と同じ、p221
[7] 竹村和子『思考のフロンティア フェミニズム』(岩波書店・2000)ⅲ~ⅹ
[8] 注7と同じ、ⅵ
[9] 注7と同じ、ⅶ
[10] 上野千鶴子『不惑のフェミニズム』(岩波現代文庫・2011)p410
[11] 注10と同じ、p410~411
[12] 注7と同じ、ⅶ
[13] 神谷悠一『検証「LGBT理解増進法」 SOGI差別はどのように議論されたのか』(かもがわ出版・2023)P51~57
[14] 注2と同じ、p28
[15] 注2と同じ、p221~225
[16] 注2と同じ、新田啓子「すべてが途切れなく」p396
[17] 赤坂憲雄・藤原辰史『言葉をもみほぐす』(岩波書店・2021)p14~15、本書の臨床性にまつわる批評は別稿(「言葉と距離と喪失のなかで――ある手紙について、および大庭みな子「青い狐」論」『ぬかるみ派 vol.3 絶滅の世代』(二〇二三・十一月))に纏めたので、そちらも参照されたい。
[18] 注17と同じ、p23
[19] 注2と同じ、p1
[20] 注2と同じ、p1~2
[21] 注2と同じ、p3
[22] 上野、注3と同じ。新田啓子「すべてが途切れなく」(注12と同じ、主にp399)
[23] 注3と同じ、p416
[24] 注2と同じ、p231
[25] 注2と同じ、p299~230
[26] 注2と同じ、p242~243
[27] 注2と同じ、p284
[28] 注2と同じ、p29
[29] 馬場あき子『鬼の研究』(三一書房・1971)、p8、ルビ・注は省略
[30] 注29と同じ、p9
[31] 注29と同じ、p10
[32] 注2と同じ、p24
[33] 注2と同じ、p24~25
[34] 注2と同じ、p30
[35] 注2と同じ、p25
[36] 注2と同じ、p26
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
長濵よし野(ながはま・よしの)2000年生まれ。神奈川県育ち。早稲田大学 大学院 教育学研究科 国語教育専攻 修士課程在籍中。大庭みな子について研究するかたわら、フリーの編集者・ライターとしても活動する。
『とある日 詩と歩むためのアンソロジー』(2023)では編集組版を担当し、「とある日」編集部として責任編集・川上雨季と共に第12回エルスール財団新人賞(現代詩部門)を受賞。X(旧Twitter):@lululu2_22
次回更新はありません。
1年間ご愛読いただき、ありがとうございました。
また、本連載は書籍化が決定いたしました。
詳細はあらためてお知らせいたします。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
