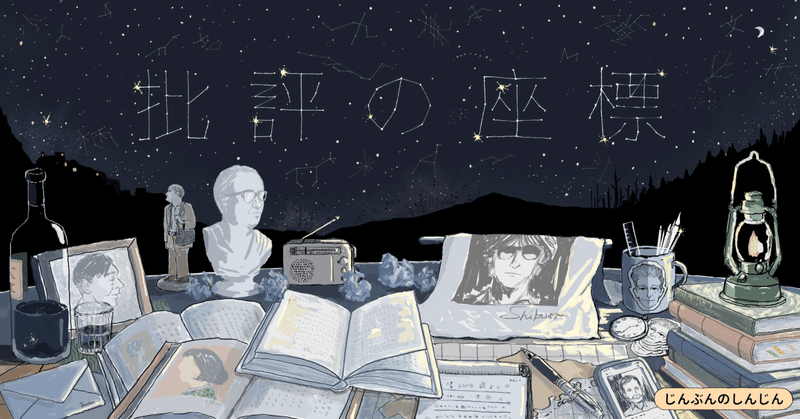
【批評の座標 第14回】SFにおける主体性の問題――山野浩一論(前田龍之祐)
第14回で取り上げるのは、近年再評価が進むSF批評家・山野浩一。小松左京や星新一などに代表されるSF作家を批判し、J・G・バラードやフィリップ・K・ディックを輸入した山野は、日本のSFひいては日本という国の「主体性」をどう見つめていたのか。新進気鋭の批評家・前田龍之祐が論じます。
ーー批評の地勢図を引き直す
SFにおける主体性の問題
山野浩一論
前田龍之祐
1.‘‘SF批評家・山野浩一’’の誕生
過去の日本の批評家の仕事を振り返りながら、「批評の地勢図を引き直す」ことを目的とする本企画だが、SF批評の「地勢図」を考える際に多くの読者が想起するのは、巽孝之編『日本SF論争史』(勁草書房、2000年)によって纏められた一連の議論ではないだろうか。
同書は、日本初のSF商業誌『SFマガジン』の創刊(1960年)を皮切りに、急速に拡散と成熟を遂げていった日本SFにおける論争の歴史を、安部公房のSF論にまで遡って描き出した労作で、SF批評の入門書としてもよく読まれている。
編者によれば、そこで描かれた系譜とは「いずれも先行するSF論を批判する実質的な論争のかたちで展開されて」[1] おり、この「SF論争という文化」が日本SF批評の歴史を形成しているのだという。
だが、その事実を認めながら、ここで私はSF批評のもう一つの「地勢図」に目を向けたいと思う。かつて『週刊読書人』上で毎月連載されていた「SF時評」の役を担っていた、作家たちの系譜がそれである。1968年から一年間、筒井康隆がその仕事を務めてから、後にバトンは『SFマガジン』初代編集長の福島正実、日本初の専業SF批評家である石川喬司らに引き継がれ、2010年に林哲矢の代をもって途絶するまで、40年以上にわたって日本におけるSF批評の現場を支えていたのだ。
そして、本稿で取り上げる山野浩一(1939‐2017)もまた、その系譜に連なるひとりである。いや、正しくはとりわけ大きな功績を残したと言うべきだろう。というのも、1972年から8年間、山野はこの時評を歴代で最も長い期間担当していたからである。その点で、日本SF批評の「地勢図」は、彼を中心に測定されなければならない。では、改めて山野浩一とは一体何者なのだろうか。
1964年、師匠であった寺山修司の薦めで、小説「X電車で行こう」を『宇宙塵』(後に『SFマガジン』に転載)に発表してデビューした山野浩一は、すぐに「新人随一のホープ」[2]として期待され、業界の注目を集める存在だった。
山野自身も「デビューにあたっては当時の文化人の多数に全会一致のような支持を受けてい」たと回想していたが[3]、注意したいのは、それにもかかわらず山野は決してSFの熱心な読者ではなかったという事実である。
「SFとの出会い」について語ったインタビュー記事で、山野は次のように述懐していた。
私にとってSFとのほんとうの出会いは、SFを知ってのち随分たってからのことである。子供の頃には手塚治虫の漫画を愛読しており、SFというような言葉も相当以前から知っていて、「SFマガジン」も創刊当時に一度くらい読んだことがあったと思う。
〔…〕かくて、私はこと志と異って(ママ)SF作家となったのだが、これがSFとのほんとうの出会いであったわけではない。私はそれから多くのSFを読むようになったが、確かにSFというものには思考世界を自由に展開できる素晴しい可能性がありながらそうした自由な思弁を切り開いた作品がほとんどないのである。
もちろん、後にはJ・G・バラードを始めとする「はっきり過去のSFへの不満を述べ」た「スペキュレイティヴ・フィクション」に対する共感から、「ほんとうのSFとの出会い」は果たされることになるのだが、重要なのは、こうした山野の出発点において、次第に高まっていくSF業界への違和感の根を見ることができる点である。
その違和感とは、日本のSF業界における「批評不在」の状況、言い換えれば「未来」や「宇宙」、「ロボット」などといったギミックばかりに執着するような、SFのある種の‘‘お約束’’に居直る姿勢に対する批判意識から発するものだったと言える。「SF時評」を務めていた他の作家たちと比べても、こうした態度を示したのは山野ただ一人であり、その意味で、彼はSF批評家としてきわめて特異な存在であった。
さて、デビュー時の絶賛から一転して、『宇宙塵』の読者は山野へ「面白くない作品」、「SFの主流ではない」[4]などの批判を向けるようになる。それに対して山野は、「小生の書きたいものが現段階の主流と一致しなくても仕方がない」、「「宇宙塵」が「宇宙塵」向きの作品ばかりを掲載していたのでは、発展性を失う」[5]と応えると、その後に小説「開放時間」(1966年)を発表したタイミングで、〈宇宙塵=SF業界〉から次第に距離を置き始める。そして、自身の考えるSFとそれをめぐる状況とのズレの意識を、「ポレミックな評論活動に軸足を移」す[6]形で前面化させていくのだ。
つまり、日本SFを批判する山野と、それに対するSF作家の荒巻義雄による再批判という形で展開された〈山野‐荒巻論争〉や、『日本読書新聞』での書評活動などに端を発する、‘‘SF批評家・山野浩一’’が、この時誕生するのである。
そして、このようにして批評家としてのキャリアを歩み出した山野浩一は、1969年に「日本SFの原点と指向」という長編の評論を発表する。それはこれまでの日本SF批判をより具体的かつ精緻に展開した「集大成的論文」[7]であった。が、この批評文を山野浩一の代表作と見なすのには浅からぬ理由がある。それは日本SF批判とも重なり合いながら、山野が常に考究していた主題――すなわち、「主体性」をめぐる議論を、はじめて明らかに提示した文章だからである。
山野の根本的な思想を捉える際に注目すべきなのは、この「主体性」という語をおいてほかにない。このことを踏まえた上で、「日本SFの原点と指向」の内容を確認しておこう。
2.日本SF批判と「主体性」
「日本SFの原点と指向」は、当時『SFマガジン』を中心に活躍していた作家たちを次々と批判の俎上に載せていく論考である。まず、ここで日本SF全体を「建て売り住宅」と喩えている点に注目しておきたい。
日本に於けるSFジャンルに属する作家、つまり一般にSF作家と呼ばれる人々はすべて翻訳作品によるSFを知っており、すでに存在していたSFというジャンルの中に登場したのである。これはいうなれば、建て売り住宅に入居したようなもので、日本文明への対応性とか、作家の感性に対する適応性などに無関係にジャンルが存在し始めたのである。
なるほど、たしかに日本SFの急速な発展には「翻訳作品」の寄与は大きかったかもしれないが、山野によれば、それはアメリカSFという名の「建て売り住宅」を借り受けているに過ぎないという。ここで言う「建て売り住宅」とは具体的に、多元世界、宇宙空間、タイムマシン、ロボット……等々、SF特有の「小説世界」を構築するモチーフの数々を指すものと言っていいだろう。
たとえば、山野はその最初の「居住者」として星新一と光瀬龍という二人の作家を挙げ、両者の作品の価値を認めながらも、しかしその形式自体は、フレドリック・ブラウンの「ショートショート」の方法(星)、ロバート・A・ハインラインの「年代記」の方法(光瀬)、すなわちアメリカのSF作家が既に拵えた「設計図」を利用したものだと指摘する。
ただし、そうした「設計図」(SF的拡大世界)は、それぞれの作家の「主体性」に紐づいている限りにおいて、物語の幅を拡げうる役割を果たすという。その意味で、問われるべきなのは「建て売り住宅」そのものというより、「日本文明への対応性」や「作家の感性」などとは「無関係」に、海外SFの道具立てだけを借用して小説を書いている、日本のSF作家の怠惰な振る舞いのほうであった。
では、ここで言う「主体性」とは何か。それは端的に言えば、ある作品を立ち上げる際に作家の拠って立つ「創作原点」や「立脚点」[8]、言い換えれば、自身に固有の問いを見つめる態度にほかならない。山野は次のように書いている。
現実に世界文化は民族、国籍などというものを単位にして異った歴史体験と、風土による異った感性を持ち、そこにオリジナルな観念、思想を展開し、文明を切り開いており、日本人作者には日本人としてのエゴが存在し、そこにこそ主体性も存在している。
つまり、それぞれ異なる国籍、歴史体験、生活環境、他者関係などから構成される問題意識のなかに、各人の「主体性」は現れるのであり、そうした意識はおのずと創作=作品にも反映されていくはずだろう。
要するに、山野の言う「主体性」とは、自身の履歴を振り返ったとき――もちろん、そこには過去の失敗や後悔も含まれる――見出されるある個人的な問い(主題)に基づいて、行動や言動をできるだけ一貫させようとする態度であるとともに、作品を造形する際の前提となる作者の「創作原点」から導かれる、制作の指針のようなものだと、ここでは定義しておきたい。
しかし、繰り返すように、日本SFはそのような「主体性」をかえりみずに、「借りもののSF世界」をラディカルに拡大していくばかりで、その世界と作者の問題意識を繋げる意志を放棄したまま発展を遂げていった。
なかでも、日本SFのこうした発展過程を推進した作家として山野浩一は、小松左京へ厳しい眼を向けて次のように書く。
小松左京の作品は、こうした〔日本SFが建て売り住宅的に出発した〕危険性の中で、それでも大きく変貌していった。それは、主体の論理への帰還ではなく、客体へのさらに強引な接近としてであり、ここに小松左京の明解な指向性を求めることができるであろう。
小松の近作『継ぐのは誰か?』にはほとんど小松の作家主体は登場しない。進化論や情報論などSF的拡大世界に内在する客体的な論理そのものが小説原点となり、いうなれば初期の作品によって切り開かれた小松の小説世界が二次的に小説を生み出し始めたのである。
なるほど、とはいえ山野は「地には平和を」(1961年)や『日本アパッチ族』(1963年)などの小松の初期作品については、「作者の悩みが極めて明確に現われていた」[9]ものとして一定の評価を与えていた。だが、次第に作品内に小松自身の問いやテーマ、すなわち「主体性」は見られなくなっていき、SF的なモチーフの単なる組み合わせによってしか成り立つものに過ぎなくなったとの評価を下すのである。
そして、小松左京の推し進めた「客体の拡大」(主体なきSF世界の開拓)が、「日本SFを原点のあいまいな八方破れの落とし穴に引き込」[10]んだ結果、後に現れたSF作家たち(眉村卓、平井和正、豊田有恒etc.)については、各々の〈創作原点=主体性〉がほとんど読み取れない点で、アメリカSFの「建て売り住宅」から一歩も抜け出ていないとして、山野は個別的にその課題を論じていく。また彼らは当時『SFマガジン』で活躍していた人気作家であり、山野の日本SF批判は、ここにいたってある種論争的な熱を帯びていった(先に触れた〈山野‐荒巻論争〉は、山野の批判を受けた荒巻義雄が、日本のSF作家を「弁護する」と反論して開始されたものだった)。
苛烈な日本SF批判を展開しながら、SFにおける「主体性」の欠如について問題視していた山野浩一は最後に、「小説側の主体」からテーマを立ち上げている例外的な作家として安部公房を挙げた後、次のように結論づける、「借りもののSF世界が、日本の文明に対応した作家主体の論理により真実性を与えられねばならない。そして、この主体的作業の苦悩こそ、日本SFの指向性でなければならない」[11]と。
ところで、「日本SFの原点と指向」の発表から数年後、このような言葉を山野は残していた。
本来、主体性というのはあってしかるべきだし、小説を書く以上はそういうものがなければ書けないはずなのに、SFの場合はアイデアとかモチーフだけで書けるような面もある。極端な話一人の作家が――例えば小松左京の場合なんかですけど、一つの作品で出た結論とまったく違う結論を別の作品で出したりしているんですね。やはり、そういうのは主体性を疑うでしょう。どう考えてもね。
ここでは、「一つの作品で出た結論とまったく違う結論を別の作品で出したりしている」ことに対して「主体性を疑う」と述べられている。ある場面でAと言って、また別の場面でBと言うような一貫性のない人間は誰にも信用されないが、時に「アイデアとかモチーフ」が優先されるSF小説においては、そうした主体的な態度はしばしば見過ごされがちである。おそらく山野は、ここに見られるようなSF作家の‘‘不真面目さ’’を指摘していたように思われる。
しかし、だとすればそうした指摘は、単なる作家批判に留まらず、「主体性」なき人々一般へ向けた言葉だと言えはしないだろうか。
その推測が過言ではないというのは、「日本SFの原点と指向」の次の一文を読めば理解されるだろう。
日本文明は、戦後、迷うことなく経済的発展を志した。インドや中国がまず独立、つまり国家の主体性の確立を指向して迷い続けたのに対し、日本という国は恥じることなくアメリカに主体性を売り渡し、朝鮮やインドネシアの苦悩を踏み台にして、極めて状況的に巧妙に立ち廻り、見事な経済発展を為しとげた。
この後「SFに関しても似たことがいえる」と続けられるが、要するにここでは日本SFのあり方が、「恥じることなくアメリカに主体性を売り渡し」た戦後日本の姿を映していると指摘されている。ここで注意したいのは、山野は、SF作家を非主体的な存在だと捉えていると同時に、しかし彼らはそうした性格を有する戦後日本人の一部に過ぎないとも認めていることだ。
以上の点から、1970年に自身が編集顧問を務める雑誌『季刊NW‐SF』を創刊した山野が、巻頭言で日本の「大衆化」状況を注視していた事実も、その延長線上で読むことができるだろう。少し長くなるが引用する。
現在の日本では、思想や論理の持つ重要な意味が見失われつつあり、政治は力関係のバランスの上に成立し、新聞報道は読者の反応によって作られ、あらゆる文化は情況的に生まれていく。人々は主体的な自己世界の代りに現実への対応性だけを持ち、マスプロされた情報を片っ端から受け入れながら楽天的な日常生活を送っているのである。
SFは一面でこういった、ピカートのいう「アトム化時代」への順応力を持っており、巨大な情報メーカーとなり得るものである。そして、疑いもなく一部のSFはそうした役割を果たそうとしている。「アポロ計画」や「万国博」とSFの結びつき、権力者たちの考える‘‘素晴しい未来’’を立派に画いてみせるSF、特に許せないのは「未来学」などというものがSFジャンルの成果として堂々とまかり通り、そんなものに飛びつく一部SF作家がいるということだ。
少くとも未来は、このおろかな現実ののちに登場してはならないものであり、現在の貧しい思考の中で計画されてはならないものである。一体、誰がこの現実以上に未来まで管理しようとするのだ!
当時、大阪万博のテーマ委員だった小松左京が主に掲げていた「未来学」を、SFの輝かしい成果として称揚する空気に「アトム化時代」(マックス・ピカート)の反映を見るこの言葉は、「日本SFの原点と指向」よりも広い射程のもとで語られた同時代批判として読める。山野が常に警戒していたもの、それは戦後から高度成長期にかけて広がりつつあった日本の〈アトム化=大衆化〉現象であり、それとともに露わになった「主体性」なき人々の態度、そしてそのなかで「人類の進歩」としての未来を夢想する日本SFの楽天的なムードであった。
そして、ここから山野浩一が見出し、主に雑誌上で主張するようになるのが、1960年代に英SF雑誌『ニューワールズ』に寄稿する作家たちを中心に提唱されていた、「スペキュレイティヴ・フィクション」という言葉だった。それは「素晴しい未来」を無批判に信じる「未来学」的なSFとの区別のために使用された造語であるが、このようなSFに山野は「作家の主体」を基軸とする‘‘文学としてのSF’’を期待するようになる。
では、スペキュレイティヴ・フィクションとはどのような特徴を備えたSFなのだろうか。あるいは、常に厳しいSF批判を展開する山野が、それでもSFに期待していたものとは何だったのか。
3.スペキュレイティヴ・フィクションとはなにか
前述のように、スペキュレイティヴ・フィクションとは、1960年代中期に主にイギリスで起こったSFの変革運動――一般にニューウェーヴSFと呼ばれる――のなかでよく使われた言葉だった。
その運動を主導していたSF作家のJ・G・バラードは、「内宇宙への道はどれか?」(1962年)というエッセイのなかで次のように書いている。
まず最初にサイエンス・フィクションは、宇宙に背を向ける必要があると私は考える。雑誌用SFの九割を占める、星間旅行、地球外生物、銀河戦争、あるいはそれらの混合からなるアイデアに、まず背を向けるべきなのだ。偉大な作家ではあるが、H・G・ウェルズがその後のSFに及ぼしたのは、悪影響以外のなにものでもないと私は確信している。彼の提供したアイデアのレパートリーが、過去五〇年にわたってこのメディアムを独占することになったというだけではない。単純なプロット、ジャーナリスティックな語り口、シチュエーションやキャラクターの標準的な幅、そういった文体や形式の慣例をすべて確立してしまったのである。
これに続けてバラードは、近年の絵画や音楽などに見られる「思弁的な傾向」が、「規格化しつつある」SFにも波及することに期待を寄せているが、このようにスペキュレイティヴ・フィクションが主張されるようになった背景には、テンプレ化した物語やキャラクター造形が「雑誌用SFの九割を占める」状況に対する、(数少ない)作家たちの危機感が存在していたというわけである。
それはデビュー以来山野浩一が抱いていたSFへの違和感とも重なるものであり、だからこそバラードを筆頭としたニューウェーヴSF作家に、山野は強く共鳴していた。
それでは、山野はスペキュレイティヴ・フィクションを具体的にどのようなものとして考えていたのか。
たとえば、「総括! 新しい波」(1972年)という文章のなかで山野は、バラードやP・K・ディック、またはスタニスワフ・レムなどのニューウェーヴSFに共通する要素を、六項目に纏めて論じている。ここでそのすべてを見ていく余裕はないが、それによれば、「スペキュレイティヴ・フィクションのSF」にはまず「現代感覚とリアリティ」が求められるという。
つまり、「例え未来や架空世界を画くとしても」、それは「技術革新や社会統計によって算出された未来学的未来」などではなく、あくまで「作者の現代感覚から内的に生み出されたもの」[12]でなければならない。だが、注目したいのは、そうした「未来」は必然的に「現代への寓意」として読むことができる点である。
なるほど、ジョージ・オーウェルの『一九八四年』などはその典型かもしれないが、ある種のユートピア(ディストピア)世界を描く際、その世界にリアリティを与えるには、作者が生きている現実への眼差しがまず問われるだろう。そうして出来する「架空の未来」は、私たちの世界を相対的に捉え返す、‘‘現実への批評’’とも言うべき役割を果たす。読者がスペキュレイティヴ・フィクションに求めるのは「作者の展望世界」だと山野は言うが、「SFこそ真の現代小説となりつつある」[13]というのも、その意味において理解できる言葉だろう。
しかし、そのような世界を巧妙に作り上げたとしても、そこに生きる人々(登場人物)の描写がなおざりにされていれば、SFは「エンターテイメント小説」ではあっても、文学とはならない。山野は言う、だからスペキュレイティヴ・フィクションは「人間の小説」であるべきだと[14]。すなわち、「未来世界を巨視的に眺めようと」する従来のSFにおいて無視されてきた、「テクノロジー文明」における「現代人の不安や焦燥」に目を向けること。そして、それを描くことがバラードの言う(「外宇宙」ではない)「内宇宙」への道に通じていると、ここでは述べられている。
そして、このような「思弁小説」を本格的に論じるために、山野浩一が着手したのが、「総括! 新しい波」と同時期に開始された「小説世界の小説」(1973~82年)という連載評論だった。それはH・Gウェルズからスタニスワフ・レム、あるいはU・K・ル=グウィンまでのユートピア文学の系譜を辿る試みであったが、重要なのは、ここで山野が「あえて「SF」と呼ばねばならない意図の問題」について、はじめに触れている点である。
確かにSFには先に述べたような逆向きの指向性が対立して存在し、私が述べようとするSF論に対して全く反したSFが常に存在し続ける。従って私の論理も一方でSFを礼賛しながら、一方で攻撃するという方法をとらざるを得ない。
〔…〕ただ、もし誰かが『お前は一体、SFを擁護しようとしているのか、破壊しようとしているのか』と尋ねれば、私は迷わず『擁護する』と答えるだろう。なぜなら、SFはその悪しき発展プロセスに於いてすら、様々な真実を暴露する役割を果たしてきたからである。
これまでSF(スペキュレイティヴ・フィクション)の意義を主張しながら、同時にSF(サイエンス・フィクション)を批判する姿勢を崩さなかった山野は、その矛盾した自身の立場を十分自覚していた。しかし、だとすれば「真実を暴露する役割」としてのSF特有の意義とは一体何だろうか。
たとえば、SF研究者のダルコ・スーヴィンは、大著『SFの変容――ある文学ジャンルの詩学と歴史』(原著1979年)のなかで、他の文学ジャンルとSFを分ける定義として、「認識異化」(cognitive estrangement)という語を提案していた。
スーヴィンはすべての「散文文学」を〈自然主義的フィクション〉と〈異化的フィクション〉に区別した上で、後者にSFやファンタジー、また民話などを位置づける。「異化」とは言うまでもなく、日常の世界の論理や法則を突き崩して転倒させるひとつの方法であるが、実際SFはそのような方法に基づいて「さかしまの世界」を構築してみせるだろう。
だが、それよりも重要なのは、SFの「認識」的側面である。スーヴィンは言う、「読者の正常なる世界にもどり、フィードバックするような機能がなければ〔…〕異化のジャンルとして機能をはたせない」[15]と。つまり、「認識異化の文学」としてのSFは、「異化」的という点でリアリズム文学と区別される一方で、作者(読者)の「経験的環境」への反映と考察、すなわち「認識」を齎す点で、ファンタジーや民話とも区別されると、ここで指摘されているのだ。
SFのリアリティは、「超自然環境と作者の経験環境とのあいだ」の「緊張」[16]の度合いによって決定されるとして、スーヴィンは次のように書いている。
SF独特の存在様式のほうは、現実にフィードバックする、つまり虚構と現実とのあいだで往復運動が生ずる。SFのプロットや出来事を理解しようとするなら、まず、作者の現実規範や内包された読者の現実規範をひとまず忘れ、新たに物語によって実現した新事象のなかにどっぷりと漬かり、そのあと、新たに獲得されたパースペクティヴによって現実そのものを新鮮な目で見なおすべく、現実のほうに帰ってこなければならない。
スーヴィンのこの定義は、山野の言うスペキュレイティヴ・フィクションの特性を簡潔に言い当てているとともに、私たちがSFを読む際の心理の一端を突いているように思われる。
このような「往復運動」を通して開かれる小説世界は、山野にとって「町で出会った女の子との関係とかの次元でしか、ものをとらえていない」「私小説の伝統」から脱した――科学技術の世界に生きざるを得ない――「現代の人間ていうものを追求する文学」[17]として、やはりSFでしか表現できないものだった。
1978年、山野はサンリオSF文庫というレーベルの創刊に携わり、バラードやディックを筆頭としたスペキュレイティヴ・フィクションの作家を論じるだけではなく、その輸入・紹介にも注力するようになるが、創刊二周年を迎えた際に書かれた以下の言葉は、彼のSF観を端的に表すものとして重要である。
「編集顧問として、私はあくまで内容本位を貫き、時流に乗るよりも優れた作品、真に読者の求める作品を選んできた」と述べた後、山野はこう続けている。
これまでの作品で私が特に気に入っているのはT・M・ディッシュの「334」とケイト・ウィルヘルムの「クルーイストン実験」とスタニスワフ・レムの「枯草熱」です。いずれもジャンルSFの作家の作品ですが、内容は完全な現代小説で、しかも可能な未来を暗示し、現代の我々のアイデンティティを追求しています。それは我々自身の生き方と、現代社会のあり方に鋭く対位するものといえるでしょう。私は何よりもこうした作品を多くの人々に読んでもらい、シリアスに現代という科学技術の世界を考え直していただきたいと願っています。
以上のようなスペキュレイティヴ・フィクションの要諦をひとことで言えば、それは次のようなSFだと言えないだろうか。見果てぬユートピアの夢を憧憬するのでも、テクノロジーの加速度的な進歩を賛美するのでもなく、現実に対する内省を未来への想像力によって深めていくものであり、それは小説世界に生きている個人(人間)を中心においてなされなければならない営為なのだと[18]。
しかし、それゆえに問われなければならないのが、このような往還を可能にする「小説側の主体」だということは、改めて強調しておきたい。
本稿はここまで山野浩一の思想として「主体性」という言葉に注目し、そこから生まれるスペキュレイティヴ・フィクションの内実を確認しておいた。しかし、では、何故山野はこれほどまでに「主体性」を重視していたのだろうか。
4.「介護者」としての山野浩一
もちろん、その背景には「今なら東大へ入って官僚になったタイプ」だという父親への反抗心から、「自己形成」を遂げた[19]という山野の個人的事情も間違いなくあると思われる。
あるいは、60年代の政治の季節とその挫折を経験した世代(時代)の問題と言うこともできるかもしれない。たとえば、大学時代山野が作品を出した学生映画祭にて自身も映画を出品し、以来交友を深めた映画作家の足立正生は、当時を振り返って「安保後の私たちがどうあるべきかを問う必要があ」[20]ったと語り、その上で山野の映画の「絶対にへこたれないでギャグっていくパワー」[21]に、安保敗北後の「内容と感性」[22]を受け取ったという。また、1960年に山野が雑誌『映画芸術』へ投稿した「個性なき新しい波」という映画評論は、エネルギーの抑圧を追認的に描くだけの日本映画を批判するという内容であった。
このように、デビュー以前以後にかかわらず問われ続けていた山野浩一における「主体性」の問題であるが、しかし、一口に「主体性」と言っても、その主体は主体だけで成り立つことはできるのか、という疑問は拭えない。言い換えれば、自意識に苛まれながら自信を喪っていく人間に「主体を持て」と言ったところで、それはなんの養分もなしでは育たないのではないか。
ここまで見てきたように、山野は絶えず時流に抗した強い人間であるように映る。しかしその強さは、業界の外に自らの居場所があったがゆえに可能だったという事実は、やはり付言しておきたい。それは10年以上自費で発行していた『季刊NW‐SF』とそれを支えた仲間の存在、または「NW‐SFワークショップ」に集った弟子たちとの関係を基盤とするものだった。山野の「主体性」は、この関係を形成する人間的魅力の別名だと言っていいだろう。
その上で最後に、山野浩一の人間性を表す感想をひとつ紹介して稿を閉じたいと思う。山野の死後に追悼座談会に出席した小谷真理の言葉である。
山野さんといえば、わたし、親しくお話させていただくきっかけが介護でした。山野さんはご自身を昔革命家で今は介護をしているというふうにおっしゃられていたけど、どちらも人のためになることをする、という意味では一貫されていたのだと思います。
2007年頃より妻の介護生活を始めた山野は、その10年後に自身が癌を患って逝去するまで、晩年のほとんどの時間を彼女のために費やしていた(妻のみどり氏は山野逝去の翌年に他界した)[23]。
小谷が言うように「人のためになることをする」というのが山野の一貫した態度であったなら、私はここに彼の「主体性」の在処を見たい。周りの関係のなかで主体は支えられるが、一方で主体的であるからこそ他者にも開かれる。この自覚のもとで、彼は時代の趨勢に背を向け、自分の信条のみを貫いて言葉を残していた。少なくとも私はこのような生き方に、理想の批評家の姿を重ねたいと思う。
[1] 巽孝之編『日本SF論争史』勁草書房、2000年、7頁。
[2] 高橋良平「解説」、山野浩一『鳥はいまどこを飛ぶか』創元SF文庫、2011年、406頁。
[3] 「山野浩一自筆年譜」より。なお、ここでの「文化人」には三島由紀夫も含まれていた。「一SFファンのわがままな希望」(1963年)という文章を『宇宙塵』に寄稿するなど、SFの熱心な読者だった三島は、SFを「将来最も怖るべきジャンルと考へて」いるとの私信(全集未収録)をデビューしたばかりの山野に送っていたという。また山野も自身の「恩師」として、安部公房とともに三島の名前を挙げていた。石川喬司「三島由紀夫とSF」(『ユリイカ 特集SF』1980年4月)、および山野浩一「アヴァンギャルドとSF――三島由紀夫と安部公房」(『國分學 解釈と教材の研究』1975年3月)を参照。
[4] 匿名「宇宙塵10・11月号月評」、『宇宙塵』1965年11月、57頁。
[5] 山野浩一「読者欄への投稿」、『宇宙塵』1966年2月、128‐129頁。
[6] 高橋良平「解説」、前掲書、408頁。
[7] 「山野浩一自筆年譜」より。
[8] 山野浩一「日本SFの原点と指向」、巽孝之編『日本SF論争史』勁草書房、2000年、150頁。
[9] 同前、146頁。
[10] 同前、146頁。
[11] 同前、157頁。
[12] 山野浩一「総括! 新しい波」、『SFマガジン』1972年9月、21頁。
[13] 同前、22頁。
[14] 同前、22頁。
[15] ダルコ・スーヴィン『SFの変容――ある文学ジャンルの詩学と歴史』大橋洋一訳、国文社、1991年、103頁。
[16] 同前、43頁。
[17] 山野浩一「一番必要なものが無視されている」、『技術と人間』1983年7月、4頁。
[18] 山野のこうしたSF観は、昨今注目を集める、SF的発想による未来予測を企業やブランドの開発戦略に応用する「SFプロトタイピング」という手法や、テクノロジーの発展などをもとに資本主義を徹底させてそれを打ち破ることを夢見る「加速主義」という思想潮流に対する、ある種のカウンターとしても解することができるだろう。ここで仔細に検討することは控えるが、両者はともに楽天的な「進歩史観」を前提にする点で共通しており、その発想への批判的姿勢がなければ、SF作家(小説家)の役割は科学者や技術者と区別できないものになってしまう。ジュディス・メリル『SFに何ができるか』(晶文社、1972年)の言を借りれば、「超テクノロジーの加速度的生長の不可避さに対する、誠実な問いかけ」(29頁)が、現在のSF作家にも求められるだろう。詳しくは、岡和田晃「「未来学」批判としての「内宇宙」――山野浩一による『日本沈没』評からフェミニズム・ディストピアまで――(上)」(『季報 唯物論研究 第160号』2022年8月)を参照。
[19] 「山野浩一自筆年譜」より。
[20] 足立正生『映画/革命』河出書房新社、2003年、78頁。
[21] 同前、82頁。
[22] 同前、78頁。
[23] 個人ブログ「山野浩一WORKS」(https://yamanoweb.exblog.jp/)を参照。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
前田龍之祐(まえだ・りゅうのすけ)1997年東京生まれ。日本大学芸術学部卒業。「「ユートピアの敗北」をめぐって――山野浩一「小説世界の小説」を読む」(『SFマガジン』2020年8月)で商業誌デビュー。その他の著作に、「近代とSF――スペキュレイティヴ・フィクション序説」(『江古田文学』2022年4月)など。
次回は11月後半更新予定です。安井海洋さんが宮川淳を論じます。
11月末をもって袴田渥美が編集補助班から離れます。
今後の編集補助は赤井・松田が担当します。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
