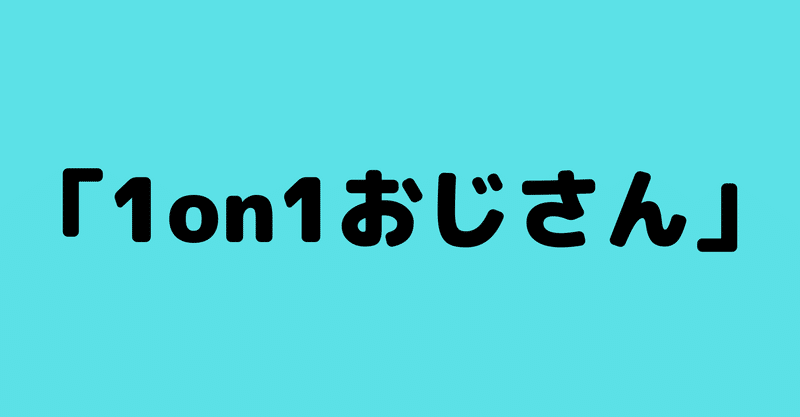
「1on1おじさん」
こんにちは。こがねんです。ファッションテック企業で「組織開発」をしています。
「組織開発」とは何でしょう。
これにはいろいろな定義がありますが、僕は「人の集まりが同じ目的に向かって協働するチームになるためのあれやこれやの働きかけ」くらいに考えています。
組織は単に人の集まりというだけでなく、属性・職種・役割・役職・部門はもちろん、スキル・マインド・価値観・感情・経験や、お互いの繋がり・関係性・距離感など、実に様々な要素の集まりなので「組織開発として求められる働きかけ」は多岐に渡ります。
主だったものだけでも、人事制度を整えたり、組織サーベイを実施したり、社内研修を企画したり、社内のコミュニケーションを活性化したり、マネジメントに悩む管理職のサポートをしたり、経営の対話の場をサポートしたり、キャリアに悩む社員の壁打ちをしたり、業務プロセスを改善したり、と幅広い取り組みをしています。
今日はそうした取り組みの中でも、最近、特に重視している活動、その名も「1on1おじさん」活動についてご紹介したいと思います。
ご紹介するのは、一見すると地味で地道で「これいったい何のためにやっているの?」と言われかねない活動ですが、実はこの取り組みがあるからこそ、先ほど挙げた他のすべての「組織開発の働きかけ」の精度が劇的に向上する、いわば「組織開発のセンターピン」といっていい取り組みです。
「1on1おじさん」。
この牧歌的な響きからは想像もできないと思いますが、すべての組織開発はここから始まり、ここに戻って来る、出発点であり、同時に終着点でもある、ゆっくりと、だが確実に組織に影響を及ぼしていける、持続的、かつ破壊的なイノベーション活動だと思っています。
では「1on1おじさん」とは、いったいどんな活動でしょうか。
「1on1」については聞いたことがある人も多いかも知れません。「上司と部下が定期的に行う対話の場」のことで、部下の目標達成や成長を支援する取り組みとして導入する企業が増えている施策です。「1on1おじさん」活動は厳密に言えばこの定義には当てはまらないのですが、「対話の場」としての型や見え方が「1on1」に似ていることと、言葉の親しみやすさからこの言葉を選んでいます。
そして「おじさん」についても聞いたことがある人が多いと思います(そりゃそうだ)。親戚の「おじ(伯父・叔父)」を親しみを込めて呼ぶ場合と、中年一般男性を呼ぶ場合に使われる言葉で、今回は後者の意味で使っています。(そりゃそうだ)
「1on1」についてはわかった、「おじさん」についてもわかった(というかわかっていた)、でも「1on1おじさん」と言われるとやっぱりなんだかわからない。そんな方がほとんどではないでしょうか。
それもそのはず、すべてはここまでもったいぶるだけもったいぶって、何か言っているようで何も言っていない文章を続けてきてしまった私のせいですので、いい加減、本題に入りたいと思います。「1on1おじさん」とは具体的にどんなことをしている活動なのかについて、ご説明したいと思います。
「1on1おじさん」活動とは
「1on1おじさん」活動。
やっていることは至ってシンプルで「全社員の皆さんを対象に、ランダムに1on1的な対話の場を入れさせてもらって、ガンガン話を聴いていく」というものになります。
役職は様々で、経営陣の皆さんから事業部長・部長・課長・メンバーの皆さんまで、幅広く聴いていきます。
部署も様々で、営業部門から企画・マーケティング・開発・デザイン・物流・CS・事業企画・コーポレート部門まで、こちらも特定の層に偏ることなくお話を聴いていきます。
自分が「この人にお話しを聴いてみたいな」と思った人にお一人30分ずつ、週に3~5名ペースくらいで、1on1(という名の対話の場)を実施させていただく。それだけです。
アポイントはGoogleカレンダーでお互いに空いている時間にドンドン入れていく、というこれまた非常にラフな感じでやらせてもらっています。
とはいえ、お相手の方の業務状況も正確にはわかりませんし、同じ会社の仲間とはいえ、入社して間もない僕のことを知らない方なことも多いので、カレンダー登録時のメッセージには簡単な自己紹介・この時間の意図・ご都合悪ければ即リスケする旨の3点を記載して、お相手の方の負担にならないよう細心の注意を払っています。
なんだ要は「社員ヒアリング」のことか、と思った方も多いかも知れません。
実際やっていることは社員の方へのヒアリングそのものなので、半分正解と言えるかも知れません。でもそれだけの活動ではないということをもう少しご説明させて頂きたいと思います。
「1on1おじさん」活動の目的
「1on1おじさん」活動がただの「社員ヒアリング」ではなく、組織開発における重要なアプローチであると言える理由は大きく3つあります。
1つは「組織を構成する人たちのことをちゃんと知る」という目的です。
組織とはそもそも人の集団であり、人と人との関係性の概念ですが、組織の出発点はどこまで行っても「中にいるお一人お一人がどういう人か」という点になります。
ポジティブな人、慎重な人、人当たりのいい人、コワモテの人、考える前に行動する人、行動する前にめちゃくちゃ考える人、本当に様々です。
そんな組織の中にいる一人一人の「人」を知る。つまり情報を収集するという目的というよりも、お会いすることそれ自体が大いなる目的になっている、そんな活動が「1on1おじさん」活動なのです。
まして時代はリモートワーク全盛期。
オフィスなど物理的な空間における偶発的な接触が減ってきた状況の中で、いわば意図したコミュニケーションしか起こらない世界においては、積極的に「一対一の対話の場」を創っていく、それ自体が非常に重要だと思っています。
2つ目に「見えない組織を可視化する」という目的があります。
組織開発の領域ではよく「群盲象を評す」という表現が使われます。目が見えない人たちが集まってそれぞれにゾウの一部を撫でて、脚を触った人が「これは柱だ」と言い、耳を触った人が「これは団扇(うちわ)だ」と言うけれど、誰もそれがゾウであることには気が付かない、という例えで、組織の中の人が組織の全体を見渡すことの難しさをよく表しています。
ただその一方で、組織とは「組織の中にいる人たち一人一人からどう見えているか」という「一人一人の真実」の集積で見えてくるもの、ということも同時に言えると思っています。経営者から見えている組織、ミドルマネージャーから見えている組織、メンバーから見えている組織、人事から見えている組織。それぞれ全体像は見えていなくても、見えている範囲では重要な真実をとらえていると言えると思います。
「1on1おじさん」活動は、そんな一人一人の中にある「小さな真実」を集めて行って、「誰にも見えない組織」を「見える化」していく活動とも言えるのです。
そして、こちらもリモートワークの影響で「組織の見えない化」は留まるところを知りません。一人一人の声を集めていく活動は「組織の見えない化」にブレーキをかけ「組織の見える化」を加速していく上で必須のアクションとも言えると思います。
最後に「組織の中にいる全員で組織そのものを創っていく」という目的があります。
組織開発の分野でよく使われる表現に「いまここ」という概念があります。組織には「いまここで何が話されているか」「いまここで何が起こっているか」という「目に見えやすい部分」(専門用語で”コンテント”といいます)と、その水面下の「いまここでどんな感情が渦巻いているか」「いまここでどんな考えや価値観が交錯しているか」という「目に見えづらい部分」(”プロセス”といいます)があって、関係者全員でこの「2つのいまここ」に目を凝らすことで「いまここ」にある組織の状態に気づき、「いまここ」にある組織の課題を認識し、「いまここ」から組織のあるべき姿をイメージすることで、組織はよりよい状態に近づいていく、という考え方です。
「1on1おじさん」活動は、この「いまここ」の組織状況を多くの人の目線で語ってもらうというだけでなく、語っている人自身に「いまここ」の組織状態に気づいてもらい、組織課題を認識してもらい、組織のあるべきを言語化してもらうことで、「語り合っている組織そのものに一歩ずつ近づいていく」という力学を働かせることができると考えています。
組織開発の領域ではこのことを「Words create world(言葉が世界を創っていく)」という言葉でも表現しています。まさに「今日、口々に語られた組織の状況」こそが「今日の組織」を創っているし、「今日、口々に語られた組織のあるべき姿」こそが「明日の組織」を創っていく、という考え方です。
さて、このあたりになってくると、サンドイッチマンばりに「ちょっと何を言っているかわからない」という方も出てきちゃうかもしれませんが、ニュアンスというか雰囲気というか空気感みたいなものが伝わればいったんそれでいいかなと思っています。
(このあたりはもっと丁寧に語るべき、語りたいテーマだなと思ったので、本記事の加筆修正や別記事でも色々お伝えしていきたいですし、皆さんともっと語り合いたいなと思っています)
「1on1おじさん」活動の実施方法
さてさて、ここまでで「1on1おじさん」活動がどんな活動で(WHAT)、なぜやっているのか(WHY)はお伝えできたと思うので、どうやっているのか(HOW)についてもお伝えしていきたいと思います。
実際にアポイントが取れて、1on1のその日を迎えたら、具体的にどのように30分間を進めているのか、そのあたりの説明となります。
ヒアリングしているのは超シンプルに2点だけです。
①「どんな方ですか?」
②「どんな会社に見えていますか?」
この2点だけ。「おいおい、それだけかい」という声が聞こえてきそうなのでもう少しご説明します。
①「どんな方ですか?」は、「これまでのキャリア」「入社動機」「入社後の経歴」「仕事の流儀」あたりを中心に、話が盛り上がったら「ご出身」や「ご趣味」などプライベートのことも教えてもらうこともあります。
②「どんな会社に見えていますか?」は、まさにこちらが本題になるのですが、「会社の中の人や組織に関することで『良いな』『素敵だな』と思っている点」と「会社の中の人や組織に関することで『課題だな』『もっとこうなるといいのにな』と思っている点」を教えてもらいます。
そして、このシンプルな2つの質問は、単純なようでいて、実はわりと考えて構造化されている仕掛けになっています。
1点目の質問(どんな方ですか?)で、聴き手である僕は「相手の視点」「相手の立場」「相手の価値観」を手に入れることができます。いわば「組織を眺めるカメラ」を増やすことができる、ということです。
そして2点目の質問(どんな会社に見えていますか?)で、聴き手である僕は「組織の強み」「組織の課題」を知ることができるわけですが、この時に1点目の質問が効いてきます。先に「相手のカメラ」を手に入れていることで、裏側にある相手の方の「感情」「価値観」「経験」を含めて「意見」や「課題意識」を聴くことができる、というわけです。
1点目の質問で「組織を観る角度」を手に入れて、2点目の質問で「そこから見える真実」を手に入れる、という2段構えの問いかけで、組織を多角的・立体的にとらえることができるだけでなく、特定個人が持つバイアス(偏り・偏見)に影響され過ぎることなく組織情報を集めていくことができる、というわけです。
いかがでしょうか。シンプルな2つの問いかけから得られる情報が、組織開発にとってどれだけ重要なものになるか、お伝えできたでしょうか。
また、ここまでの説明でこの「1on1おじさん」活動が「誰にでもできる活動」であると同時に「効果的な組織開発アプローチ」であることが少しでもお伝えできていれば嬉しいです。
「1on1おじさん」活動を続けると何が起こるか
前述の2つの質問をし続けて、お話をお聴きした人の数が増えてくるとどんなことが起こるか。
僕はいまの会社に入社して10か月の間に150名以上の方にお話を聴いています。現在1300名の会社なので10%強です。これくらいお話を聴き続けるとなかなか興味深い現象が起こってきます。
まずは、一定の割合の方のお話を聴き続けることで、ここまでお話ししてきたように「組織の中の人を知る」「組織を見える化する」「組織を創っていく」感覚が積み重なっていきます。
経営陣よりも他の人事関係の誰よりも現場のマネージャーよりも、誰よりもこの会社の人と組織を知っている状態になってくる。なので当然、人と組織の良いところも課題も最も正確に語れる人間になってくるという大きな収穫があります。
もう一つは、「自分自身が会社そのものになっていく感覚」があります。
「Aさんが言っている」「Bさんが言っている」・・・というN=1の意見が自分の中にどんどん降り積もっていくことで個人としての誰がではなく「この会社がそう言っている」「組織の声としてこういう思いが聴こえてくる」という感覚になってくるのです。
最近の組織開発のトレンドでは「組織は生命体である」という考え方があります。(話題になったティール組織もこの考え方ですね)
1つの生き物としてとらえて、その進化・成長を支援していくつもりで働きかけないといけない、という意味ですが、僕の場合は「僕自身が組織という生命体そのものになっていく」という感覚を味わうことで、「組織は生命体である」を実現(体現?)していっているところがあるという感じになります。
ちょっとスピリチュアルな表現が入ってしまいましたが、実際に自分の経験として体感していることなので、受け止めていただけるかどうかは分からない中で、いったん書いちゃってみました。
「1on1おじさん」活動のアウトプット(成果物)
ただ、もう少しドライな話をすれば、「1on1おじさん」活動は、僕はもちろんのこと、お話を伺う社員の皆さんの業務時間(=人件費)を使わせてもらっている取り組みとなりますので、もう少し具体的なアウトプットの話もしたいと思います。
僕がこの取り組みからこれまでにアウトプットしてきた成果物は大きく3つです。
①「組織のGood・Motto」
②「組織の人間関係相関図」
③「組織のカルチャーマップ」
いずれも現職の内情に触れる内容なので実物をお見せすることはできないのですが、それぞれ概要だけ共有させてもらいます。
①「組織のGood・Motto」はその名の通り「組織の良いところ(Good)」と「組織の課題(Motto)」をリストアップしたものです。どんな人たちがどんなカルチャーをつくっているか、会社が掲げている標語は組織に行き渡っているか、戦略は実行に移されているか、など様々な観点で「Good」「Motto」を洗い出した資料を作成しました。ヒアリングN数が100名を超えたくらいの時に経営に報告したところ代表から「まさにこういう状態だよね」というフィードバックを受けることができました。
②「組織の人間関係相関図」はテレビドラマの登場人物紹介に使われるような人と人との関係性を矢印で繋いで図示したものです。個人名ではなく部署名・役割名を人型のピクトグラムで表し、連携状況や衝突関係を矢印やコメントで追記して組織の問題として可視化した資料を作成しました。こちらも経営のボードで議題として扱われ、実際の組織編制や最適配置などに活用されました。
③「組織のカルチャーマップ」はMISSION・VISION・VALUEや創業来大切にしてきた価値観など、これまで語られてきた「組織の言葉」を整理統合して、「組織として何を目指すか」「どんな人と組織とカルチャーを目指すか」「それを支えるインフラをどう整備していくか」「そのために社員一人一人がどういう存在であるべきか」を階層ごとに表現した一枚絵をつくりました。こちらはグループ企業内のイベントで他社の参加者に紹介したり、現在進めている人事制度企画の判断材料の1つとして活用が進んでいます。
「1on1おじさん」活動は、相応にコストのかかる取り組みなので、きちんとアウトプットに繋げることが重要だと思っていますし、そのゴールを意識しているからこそ、多くの方に胸を張って協力をお願いできると思っています。
それ以上に、ただのヒアリングで終わらせてしまうにはもったいない、それくらい重要な情報が集まってくる活動ですので、進める中で「何かしらアウトプットしたくなる」「どうにかして可視化して共有したくなる」そんな活動であるとも言えると思います。
おそらく、ここに挙げた3つのアウトプット以外にももっともっと可視化・共有の方法はあると思いますが、それはまた別の機会にお伝えできればと思います。
「1on1おじさん」のまとめ
さて「1on1おじさん」いかがでしたでしょうか。お役に立つ情報になっていたでしょうか。なっていれば幸いです。
最後に、この「1on1おじさん」という言葉にまつわる裏話を2つご紹介したいと思います。
1つは、僕が今の会社に転職したときに「人材開発のプロ」「1on1のプロ」と目されていたことで「こがねんさんと言えば1on1」というタグ付けがされていたということです。
そのため「1on1というキーワード」と「自分の存在」を繋ぎこみやすかったというメリットもありましたが、それ以上に「1on1」という仕組み・仕掛けを使って会社を良くする責務が、僕にはあったということです。
その責務を果たすために、まずは「1on1の目的や手法」を整備したり管理職向けの「1on1研修」を実施したりして「1on1の伝播浸透」をすることが会社からは期待されていたのですが、それだけではなく、「1on1が持つ人材開発・組織開発パワー」を最大限に解き放ってみたい、それを証明してみたい、そんな想いが僕の中にあったことも、この「1on1おじさん」活動に繋がっているんだと思います。
そしてもう1つ、実はこの「1on1おじさん」というキーワードは、もともとはわりとネガティブな意味で使われる言葉だったという裏話です。
前職企業では「1on1(≒人材育成)が大好きな管理職」とりわけ「1on1(≒人材育成)さえやっていればマネジメントできてると考えてしまう管理職」を指して「そうなってはいけないね」という反面教師的な意味で「1on1おじさん」と言っていました。
この思い自体は今も変わっておらず、人材育成にだけフォーカスしてしまう管理職を増やしてはいけない、1on1がマネジメントの逃げ場になってしまってはいけない、と考えています。
一方で、「1on1がいいものである」「1on1に親しみをもってもらいたい」「1on1には多くの可能性がある」ということを今の会社でもっともっと伝えていきたい、そんな思いもある中で、ふと思い出したこの「1on1おじさん」というキーワードはその目的にドンピシャでハマる、と考えて、使ってみることにしたという経緯があります。
冒頭でも書いた通り、1つの組織がいいチームになっていくために揃えなければいけない要件や求められる働きかけは果てしなく多いです。
「どんな目的で集まっているか」「どんなゴールを目指すのか」「どんな戦略を進めるのか」「どう役割分担するのか」「どんなルールとフローで仕事を進めるのか」「どんな関係性を築いていくのか」「いま組織はどんな状況か」「どんな組織課題があるか」「どんな組織を目指していくべきか」・・・。
そして、こうした「組織の成功要件」を揃える大前提として避けて通れないのが、中にいる一人一人の人が、いまどんなことを考えて、何を願っていて、どんなジレンマを抱えているのか、についてアンテナを張って、そのエネルギーを集めていくことだと思っています。
組織開発のフレームワークは数多くあれど、その手前で「組織が一人一人の人の集まりである」という当たり前の大前提に立ち続けること。そして、少しずつ「同じ目的に向かって協働するチームになっていく」こと。最終的には、その向こう側にある「1つの生命体になっていく」こと。そのための基本動作が今日お話しした「1on1おじさん」活動になると僕は考えています。
繰り返しになりますが、この記事でお伝えしたことに難しいことは一つもなかったと思いますし、いつでも、誰でも、どんな立場でも始められる取り組みだと考えていますので、この記事が皆さんの組織開発を良いものにしていくヒントになっていればこれに勝る幸せはありません。
皆で、いい組織をつくっていきたいですね。
それでは、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
