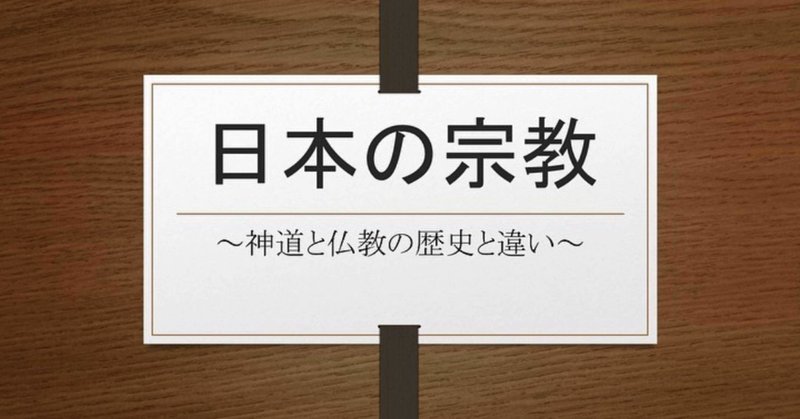
神道と仏教てどう違うの?

日本には宗教が2つあります。まずは仏教。
仏教は三大宗教のうちの一つな程、信者が多い宗教です。中国っぽい雰囲気ですが元々はインドで生まれました。ブッダは貴族出身でしたが当時流行っていたバラモン教の階級制度(カースト制)に疑問を抱き、皆が救われるような宗教を生みだしました。それが仏教で、その後インドから中国を経て日本へ広がっていきました。ちなみに日本に広がる頃は仏教はインドっぽい雰囲気より政治で使えて、自分以外の人々を救う形(大乗仏教)に変わってました。現在はインドはヒンドゥー教の方が多く、中国は共産主義によって宗教は広く否定されています。

次に神道です。
神道とは日本にもとからある宗教です。神道は2種類あります。
まずは自然崇拝です。これは自然を神様とします。なので雷や嵐を神様の怒りと考え、雨は神様の恵みとして受け取ります。これはおばあちゃんやおじいちゃんに言われたことがある人もいるんじゃないでしょうか?また食べ物や飲み物も自然からの恵みとして考えるので、「いただきます、ごちそうさま」を食前 食後に言います。これは馴染み深いですね。
もうひとつは人や物を崇拝します。これは人や物にも神様が宿っていると考えます。物に神様が宿っているので大切に扱いましょうといった意味なんでしょうね。つくも神という神様も有名ですね。
一方人はというと神道では人すらも神様になってしまうのです。日本史では菅原道真、平将門などは怨念を恐れて人々は天満宮に祀り、首塚に祀ったりしました。徳川家康などは東照宮に祀られ、繁栄を祈っています。もっとわかりやすい例としては祖先や亡くなった人に祈ります。子供に対して亡くなった人というのは「星になった」と表現されます。これは亡くなった人=自然物=神様として表現しているとされています。

では仏教と神道はどう違うのでしょう?
たくさん違いはありますが大きな違いは「お酒」です。神道ではお酒は飲んでもいい!仏教ではお酒は飲んではいけない!とされています。
これは神道においてお酒は神様と共に楽しむもの、つまり私たちが飲めないものを神様に飲ませるわけにいかないという考え方があります。一方で仏教ではお酒は神様専用の飲み物とされ、人が飲むことは禁止されています。
これを通じて仏教は人と神様の距離が遠く、神道は人と神様の距離が近いといえます。

仏教と神道の歴史は神道の方が古いですが、飛鳥時代に仏教が日本にやって来て以来、合体します。神道と仏教を混ぜて考えることを神仏習合といいます。大化の改新では神宮寺(神社+寺)が建てられたりします。


上記のスライドを見て分かるように鎌倉時代の前後で神道より死後を重視する仏教を庶民は惹かれていきます。しかし、鎌倉時代を経て仏教も神道も同じように愛されることになります。
そして江戸、仏教や神道より中国からの儒教を重視するようになります。庶民的な仏教や神道より年上などを敬う儒教の方が幕府にとって支配に使いやすかったのでしょう。

徳川家康は一方で仏教を使って庶民を管理します。
寺の上下関係を決定し、その寺の周辺地域に住む人々の葬式や結婚式などのイベントをその寺に任せることでその周辺地域を寺を用いて管理するということを成功しました。
また皆が仏教を信じるようにキリスト教を弾圧したりもしました。
そして、明治になって仏教は排斥され、天皇の宗教でもある神道が重視されることになります。
宗教は歴史を知るために必須です。また日本の宗教は外国の宗教より難しいですが、分かると一層学びが深まるでしょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
