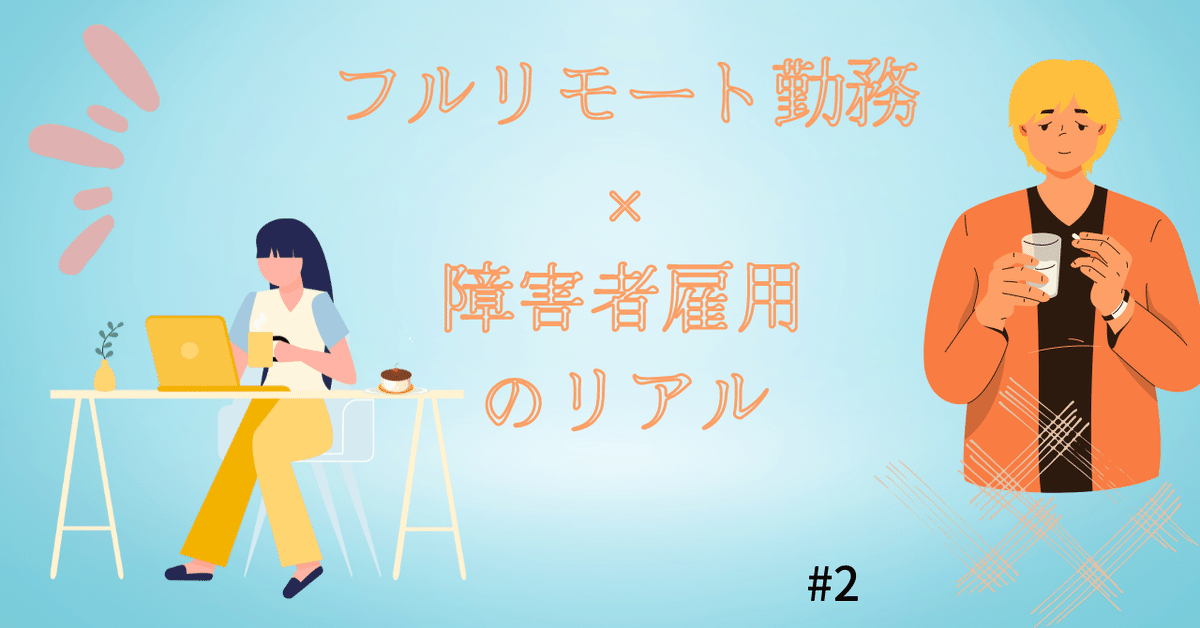
障害者雇用におけるフルリモート勤務に必要なこと。
弊社で採用しているフルリモートフルフレックスという働き方。
前回の記事では、場所/時間の制約という「障壁」を取り除いた結果として、創業時にこの働き方を採り入れ、フルフレックスでは成功を収めているというお話でした。
今回は、フルリモート勤務の運営でうまくいったこと、困ったことのリアルをお伝えします。
↓各記事へのリンクはこちら
(前編)フルリモートフルフレックスというバリアフリーの形
(後編)障害者雇用におけるフルリモート勤務に必要なこと。
(執筆:ミッションパートナー ちひろ)
フルリモートは可処分○○を増やしてくれる
ーフルフレックス勤務が成果を最大化しやすいというお話がありましたが、フルリモートにしたのは、出社型だとフルフレックスにしづらいということでしょうか?
(成川)
いえ、フルリモートそのものにメリットがあると考えています。
僕の感覚として、単位業務時間あたりのアウトプット量/質は下記の序列のような気がしています。
全員同じ場所にいてすぐに話せる、個人の好みに合わせて環境(音、光、匂い)を変えられる
全員リモート
出社/リモート混在
1は実際にはなかなか難しいですね。
それに、業務時間には含まれないけれど、プライベートとも言えないような、通勤、身支度、休憩するための移動などの時間を考慮すれば、序列は2→1→3となるんじゃないかなと思っています。
さらには、優秀な人材を獲得したいなら、可処分所得、可処分時間、可処分精神をどれだけ提供できるかで勝負しなければならないため、2の全員リモート一択になります。
3は、現時点では明らかに無し、だと思っています。
もし全員出社ができないのであれば、2を選択し、かつ量/質向上のためにリソースを投入した方が良い。
ーコロナ禍では、現実案として3を選んだ企業も多いですよね。リモートにできない社員との不公平感を避けるため、そもそもリモートワークを導入しなかった企業もあります。
フルリモート勤務は、工夫と信頼が必要
ーフルリモートで実際に一年間運営してみてどうでしたか?
(成川)
日々の業務の進捗に関しては、社員に書いてもらう日報や個人面談でしっかり追えているので、思った以上に透明化されています。
業務時間中にずっとビデオ通話をつないでいる企業もありますが、僕はそんな必要はないと思っています。
会社が社員に求めることは、「そこに8時間座っていること」ではなくて、「成果を出してもらうこと」なので。
1日で見える成果が出なくても、今日はどんなことを考えて何を調べて、どう手を動かしたのか。
ここ数日で煮詰まっていることは何か。
そういったことをきちんと報告/共有してもらえれば、顧客との調整や納品のスケジュールも立てやすくなる。
ずっと隣で見張っていなくても不安感はないです。
(阿渡)
不安というと、連絡が途絶えたりすると別の意味で不安になります。
例えば日報が出ていない社員がいるとします。
単に忘れてしまっただけなら、こちらからリマインドして出してもらえばいいだけです。
でも、そうじゃないかもしれない。
体調が急変したのかもしれない。
ちゃんと生きているだろうか。
オンラインチャットで連絡が取れなければ、電話をする。
それでもだめなら、家まで会いに行かなくてはならないような状況かもしれない。
だから、日報が出ないだけでもすごく心配になりますね。
フルリモートのデメリットをあえて挙げるとすれば、社員の異変に気づくのが遅れることかもしれません。
毎日顔を合わせていてもわからないことはありますが、少なくとも目の前にいるという安心感はあります。
限界を超えてしまう前に、少しのストレス負荷でも本人に相談してもらえるような信頼関係を築いていきたいなと思っています。
ーそのお話を聞いて、精神/発達障害者雇用が難しいと言われる意味がわかった気がしました。理屈だけではないマネジメント面での大変さは、健常者がマジョリティの職場とは次元が違いますね。
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
