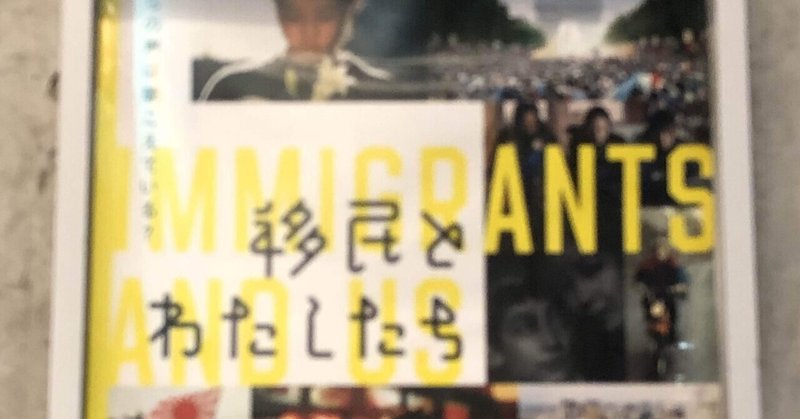
人間らしさとは何か。『ル・アーヴルの靴みがき』を見てきた
先日ユーロスペースで、アキ・カウリスマキ監督の映画『ル・アーヴルの靴みがき』を見てきた。
この映画は、「移民とわたしたち」というテーマで開催された日芸映画祭のラインナップのひとつ。現在、日本ではこの映画の上映権が切れているため、学生さんがドイツの権利元と直接交渉し、このたび上映されることとなった。また、貴重な35㎜フィルムでの上映であること、カウリスマキ監督の最新作が12/15に公開されることなどもあり、客席は大入り満員だった。
『ル・アーヴルの靴みがき』はフランス北部の港町ル・アーヴルを舞台に、質素に暮らす老夫婦と不法移民の少年との短い交流を描いた物語だ。
以下、ラストを含むネタバレ感想になるので、ラストを知りたくない方、まっさらな状態で本作を見たい方は読まないようにしてください。
靴みがきで生計を立てるマルセル老人は、妻のアルレッティと愛犬ライカと暮らしている。近所のお店にツケ払いでパンや野菜を買い、食前に行きつけのバーで一杯飲む生活は、貧しいながらそれなりに満足しているようにうかがえる。しかし、しっかり者のアルレッティは自身の体調の異変に気づいていた。病院で診察を受けると不治の病と宣告されるが、医師にマルセルには伝えないよう懇願する。
そんな折、港ではコンテナの中にひそんで不法入国を試みるアフリカ系難民が警察に検挙される。密航者のひとりであるイドリッサ少年は隙をついて逃げ出し、街へ消える。
マルセルと逃走中のイドリッサが偶然出会ったことから、物語は始まってゆく。
『ル・アーヴルの靴みがき』は、今回の映画祭のラインナップの中では明るいコミカルな作風であるものの、コンテナを警察が開くシーンは、移民を取り巻く状況が伝わってくる影の濃さがある。この影の濃さと移民たちの表情に、少なからず私はショックを受けた。この影の濃さを、表情を、私は、日本人の大半は、知らない。
イドリッサと出会ったマルセルは、靴みがきの技を教え、イドリッサの母がいるイギリスへなんとか彼を送り出そうと奔走する。マルセルの周りの人たちも彼らを援助し、金策や警察へのごまかしに協力する。
彼らがしていることは、法の上では悪だ。登場人物たちもそれぞれ薄暗い事情を持ち、清廉潔白な市民ではない。
なのに、彼らがしていることを、悪とは思えない。
悪人なのに、悪人がいない映画なのだ。彼らの心は豊かで、間違いなく良心ある強い市民だ。
移民というワードで思い出すのが、ウィシュマさんの入管での事件だ。
入管の職員としては、法に従っただけという言い分なのだろう。そういう意味では善を行おうとした、とも言える。しかし、やっていることはとても残忍だし、事件の後の対応も非人道的といわざるをえない。
悪いこととわかっていながら、目の前の人を救おうとする。
法に従うために、法に従わない目の前の人を人として扱わなくていいと考える。
『ル・アーヴルの靴みがき』とウィシュマさんの事件は対極をなして、どちらも「人間らしさとは何か」と私に問いかける。
『ル・アーヴルの靴みがき』はファンタジーだと言う人がいる。ラストは確かにファンダジーだろう。
私は、ラストの奇跡は少年と握手をしたからではないかと思った。
何かがちょっとうまくいけば、あるいはいかなければ、少年が妻と会うことはなかった。人々の優しさが少年と妻を引き合わせた。
少年はもしかしたら、もとからそういうチカラ(超能力的な)を持っていたのかもしれない。もしかしたら、そのチカラは少年が生まれ育った土地でも発揮していたのかもしれない。
しかし、そういうチカラを持っていても、移民せざるを得ない状況というものをどうすることもできない。ある一人の超常的なチカラで解決できるほど、社会問題は単純ではないのだ。
マルセルたちの行動のような優しさは「人間っていいな」と思わせる。解決しない問題の中に、その「人間っていいな」が点在しているのだろう。それが少しでも大きな円になってゆくよう、私の中にもあるだろう良心の声を聞く冷静さを持ちたいと思う。
最後に、日芸映画祭について。
日芸映画祭は毎年12月上旬に開催されている。テーマの選定、企画、上映交渉、運営まですべてを日芸映画学科の学生さんが担う。上映ラインナップはどれも興味深いものばかり。学生さんたちが作ったパンフレットを読むのも楽しみのひとつだ。
私は4年前から映画祭の中のどれか1本を見るようにしている。どれもおもしろかった。
来年もたぶん開催されるだろう。どんなテーマになるのか、どんな映画に出会えるのか、楽しみにしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
