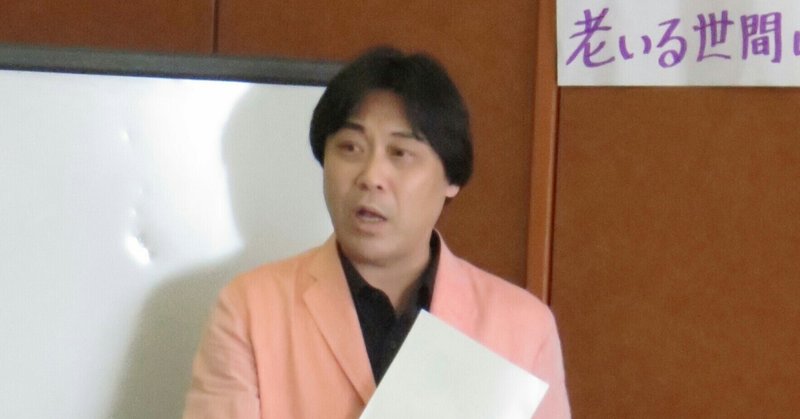
人生100年をこう生きるッ!
社会福祉士の山崎宏です。今回は、私の老後観のお話です…。
気づけば、この仕事をしてもうじき四半世紀になります。社会人デビューして15年を外資に捧げた後、縁あって相談援助の国家資格を取得しました。当時はずっと合格者が(受験者数に対して)30%を切っていたので、毎年95%以上の合格率の医師を羨望の眼差しで見ていたものです。「だれでも合格るんだな、医者の国家試験って」と、医学部にいった友人たちに負け惜しみを言ってたものでした。それがつい先日、2024年の社会福祉士国家試験の合格率が60%近いと知って、ロートルは複雑な思いで受け止めています。
社会福祉士になってからは、百貨店で、病医院で、さまざまな人たちの相談に応じてきました。2012年からは独立してすべて自分の思ったように動いて今日に至っています。結局、50歳を過ぎたら、会社や上司の意向に合わせることがストレスになったんですよね。他にも、来る日も来る日も通勤ラッシュに揉まれる不快感。思うように動いてくれない同僚と部下への唖然感。稼いだお金の殆どを組織にピンハネされる不条理。好きでもない人たちとの人間関係による疲弊…。
今になって思えば、歳を取ったんでしょうね。若い時分は我慢できたことが、カラダ的にもココロ的にも耐えられなくなった…。これが老いるということなのだと、今ではよ~くわかります。
人生100年時代となって、これを四半世紀ごとに区分けすると、現在の私は第3四半世紀のなかを生きています。生まれてから最初の25年は『自分さがし』、つぎの25年は『自分づくり』、そして今は『自分のこし』の真っ只中だと思っています。なので、悩める人たちの暮らしの安定と充足に貢献するという、社会福祉士の本然をひとりでも多くの若い世代に引き継ごうと躍起になっています。
とはいえ、第3四半世紀は75歳まで続きますから、『自分のこし』ばかりでなく、人知れず『自分づくり』を継続しています。どうあがいても肉体は朽ちていきますから、アンチエイジングというか、健康の維持には固執しています。最近の言葉だと、フレイル予防ですかね。
あさ行動を起こす前に、ストレッチ、スクワット、スキッピングジャンプを続けています。3S体操と言っていますが、ほんの10分から15分。フリオの『キホーテ』、ジグソーの『スカイハイ』、『ロッキーのメインテーマ』を流しながら、ベッドルームで取り組んでいます。人には絶対に見せることのできない時間帯です(笑)。
社会福祉士の仕事は、オンサイトでの実務代行以外は、ほぼほぼデスクワークです。特にコロナ以降は、ホント、無益無用の外出がなくなりました。電話やメールやLINEで相談を受けるのも、カウンセリングをするのも、関係者と折衝するのも、ぜんぶバーチャルです。これらがなければ、好きな本を読もうが、好きな動画を見ようが、考え事をしようが、居眠りをしようが、完全に自由です。これは素晴らしいことです。
三度目のハタチを生きている私ですが、人生でいちばん価値あることは、思考も行動も、時間もお金も、すべて自分でコントロールできることだと思っています。組織に属していれば絶対にありえないことです。もっと言えば、仕事も顧客も自由にできるということになります。誤解されると困るのですが、要はイヤな仕事はしなくていいし、イヤなお客さんとは付き合わなくっていいということです。つまりストレスがほぼなくなるわけですから、年齢がいったらこれっきゃないと思うのです。同年齢でいまだに毎日オフィスに通い続けてる人もいますが、尊敬せずにはいれませんね。立派です。
話を『自分のこし』に戻すと、この第3四半世紀に入ってから、私は既に3つのことに取り組んでいます。それは、(老い先を託す相手への)おカネの引継ぎと、生前葬と、健康維持です。もっと具体的でわかかりやすく表現すれば、非課税贈与と、還暦祝賀パーティーと、認知症予防。これらはみな社会福祉士としての仕事にも絡む話ですが、長生きしなければならない時代ゆえの、あるべき終活と言っていいでしょう。
終活の大目的は、『大切な人たちに迷惑をかけないようにしておくこと』と、『最後のさいごまで自分の人生の主役で在り続ける(舵を取り続ける)こと』です。
もう少し具体的にいうと、前者は、エンディングまでの想定リスクごとに方針を決めて、老い先を託す相手にそれを伝えて、それを実現してもらうのに必要と思われる予算を渡しておくこです。まずは自分なりの尺度で人事査定のようなことをして老い先を託す人を決めて、介護と医療と葬儀の方針を決めて伝えて、ムダな税金を納めなくていいようにコマメにおカネを渡していくんですね。
特に、葬儀や祭祀関連事務については、こどもたちの合意を得た上で、一切やらないことにしました。私のリアルなエンディングにおいては、遺族は何もしなくていいということです。いわゆる直葬&ゼロ葬の段取りを済ませてあります。あと、墓じまいも。これで喪主をはじめとする遺族はもちろん、弔問客として呼ばれる人たちも面倒から解放されます。諸々の法事もなくなります。スムーズにこうできたのは、私の父の代からお墓を分けたことと、私がひとりっ子だったことが大きかったですね。
代わりに、還暦・喜寿・米寿にはパーティーをやります。これを生前葬として位置づけているわけです。当然ですが、葬儀社のプランみたいに、死に装束をまとって棺の中に入るようなことはしません。明るく楽しく飲んで食べて歌って踊ってどんちゃん騒ぎです。
後者は、医者や弁護士やケアマネや後見人や、好きでもないし信頼もしていない誰かに制約を受けることなく(健康寿命を最大限延ばして)人生100年を謳歌することだというのが、私の持論です。そのためにはフレイル予防です。筋力と認知機能と社会接点を維持することです。具体的方法論が、前述の3S体操であり、新しく学んだ知識や情報を人に伝えることであり、老いらくの恋と仕事を続けることです。
こんなPDCAを繰り返しながら生きているのが、私の第3四半世紀なのです。で、いよいよ第4四半世紀になると、いわゆる後期高齢者の仲間入りです。この人生さいごの25年は、『自分さがし再び』です。それこそ天からのギフトだと思って、肩の力を抜いて、Reborn to the future です。75歳の社会福祉士としての自分にできることを継続するのか、まったくちがう何かにトライするのかはまだわかりませんが、自分が生かされていることの意味を、その時までに見つけられたらいいな~と思っています。
こんなところでしょうか、私の老後観は…。
GWに同窓会をやりましたが、正直な感想は、「歳は取りたくないよな~」でした。私なんぞ、明らかに若い方でしたからね。それもひとえに、人生の折り返し地点からずっと、ストレスフリーの生き方をしてきたからかもしれません。
読んでくれたみなさんも、ご自分の老後観について、ちょっと考えてみてはどうでしょうか。今回のお話が、そのきっかけになればうれしい限りです…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
