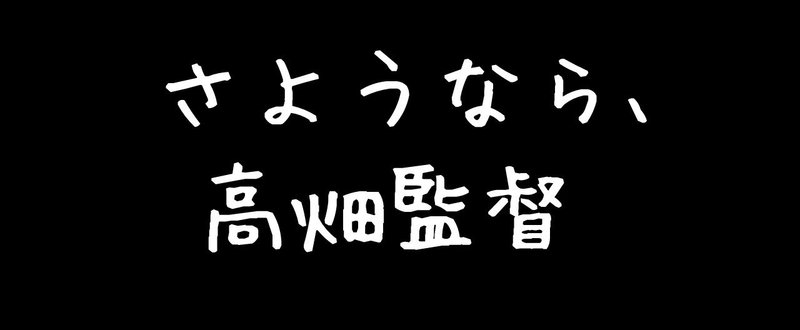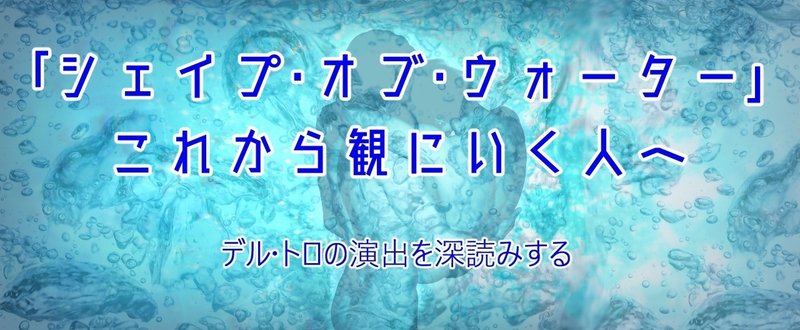#映画レビュー

2018年最もオススメしない映画『デヴィッド・リンチ:アートライフ』
『デヴィッド・リンチ:アートライフ』を鑑賞してきました。はてしない闇を湛えた創造者、映画監督兼画家のデヴィッド・リンチ。心酔しているんです。私にとっては『バーフバリ』観てる場合じゃないんです。いや、『バーフバリ』も楽しく観ましたが、あれは一過性の楽しさ。リンチの映画は今の自分を形作っている何かの、かなり奥のほうにまで染み込んでいるのです。 このドキュメンタリー映画は、彼を愛する人々へのボーナス・トラックです。ですので、この映画を人に薦めるつもりは全くありません。リンチに思い入れがない人が観ても仕方ないし、リンチ・フリークはわざわざ薦めなくても勝手に観に行きます。 作品中にて、『0.9502秒前に撃たれた男』『ボブは全く知らない世界の中で自分を見つける』『彼女は傷つき家に歩いて帰ると誰かがいた』などといった、リンチによる妙なタイトルの絵画が色々登場します。また、リンチの語る幼少期のエピソードも心に残りました。 「街に行ったとき、向こうから深い闇がやってきた。それは巨大な裸の女だった。彼女は泣いていた。なんとかしてあげたかったが、私にはどうにもならなかった…」 正直、興味のない人にとっては、ただただ気味の悪い映像が次々と流れる、拷問にちかい88分だと思います。リンチ作品はホラーにも、サスペンスの範疇にも収まりません。造られた恐怖やスリルを語る作家ではないのです。 青年のころのリンチは、地下室にこもって果物や小動物の死体が腐ってゆく様子をずっと観察していました。その体験が、彼の様々な作品に投影されています。飾ることのない、剥き出しの死と生の姿を垣間見せてくれる存在なのです。 微笑ましいシーンもあります。アトリエにて、幼い娘さんとふたりで創作活動にいそしむ姿。こんな幼児が闇の深淵に触れて、情操教育的に大丈夫か?という疑問は残りますが。 あと、この映画の監督には、ジョン・グエン、リック・バーンズ、オリヴィア・ネールガード=ホルム、という人物が名を連ねていますが、このうち、リック・バーンズについては「名前は偽名で、正体は明かせない」とのことです。よくわかりませんが、この不穏な気配はいかにもデヴィッド・リンチのドキュメンタリー、という感があります。 今回の映画を観て、最近、自分の中のデヴィッド・リンチ成分が欠乏していることを実感しました。あらかたの作品を見直しましたが、まだ足りません。願わくば、リンチの短編映像をどこかの劇場で公開して頂けないものでしょうか。餓えているのです、闇に。 More dark! 『デヴィッド・リンチ:アートライフ』監督:ジョン・グエン、リック・バーンズ、オリヴィア・ネールガード=ホルム 2016