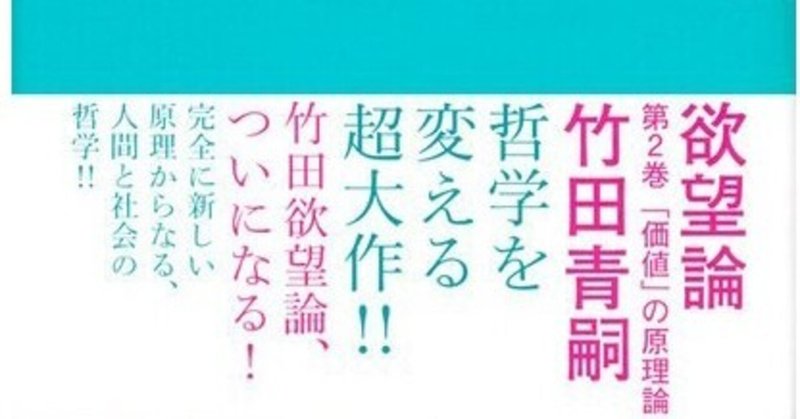
【解説】竹田青嗣『欲望論』(19)〜芸術とは何か?
1.芸術の現象学
独断論にも相対主義にも陥らず、私たちは芸術の本質をどう洞察することができるだろうか?
竹田はまず次のように言う。
多くの若者は、ある時期にさしかかって特定の音楽家、歌手、作家、詩人、画家などになぜか強く引かれ、その作品のみならず、その芸術家、アーティストに強く憧れるという体験をもつ。この独自の表現的結晶作用の体験は、美的体験と同じくその由来を誰も現前意識の直接性としてたどることができず、まさしくその理由で未知性、稀少性、不思議さと背後世界性を直観させるようなものとして現われる。
芸術作品は、私たちに強い偉力を感じさせる。それゆえ私たちは、その背後に何か「本体」があるのではないかと感じ取ることがある。
しかし芸術の背後に「本体」などはない。
私たちが探究すべきは、美的・芸術的現象の普遍的構造の解明なのだ。
すなわち、芸術の本質観取。
ここで竹田は、「作品的感銘」と「表現的偉力」という概念を提示する。
われわれは、以後、作品に向き合う人間を鑑賞者と呼び、作品に異例の仕方で動かされることを、さまざまな日常的、関係的な出来事によって生じる「感銘」とは区別して「作品的感銘」と呼び、その強度を「表現的偉力」と呼ぶことにしよう。
これは芸術である、と感じるとき、私たちは必ず、そこに「作品的感銘」と「表現的偉力」を感じ取っている。竹田はそう言うのだ。
例によって、この竹田によって取り出されたものが、私たちがそれを「芸術」であると「確信」する時の本質条件になっているかどうか、私たちは自らに“確かめる”ことができるはずである。竹田の本質観取を吟味し、さらに深めていくことが求められていると言えるであろう。
竹田は続ける。
この芸術体験に出会った者のうち、ある者は自ら「表現的偉力」を再現したいという欲望に駆られる。この動機に押されて創造を試みる者は「作品」を模倣するが、この模倣の企投は、作品が自らに与えたあの「作品的感銘」を再現することを目がける。作品とその創造行為の偉力が引き起こす憧れと羨望を経験して、自分もまた創造者たろうとする人間は、この場面ですでに「芸術」とは何かについての最も基礎的な本質をつかんでいる。ある音の響き、旋律と律動性、ある言葉の不思議な連なり、物語が紡ぎ出す仮想の出来事の連鎖、それらが生み出す夢想、情緒、感情の高揚、幻影、色彩、深い情感、自分の琴線に触れ心の深部を揺り動かしたあの何かを自らが再創造すること、それが問題のすべてである。創造を試みる者にとっては、事態はこの上なく簡明であって、この作品的感銘の体験の再創造が芸術、あるいは表現作品の意味にほかならない。
この感銘と偉力に打たれた者のうち、この感動を自らもまた生み出したいと思う者が創造者の道を進もうとする。
また一方で、多くの者は、この感銘と偉力は一体何なのか、語りたくなる。
ここに、批評のゲームが登場することになるのだ。
一般に、作品的感銘に打たれその偉力に動かされたものは、この偉力についての語りの欲求に駆られる。作品の偉力についての語りの欲求が現われなければ、そもそも批評は生じない。
作品への感銘に打たれたものは、その体験の稀有性を語りたいというだけではなく、この作品の感銘の内実、それがいかに自分の心をつかみ、動かしたかを誰かに語り了解してもらいたいという欲求に駆られる。〔中略〕それゆえこの感銘の内実についての語りの欲求は、感銘についての単なる報告なのではなく、感銘の本質を言い当てたいという欲求、作品の偉力の本質探求の欲求であるとともに、それを他者と共了解したいという欲求でもある。
芸術作品体験の本質契機を、竹田は次の3つ提示する。
作品体験における本質的契機。第一に、作品的感銘、第二に芸術の本質探求、そして第三に芸術的判定。
芸術作品は、私たちに「作品的感銘」を与え、それゆえその本質を探求したいと欲求させ、そしてその上で、「これは芸術である」と判定させるようなものなのだ。
私たちが芸術と呼ぶものは、すべてこれらの本質を備えているはずである。
そう竹田は言うのだが、このこともまた、私たちは自ら“確かめる”ことができるはずである。
ところで、言うまでもなく、この最後の判定にける、芸術の絶対的基準などはない。
しかしそのために、芸術など徹頭徹尾相対的なものであるなどという相対主義的芸術論が、またも生まれることになる。
このことについて、これほど馬鹿げた芸術論はないと竹田は言う。
ある仕方でタイピングされたアルファベットの並びを、なんらかの暗号やアナグラムとして解読しようとする試みは、それがいかに何らかの隠された意味を含んでいるように見えようと、たとえばそれがチンパンジーによって打たれたアトランダムな記号配列にすぎないことが明かされるや否や、まったく無意味なものとなる。同様に、何か意味ありげな抽象画が、ブタの尻尾で描かれた色彩画であることが判明するや否や、この絵に対する「本質探求」は無意味なものとなって停止する。言語現象においては話者の意の志向的信憑が不可欠であるように芸術現象においては作者の創造的膂力への志向的信憑が、不可欠の本質契機だからである。「作者の死」の観念は、芸術相対主義の観念から捏造された帰謬論的誤謬の一典型にすぎない。
芸術作品において、私たちは必ず、何らかの創造的膂力への感銘を感じ取っているはずなのだ。
では、その本質、その普遍性は、一体どこにあるのだろうか?
その問いをこそ、私たちは問わねばならない。言うまでもなく、「本体論」に陥ることなく。
2.芸術の普遍性
竹田は言う。芸術作品が芸術であると普遍的に判定されるのは、徹頭徹尾「芸術–批評のゲーム」においてである、と。
芸術作品がまず存在し、その後に、その卓越性、真正性の判定についての批評のゲームが現われるのではない。ある創作物から何かを感じ取ったものがそれについて語り、これについての異なった語りの多数性が現われることで批評のゲームがはじまり、この批評のゲーム、すなわち作品が与える感銘の卓越性や優劣をめぐる言説のゲームの中で、あるものが「芸術作品」と呼ばれる。このゲームの関係的集合性が芸術というジャンルを形成する。
芸術の判定は、どこまでも間主観的な信憑において成立するのだ。
こうしていまや、芸術作品の起源が理念、絶対者、理、存在といったものに還元されえないことは明らかである。これが真の作品であるという個々「確言」の集合性が芸術作品を生み出し、芸術的価値なるものを集合的信憑として生み出す。あるいは、これこそ「真の作品」であるという批評、この判定についてのせめぎあい、そこから現われる間主観的な信憑だけが「芸術」を生み出すのである。
芸術-批評ゲームは作品の真正性、卓越性についての「確言」のゲームである。ここでは作品が比べられ、「真正性」に達しているか、またどれがより優れているかが「確言」されなければならない。作品の卓越性についてのこの「確言」、どれがより優れた芸術であり、どれが「真の作品」であるかを表明することが芸術-批評ゲームの基本ルールである。
芸術の普遍性は、こうした「芸術–批評ゲーム」において、間主観性に成立するものなのだ。
もっとも、芸術の判定に絶対的な基準がないがゆえに、「芸術–批評ゲーム」にはいくつかの困難がつきまとうことになる。
たとえば、「権威主義」。誰か権威ある「批評家」が、不当に力を持ってしまうことがある。
あるいは、「政治的利用」。かつてのマルクス主義のように、芸術を政治利用する動きが起こってしまうこともある。
そしてまた、「サクセスゲーム」。資本主義社会においては、芸術作品は商品となる。それゆえ作品は、「芸術–批評ゲーム」のうちに止まらない様相を呈することになるのだ。
相対主義的芸術論は、ここに目をつける。
普遍性探求のゲームである芸術-批評の制度は、文化的なサクセスゲームと明確に区分することがますます困難になる。こうなると、作品を創造する人間、批評する人間、享受する人間の三者の間でヘーゲルが示唆したような「相互的欺瞞」、作品創造者も批評者も享受者も表向き芸術の普遍性を強調しているだけで、実質上互いに文化的サクセスゲームとしてそのうちを生きているにすぎないのではないか、という相互的不信と欺瞞の戯れが生じる。そしてこういう場面では、芸術相対主義は、権威化しサクセスグゲームと区別のつかなくなった芸術-批評のゲームに対して、普遍性の根拠についての疑義の声を上げるという役割を果たす。
芸術など、結局普遍的なものではなく、人びとの幻想的な商品にすぎないのではないか。
相対主義的芸術論はそのように主張するのだ。
しかしこれもまた、本質を取り違えた考えと言わねばならない。
多くの政治権力が正当性を欠いたものであるということと、権力の正当性の原理を哲学的に導出しうることとが別問題であるのと同じように、芸術ゲームが時に商品ゲームになってしまうということと、芸術の普遍性の原理がありうることとは別問題なのだ。
芸術の普遍性は、長く広範な「芸術–批評ゲーム」を通して獲得されていくものである。そしてこの構造自体は、動かしがたいものなのだ。
おわりに
これで、竹田青嗣『欲望論』第1巻、第2巻の紹介・解説を終えることにしたいと思う。
原著が長大な作品であるだけに、この解説もずいぶんと長くなってしまったが、それでも、本書の意義を十分に伝え切れたか、少々心もとなくもある。
繰り返し述べてきたように、竹田が切り開いた現象学ー欲望論の哲学は、まず認識論の徹底した原理を解明することで、形而上学的独断論と相対主義の対立を完全に終わらせた。
続いて、さまざまな人間的な意味や価値の本質を、その「確信成立の条件」を問うという仕方で明らかにすることができることを示した。
その際の重要な原理が、「欲望相関性の原理」である。私たちはさまざまな意味や価値を、「欲望相関的」に認識しているからだ。
この原理に基づいて、本書第2巻では、時間、他我、身体、善、美、芸術などの本質観取が試みられた。
何度も言ってきたように、これらの本質観取は、いずれも私たちが後追いして“確かめられる”ものになっているはずである。
したがって、不十分な点や訂正すべき点があれば、後続世代によってさらに深化されるべきものである。
と同時に私たちは、この現象学ー欲望論的方法を駆使して、今後、さまざまなテーマの本質観取を展開していくことができるようになる。
拙著『どのような教育が「よい」教育か』、『「自由」はいかに可能か』、『愛』などは、私自身のそのような哲学的探究の1つである。
現代においては、とりわけ「よい社会」とは何か、それはいかに可能かという、社会構想の哲学の立て直しは急務であるように思われる。
それもまた、この現象学ー欲望論の哲学こそが可能にするはずだ。
かつてフッサールが言った言葉を借りれば、いま、私たちの目の前には、新たな哲学の「無限の領野」が広がっているのだ。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
