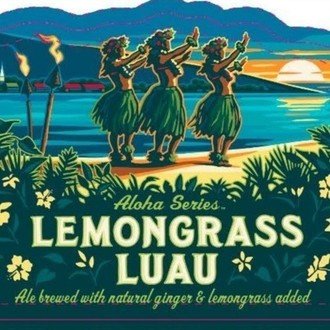読書記録 「最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常」
10代の頃、芸大に憧れたことが何度かある。
「芸術を極める」とか「芸術家への登竜門」と考えたことは一度もない。
勘が働いたとしか言いようがないのだが、なんだか自分にはとてつもなく居心地がいい場所であるような予感がしたのだ。
この「最後の秘境 東京藝大」が文庫化されたのを知って、読んでみることにした。
単行本が出た時に話題になったので、本の存在は知っていたけれど、中身はなんとなく想像がついてしまい、読んでみるところまでは行かなかった。
体調が悪く、半ば自宅療養みたいになった日曜日、ベッドでくすくす笑いをしながら藝大に潜む変人、もとい天才たちの生活を楽しんだ。
「芸術」と言われてしまうと常人には近づきがたい崇高さを感じてしまうかもしれないが、芸術の本質というのは実はそれほど大したものではないと思っている。基本的に無くても誰も困らないものなのだ。
ただ「邪魔にはならないけれど、あってもさして役に立たないもの成分」が含まれると、現実社会でものすごく役に立ったり、生活が豊かになる場合がある。だから「芸術」ってすごいと思われがちだし、とりあえず存在が認められるんだと思う。
「違う視点を提示するのがアートの仕事」なんてよく言うけど、そんなに視座視点をコロコロ変えられても目が回るだけ。
そもそも誰かの視座視点を変えてやろうだなんてこれっぽっちも思ってないような気がするし。
要するに芸術なんて(とあえて引きずり降ろすような言い方をするけれど)、作ってる人間が一番面白がっているだけのものなのだ。
ただその発想力、具現化するエネルギー、誰がなんと言おうが関心がない独善的なパワーが中学生の部活とNBA選手ぐらい違う。そこに一般人は驚愕して、その驚愕を敬意と勘違いさせるんだと思う。
繰り返すけど、奴らのほとんどは自分たちが一番面白がっている(どれだけ多くの言葉で言い繕っても)のだろうし、そんな気持ちがなければ芸術を学ぶ場所に来ようだなんて思うまい(社会的使命感で藝大に入った人なんていないだろうということだ)。
僕がそんな風に藝大や芸術を捉えている前提でなお芸大に行きたかったなあと思うのは、あそこがはみ出てしまった人間を合法的に受け入れるように感じるからだ。
「大学」と言っているけれど、僕からすればどこかしら「収容所」とか「入院先」「シェルター」、社会的な広さでの「パニックルーム」のように思えるのだ。行き場を見つけるのに苦労するある種の人たちが流れ込んでくる場所。
「変わっている」と事あるごとに言われ続けた身としては「藝大ぐらいしか」居場所はなさそうに思えたのだ。
現実は藝大は専門病棟で、僕は所詮は一般病棟に見合った患者なのだった。
藝大の学生はやはりすごいのだ。
いいなと思ったら応援しよう!