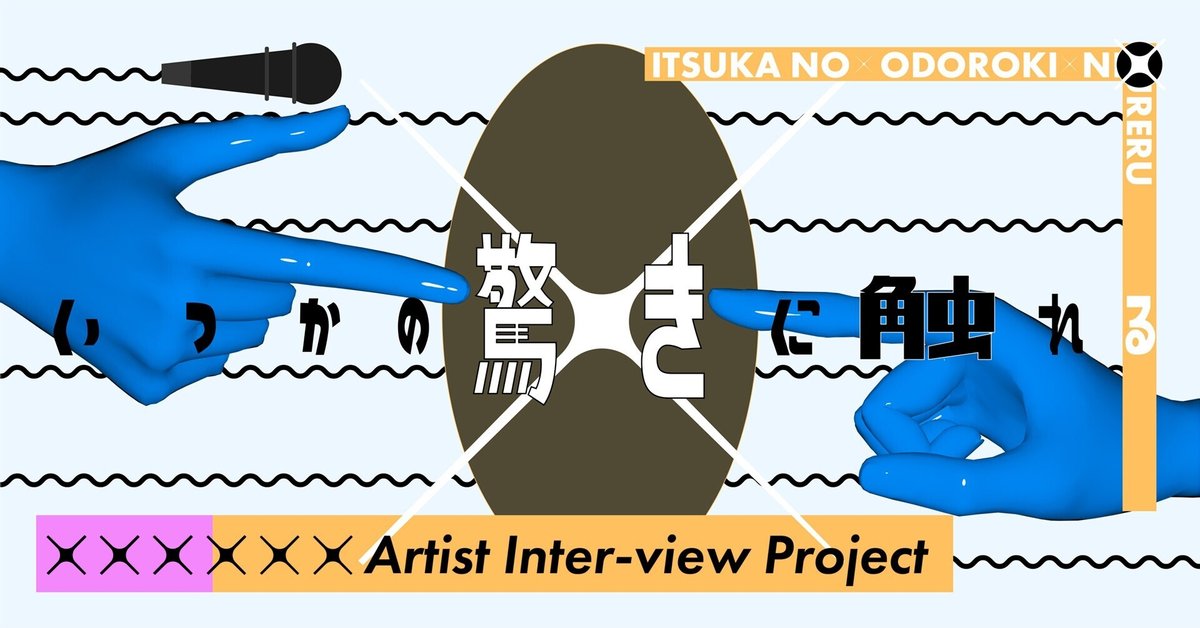
井上徹&斉藤隆文(オル太) インタビュー「都市の身振りを再演する—「超衆芸術スタンドプレー」について 」
アーティストの活動の端緒となるような経験=〈驚き〉に焦点をあてるインタビュー・シリーズ企画。アーティストが関心を持っている場所を訪ねて、話を聞きます。第3弾は、アーティストコレクティヴ「オル太」のメンバーである井上徹さんと斉藤隆文さんです。オル太は墨田区でのレジデンスやリサーチをもとにした映像インスタレーションの展示『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』を2020年11月に開催しました。2019年に行われた墨田区の「sheepstudio」でのレジデンスには、オル太メンバーの井上徹さん・斉藤隆文さん・川村和秀さんが中心となって参加。今回は墨田の街を井上さん・斉藤さんのふたりとともにめぐったのち、展示会場となった「北條工務店となり」でインタビューを実施しました。
「超衆芸術スタンドプレー」は「都市」に注目するプロジェクトとして、これまでさまざまな場所での実践を重ねてきました。本インタビューでは、プロジェクトに込められたふたりの関心やその試みについて、2020年2月にロームシアター京都で上演された『超衆芸術スタンドプレー』と『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』を中心に語っています。
(企画編集:西本健吾)
1. なぜ、記録するのか—都市の「ずれ」への眼差し

『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』(北條工務店となり, 2020) 写真:縣健司 ©️OLTA
——まずは「超衆芸術スタンドプレー」の特徴でもある「記録」の方法や、その対象についてお聞きしたいです。この記録はインスタグラムにもアップされ続けています。
井上:都市で起こっている行為をパフォーマンスと捉えて、それを記録しアーカイヴ化してくというところに、「超衆芸術スタンドプレー」を始めたきっかけがあります。パフォーマンスって、当たり前の話なんですけど記録しないと残らない。たとえば渋谷に宮下パークができましたが、僕らはそれがつくられていく様子も記録していて、京都での公演『超衆芸術スタンドプレー』(2020年2月)に組み込まれています。けれど、記録していたときはその後どうなるかはわからなかった。ホームレスの人の排除も急に起こるわけではなく、段階を経てなされていくわけで。それを書き留めておく。これは、その後に起こる都市の変化の前兆を見ていくような感覚です。
もうひとつ重要な要素は「笑い」です。「スタンドプレー」は、スポーツ選手が競技とは関係なく目立とうとする行為を意味します。この言葉に着想を得て、僕らは都市の中のルールや仕組みからずれてしまっている現象を「スタンドプレー」として記録しています。以前、信号待ちをしながら携帯電話で話している人がいて、それをなぜか隣の人も近くで聞いているという状況を記録したことがあります。信号にもうひとつデバイスが組み合わさってちょっとした「笑い」のある出来事が起こっている。哲学者のアンリ・ベルクソンは「笑い」とは社会的身振りであるといっているんですが、「超衆芸術スタンドプレー」ではあるルールに沿おうとするのにそこからあぶれてしまうような現象を大衆とモノの無意識から生まれる「笑い」として注目しています。
斉藤:「超衆芸術スタンドプレー」はこれまでにも回を重ねてきていて、その度に注目する現象は異なるのですが、井上がいうように共通しているのは、現代という時代や都市の事象について考えることです。ただ補足すると、「笑い」はあくまでも都市を考えるための一つの切り口であって、今回の展示ではそこまで前面には出していません。記録には写真や動画で撮影する、文章で起こす、スケッチで記録する、といった方法を用います。

(墨田でみつけたパイロンを撮影する斉藤さん)
——個人的にはスケッチの手法が気になります。
井上:写真や動画にもそれぞれ意味はあるのですが、スケッチという点でいうと、『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』で注目した今和次郎は関東大震災後の都市を記録する際に、写真も撮りつつ同時にスケッチもとっているということがあげられます。スケッチをとることで、自分が考えたことやどこをピックアップしたのかを詳細に書き込むことができたり、あるいは「見えていない」部分も描いたりすることができる。このことは、シャルル・ボードレールが『現代生活の画家』において、写真が対象を蒐集するための手段であるなら、スケッチは対象を所有するのではなく模倣する、と述べていることともかかわると考えています。
——今和次郎についてはこれまでずっと意識してきたのでしょうか。
井上: 2019年の『スタンドプレー vol.4 多摩ニュータウンでのアクティビティ』のときから、特に念頭におくようになりました。そもそも「超衆芸術スタンドプレー」が赤瀬川原平の「超芸術トマソン」から着想をえています。そして超芸術トマソンが今和次郎の「考現学」を引き継ぐものです。そういう意味では今和次郎の要素は最初からあるのかもしれません。ただ、考現学や超芸術トマソンと「超衆芸術スタンドプレー」が異なるのは、都市の現象をもう一度僕らが身体化し、再演できるように記述しているという点です。たしかに僕らは街で見かける「ずれ」の現象を「スタンドプレー」と呼んではいるのですが、正確にはこれは一つの再演に向けたプロジェクトの名称です。この再演が重要だと思っています。
2. 身体化とそのフィールド—共鳴する「スタンドプレー」

『TRANSMISSION PANG PANG 大嘗祭』(千葉, 2019) 写真:倉谷卓 ©️OLTA
——身体化と再演というキーワードについてもう少しお聞きしたいです。
井上:オル太の『TRANSMISSION PANG PANG』というプロジェクトがあります。これは各地の祭りの身振りを、ボードゲーム化して参加者と一緒に再現していくことで現代における「伝承」を考えるというものです。身振りを様々な仕方でスコア化し、カードに落とし込み、それをもとに参加者が身体を用いて再演するのですが、踊りを知らない人たちはカードの絵だけをみても、なんとなくはわかるけど、完全にはわからない。そこで参加者は自分たちで想像して、アレンジを加えてみる。そこに面白さがあって、この試みは多分もともとの身振りを動画で見てもうまくいかない。答え合わせになってしまうんです。この余白が大事だと感じています。

『超衆芸術スタンドプレー』 (ロームシアター京都, 2020)写真:田村友一郎 ©️OLTA
——京都での『超衆芸術スタンドプレー』では、過去の「スタンドプレー」で用いられた身振りを含め、過去の記録が一同に介していた、という印象を受けました。
井上:作品の素材となる記録の内容について全員が体験しているわけではありません。なんなら伝聞で伝えられることもあります。そこからメンバーでもう一度パフォーマンスに起こしていくことで、異なる場所・時間でメンバーが記録してきたもの同士の結びつきが見えてくるということがあるんです。京都での『超衆芸術スタンドプレー』は東京オリンピックをひとつの背景としているんですが、これまでの記録や記録をもとにオル太が執筆した文章から、オリンピックとの繋がりが見出せたりする。ちょっとずつ積み上げていったものを、身体化を通じて自分たちでもう一度解釈していくことで、結果的にオムニバス的な構成になりました。各地で記録してきたスタンドプレーが共鳴するというような感じかもしれないです。
斉藤:井上が言ったように、都市の現象を記録しているときはなにが表現されるのか、自分たちもはっきりしたものは持っていません。そして、作品になったときも僕らが最終的にこういう答えがあると提示しているわけでもありません。土台というかフィールドをつくっているという感覚です。些細なことから大きな事象を含む記録を集合させるための、場をつくっている。それは素材となる記録を集めることとはまた違います。翻案して、アウトプットするので。また、記録されたものがすべてでもなくて、京都での『超衆芸術スタンドプレー』では古代ギリシアで使われていた壺が登場します。あるいは伝統芸能の日舞から身振りを持ってきたり。

井上:ただ、斉藤には集めること自体の執着もまた感じる。
斉藤:執着はあると思いますし、それがモチベーションになっている側面はあります。例えば今回、僕は墨田の長屋に注目していたんですが、途中でぶった切られている状態のものが結構あったんです。そこから過去のその長屋の写真をできる限り集めて、時系列で並べてどういう変化があったのか調べました。あるいは、同じような資料でも、ちょっとでも違う箇所を見つけたらとりあえずコピーしてしまう。オル太で共有すると細かすぎるとか、なんでそれを採集したのか伝わらないことも多いんですけど、それでもそういった小さな差異に注目したいと思っています。それと、都市の写真記録を撮るときは意識的にスタンドプレーと呼べるかわからないようなものも集めるようにしています。
井上:それぞれのメンバーが異なる関心や手法で集めてきた情報から要素を抽出することができるというのは、コレクティヴだからできる一つの手法だと思います。そういう意味で斉藤の集めることへの執着や小さな差異への注目というのは作品制作のエンジンになっているのかもしれません。
3. 墨田という固有性—「深刻さ」のジレンマ

——今回の『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』は、墨田という特定の場所をあつかっています。そこでのリサーチについてお聞きしたいです。
井上:墨田は関東大震災以降に街の形がおおきく変わったんですが、今和次郎が書き留めたバラックのスケッチだったりは震災後の都市の激烈な変化の記録です。そのような急速な変化に介入するようにバラックを装飾する運動があったりしたんですけど、そこに「スタンドプレー」を見出せるんじゃないかというところから始まりました。美術も、築地小劇場で当時上演された『朝から夜中まで』(1924)での村山知義の舞台美術をベースにしつつ、今和次郎によるバラックのスケッチを当て込んでいる。なので、墨田のバラック建築を通じて今回は都市と向き合ったという感覚があります。
斉藤:さっき話した、長屋が途中でぶった切られた状態を記録したことともかかわりますが、ブリコラージュというか建物をリペアして使ってくようなスタイルの影響は今回の展示の舞台美術にも反映されています。また、区画整理が進む現代の墨田も変化しています。レジデンス中、一か月だけの滞在でしたがそのあいだにもどんどん街が変わっていて。頑固に建っていた建物もあったのですが、今日墨田をめぐっているときに見たらなくなっていました。
井上:墨田の建築には早い段階から着目していましたね。たとえば玉ノ井という地域はかつて色街として栄えていて、風俗業としての「カフェー」というものがありました。その建築様式が面白くて、表向きは洋風に飾ってあるんですけど、中は普通の日本長屋になっているんです。ただ、今はほとんど残っていません。

『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』(北條工務店となり, 2020)©️OLTA
——切られた長屋やバラックやコラージュ建築に、都市の機能からの「ずれる」を見出すというお話しでもあるようにも思えます。その眼差しが現代墨田にも向けられている点も興味深いです。
また、特定の場所をあつかったことに加えて今回は歴史も重要な要素になっています。歴史をあつかうことになったきっかけは何だったんでしょうか。
井上:最初はこれまでのように街の現象を追いかけ記録していたんですが、だんだんといろいろな葛藤が渦巻いている街だということがわかってきて、歴史にも興味を持っていきました。たとえばさっき話した玉ノ井だとその歴史を良く思ってない人がいて、玉ノ井駅だったところも東向島駅に名前が変わったり。それと、表面上に見えている現象だけを追いかけていても、どこかで行き詰まってくるような感覚があったんです。そしてだんだんと記録する理由が「ビジュアルが面白いから」とかになってしまった。でもそれだけではリサーチとして幅が狭くなってしまう。
その結果、今回の作品は歴史的なテーマをいくつかあつかうことになりました。特に関東大震災のときにおきた朝鮮人虐殺は重要な要素です。最初は、新聞や博物館のようにアウトプットすることも考えていたんです。ただ、リサーチ結果を深刻なままで出すということに抵抗感があった。朝鮮人虐殺については、当時の自警団が半ば強制的に地域から一人参加しなきゃいけないというルールのもとで結成されたということもあり、直接は加担してないにしてもほとんどの人がかかわっていたということもあって、できれば話したくないって人が多いんです。それと、墨田には墨田の歴史を調べることを趣味にして発表会をしている人たちもいる。あるいは今回のリサーチでもお世話になった「ほうせんか」という団体はずっと朝鮮人虐殺のことを調査してきた。そういったことを知るなかで、どこまで僕らが掘り返していいのかっていうのは悩みどころでした。それで、深刻な出来事を、深刻であることに変わりはないんですが、どうにか別の仕方にもう一回置き換えて表現したいということになった。
4. 歴史をあつかう手つき

(荒川放水路にて)
——歴史に向き合うその方法について、もう少し踏み込んでお聞きしたいです。
井上:一つは、「見えなくなった歴史」や「聞こえなくなった声」にフォーカスした、というのがあります。今回の作品の舞台にもなった荒川放水路には旧四ツ木橋という、今はもうなくなってしまった橋がかかっていたらしくて、そこで朝鮮人への暴行とか虐殺が行われていたらしいんです。それと、目に見えなくなってしまった歴史を調べていくと、川とか暗渠みたいなものがポイントとして出てきました。たとえば曳舟川という川が墨田から埼玉の方まで延びていたのですが、今はもう「曳舟川通り」という道路になってしまっている。川には僕自身も思い入れもあって、地域を分断するものだったり、交流の場だったり、物流の手段だったり、いろいろ面白いんですよね。ともかく、そういった「見えないもの」というテーマが定まったことで表現の道筋が見えた気がします。
斉藤:今回のリサーチではインタビューも行なったんですが、その過程で強い表現にも出会って。僕は角打ちとか飲み屋にいっていろいろと話を聞いたんですけど、言ってしまえば差別的とも取れるような言葉が結構ストレートに出てた。それはそのままではもちろん使えない。そういうバランスをみて、表現したっていうのはあるかもしれない。結果として、映像作品は全部、展示会場となったこの建物の中で撮影されているし、資料やリサーチ写真がそのまま出てくるということはありません。永井荷風や釈迢空、小津安二郎の映画をとおして歴史をあつかうということはあっても、歴史資料を直接用いるということはしませんでした。

(竹久夢二についてのリサーチ資料)
——斉藤さんは今回も「斉藤単勝」名義で漫画を描かれていますが、これも一つの歴史のあつかい方なのではないかと思います。
斉藤:朝鮮人虐殺に関する証言記録をもとに起承転結をつけて漫画にし、映像として上映しました。震災直後の1920年代・30年代の時代状況のなかで漫画でなされていたさまざまな表現と出会ったことがおおきいです。その想像力というか、パワーに惹かれました。たとえば竹久夢二は都新聞での連載のなかで、バラックに住んでいる人の、捉え方によっては力強さのようなものを描いているし、宮武外骨は当時の新聞の切り抜きのコラージュとか、皮肉めいた風刺画を残しています。
映像に出てきた漫画を一つ紹介すると、日本語を喋っている自警団が日本語がたどたどしい人を殴りつけようとして、誤って日本語を喋る相方を殴ってしまい、殴られた日本人が歯が抜けてちゃんと発音ができなくなってしまうという4コマ漫画を描きました。3コマ目で逆転が起こるんですが、事象的には過去のことだけれど、今の人でも起こりうるかもしれないこととして、鑑賞者の頭をよぎるような瞬間をつくるというか、鑑賞者の心の底でそういう感情があるかもしれないというところを突くような意識で描きました。
——京都での公演はロームシアター京都という劇場で、オリンピックという巨大な祝祭的状況をあつかっていました。それに対して、今回は元々工務店だった場所で、築地小劇場をレファレンスとしている。「舞台」というもののスケールがおおきく異なっていたと思うのですが、この変化についてはどう感じましたか?
井上:墨田の問題って、一つひとつちゃんと見ていくと、近代日本の都市をめぐる話になると思うんです。墨田は皮革産業が周辺地域から集約された街でもあるし、明治以降の都市をめぐる問題が凝縮されている。京都での『超衆芸術スタンドプレー』はいろんな場所の事象を集めることで「都市」を浮かび上がらせる試みだったんですけど、今回の『超衆芸術スタンドプレー 夜明けから夜明けまで』の場合は局所的なテーマから広がりが生まれた感覚がありました。

『スタンドプレー vol.4 多摩ニュータウンでのアクティビティ』(多摩ニュータウン、松が谷周辺, 2019) 写真:北沢美樹 ©️OLTA
——最後に、次に「スタンドプレー」の作品を手がけるとして訪れたい都市はありますか?
斉藤:もう一度、京都がいいんじゃないでしょうか。京都の崇仁地区という場所は区画整理の影響もおおきいと思うんですけど、フェンスだらけの迷路になっているような場所もある。もうすぐなくなってしまいそうな建物がポツンと建っていたりもする。墨田との連続性を感じる場所で、普通イメージされる「京都」のイメージとは違う。
井上:あと、墨田の曳舟の文化を調べている人から、京都の高瀬川でも曳舟をしていたということをお聞きしました。その高瀬川が流れているのも崇仁地区なんです。そういうつながりからも、もう一度京都でスタンドプレーをやってみたいです。
——今後の「超衆芸術スタンドプレー」の展開がとても楽しみです。本日は貴重なお話、ありがとうございました。

インタビュー日:2020年11月29日
撮影:倉谷 卓(写真家, RAMインターン)
バナー作成:レーズン(Video and Game Maker, RAMインターン)
協力:オル太、ファンタジア!ファンタジア!、和田信太郎(RAMディレクター)、中島百合絵(RAMプロジェクト・マネージャー)
企画編集・インタビュー:西本健吾(RAMリサーチャー)
井上 徹(いのうえ・とおる)
1986年、神奈川県生まれ。 2010年に多摩美術大学絵画学科卒業。自身が拾う音から環境や彫刻、インスタレーションを展開する。主な展覧会に、Bangkok Biennial 2018「BARRAK : survibes」(White Line、バンコク、タイ、2018)。主なイベントに「Draw!The Party!From White!」(The CAVE、神奈川、2017)、「WE ARE TALKING ABOUT TO THE PRESENT」MIKE KELLY「DAY IS DONE」トークイベント(ワタリウム美術館、東京、2018)。
斉藤 隆文(さいとう・たかふみ)
1986年千葉県生まれ。2012年に多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修士課程を修了。作品を装置に置き換え、自身が介入し現在に潜む狂気や歪みをあぶりだそうと試みている。個展として「波ものみこむ手」(Art Center Ongoing、東京、2019)、「おぼろげな凱旋ス -屁理屈めいた肉-」(コ本や、東京、2018)「おぼろげな凱旋ス」(Art Center Ongoing、東京、2015)。主なグループ展に「犬が西向きゃ尾は東」(Art Center Ongoing、東京、2014)、「脳に映るは移る日蝕」(akibatamabi21、東京、2012)。主な映像上映に、「COVERD TOKYO:Hikarie」(Hikarie、東京、2014)、「Experimental Film and Video Festival In Seoul」(KOREAN FILM ARCHIVE、韓国、ソウル、2014)。
オル太
アーティスト・コレクティブ。井上徹、川村和秀、斉藤隆文、長谷川義朗、メグ忍者、Jang-Chiの6名からなる表現集団。2009年結成。いずれも多摩美術大学絵画学科油画専攻出身。人間の根源的な欲求や感覚について、自らの身体を投じたパフォーマンスを通じて問いかけている。
https://olta.jp/
※本企画は東京藝術大学大学院映像研究科が主宰する「メディアプロジェクトを構想する映像ドキュメンタリスト育成事業」(RAM Association: Research for Arts and Media-project)の協力で行われました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
