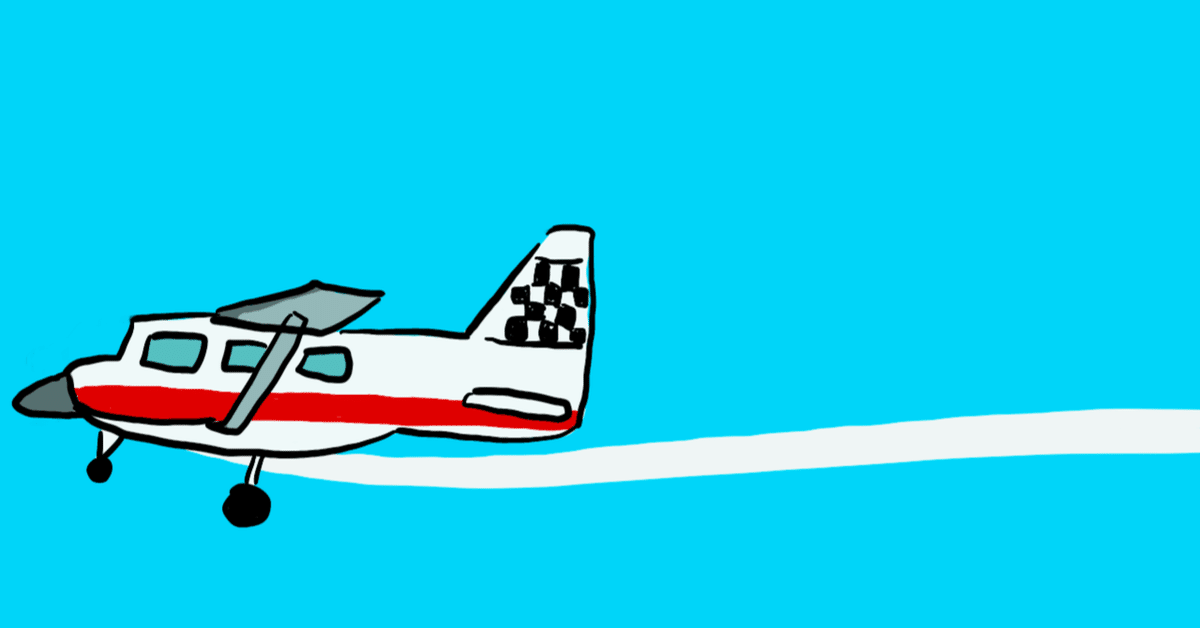
「筑波大学ILC」と「マジョリティの特権」と「安心な対話の場」をめぐる小さな旅
先日、「筑波大学インクルーシブ・リーダーズ・カレッジ」の1コマで、「マジョリティの特権」をテーマとしたワークショップを企画し、ファシリテートする機会に恵まれました。
今回は、このワークショップを実施する一連の過程から感じたこと、学んだことを書きたいと思います。
「筑波大学インクルーシブ・リーダーズ・カレッジ」(筑波大学ILC)とは?
筑波大学ILCは、「『Diversity / Inclusion /Trans-creation(多様・共生・共創)』をキーワードとして、現代日本の喫緊の課題であるジェンダーや障害、多文化、世代に関する学びを得るとともに、それらの学びを通じて新しいリーダー人材を輩出することを目的」(筑波大学ILCのウェブサイトより)とした筑波大学のエクステンションプログラムです。
昨年、僕自身も第3期生として受講しました。
各分野の研究者や実践家の話に加えて、参加者同士の対話からもたくさんのことを学びました。
半年間にわたって、平日の夜に毎週1回2時間のセッションに参加するのは大変でしたが、充実したプログラムでした。
半年間のプログラムを終えてからも、修了者同士で分科会を企画・運営するなど、仲間とともに学び続けることができる環境があります。
「マジョリティの特権」とは?
ワークショップのテーマとなった「マジョリティの特権」の概念は、もともとはアメリカにおける社会公正教育の文脈で発達してきました。
日本では、上智大学の教授の出口真紀子さんが、この分野の第一人者として研究と教育に注力しておられます。
マジョリティの特権についての解説は、こちらの出口さんの分かりやすい記事にお任せしたいと思います。
僕自身は、マジョリティの特権の考え方に触れたことを機に、ものごとの見方が大きく変わったと感じています。
出口さんは、「見えない自動ドア」という比喩を用いて、マジョリティの特権を説明しています。
まさに、僕の人生では見えない自動ドアがたくさん開いてくれていた、ということに気付かされたわけです。
出口さんは、マジョリティの特権を持つからこそ果たすべき責任があると言います。
「アメリカでは、ペギー・マッキントッシュさんが『白人特権』を提唱して初めて、白人は白人の特権に向き合いましたが、実はそれ以前からずっと黒人は声をあげていました。でも、白人は白人の言うことしか聞かなかった。だから、“特権”を持つ側が声を出すことがすごく大事です。
社会を変える力を持つ上に、中立客観的にみられたり、好意的にみられたりするからこそ、その“特権”を使わない手はないでしょう。マジョリティーを教育するのは、“特権”に気づいたマジョリティー側の責任です」
DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の研究者でも専門家でもない自分が、マジョリティの特権をテーマとしたワークショップを手がけることへのためらいは、正直なところありました。
ただ、特権に気づいたのに何もしないわけにはいかない、という気持ちが後押ししてくれました。
そして、「気づいたとしても何もしなくても済ませられる」特権を放棄するところから始めようと思いました。
具体的にお名前を挙げることはしませんが、筑波大学ILCを受講するように誘ってくださった方、ワークショップのファシリテーションをする機会を与えてくださった方に、あらためて感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。
「安心して対話できる場」をつくる
筑波大学ILCには、企業でDE&Iの推進を担当している方、自身がマイノリティの当事者である方が多く参加しています。
DE&Iや差別に関する知識のある参加者が多い場ではあるものの、自分自身のことを話してもらうことになりますので、「安心して対話できる場」をどのようにつくるか?ということを、ワークショップの設計と運営でもっとも重視しました。
特に気をつけたのは、次の3点です。
ファシリテーター自らが、自分を開いていくこと
対話のルールを明確に示し、何度も伝えること
参加者を信じること
1点目の「ファシリテーター自らが、自分を開いていくこと」については、よく言われることでもありますが、実際に行うには、ときに勇気が必要になります。
「自分のことを話して、ちゃんと受けとめてもらえるだろうか?」「変なふうに誤解されてしまうのではないだろうか?」といったことが頭をよぎるからです。
一方で、ファシリテーターから自分を開いていくことは、対話の場におけるオープンさの1つの具体例を示すチャンスでもあります。
今回のワークショップでは、僕の自己紹介にからめて、「DE&Iの専門家ではないこと」「自分自身も学び、成長しようとしている過程にいること」「マジョリティの特権に関する個人的な経験」などをお話ししました。
2点目の「対話のルールを明確に示し、何度も伝えること」は、場をホールドする立場になった者として忘れてはならない要素です。
互いを尊重し合い、学びあうための、約束を交わす行為と言ってもいいでしょう。
このワークショップでは、次のルールを参加者の皆さんにお伝えしました。

3点目の「参加者を信じること」は、文字通り、参加者の皆さんを信じ、場のちからを信じることを意味します。
もちろん、ルールが守られなかったり、対話の進め方が分からなかったりする際には、ファシリテーターが輪の中に入っていかなければなりません。
ただ、信じることは、対話のちからを引き出す第一歩だと思うのです。
ここまで、「筑波大学ILC」と「マジョリティの特権」と「安心な対話の場」をめぐる小さな旅について書いてきました。
インクルーシブな世の中を実現するための道のりは、実際に容易ではありませんが、対話が重要な役割を果たしてくれると信じています。
安心な対話の場をつくること、これからも、この探究を続けていきます。
最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
