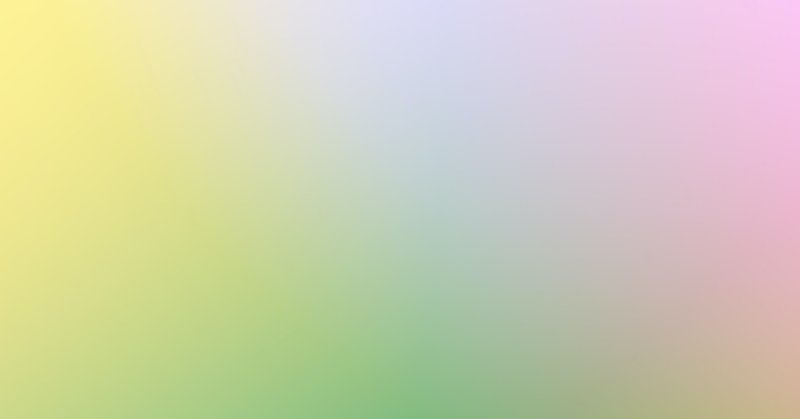
「私」はずっと「私たち」だった。
参加していたWeのがっこうが12/11で最終回を迎えました。本当に自分の感覚や思想、気づきを共有出来る素晴らしい仲間に出会えた最高なプログラムだったなとつくづく思います。
ちょっと時間が経ってしまいましたが、最終回までに発酵して(もう少し発酵できそうな感じはあるけれど)、気づきとして発現してきた言葉たちをポロポロと書き連ねていきたと思います。
もともと、気候危機を引き起こした「人間と自然の関係性の歪み」に問題意識を抱いて、じゃあ私たちはどんな自然との関係性を構築したら良いかを考えたくて、参加したWeのがっこうでしたが、最終的には自然や他者、未来、過去、ものを、ケアできる関係性を作ることが必要なのか。それはつまりWell beingだ、と思い、Well Beingの道を進んでいきそうな予感が強くしています。
今日までにたどり着いた気づき、今までの気づきと結びついて結晶化してきたものを何個か。
私は、ずっと、そしてこれからも「私たち」だった。
最近、自分が行なっていた探究とも並行している気づきでしたが、どんどん自分「一人」として「個」としてという存在論が壊れていく感覚を強く味わいました。
私たちの体の中には数兆もの微生物が棲んでいる。そしてなんなら私たちの体の発現を可能にしているのは微生物だったりする、となると私はこの世界に生み出される瞬間から他者との合作として生まれている。
世代間の流れを考えると、今私は今までの世代が生きて届けてきた恵みを受け取って生きている。この社会、文化、使っている言葉、食べているもの、全て人間が生きて「名もなき先人たち」が集積させていった言葉たちや、「名もなき生命たち」のエネルギー・物質を受け取って生きている。そして私も、私のこの存在、行為、使う言葉、他者への影響が、「名もなき先人」の一人として、未来を作り、これからの世代の過去となっていく。そのプロセスの中で、私たちも精一杯生きるということが、恩恵を次の世代に受け継いでいくことになる。
そう考えると、私たちは一人ではなく、今までの世代・先人たちがいたから私たちがいる。その時間の流れに身を置くと、私は全く「一人」でこの世に生まれてきたのではなく、大河のように流れる「私たち」という時間の一部でもある。
社会の中で、私たちは数えきれないほどの人々や存在に依存して生きている。そう考えると、依存先も含めた、「私たち」が「私」であるのではないか。
私は、なるほど、全く「私」一人ではないじゃないか。この世に生まれ落ちて、今まで生きてきて、これからも、ずっと「私たち」だったんじゃないか。
西洋社会が作り出した、個人主義的な幻想が壊れ、自分にとっては新しい関係性へのHomecomingが起きたように感じます。
これは以前Noteでも書いた、互いを「Kin・類縁」といて捉えることとも似ていると思います。私たちは別の命でも、根本で繋がっている。同じ「族」であるという感覚を、人間だけじゃなく、微生物、動物、植物、なんならきている服などのものまでと感じることができる。
そう考えてくると、私がもともと興味があった、「自然とどんな関係性の構造を作るか」という構造的な観点から、その中において一つ一つの存在とどう繋がれるのか、ということに視点が移ってきた感覚があります。
自然と人間のヒエラルキー的な関係性から、人間が自然の中に生かされていて、他の生き物、命、存在たちと、水平的に網の目のように分散的にオーガニックに繋がる関係性というビジョンはあまり変わっていません。
ただその絵を大きく彩ってくれたのは、その存在存在を繋ぐのは、「愛」や「ケア」なのではないか、と思ったことです。
ネイティブアメリカンの部族はI love youの代わりに、I kin ye. (あなたは私と同じだよ。私たちは同じ所に繋がっているんだよ)という言葉を使うことが表しているように、大切な関係性で繋がった存在を、想い、祈ること。
その行為に、「かなしみ」が大きく介在していると思ったのです。
「僕たちはどう生きるか」の中で、森田真生さんが「悲しさ」についてティモシー・モートンの話から繋げて言及しています。
「悲しみは、感情の土壌なのかもしれないと思った。肥沃な土壌に、多様な植物が育っていくように、悲しみの土壌が豊かであればあるほど、そこに深い喜びや希望も育つ。」
そして彼はさらに「「他者のために他者の安らかなることを悲しみ願う」ことこそ「悲願」という言葉の真意ではないか。」という話を紹介していました。
「他者のことを、悲しくなるほど願う」その人間の根本的な感情の土壌としての、「悲しみ」。”Sadness”だけではない、もっと相手のことを思い、かなしむ。
「アニミズムという希望」において、思想家の山尾三省は沖縄の方言で、「愛さ」と書いて「かなさ」と読むといいます。
「愛という字をカナと読むことの読み方の深さと素晴らしさですね。英語のラヴ(Love)には、決してそのような響はないと思います。同じ愛ではあるけれども、カナと呼ばれる愛と、ラヴと呼ばれる愛には大きな距りがあることを感じます。カナと呼ばれる愛の内には、なにかしらかなしいほどに愛しいものがあり、それは愛というものの本質を、つまり霊性をひどく適切に表現しているようにぼくには感じられます。」(70)
「かなしいほどに愛しいもの」、これは森田さんの語る「悲しさ」と同じように感じられました。
私たち、である他者たちをかなしみ、願い、祈る。その胸が苦しくなるような、かなしい愛しさ、ということを抱くことがケアをすることではないか、と思ったのです。
自然、人間、動物、植物とか、そういうラベリングを取っ払って、存在として繋がる時に、互いをかなしみケアすることがどう出来るか。かなしむことができたら、搾取したり抑圧したり、まず声もないような存在に消し去るってことはもうできなくなる。
ただ「かなしみ」を抱き、その感覚に気づくようになると、それがいかに弱く、脆いものか、自分自身の特に弱い部分との接続でもあるのだと気づかされました。それを守っていくことがとても必要になる。
だし、自分の体の声を聞いて、精一杯生きること。
自分の体の声を聞くことこそが、自分の体内に棲む存在たちからの声に応答していることでもある。だから感覚や直観との対話・応答こそが、自分の中の他者たちをケアすることになるのではないかと思います。
そうやって自分自身の中の他の存在をかなしむことは、今の自分自身と真正面から向き合い、生きるということでもあります。Weのがっこうでお話を伺った現代仏教僧の松本紹圭さんは、良い祖先たちになるには「今を精一杯生きること」が大切だとおっしゃっていました。未来は常に今の積み重ねの先に出現しており、今この瞬間に私たちは未来を作り出している。
自分自身の体に応答しその中の存在たちと一緒に精一杯生きる。それが未来となり、次の世代への祈りとなる。
私は私たちのもとへと帰っていく。
私たちがずっと発していた声に耳を傾け、愛し、かなしみ、精一杯を生きていきたいと思います。
Weのがっこうは、今年から1期もスタートするとのことです。よければぜひご参加ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
