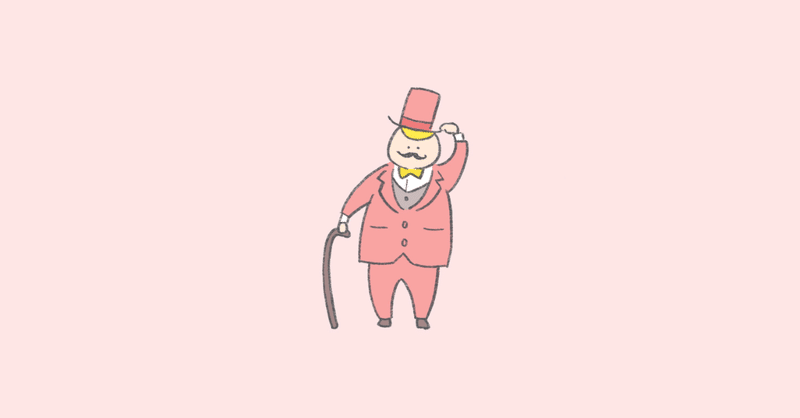
ピンクのドレスが、私に教えてくれたこと
その昔、私はまぎれもなく、クラスで一番ダサい女の子だった。
物心ついた頃から、服を買いに行くのが苦手だった。
うちの母は、1000円で買ったクマのワッペンがついた毛玉だらけのトレーナーを何年も着潰しているような人で、その母と一緒に買い物に行っても、可愛い!似合う!なんて会話は皆無。ふたりして黙々と、端から値札をひっくり返しては見ているばかりだった。
「高い」と顔をしかめられるのがいやで、本当に欲しい服は選べず、もっぱら、パーティハウス(地方のしまむら的なお店)の山のように積まれた値下げコーナーか、当時、まだ黎明期であまり可愛くなかったユニクロで、値段ばかりを気にして選んでいた。
そんなことを繰り返して育った私は、中学生になった頃には、「ダサい服を着ている」のではなく、「自分はダサい」のだと思い込んでいた。そして、いいと思う服ほど、自分には不釣り合いで滑稽な気がして、選べなくなっていた。
ちなみに当時着ていたのは、ベージュのダボっとしたユニクロメンズの短パンに、キューピーマヨネーズのロゴが入ったコラボTシャツ、私服なのに校則通りの白い靴下。
正直今の私なら、そんな子がいてもいいじゃないのとは思うけれど、当時の自分の自意識では、「クラスで一番ダサい男子よりやばい」レベルの格好をしていた。
自分でも気後れしてはいたので、塾でも遊びでも極力制服。
でも悲しいかな、隠しきれるわけもなくて。
私服がダサすぎて、オシャレグループの女子たちにいいようにからかわれたり、私服を見られたくなくて、放課後友達と遊びに行くのを断ったり。
自己肯定感も底辺で、それはもう、私の青春にゆゆしき影を落としていた。
高校二年になったとき、そんな私に一度だけ、彼氏ができたことがある。
別のクラスで話したこともない、それもちょっとイケイケな男子に、突然告白されたのだ。
彼は友人の元カレだった。
普通だったら絶対付き合わなかっただろうけれど、当時、私は私服がダサいことがバレていじめられ、好きだった部活を辞めてしまったところだった。そしてその友人というのが、同じ部活で私がいじめられているのをニヤニヤしながら見ていた子だったので、なんだかグチャグチャで投げやりな気持ちで、勢いで付き合ってしまったのだった。
「ねえ、初デート、何着ていくの?」
私がろくな服を持っていないことを知っていた中学時代の友人に、心配そうに尋ねられ、私は猛烈に気が重くなった。
当たり前だけど、デートに来ていく服なんて一枚たりとも持っていなかった。日曜の映画に制服で行くのは無理がある。
「服、買いに行こう。私が決めてあげるから」
自分のことのようにワクワクしている友人に半ば強制的に連れられて、乗り換え駅のデパートに行った。
「そもそもさ、どんな系の服が好きなの?」
何系? 好き? わからない。自分がどんな服装が好きかなんてわからない。安いか、馴染みがあるか(例えばキューピーマヨネーズのロゴのように)でしか、長年服を買ってこなかった。
「これは?」
「え、ちょっと違うかな…」
「これは?」
「え、うーん、ちょっと、違うかな…」
ぼやぼやしながら友達について回り、1着も買えないまま1時間経ち、2時間経ち、しびれを切らした友人が、もう見るからに「コンサバ・デート服」みたいな服が売っている店の前で立ち止まった。
「ねえ、もうこれにしよう! 絶対にこれ!」
それは、胸元にパールがパラパラとついた、パステルピンクのニットだった。
「絶対に似合うって! もうこれにしよう! これ買うまで私もう動かない!」
ピンク? 私が? そんなの着れない。絶対に着れない。
せめて水色にしようと言っても、彼女は断固として譲らなった。
「ダメ! みずたまはピンクが似合うの!」
挙句、店員さんにも一緒になって押し切られ、それまでの人生で一番高かったそのパステルピンクの4000円のニットを、目をつむるようにして私は買った。
後日、初デートの夜。彼から電話があって、私はあっさりとフラれた。
そうなることはわかっていた。
私には、あのキラキラとした可愛いすぎるピンクのニットが、どうしても着られなかったのだ。
◇
大学生になって、社会人になって、化粧をして、雑誌を読んで。
なんとか年齢的にも、「シンプルな服装でもそれなりに見られる」年齢になってきたことと、何よりユニクロ様がどんどんお洒落になってくださったおかげで(!)ヤバさは半減したと思うけど、私は相変わらず服の値段を気にしてばかり。地味だったり、年相応じゃなかったり、洗練されていなくて、やっぱりちょっと、へんてこりんな格好をしていたと思う。
そんな私に転機が訪れたのは、一念発起、出会い系アプリで出会った夫とめでたく結婚し、式を挙げることになったとき。
はじめから安い式場ばかりをピックアップする私に、夫は「なんでそんなに金額ばかり気にするの」と呆れていた。
何度も険悪になった末、夫がここにしようと言ってくれたのは、ドラマのロケでも使われるような、非常に洗練された(そして私にはあまりに素敵すぎる)、青山の式場だった。
衣装合わせをする段になっても、何度も夫と喧嘩をした。
やっぱりもじもじと一番安いドレスから試着していく私に、夫はことごとくNGを出した。
特に決まらなかったのはカラードレスで、ネイビーやグレーや、地味な色のドレスばかり試着する私に、夫はどんどん苛立っていった。私は私で、度重なるNGと不機嫌な夫にほとんど半泣きで、ドレスなんて自分には到底似合わないのだと絶望的な気持ちになっていた。
あまりに決まらず空気が重くなり、一息つくために入った喫茶店で、夫は深いため息をついた。
「お金はもちろん大事だと思うけどさ」
「なんで似合うとか、一番可愛いと思うものとかじゃなくて、こんな大事なことを、なんで値段で決めようとするの」
「ピンクのやつがいいと思うって。俺はもう何度も言ってるよ」
夫が薦めてくれていたそれは、一際華やかで追加費用が何万円もかかる、コーラルピンクのドレスだった。
ああ、同じことが昔にもあったな、と思った。
結局一度も袖を通さなかったピンクのニット。着てみればよかったのかな、と何度も思っては打ち消して、処分もできないまま、多分まだ実家のタンスに眠っているあのニット。
夫と、そして遠い昔の友人の言葉に、全身を預けるようにして、そして正直に言うと、もうさっさと決めてしまいたくて、私はピンクのドレスに予約を入れた。
挙式当日。綺麗にメイクをしてもらって、あの鮮やかなドレスに袖を通した時のときめきは、今も忘れられない。
パニエをはいて、背中の紐を一つずつ締めてもらって、鏡の中にいる自分を見た瞬間、えも言えぬ感情が一気に押し寄せた。
それは喜びだった。
その鮮やかなピンクのドレスは、あまりにも可愛かった。
そしてそれは、身につけた人を、今までのいつよりも、可愛く見せてくれるドレスだった。
どうしようもなく嬉しかった。飛び跳ねたいくらい、涙が出るくらい、信じられないくらい、嬉しかった。
可愛い服を着ることが、こんなに嬉しいことだと知らなかった。
身体の奥がぱちぱちと弾けるような恥じらいと、それを全て攫ってしまうような猛烈な嬉しさで、指先が細かく震えていた。
ハレの日と日常という規模の違いはあるだろうけれど、ああ、みんなこんな気持ちが嬉しくて、女の子たちはお洒落をして、可愛い服を着るんだと、私は人生で初めて理解した。
結婚式なんて恥ずかしいばかりだと思っていた。疑心暗鬼になったり、いやな気持ちになるものだと思って、当日がくるのを怖いと感じていたくらいだったのに。
式に来てくれた友人たちも、すごく驚いて、沢山褒めてくれた。まさかピンクにするとは思わなかったと、口々に言ってくれた。
いつもなら素直に受け取れない、そんな褒め言葉にさえ、天真爛漫にありがとうと言った。もう、ただただ、明るくて、嬉しくて、幸せだった。
服にまつわる数々の黒歴史や自信のなさ、後ろめたさ、恥ずかしさ。
数々のコンプレックスに天変地異が起きたような、蛹が蝶になったような、とにかく自己肯定感が爆上がりした一日だった。
◇
それから少しずつ、服を買うことに吹っ切れていった。
それまで手を出そうとも思わなかった、少しいい革の鞄や、とてもじゃないけれど選べなかった仕立ての良いコートなんかを、非常にドキドキしながらも手に取れるようになってきた。
自分に似合うものを選んで、堂々と身につける幸せが、30歳を超えて、やっとわかるようになってきた。
何より、馬児にも衣装じゃないけど、私でも、素敵なものを身につけると、それなりに素敵に見えるのだと気づいてしまった。服というのはすごいものだ、と。もう、この魔法を使わずにはいられない。
少し恥ずかしいけれど、私は自分のドレス姿の写真を携帯の中に持っている。そしてたまに見返す。見返すたびに、ついつい嬉しくなる。…バカですよね。
それでも、たとえば夫と喧嘩したとき、「だけどこの夫は、私にあのピンクのドレスを着せてくれた人なのだ」と思うと、なんだか許せてしまったりするから、馬鹿にできない。
いつか息子が結婚したら、お相手の方が嫌でなければ、なるべく式は挙げなさいと、言おうと思う。ドレスの金額には、目を瞑ってあげなさい、とも。
この記事が受賞したコンテスト
私の、長文になりがちな記事を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。よければ、またお待ちしています。

