
月末映画紹介 『デッド・ドント・ダイ』 『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』批評
新型コロナウイルスの影響によって休業していた映画館がようやく再開し始めた。まだコロナウイルスの驚異は続いており、客足も遠のいたままだ。新作の公開もいまだ見合わせているものが多いが、そんな中でも素晴らしい作品が公開されているので紹介しようと思う。
古き良きソンビ映画に敬意を捧げる『デッド・ドント・ダイ』
名監督、ジム・ジャームッシュの新作映画であり、ゾンビアポカリプスをテーマにした作品である。
ジャームッシュの作品はどれも静謐で、しかしユーモアもある独自のものだ。ゾンビ映画であればアクションも発生するし、観賞前はどうなるのだろうと思った。
しかし、いざ観賞してみるといつも通りジャームッシュ節満載の素晴らしい作品だった。
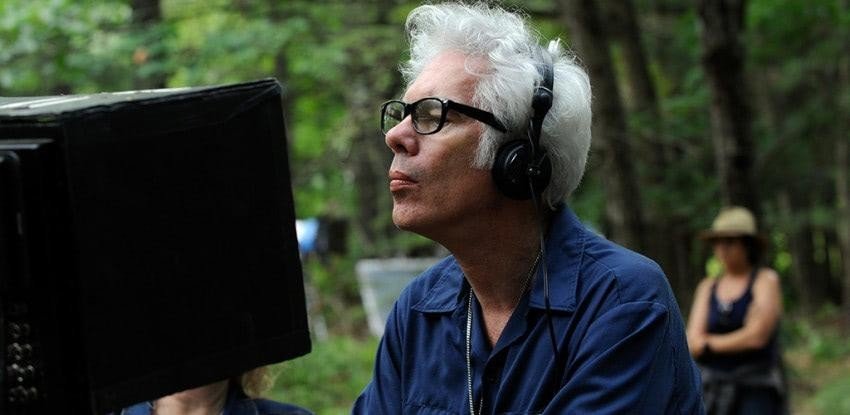
ゾンビは弱い
多様性が強調される時代になったせいか、昨今のゾンビ映画には多様なゾンビが登場する。走るゾンビ、武器を使うゾンビ、喋るゾンビ、巨大化するゾンビなど様々だ。
しかし、ゾンビ映画の歴史を紐解くとゾンビは弱いものであることが分かる。いや、弱くなくてはならないと言った方が良い。
ゾンビ映画を大成させ、現在僕たちが持つゾンビのイメージを作り上げたのはジョージ・A・ロメロ監督の『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(1968)という映画である。
(この映画は版権がないのでYouTubeで鑑賞できる)
ブードゥー教における使役される死体という精霊であった。ゾンビはこの『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』によってよろよろ歩き人肉を求めて襲いかかる存在というイメージが定着した。
ロメロがよろよろ歩くゾンビを生み出した理由は当時の社会状況をメタファーとして描くためだった。
1960年代のアメリカでは白人と黒人の対立が激化していた。武力闘争も止むを得ないとするマルコムXの登場と暗殺を初め、黒人の公民権運動が無視できないものとなっていたからだ。
そんな時代に作られた『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』では、ゾンビに襲われた白人女性が黒人男性の家に逃げのび、立て篭もる。
1965年まで白人と黒人は結婚できず、人種間対立が原因の暴力が多発していた時代に主人公が黒人で、白人女性が黒人男性の家に二人きりになるという映画はそれだけで当時の観客にとって衝撃的だった。
60年代はカウンターカルチャーの時代だった。ベトナム反戦運動、公民権運動、ヒッピー、ロックンロールのような体制に対して反発する運動やカルチャーが激化した時代だ。
しかし、若者を中心に盛り上がったベトナム反戦運動に対して、当時の合衆国大統領リチャード・ニクソンは「声なき多数派は私を支持している」という文脈の発言をした。声なき多数派=サイレント・マジョリティは実際にニクソンを大統領に再戦させたのだ。
アメリカ南部に多いサイレント・マジョリティのブルーカラーの白人たちは今もトランプを支持し、黒人を差別し、銃を支持し、キリスト教を字義通りに信仰している。
当時も今も、知識層やリベラルは声を上げ保守的な大統領を批判し、人種差別に反対し、女性の権利拡充に声を上げている。しかし、学歴が低く、自分たちの声を届かせることができない保守層、サイレント・マジョリティこそアメリカの多数派なのだ。
彼らは一人一人の力は弱い、なぜなら知識層ではなく、地位もないから。
そして時代の流れに乗れなかった保守的な人々だ。
ロメロはこのサイレント・マジョリティをゾンビというメタファーを使って描いたのである。だからゾンビ一人一人は弱く、歩みが遅いのである。まるで時代に乗り遅れた人たちのように。
『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』はサイレント・マジョリティである保守的な白人と黒人や若い世代(映画では若い女の子に象徴される)などの対立を描いた極めて社会的な映画なのだ。
この映画のあと、後続の映画作家たちによってゾンビはどんどん強い存在へと変化を遂げる。ロメロは亡くなるまで弱いゾンビにこだわり続けたにも関わらず。
ジャームッシュは時代の流れに反して『デッド・ドント・ダイ』で、ロメロのゾンビ像に忠実な弱いゾンビを描いている。
ではジャームッシュは一体ゾンビを描くことで何を表現しようとしたのだろうか?
※以下ネタバレを含みます
冷笑と無関心へのジャームッシュの怒り
『デッド・ドント・ダイ』はジャームッシュ映画の常連たちが多数出演しているが、派手なシーンはほぼ皆無である。ジャームッシュらしい映画だと上述したが、ゾンビ映画にしてはあまりに静かすぎるのである。
その理由はこの映画全体が覆う冷めた空気感である。ジャームッシュの映画は基本的に静謐であるが、その静かさには温かさを感じることが多い。しかし今回は冷たい静かさなのである。
この映画の登場人物の多くが、ゾンビが現れてもパニックにならない、ゾンビを殺したりすることにも感情が動くことがない。そしてそんな状況でもジョークを飛ばしたりする。
この映画のキャラクターを見ていると、政治も社会も人間関係も、数えきれないほどの異常事態が起こっているのに無関心で、冷笑的な態度をとる現代人を彷彿とさせる。
異常事態だが、自分が何か行動したり発言することは無意味であると信じてやまない現代人を象徴しているように感じるし、他者への共感能力が低下し、黒人男性の前で「Make America White Again」というキャップを被るスティーブ・ブシェミ演じるトランプ支持者の男も極めて示唆的だ。
無関心で冷笑な人間は全員殺され、生き残ったのは5人。3人の少年、世捨て人、日本刀を振り回す女性。
ジャームッシュは子供たちは未来だとインタビューで述べている。トム・ウェイツ演じる世捨て人は世の中への関心と警戒を捨てなかった。ティルダ・スウィントン演じる女性はUFOに乗って消える。それは先の見えない世の中における奇跡、もしくは希望かもしれない。
生き残った人に共通するのは社会との繋がりと共感ではないだろうか?
僕はそう感じた。
参考
時代を超える普遍性を持たせた脚色『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』
ルイーザ・メイ・オルコットという女性作家の半自伝的小説『若草物語』を、『レディ・バード』のグレタ・ガーウィグが監督した作品。アカデミー賞では6部門ノミネートされ、衣装デザイン賞を受賞した。
オルコットとガーウィグという二人の芸術家
オルコットが『若草物語』を発表した19世紀は、まだまだ男性中心の社会であり、女性の悩みや夢、思想、すなわち女性の実存の問題を描いた小説は革新的だった。

ルイーズ・メイ・オルコット

グレタ・ガーウィグ
オルコットやラルフ・ワルド・エマーソン、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー、マーガレット・フラー といったリベラルな作家たちは神秘主義やフェミニズムを唱え、彼らは超越主義と呼ばれた。
しかし、オルコットはのちに超越主義的な共同体を批判的に描いている。このことはガーウィグがこの映画を制作することにとって強い影響を与えていると思われる。
ガーウィグは19世紀のこのリベラル小説とオルコットと極めて先進的な女性作家の生涯を、21世紀の彼女なりの思想を取り入れ昇華させたと言える。
時間軸をバラバラに入れ替えながら、画面の色調や編集によって混乱しないような天才的な演出術、オルコットの人生と自分の人生を重ね合わせメタフィクション的に描く脚色の才能、どこをとっても映画として素晴らしい。
ガーウィグは本作の制作に際して、オルコットの作品、生涯、研究書、ありとあらゆる関連文献を隅々まで読み込み、撮影に望んでいる。
オルコットは生涯結婚しなかった。19世紀という時代は、結婚は女性の自由を犠牲にすることを意味していた。体も自由も財産も思想も夫の所有物になる。先進的思想を持っていたオルコットは自由を失うことを嫌い、結婚を放棄したのである。
よってこの映画も、オルコット自身=次女のジョーの思想が色濃く反映している。
予告編にもあるセリフなので書いてしまうが、
「女の幸せが結婚だけなんておかしい!そんなの絶対に間違ってる!
でも、どうしようもなく孤独なの」
というセリフがこの映画の最も大きなテーマとなっている。
フェミニズムとノンバイナリー
ガーウィグは映画監督ノア・バームバックのプライベートのパートナーであるが、家庭に篭ることなどなく極めてアクティブに活動してきた。ガーウィグが脚本を書き、バームバックが監督した『フランシス・ハ』という映画がある。
自由奔放な女性フランシスをガーウィグ自身が演じており、線路に放尿したり自分で脚本書いてそれやるか?という映画だ。不完全で、半端な女性だが、それでも自力で生きていくという人生への強い意志を感じる傑作だ。
そして、アカデミー賞にもノミネートされた監督作品『レディ・バード』は、彼女の半自伝的作品であり、ガーウィグにとっての『若草物語』とも言える作品である。
その作品でも、母親に反発して車から飛び降りるような強気な女性をシアーシャ・ローナンが演じており、ガーウィグ自身がモデルと言われる。
ガーウィグが生み出す女性たちは常に自立していて、打たれ強い。どの作品もフェミニズム映画と呼んでいい映画だ。
しかし僕はガーウィグの映画は女性の権利や自由を訴えるような映画とはまた少し違うイメージを抱いている。どの映画も性別を感じさせない、所謂ノンバイナリーなイメージを感じる。フェミニズムであり、ノンバイナリーである、個人主義という言葉が一番相応しいのがガーウィグ作品の特徴だろう。
『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』は「結婚だけが女性の幸せではない!」というジョーのフェミニズムがテーマであるが、貧しくても夢を捨てても愛する人との結婚が私の幸せだと考えるメグの価値観も尊重する。お金が大切でお金のない結婚は意味がないと考えるエイミーの思想もまた尊重するのである。この映画はフェミニズムの観点から批判されてきたありとあらゆる価値観すらも許容する個人主義映画なのだと思う。
そして今作もノンバイナリーな雰囲気を感じる作りになっているが、これはガーウィグが意図的にそう演出していると考えられる。
なぜならオルコットは性同一性障害だったことが分かっているからだ。「私は女の体に閉じ込められた男」だと告白する手紙が残っており、ガーウィグもこの手紙を読んだことをインタビューでも語っている。
オルコットの作家としての生き方、女性としての生き方、性別を超えた人としての生き方をガーウィグは自分自身と重ね合わせ、リスペクトを込めて描いた。
自己を、オルコットを、パートナーを、女性を、ノンバイナリーを、全ての人のためにこの映画はある。大傑作だ。
参考
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
