
なぜゲームの実写化は失敗してしまうのか?
ゲーム誕生から一貫して失敗し続けるゲーム実写化
『バイオハザード: ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』を映画館で観てきました。厳しい映画でした。あまりの厳しさにお手本のような苦虫をすり潰したような顔をしながら映画を観てしまいました。
思えば、ゲームの実写化というのはほとんど上手くいっていません。
古くは『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』『ストリート・ファイター』、21世紀に入ってからもミラ・ジョボビッチ主演『バイオハザード』『サイレントヒル』『トゥームレイダー』『モンスターハンター』など厳しい作品が並んでいます。
『ソニック・ザ・ムービー』でのソニックのビジュアルがヤバすぎて公開前に緊急で修正が入ったのも記憶に新しいところ。

ゲーム実写化の失敗は僕の主観だけの問題ではありません。
アメリカの批評サイトMetacriticは評論家の平均スコア100点満点中61点以上の作品を高評価の作品と位置付けており、49点以下の作品を低評価の作品としています。
上記の作品の評価を見てみましょう。
『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』35点
『ストリートファイター』34点
『バイオハザード』33点
『サイレントヒル』31点
『トゥームレイダー ファースト・ミッション』48点
『モンスターハンター』47点
『ソニック・ザ・ムービー』47点
『バイオハザード: ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』44点
と言ったように高評価な作品は一つもありませんでした。
ちなみに僕がざっと調べた結果では『サイレントヒル』の続編『サイレントヒル リベレーション3D』が16点でゲーム実写化史上最低でした。
脚色の難しさ
では一体どんな理由でゲームの実写化はことごとく失敗してしまうのでしょうか?
理由は大きく分けて2つあると思います。
一つは脚色の問題です。
脚色とは元々存在する物語に手を加えアレンジする作業です。これはゲームでも小説でも実話でも、物語を別のメディアに移植する際には、多かれ少なかれ必ず発生する作業であり、避けては通れない大切な作業です。アカデミー賞では脚色賞という部門があり、その年の最も優れた脚色に賞が授与されます。
ゲームを映画として脚色する際、いくつかの問題が生じます。一つは尺の問題です。
映画はだいたい90分から長くて3時間くらいの長さが一般的ですが、ゲームはクリアするまでに総計30時間〜60時間、やり込み要素も含めれば100時間を優に超える時間がかかります。
もし2時間で全クリできてしまうゲームがあればゲーマーたちから総スカンを喰らうのは必至。無料ゲームや低価格のゲームを除けば数週間から数ヶ月かけてプレイするボリュームが一般的なのです。
それを約2時間ほどの映画にまとめるのだから、必要な部分と不必要な部分を淘汰していく脚本的な編集はかなり多く必要になります。元の物語から数%の部分だけを抽出し、魅力的な物語にする脚色の技術は簡単なものではありません。
小説などは大巨編であっても、アクションより心情が事細かに描写されることが多いので、実際の物語のボリュームはゲームほどにはならないことが多いです。なぜなら文字メディアである小説は「動き」よりも「心情」を描くことに長けているからです。
映画ももちろん心情を描きますが、それは演技における表情や仕草を通して、もしくはカメラワークや編集を通して、つまり「動き」を通して描かれるのです。
もちろんモノローグや直接的なセリフで淡々と心情を語っていく映画もあるのですが、基本的に、それでは面白くありませんし、映画の特性が活かされていません。
ゲームや小説であればテキストで分からせればいい部分も、映画では必ず映像で理解させなければなりません。ポケモンの「こうかはばつぐんだ!」を映画で伝えるには、全て映像で表現しなければいけません。
そしてゲームはプレイヤー自身がキャラクターを操作し、世界観に没入してキャラクターになりきるメディアです。しかし、映画はあくまで観客として画面の中で起きていることを観測することしかできません。
どちらが優れているという話ではなく、同じ映像メディアでも根本的な在り方が違うということは言えるでしょう。
正解が分からないキャクターデザインの問題
そしてもう一つはキャラクターデザインの問題です。
小説やゲームを実写化する際は、元のキャラクターを現実の存在として描き直さなければいけません。
ファンタジーであればあるほど、現実の姿として再構築するのは難しくなります。なぜならリアリティがないからです。リアリティがないものをリアルに描いた時、人間は拒否反応を示すものです。
ここで改めて思い出してほしいのが上の写真のソニックです。大規模な修正が行われるほどに世界中から大批判を受けたソニックですが、これはあまりにリアルすぎたのが原因でしょう。可愛らしさがなく、本当にこういう動物がいるかのようです。
人間が人間でないものをまるで人間かのように扱う時に「不気味の谷」という概念が存在します。
例えば、ロボットを例にしましょう。

気持ち悪いでしょうか?恐らく多くの人が不快には思わないでしょう。
それではこちらはどうでしょう。


上は日本テレビのAIアナウンサーのアオイエリカさんです。
下は紅白歌合戦に出場したAI美空ひばりです。
ちょっと気味が悪くないですか?
最後にこちらはどうでしょう?


上は『ブレードランナー』のロイ・バッティ。アンドロイドと人間の見分けがつかない世界のアンドロイドです。
下は『Nier : Automata』の2B。数多のコスプレイヤーがコスプレをしたアンドロイドのキャラクターです。
恐らくこの二人は気持ち悪くないと思います。
僕が今「二人」って書いても違和感を感じなかったらそういうことです。
ウォーリーのように、人間の形をしたロボットや人間と同じようにコミニュケーションを取るロボットに人は親近感を抱きます。
ところが、アオイエリカさんやAI美空ひばりのように、段々と人に似過ぎて来ると、むしろ不気味に感じるのです。
しかし、人と見分けがつかなくなれば、もはや不気味さも消えてしまいます。
これが不気味の谷の概念です。
この理論を敷衍して考えると、ソニックも必要以上にリアルだったから批判されたと考えることができます。人間ではないキャラクターにはデフォルメが必要です。
ミッキーマウスがこんなんだったら嫌でしょ?

そしてゲームを実写からする際は人間のキャラクターにもアレンジを加える必要があります。ゲームでは許されるコスチュームの多くは、現実で着るとただのコスプレになってしまうためです。
しょぼいコスプレ感を出さないためにアレンジを加えると、イメージと違うという批判に晒されることに繋がってしまうのが難しいところです。
映像メディアであるゲームは、小説以上に確固たる共通のイメージがあります。正解が示されているのに、正解の通りにやるとしょぼくなってしまうというジレンマです。
リアルにすることも、忠実に再現することも、アレンジを加えすぎることも、正解になりうるし、不正解にもなりうる。これがゲーム実写化の難しさです。
正解になるかどうかは、俳優の容姿と演技力、衣装やメイクアップアーティストの能力、演出や脚本の方向性など様々な分野の微妙な匙加減で決まると言っても過言でもありません。
この絶妙な微調整に成功しているのが、MCUでしょう。ゲームではなくコミック原作ですが、原作のイメージを損なわず、古臭さを払拭することにほぼ全キャラクターで成功していると言えます。
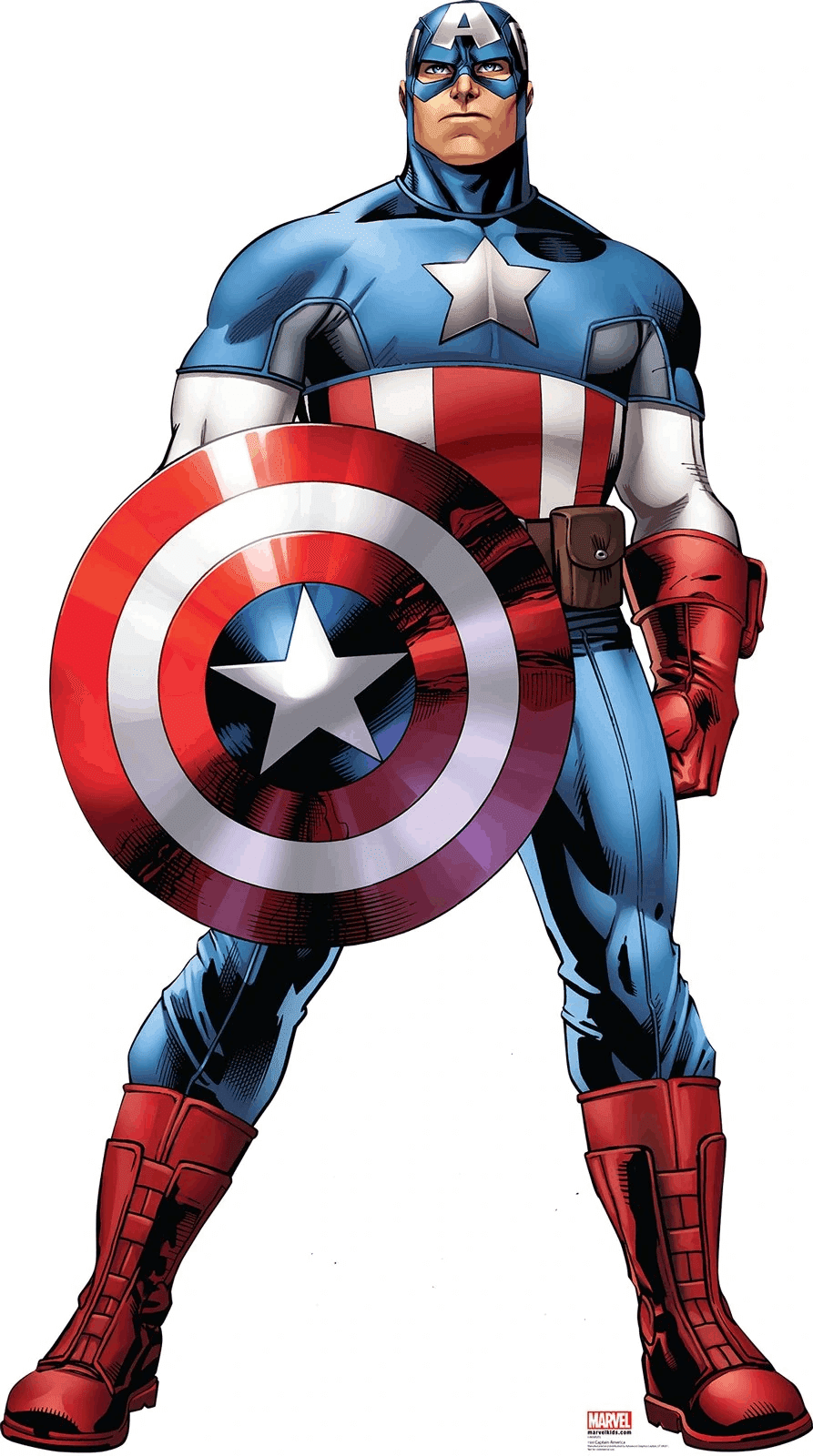

また、ザック・スナイダー監督の『ウォッチメン』は、敢えて原作を忠実にキャラクターを描いていて、時代に取り残されたヒーローたちというテーマを明確にする効果を効果を発揮しています。


全く逆のことをしているのが『名探偵ピカチュウ』で、ライアン・レイノルズがまんま本人のようにピカチュウを演じるというポケモンを根本から再構築するキャラクター造形は、大きな話題になりました。

以上の理由から、ゲームの実写化のほとんどは成功していません。
ゲームはゲームとして割り切り、無理に映画化しない方がいいかもしれません。
来週には『アンチャーテッド』が公開し、『メタルギアソリッド』の映画化も企画中です。これらの映画化が大成功して、僕の分析をぶち壊してほしいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
