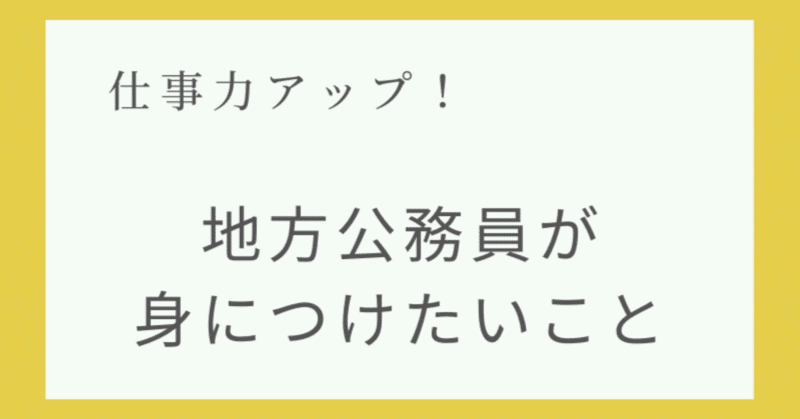
仕事力アップ!地方公務員が身につけたいこと:地方公務員に求められるコミュニケーション能力を考える
企業や行政の現場で、入庁直後に退職してしまう若者が増えています。社会人に必要な能力として「コミュニケーション能力」が重視されていますが、コミュニケーションが十分に取れていればこうした事態ももっと少なくて済むのではないでしょうか。
コミュニケーション能力とは、一方的に相手に合わせることではありません。双方向のやりとりが重要です。学生のコミュニケーション能力だけでなく、学生を受け入れる現役公務員にも、新採用の若者の考えを受け入れるだけでなく、自分の考えを理解してもらえるよう伝える力が求められます。そのためには、どうすればいいのでしょうか。
社会人に求められる力として「コミュニケーション能力」が重視されている
地方公務員になるためには、試験に合格するための学力だけでなく、地域を支える人材としての人間性も重視されます。そのため、採用試験では面接やグループディスカッションなど、コミュニケーション能力を測る試験も多く行われます。面接では「上司と意見が合わない時はどうしますか?」「残業を命じられた時はどうしますか?」などの定番設問がありますが、期待されるのは肯定的に答えることです。「上司と意見が合わない時は、上司の話を素直に聞く」「残業を命じられた時は仕事に必要なものとして受け入れる」。地方公務員が市民のために働くという使命感を持ち、チームワークを大切にするという役割を果たす以上、それは必要な姿勢です。
入庁直後に退職または休職してしまう若者たち
しかし、採用試験に合格した若者の中には、入庁直後に退職または休職してしまうケースが多く見られます。その理由の1つは、コミュニケーションの不足があるように思います。先輩や上司との人間関係に悩んだり、仕事のやり方に馴染めなかったり、自分の意見を言えなかったりすることで、ストレスが溜まってしまうのです。最近は退職代行サービスまで登場し、採用した側も若者の本心が分からないまま退職してしまうケースも多いです。
採用された若者だけに問題があるのか
これは、採用された若者に一方的な否があるのでしょうか。もちろん、そうした側面もあるでしょう。社会がそのような若者を生み出した面もあるかもしれません。しかし、コミュニケーションは本来、双方向で行うものです。現役公務員と新採用職員では経験者と未経験者、先輩と後輩という立場の違いはあるとしても、新採用職員が先輩の考え方を無批判に受け入れることがコミュニケーション能力ではありません。それと同じくらい、現役公務員が新採用職員の考え方に耳を傾けることもコミュニケーションには必要であり、それができるかどうかは先輩のコミュニケーション能力次第なのではないでしょうか。
「今どきの若者は…」という言葉は、どの時代にも見られた
「今どきの若者は…」という言葉は、どの時代にも見られました。「新人類」などという言葉もかつて流行しました。したがって、採用直後に退職する若者を一方的に責めるのではなく、現役公務員にも若者の考えを聞く力が求められると思います。市民に寄り添うサービスを提供している地方公務員には、特に当てはまるでしょう。若者は、新しいアイデアや感覚を持っています。それを活かすことができれば、地方公務員の仕事ももっと楽しくなるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
