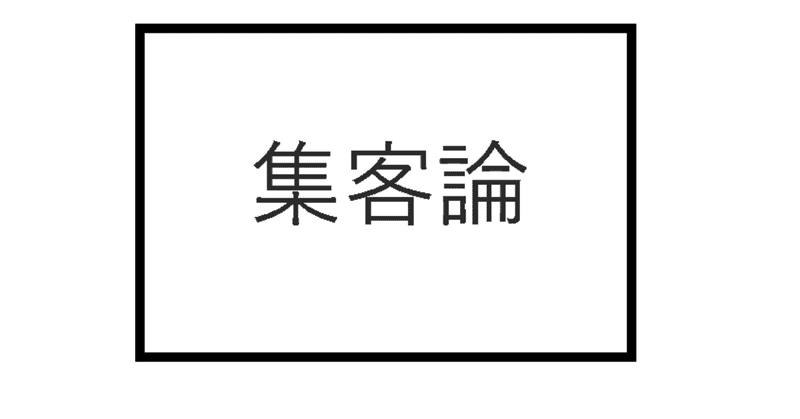
#350 集客論
はじめに

この論文は理想論である。集客論を書くことができ、活用できるものなら、起業をした人の苦労を減らすことができよう。理想論と書いて、理想論と言うタイトルで書くのもいいかとも思った。
集客の意識を持つ人はどのような人だろうか。おそらく、集客しようと思っている人である。また、集客について書く人はどのような人だろうか。集客について教える仕事をしていく人だろう。
もちろん、確実な集客論を書くためには、確実な結果を出すことが大事だ。しかし、その確実な集客の結果を出したことがない人でも集客意識を持つことはできるし、集客について書くことはできる。
もちろん、実績、結果を持っていた方が信用性が上がる。けれど、一様は書くことはできる。それは想像かもしれないし、空想かもしれない。僅かな経験や体験かもしれない。けれど、書けないことはない。
仮に集客の経験を持った人間が集客論を書く状態はどのような状態だろうか。もしも、もっと人集めが必要な状態だとしたら、それは十分な経験を元にして集客論を書き始めているだろうか。
もちろん、経験はあった方がいい。けれど、問題は、今の時代での集客に成功をしているかどうか。時代を捉えることができるかどうか。そして、書く意味があるかどうかだ。
これらを備えた人が何人いるだろうか。また、教えることは難しいというか、教えるためには準備が必要となってくる。何をどのようにして教えたら、効率的になるかなども考える必要性がある。
集客とは認知活動のようなものであり、それは考えるということだけでなく、行動が大事的な感じがする。つまり、考えることも大事だけれど、行動をベースに置くことで認知活動が成立するとしたとする。
それらがバランスよく整えることができればいいが、必ずしもそうではない。最も理想はそうである。バランスよく行うことだ。行動ばかりだとセールスっぽくなる。それはマーケティングと異なる感じになる。
タイトルは集客論だが、マーケティングと考えてもいい。私が書く論文は、今は漢字二文字と論で作成している。HP論などが出てきてしまったら、漢字の括りが外れるが、マーケティング論とタイトルにしない理由はこれだ。
そのため、できる限り漢字二文字で収めようとすると、マーケティングではなく集客と言うことになる。今の時代は個人と個人が向き合うため客と言う概念も薄れてきている感じもある。
そのため、顧客とか、集客とか、客が入っている言葉を使うことで心との距離感が合わなくなるような感じがすることもあるかもしれない。というのも、今までの距離感では解決できるものも解決できないことがあるためだ。
よって、知り合い的な感覚の距離感を保つことで、より良い円滑なコミュニケーションを行い、情報交換をして、頭の中を整理して良いものを提供していくと言う流れが好ましくなっていくような感じもある。
つまり、客という言葉は、昔からあったような感じはするが、高度経済成長時代を経て距離感と言うか、土地柄の知り合い感が薄れて、なんかよくわからない状態になっている感じがある。
そのため、客側としても踏み込みにくくなるし、店側としても踏み込みにくくなる。結局、その踏み込みができないために情報交換がうまくいかずに問題が解決されないで終わるケースもあるかとは思われる。
もちろん、距離を詰めすぎても問題を冷静に解決していくことができるかどうかは微妙な話になるが、踏み込むべき所は踏み込んでいかないといけない。
ただし、それは押し売り的なことでない。仕事とキチンと向き合うということである。そして、今、そのキチンと向き合うことで発生する業務量が増加していると考える。
つまり、売上を考えれば顧客がたくさんいた方がいいことになる。つまり、集客は常に行った方がいい。そして、多くの人を集めることができたら、安定した売上を確保できるような感じに思える。
しかし、今の時代は1人あたりの抱えている問題の量が多いと想定する。その時、1人の問題を解決しようとしたら、それだけの時間を必要とする。つまり、多くの顧客を持ったら、解決が雑になる可能性がある。
理由は時間は有限だからだ。さらに言えば、エネルギーもそうだ。考えるにも脳の酸素やグルコースを使用する。グルコースは貯蔵することができずに摂取しないといけない。つまり、思考にも容量が出てくる。
つまり、多くの顧客を集客して、一定の距離感を保って、安値で販売し売上を上げていくと言うモデルや仕組みが現代に当てはまる状況や業種によって適用できない場合があると言うことになる。
薄利多売から高利少売への転化が必要だと思われる。こうりしょうばいを変換すると厚利少売という言葉も出てくる。ともかく、今には今のモデルがあると言うことになる。
しかし、薄利多売から高利少売と言うのは挑戦的な感じがある。なぜなら、少ない顧客で事業を回すことになるからだ。その顧客の環境の変化に対応することができなければ、顧客は離れると想定する。
つまり、より良い問題解決ができるかどうかや人間関係が築けていけているかどうかによる。そして、問題は薄利多売<高利少売を選択して事業を進めていくことができるかどうかによる。
それは物を売るだけではないと考える。つまり、顧客も物だけを買っているわけではない。信頼関係、信用、安心感と言った心の充実さも一緒に手に入れるために利用者となるとは言える。
となると、単に物を作り、物を売ると言うだけではいけないと言うことになる。また、これをWebサイトなどで集客しようとすると、明らかに多くの人が対象になるイメージだ。
つまり、薄利多売のイメージが先行してしまう。よって、価格を下げることになる。そして、商品自体の価値も上げにくくなってしまう。けれど、それはすでにどこかにあると考えると、それではいけないと言うことになる。
特に人は物があればある程度は生きてはいける。その上で充実な人生を送っていくためには、物だけでないライフスタイルごとの充実を求める。その充実さを得るための活用と言うことになっていく。
それは単に、商品を他の人に紹介すると言うよりは、その人を他の人に紹介したり、自分自身が他の人に紹介されたりと言うような感じで人と人との繋がりを気づく環境を手にしようともする。
人間関係が問題を解決する上で重要であり、その人間関係が築きにくい時代だからこそ、その人間関係も含めた利用を求める。そして、そこに薄利多売はあまり即していないと言うことになる。
そして、この人間関係は自分で選んだり、決めたりすることができることが大事と言える。育った環境が異なっても、育ち方が似てくる場合がある。そして、相性の良いものもいればそうでないものもいる。
物を求めると、人の存在が見えにくくなる。けれど、人から選べば、物は機能を果たしていれば十分だと考えることもある。つまり、相性の合わない人と定期的に接するよりは、相性の合う人と定期的にあった方がいい。
単に商品の質が異なることもある。けれど、人間関係がなければ作ることができない商品やサービスもある。つまり、人間関係がありきの商品、サービスを求めている場合は薄利多売ではもともと無理な消費領域となる。
人間関係と言う抽象的な言葉を用いたが、定期的に接して話をして情報を共有することができる関係性のようなものだ。それによって、生み出された商品、サービスが人間関係ありきの商品、サービスとなる。
つまり、集客をその路線で行っていくことを目的とした場合、ゴールはそこに向かう必要性がある。そのゴールに進まないと、目的から離れてしまうことになる。
顧客はそれを予期するとする。つまり、認知した時からゴールに向かうことができるかどうかを考える。そこで、ゴールに向かえないとなると離脱すると言うことになる。
これを考えると、集客は単なる集客としての認知活動ではなく、少人数を対象にして、その少人数向けに各ゴールを設定し、追うことができることが大事になる。
けれど、そのゴールも聞かないとわからないこともある。もちろん、おおよそのゴールは業界別で同じかもしれない。しかし、その途中の歩み方、手に入れるものと言うことがそれぞれ異なってくると言うことになる。
そして、Webが登場した今の時代では顧客が探すことができる情報設備を得ているようなものだ。自分の問題について真剣に考えれば、顧客は真剣に情報を収集するだろう。
つまり、情報収集をすると言うことは、ある程度前提としてあっていい。つまり、集客の前提は、見込み顧客が情報収集を真剣に行うことを前提としていいかもしれないと言うことだ。
この真剣度は色々と異なるかもしれないが、自分が仕事と向き合うぐらいの真剣度と同じだと思っていいかもしれない。そしたら、相関する。それを前提に置いたとしたら、Webに情報を置いておくことがやることになる。
つまり、Webを通じて情報を収集しようとしても、そこに情報がなければ収集することができない。見込み顧客は問題を解決するために、在る情報から選択しなければならない。
なぜなら、自分で情報を作ることができないと言うことも前提であるためだ。よって、情報を収集すると言う作業をしなければ問題解決に進むことができない。
それは、Web上に情報がなければ見込み顧客は情報を収集したり、比較したりすることもおおよそは無理になってくるという事でもある。もちろん、他の媒体で知ることができれば、それでもいい。
けれど、その可能性がない場合、また、見込み顧客がその可能性の選択肢も取ることができない場合、また少ない場合、Webから見つけ出すしか選択肢がないと言ってしまうことになってしまう。
それを前提に置いたとしたら、販売側が集客として行うことはコンテンツ制作と言うことになる。このコンテンツ制作ができて、それを見込み顧客が見つけることができたら一様は認知活動が成立したと言える。
集客とは、認知活動の次への要素もあるようで、認知した後に接点を持つためにアクションを顧客が起こすことができるようにして、実際に接点を持つと言うことになる。
まず、アクションを起こして接点を持つにも窓口的な要素を必要とする。それはいきなり扉の場合もあるかもしれないが、電話、Webメールなどの選択肢も出てくる。
そして、大事なことは、ゴールに進めるかどうかである。多種多様な状況を理解して問題解決を行っていくことができるかだ。つまり、接点の窓口を持ち、接点を持っただけで終わりではない。
実際に、ゴールを目指せそうだと思った接点を持った見込み顧客で有る場合、そのゴールに進むための道筋を立てておかないといけない。見込み顧客はゴールは見えてはいるが、道筋が見えないこともある。
そして、道筋においても、それは1つの選択肢の1つである可能性があるとこも少しは前提に置いた方がいい。もちろん、それ通りに進むことが理想ではあるが、色々と前提条件が異なると考えた方がいい。
つまり、先駆者の道筋と同じ条件でその道を進むことができるとは限らないと言うことだ。それは、まだ解決しない問題もあると言うことだ。それに知識、技術、経験なども入っていくる可能性もなくはないと言うことだ。
集客から第一の販売。そしてリピート販売、継続販売や契約に繋がるまでの道筋と言うか、集客以外の言葉で補っていくことも大事だろう。集客では第一販売の所までしか網羅することができない場合もある。
また、薄利多売の場合は、そもそも継続契約は念頭においていない。よって、薄利多売の集客は継続契約を念頭におかない集客といえる。けれど、継続契約を必要としていく厚利少売は違うだろう。もうこっちの言葉を使う。
理由は厚利少売と打つとこっちが出てくるからだ。つまり、厚利少売の集客は継続契約に繋がらなかったとしても継続契約の期待やリピート感を元にした集客でないといけない場合があると言うことだ。
そして、それは販売者にとっても都合が良いだけでなく、顧客にとっても都合が良いということで成り立っていく。となると、商品、サービスは継続契約を念頭に入れたものを考えておくことが大事と言える。
ゴールは問題解決であり、それは第一の大きなゴールに過ぎないかもしれない。そのゴールが解決したとしても、人間関係を築くと言うことは継続的なものであり、それがないと成しえない問題解決もあるとする。
その場合、第一のゴールが成立したとしても、ゴールに到達した時に第二のゴールが見えてくる可能性が出てくる。この時に継続契約をしていれば、その第二のゴールに迎える可能性が出てくると言うことになる。
第二のゴールを目指して達成することができれば第三のゴールと言うことになる。つまり、人間関係を元にしていく問題解決やゴールの場合は、同じように人間関係を円滑にしていくための環境が必要になってくる。
それは薄利多売では成し得ることはできないと考え、厚利少売へと切り替えることで成し遂げられるとする。これは販売側も見えていないかもしれない。
つまり、第一のゴールは見えていても、第二のゴールは見えてない可能性がある。それでも、人間関係を想像していく中で、第一、第二、第三の想像や理想を描き、そこに進むだろうと言うような感覚によって進むとされる。
つまり、そこを求めていくのであれば、集客をするときにも、そこを目指していく必要性があると言うことになる。理想を描くことで進むことができるとも言える可能性はあるだろう。

