
【骨博-2019-】サンプル・本文試読
2019年11月24日(日曜日)、東京流通センター第一展示場で開催する入場無料・入退場自由の《文学フリマ東京》にて頒布いたします、アンソロジー作品集の告知です。
【骨博】は、骨の特別企画展がテーマの図録風デザインで製本したアンソロジー作品集です。イラスト・漫画・小説の十五名の作家が集まり、それぞれ自由に「骨」を取り扱った作品を制作・執筆致しました。
小説作品は現代ファンタジー、歴史、ハイファンタジー、近未来SF、純文学、コメディなど多岐に渡るジャンルを掲載し、イラストもアナログからデジタルまで様々な作風のものが集まり、唯一の漫画作品にはなんと「奥さまはドードー鳥(クロフネコミックス)」「果ての星通信(PASH!COMIX)」などを世に送り出すメノタさんの書き下ろし作品を頂戴できました!
11月20日まではBOOTHにて事前予約(通販のみ/事前予約特別価格1700円/別途送料)を受け付けております。
仕様/フルカラー印刷マットPPカバー、タイトル箔押し・A5版・220頁
価格/事前予約1700円(通販のみ、別途送料)、対面一般1800円、対面大学・専門学校生1700円(要証明)、対面高校生1500円(要証明)※学生さんは学生証のご提示で御本人様分一冊のみ割引価格で販売いたします。二冊目以降は一般価格となります。
備考/先着で入場チケット風の栞がつきます。無くなり次第終了。
以下に本文の試読・サンプルをまとめました。お楽しみ頂けましたら幸いです。このページでの掲載順はあみだくじで決定しました。本誌内の掲載順とは異なります。
猿川西瓜/お月さまいくつ
「えーこの洞窟では、約千近い骨片が発見されました。すべて鈍器や刃物で破壊されていて、洞窟内に広く散乱。すべて成人の男女で、頭蓋は十三個。男性六個、女性四個、性別不明三個。老人と子どもは見つかりませんでした」
しばらく静かになったあと、少しだけ教室全体がざわついた。洞窟入り口が黄泉の国に繋がっているように見えた。
洞窟内の地図が次のスライドで映された。入り口の大きさは横幅四メートルで、一番奥は二メートルほどだ。高さは六メートル。奥にある骨片はついこの間にさらし終えたのではないかと思われるほど保存状態が良かった。
「その骨がどこにあったか、どの部分か、特定するのは大変だったわ。最初、鳥葬の場所かと思ったけれども、あきらかにおかしい」
「何がですか……」と、前列の女子学生が恐る恐る聞いた。
「骨があわないの。まずね、洞窟奥。ここに頭蓋はすべて集中していて十三体分。けれども胸骨はひとつも見つからない。骨盤は四体分のみ。鎖骨は右だけが九、左だけが八。なぜ?」
息を呑むとはこのことだった。無機質な洞窟内の地図がまるで殺人現場の推理を試されているかのように見えた。
スライドが次に進むと、地図に発見場所が書き込まれたものが表示される。
まず、解体が行われた現場は入り口。解体が進行して、頭骨や肢から骨片ができると、そのたびに奥に向かって投げられている。だから、地図上において、壁や大石のそばに落ちている事が多いのだ。
次のスライドでは、岩と岩に挟まるようにして骨片が写っていた。繊維のような細い骨が白々と光る。尖っていて脆い印象があった。握れば、ボロボロの粉になってしまいそうだった。
「えー、それでまあ一番奥から手前にかけて採取したものを調べまして並べていまして。あることに気が付きました。というのも、近くに貝塚が、まあ、あるんですが、私もよくそこにも行っておりまして、鹿とか猪の骨が見つかるわけです」
教室の空気を察してか、少しかしこまりながらもおどけた口調で境先生は話し続けた。
「その鹿や猪の骨もね、よく調べると、縄文人がどう解体していたか見えてくるわけです。お魚を三枚おろしや、胸骨を包丁でさばいて捨てるでしょう。じゃ、解体の動きが見えてくるじゃないですか。骨はメッセージです。そうして、骨に残った傷とかを調べるとね、そう、もう勘のいい人は気付いたかな? 動物解体と、この洞窟での骨片は、まったく同じ手法で処理されたものだったんだよ。細かいところまで一致していてね」
先生の声色が変わった。
清水イズ/Describe
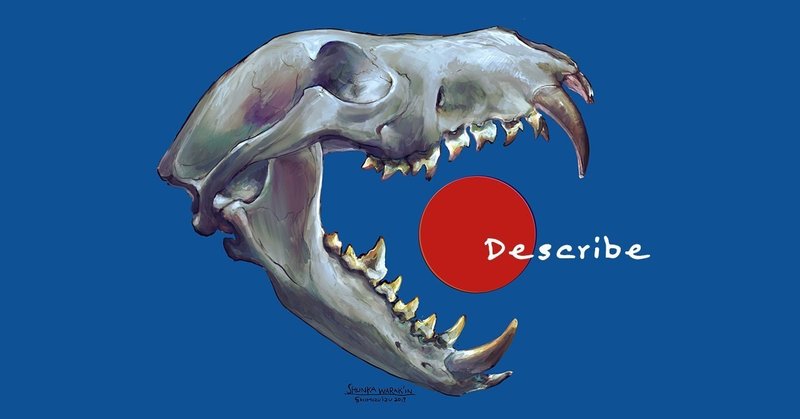
M.A.F./太古の夢から空中の夢へ
私達のいる美術部が休みの金曜日になると、梓は必ず素早く下校していってしまう。
絵が描けなければ仕方がないので真っ直ぐ帰ろうと梓なら考えそうだったが、そうではないという。
ならば、何か絵の特訓をしているのに違いない。本当に特訓なんてしているならなんてかっこいいことだろう。
それで本人が渋るのを押し切ってついて行き、電車で数駅行ったところまでやって来たのだが。
「わっ、え、デカい!」
辿り着いた先は博物館。その大広間には、ほとんど建造物のような大きさの骨格があった。
高く薄暗い天井を覗き込むように首を伸ばす恐竜と、こちらを睨み大きな口と牙を見せ付ける恐竜。
いくらなんでもこんなに大きかったとは。
その二体の周りにも、小さな恐竜の骨格や、色んな角や兜で飾り立てたいくつもの恐竜の頭がずらりと並んでいる。
「ねえデカい! 恐竜デカいよ梓!」
私は初めて見る恐竜にすっかり舞い上がって、広間の真ん中に早足で進み出た。
「うるさいぞ優。大人しくするっていうから連れてきてやったのに」
梓は、冷たくも見えるほど整った顔を少しも崩さず、長い髪を後ろでまとめて、鞄からスケッチブックを取り出した。やっぱり思ったとおりだ。
「ここが秘密の特訓場!」
「は?」
「いや、そのー、恐竜をスケッチしに来たの?」
「そうだよ。だから説明とかは勝手にプレートでも読んどけ。私も詳しくないんだ」
そう言い放つと、梓は隅のほうに鉛筆とスケッチブックを持って立ち、動かなくなった。
どう見ても真剣である。かっこいいのは確かだったが、こうなるともう私には声がかけられない。
彼女は、私と同じ美術部にいるとは信じられないほどデッサンやスケッチが上手い。
リアルな人体を描く能力は誰もが認めている。それを得るための努力も、だ。
いくらお調子者の私でも、思い付きでついてきた癖に梓の研鑽を邪魔できるわけがなかった。
山城よる(主催)/歯抜師
わずかな薄明に、ぼんやりと木々の形が輪郭を取り戻し始める早朝の森。辺りは冷たい靄に沈んでいる。
痩せこけた女の身が砕かれる音と絶叫が、秋の彩りに満ちかける山をつんざき、すぐに静まり返った。
女の身は枯れ枝のようであったが、噴き出した温かい血は冷えた空気をかすかに湯気に変え、熊の毛をしとどに濡らす。強靭な熊のあぎとに掛かれば、人間の、それも女の肉体などいとも容易く砕けてしまう。熊の爪にはあまりに薄過ぎる皮膜が破られた腹部から内臓が散り、あたりに血臭が立ち込めた。
ざあっと落ち葉を蹴散らす黒い影が、夜の残滓をうすらと抱え、まだ暗い木々の間を縫うように駆け、ぎらと光る太く厚い刃を熊の後ろ首目掛けて叩き付けた。刃の衝撃に吼えた熊が女の肉片を放り出し反撃に出ようとした瞬間、続く二つ目の影の追撃が、毛皮の下に脂をため込み始めた皮膚、まだ致命傷に到らない熊の後ろ首──初撃で斬りつけた傷に、寸分違わず叩き付けられた。
夜と朝のあわい。人里遠く、奥深い山中における刹那の出来事であった。ずん、と絶命した熊が地を揺らして倒れ臥す。
「こんな時間に、こんな場所で、女?」
熊を仕留めた二撃のうち、一撃目を与えた男は広がる血溜まりを避けて立ち、まだ若い個体であろう大きさの熊の死骸を見下ろす。大きくため息を吐き、うんざりした様子を見せた。
この山中に彼らの棲む郷があるということは広く知られているものの、詳細な場所については郷の者以外には固く秘され、ゆえに、外部の者の来訪は一切ない。
死を導き、人々の弔いの身仕度を調えることを生業として、さすらう彼ら――歯抜師の帰る場所として相応しいよう、また、死の匂いを濃厚に常纏する彼ら自身を人々が畏怖し忌避するがゆえ、その郷は山中に秘匿されていた。
郷の人間は、男衆以外は殆ど外に出ない。女子どもはせいぜい近場の林を、すぐに駆け戻れる距離で出歩く程度である。熊がうろつく薄明薄暮の時間などは腕自慢の男衆でさえ出歩くのを控える。
獣と人間が共に同じ山に棲むのだから、互いの距離を適切に保つ生活の時間がある。それは幼い子どもですら知ることだ。
「かわいそうに、こんな死に方をして」
追撃を叩き込み、熊にとどめを刺した男の方は幾分穏やかな声色で、熊の死骸のまわりに無惨にばらけている女を見下ろした。
「勝手に山に入るからだ。何処の誰だか知らんが自業自得だ」
女の身勝手な山への侵入で熊が人の血の味を覚え、それで郷が襲われてはたまらない。
痩せぎすの、冬の木立のような身体はそれでも、冬眠前の食い溜めをする熊の食糧としては食いでがあったのだろう。木の実や果物を探して徘徊するよりよっぽど効率がいい。
「人の味を知った熊は繰り返し人を襲う。気付かなければ郷人がやられていたかもしれんぞ」
「始末が間に合ったのだから、もういいでしょう。ここは私が見ているから、あなたは誰か呼んできて下さい」
ちっと舌打ちをし、遠々煕(とおとき)は熊の血で濡れた鉈の刃を拭って鞘にしまうと、落ち葉を蹴散らして駆けていった。
熊の身をこのまま放置するわけがない。捌いて毛皮をとればこの冬の誰かを暖めようし、肉は保存食にできる。内臓は乾燥などの加工を施せば薬材に利用でき、特に血は煮詰めて凝らせれば増血の薬になる。毎月の忌み籠もりに血を流す女たちが喜ぶはずだ。
熊は骨の一片とも余さず利用できる最大の獲物だった。狙って穫れるものではなく、また、狙うにしても強度の危険が伴うため、積極的に狩ろうとすることも滅多にない。
熊が女の身を貪るのに夢中だったからこそ、比較的容易に仕留めることができたが、幸運と呼ぶには複雑な心境で、日照雨(そばえ)は、落ち葉に半分埋もれて転がっている女の頭部を拾った。
熊の死骸と、女の血や肉片が散る場所から離れた日照雨は、背負っていた荷を解き、地面に道具を並べる。簡易な作業場として布を敷き、女の頭部を置いて緩慢に呼吸する。朝の冷たさを胸いっぱいに吸い込むと、頭の中が透明になってゆくような気がした。
メノタ/いさなのて

酒匂ささ/抜殻
駅前の小さな喫茶店でナポリタンを食べつつ、我ながら馬鹿なことをしているなと他人事のように思う。流石にスマホは持ってきたが、電源を切ってリュックの底に押し込んでいるあたりが情けなさに拍車をかけている。
本当に衝動のまま、こんなところまで来てしまった。それなのに着いたのは何の変哲もない田舎町で、ドラマのような劇的な出来事は起きそうもない。日常を離れて何か気持ちに変化が起きたとか、そういうことすらなかった。だからもう少し、無謀なことをしてみたくなったのかもしれない。
バスの時刻表を見れば、最終までは三時間ほど。このまま引き返すのは面白くなくて、昨夜の記憶から逃げるような気持ちででたらめに町を歩き始める。人の気配から遠ざかるように道を外れて、やがて僕は目的もなく平坦な木立の中へ足を踏み入れた。
木立の中に道らしき道はない。しかし人が入ることはあるようで、足元には踏み固められた跡がある。僕はそれに沿って木立の中を彷徨い、気がつけばすっかり方向感覚を失っていた。
来た道も分からない。行く手はただただ同じような景色が続いている。そうなってはじめて僕は怖くなった。パニック状態で闇雲に木立の中を駆け、すぐに息が上がって立ち止まる。思い出して電源を入れたスマホは圏外。途方に暮れて、またとぼとぼと歩き出す。
あてもなく森の中を彷徨い歩き、やがて時間の感覚も曖昧になった頃、僕はようやく代わり映えのしない景色から抜け出すことができた。
真っ白な湖が目の前にあった。踏み出した足元は脆い白砂、湖畔には草の一本も生えていない。白砂はなだらかに水中へ続き、湖底は死んだ珊瑚のような欠片で一面埋め尽くされている。気味が悪いほど透明な水の中に生き物の影は一切ない。
対岸まではどのくらいだろう。少なくとも数百メートルは先の対岸もまた白く、随分と奥に緑がぼんやりと見えている。湖の右手に張り出している木造の、あれは古びた社だろうか。
あたりはすっかり静まり返っている。森の中ではあれほど賑やかだった鳥のさえずりすら聞こえない。ただ囁くように風が吹き、さざ波が立つ。時折、立ち尽くす僕の足の下で白砂がシャク、と鳴く。
汗と泥に濡れた身体がひやりとした。真っ白な景色はまるであの世のようだ。僕はまだ生きているはずなのに、ここがこの世であるという確信が揺らいでくる。いっそ幻覚と言われた方がすんなり飲み込めるかもしれない。
堪らず白砂の上に腰を下ろした。酷く喉が渇いていた。駅で買ったペットボトルはもう空だ。荷物は小さなリュックひとつ、食料らしい食料も持っていない。道を探して再び木立を彷徨う気力も残ってはいなかった。それなのに、目の前にある水を飲もうとはどうしたって思えない。何故だろう、飲めば本当にこの世へ戻れなくなりそうな、そんな奇妙な予感がした。
早房透人/くらがりのはこ
私と村の関係は、木の葉が散り始めた頃に始まった。冬に備え、貯蔵するための肉や木の実を求めて山に入ったとある夫婦が私を見つけたことが全ての始まりで、彼らに手を引かれながら下った山道は、とにかく転ばないようにと必死だった。一歩踏み出すごとにかさりと音を立てる落ち葉のせいで、何度足を滑らせたことか。その度に腕を引いてくれたのは、父だったか。それとも母だったか。もう記憶は朧げになってしまっていて申し訳ないのだけれど、とにかくほっとしたことを覚えている。見上げた赤色の葉を数え、落ちてくる黄色い葉を数え、虫の声を子守唄に落ち葉を被って眠る夜はもう来ないのだと。
私が人とは違うのだということは、幼い頃からよく分かっていた。不用意に近付けば石を投げつけてくる村人たち。悲鳴を上げて逃げられることだってある。私が成長することができたのも、見世物としての価値を見出した小屋主がいたからだった。価値を損なうことがないよう健康と衣服には気を使われていたし、次の村へと向かう最中に野盗が襲ってこなければ一生を見世物小屋の中で終えてもいいとさえ思っていた。死の恐怖に命からがら逃げ出して、それっきり。誰が逃げ延びて誰が死んだのかも知らない。武芸を生業とする人だっていたけれど、戦うために身につけたわけでもないそれがどこまで通用するのか。軽業や蜘舞衆(くもまいしゅう)だって、うまく逃げることができたのかどうか。自分のことだけで精一杯だった。
madeleine/原始のころから
金木犀の花がきらいだ。
昔はすきだった。ちゃんとすきでいられた。
木の下で花弁がはらはらと落ちてくるのを待っていた。ノートを開けてそれを挟み込もう。
落ちてきてよ。
わたしのものになりなよ。
わたしのたからものになりなよ。
ノートに、閉じ込める。
こんなにも、あんなにもきれいなきんいろをわたしは手に入れた。そう思うだけで心が高鳴った。
けどね。
言われたんだよ。
あんたのノート、変な匂いするよ。
そんなことないよ。このノートにはいい香りのきんいろが閉じ込めてあるんだ。
ほら。
開いたら、それはきんいろじゃなかった。
怖いいろだった。
いい匂いもしない。植物のじめじめとした匂い。
ああ。今でも覚えてる。
お友だちが笑ってた。
あんなにいい匂いが、したのに。あんなに、きれいだったのに。
わたしには手に入れられなかった。
みんなは知ってたんだね。枯れて死んじゃうこと、知ってたんだね。
わたしは馬鹿だね。
大馬鹿だね。
七左有/烏と卵

高宮広介/RE:BONE
爺ちゃんは、ぼくが生まれたころには既に爺ちゃんだったけど、昔はもっと若くて、かっこよくて、そしてなにより強かったらしい。
爺ちゃんはぼくと散歩に出かけるたび、強さの自慢話をしてくれた。
学生のころのケンカ話、バイクに乗った暴走族に素手で勝った話、野犬の群れを逆に襲った話、大木を殴ってへし折った話。
爺ちゃんの強さ自慢エピソードは数え切れないくらいたくさんあったし、話をするたびに内容が細かくなっていって、たまに新しいエピソードが追加されたりもするので、ぼくは爺ちゃんの話が大好きだった。散歩の時間に話を聞くのが、一日で一番の楽しみだった。
数あるエピソードの中でも、特に驚いたのはクマと戦った話だ。
そのころ、爺ちゃんはあまりにも強くなりすぎたせいで人間の喧嘩相手は一人もいなくなってしまっていたらしい。
新たな対戦相手を求めて山に入った爺ちゃんは、そこで一頭のクマと出会い、そして殴り合った。クマの鋭い爪をかわしつつ攻撃するのはなかなか難しかったようだけど、それでも最後に立っていたのは爺ちゃんで、決め手は執拗なボディブローだった。
「腹を殴られて苦しいのは、人間もクマも同じ」爺ちゃんは得意そうに話していた。
そして、最後は必ず仲直り。それが爺ちゃんのケンカ話ではお約束だった。
同級生も、暴走族も、野犬も、クマも、戦ったあとには必ず握手をして健闘をたたえ合ったらしい。そういうピースフルなところも、ぼくは気に入っていた。
爺ちゃんの話はいつも面白くて、かっこよくて、聞いていると楽しくて仕方がなかった。
しかし、同時に寂しさもあった。
話の中の爺ちゃんはとんでもなく強いのに、目の前にいる爺ちゃんはぼく以上に痩せていて、全く強そうには見えない。実際、ぼくが散歩中に何度競争をけしかけても爺ちゃんはノロノロとしか歩いてくれなかったし、「ケンカしようよ」と足にキックを入れると、歩く速度はもっと遅くなった。
年を取ると人は弱くなる。爺ちゃんを見ていると、その事実を突き付けられているようで悲しかった。話の中の強かった爺ちゃんは帰ってこない。
散歩中、爺ちゃんが口癖のように言っていた言葉がある。
「タケルにも、強い爺ちゃんを見せられたらよかったのにな」
優しい口調で話していたけど、表情はすごく寂しそうだった。
ruff/脊椎奇病録
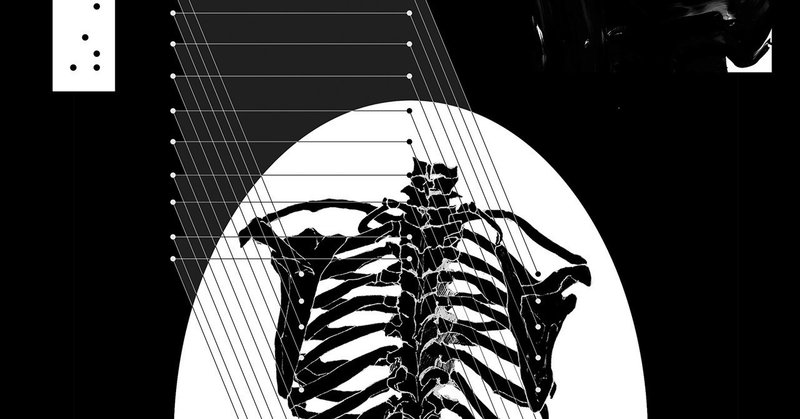
八束/インソムニア
階段の踊り場に、ひとりの娘がたたずんでいる。フランネルで仕立てたモスグリーンのワンピースに生成の袖付きエプロンを重ね、神経質なほどにきっちりと編んだ亜麻色の髪が、その薄い肩の上を垂れていた。
背後にある窓から射す光が、縞模様の影を娘の足もとに落とす。近くの浜から上がってきた蟹が床板の上を移動するかすかな物音がして、それは彼女の靴の上をも這っていったが、まるで気付いたふうもない。長い間、微動だにせず、透明なまなざしで、壁面に掲げられた無数の額縁に見入っていた。
楕円形の額はどれも彼女の手の平大で、ごく小さなものだ。薄い硝子で全面を覆い、布張りをした内側には、繊維質のものから成る造花が飾られ、中央には、きまって一本の歯が置かれていた。歯はさまざまで、先端が欠けているもの、黄ばみ、あるいは黒ずんだもの、犬歯や、明らかに子どもの乳歯や人間でない獣の歯とわかるものもある。言うならば、額装された何十本もの生物の歯が、踊り場の壁を埋め尽くしているのだった。
背後で扉の開閉音がすると、突然、集中の糸が切れたように娘は振り返った。屋敷に足を踏み入れる父親の姿を認める。
ジャコミーナ、そう親しみのこもった声を投げかけられた。
阿部屠龍/ドラゴンズハート
カルカッタに到着して既に十日。案内の男は死んでおり、部屋もとっくに引き払われた後。どころか通り丸ごとがコレラで壊滅している始末だ。指示を仰ごうにも、〈同盟〉はハリスンに連絡手段を与えていなかった。敵方に気取られるのを警戒してのことだろう。
敵方。つまり〈協会〉は、一昨年の『竜撃ち法』を足がかりに、ゆくゆくはあらゆる「スポーツ」を帝国領内から追い出す気でいる。一方の〈同盟〉側は、存在意義からしてそれを認めるわけにはいかない。今回ハリスンが巻き込まれたのはこうした対立構図だった。ナーガ狩りが〈同盟〉の目的にどのような形で適うのかはわからなかったが、自分が選ばれたのも、従事してきた任務の性質上、〈協会〉に認知されていないからだとハリスンは踏んでいた。
どちらにせよその任務もいまは手詰まりだったが。
カルカッタのバザールや酒場をめぐって聞き込みをしても、当然ながらナーガの居場所を知る者などいない。植民地官僚や軍人、観光客を相手に大型獣狩りを案内する現地人のシカーリに至っては、ナーガ狩りなど畏れ多くて耳にすらしたくないといった風情。かといって〈同盟〉の案内人の線から辿ろうにも、再度ブラックタウンに赴いてみれば、コレラ発生によりカルカッタ駐留軍が一帯を隔離していた。
ハリスンはビアマグに注がれた半パイントを飲み干した。生ぬるい苦味が胃に落ちる。こんな状況では、酒と賭博くらいしか打ち込むことがなかった。隣のテーブルでポーカーに興じる男たち、それにしなだれかかる娼婦。昨夜はハリスンも闘鶏で小金を稼いだ。何もかも見慣れた英国の風景だ。
英国市民が自らの属する連合国家を帝国として意識することは少ない。青々としたクリケットのグラウンド、広壮なカントリー・ハウスが生け垣からのぞき、ぬるいビール、紳士と猟犬、穏やかな昼下がりに老婦人が教会へと通う。彼らにとって英国とはそのような緑ゆたかな郊外の国だ。グレートブリテン島だ。一五世紀初頭のウェールズ反乱における実用的な騎竜兵部隊の登場、そしてその歴史的勝利以後は、赤い竜を旗に掲げる竜の王国でもある。ゆえにこそ彼らは本国を離れて初めて、帝国の赤い翼が世界に投げかける影の巨大さに気づくのだ。植民地の異質によってではなく、英国の普遍によって。張り巡らされた電信・鉄道・航路の網は、世界をなめらかに均し、大英帝国の延長された郊外へと変質させていく。
口髭についたビールのしずくを拭い、到着してから一度も髭を剃っていないことにハリスンは気づいた。ふたたび杯を傾ける。
涼やかな声がかけられたのはその時だ。
「ナーガを探してるっていう奇矯な紳士はあんたかい?」
ハリスンは眉を上げる。対面の椅子を引いたのは若い男だった。白い長シャツとズボンの下には引き絞った弓めいた細い身体が透ける。力強い眉と緑のまじった黒い目はやや淡い褐色の肌に際だって、彼の印象を強める。臙脂のターバンを身につけたシク教徒の装いだが、髭は綺麗に剃っていた。「ううむ」彼は顎に手を当てて首をかしげて見せた。
佐々木海月/オステッド
看板には、「志田雑骨店」とあった。
雑骨。
ザッコツ、と読むのだろうか。
聞き慣れない言葉だし、どことなく不穏な響きもある。
恐る恐るガラス戸を開け、店内に足を踏み入れた。つん、と塩素のような不快な匂いがした。薄暗く、よく見えない。商品の変質や変色を防ぐために、わざと光量を抑えているのかもしれない。背の高い棚にぎっしりと収まっているのは、すべて骨だった。何の骨なのかは分からない。どれも値札が付いていたけれど、書かれている言葉は日本語でも英語でもなかった。古めかしく、怪しげな店だと思った。
このとき、僕は慣れない松葉杖を突いていて、狭い通路を通り抜けるのにずいぶん苦労した。カウンターは一番奥にあり、レジの横には丁寧な字で書かれた貼り紙があった。――「処方箋受付」と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
