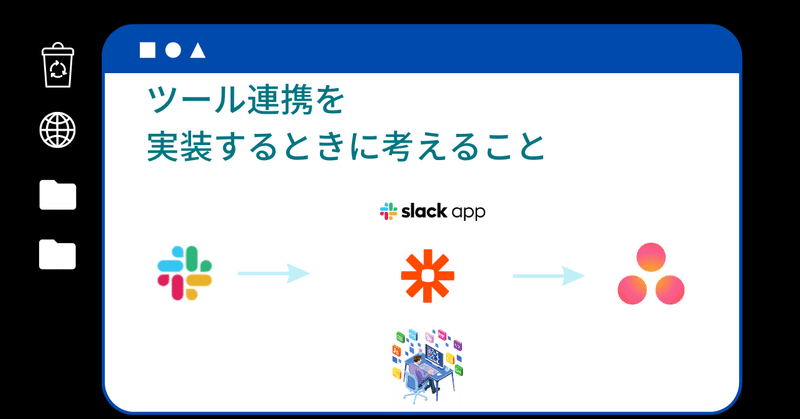
ツール連携を実装するときに考えること
おはようございます、いつきです。
先日SlackとAsanaの連携についての記事をあげました。
SlackとAsanaを連携するにあたり3つの方法があります。
SlackにはAsanaと連携するアプリがあるので、それを使う方法。
ZapierなどのSlackともAsanaとも連携できるiPaaSを使う方法。
サーバーをたてて、自前で連携する仕組みを開発する方法。
この中でどれを取るのか、どういう考え方で決めるのか整理していきます。
ぶっちゃけ感覚で決めちゃうことも多いですが普段省略している部分もあるので、思考の整理ついでに。
現状と、課題の整理
まず今回の対象ですが「社内のAsana利用者」とします。
その上で、ヒアリングしたり、社内アンケートをとり、現状と課題を整理していきます。今回は私の課題感を例にあげます。
・細かい仕事はAsanaに登録せずSlackのリマインダーなどを使って管理していたが、量が増えてきてタスク漏れが発生してきている
・Asanaはあまり使っていない
・他の人に依頼した仕事の進捗状況がわからない
この課題に対して私なりに理由を深堀っていくと、「Slackで仕事の依頼がくるが、Asanaに登録するのが面倒」ということがわかりました。

ゴール設定
今回のゴールとしては、タスク管理がAsanaでできていること。
状態としては、Slackで依頼されたタスクをAsanaに連携できていること(作成と完了)
としました。
実際はタスクの登録数や、タスクの漏れ、あとは満足度をKPIとして設定し、評価できるようにしておきましょう。

改善案のリストアップ
では、Slackで依頼されたタスクをAsanaに連携する方法をリストアップしました。
SlackにはAsanaと連携するアプリがあるので、それを使う方法。
ZapierなどのSlackともAsanaとも連携できるiPaaSを使う方法。
サーバーをたてて、自前で連携する仕組みを開発する方法。
上記を比較表にまとめてみました。
このとき「何もしない」という選択肢を残しておきましょう。よくよく考えてみたら「何もしない」で良いよねっていうことは結構あります。

次に、どう変わるのかイメージしてもらう必要があります。
現状と、変更後のイメージがわかりやすいように、動画やPowerPointにまとめるとイメージしやすくなると思います。
また、ユーザーだけではなく、管理者に対しても運用後のイメージができるようになっていると良いと思います。
ユーザーに対しては、普段の利用についてどう変わるのか(表の利便性の解像度をあげる)
管理者に対しては、負担がどう増えるのか(減るのか)(表の運用コストの解像度をあげる)
費用対効果の算出は次回
今回はこのあたりにして、次回は費用対効果を算出していこうと思います。
実際にかかるコストと、効果は削減される時間を計算します。
それではまた来週!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
