
『蜘蛛の糸』そんなことがあった、ただそれだけ vol.344
次の読書会の課題本を読んでいます。
芥川龍之介の名書『蜘蛛の糸』。
短編集で一つ当たりの話がすぐに終わってしまうのですが、短い中で一気に世界へ引き込んでくる不思議な感覚があります。
これを読んでいると、さすがの芥川龍之介というのをひしひしと感じてきます。
書物が伝達の媒体としてもっとも多く使われていたこの時代に、これだけの作品を残していたこの人はやはり相当な人だったのだろうと感じました。
何よりも作品に没入感があるのに、作者が邪魔をしない。
前置きが長くなりましたが、蜘蛛の糸を読んでの感想を綴っていきます。
全てを読んでの感想でも良いのですが、あまりにも濃密な作品なので、印象に残ったものは1つずつ。
変わらぬ犍陀多、変われぬ犍陀多
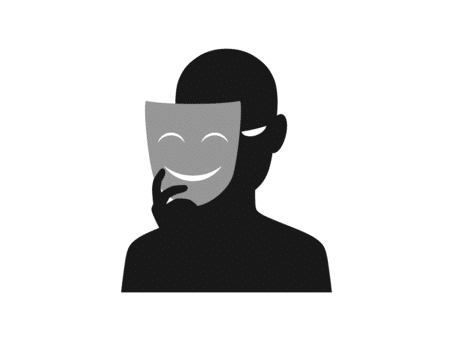
犍陀多は人生においてただ一度だけ、蜘蛛を助けたことで地獄から抜け出すための糸を掴むチャンスを手に入れました。
これは、犍陀多の人生からは到底考えられないような選択です。
何かをきっかけにしたわけでもなく、不意にした選択です。
この事実をこの物語ではどのように捉えているのでしょうか?
犍陀多がたった一度蜘蛛を助けたとて、犍陀多がしてきた所業はひどいものばかり。
それらは目を瞑ったということなのでしょうか?
それとも、そのような選択をしたのだからこの犍陀多にも変われる余地があるという選択だったのでしょうか。
どちらにせよ、この犍陀多は結局のところこれまで通りの悪事を働いていた自分が前面に出てしまい、蜘蛛の糸は切れます。
変わらなかったのか、それとも地獄という声すら出なくなるような極限状態で変われなかったのか。
どちらにせよ、人は追い詰められた時に本性が現れます。
この物語は犍陀多のそんな一面も見せているのでしょう。
蜘蛛の糸は切れたのか、切ったのか

果たして、蜘蛛の糸は何かの意思によって切れたのでしょうか?
それともお釈迦様が切ったのでしょうか?
重みによって切れるべくして切れたのでしょうか?
真相はわかりませんが、この物語はここをどのように解釈するかで大きく変わってきます。
タイミングとしては、犍陀多が罵声を浴びせた瞬間でした。
何かの意思があるように感じるのは当然のことです。
しかし、お釈迦様はさも自分は何もしていないかのようなそんな描写があります。
私は蜘蛛の糸ははなから切れるようになっていたのではとも思います。
そして、その一部始終をお釈迦様が楽しんでいただけにすぎない。
若干ブラックに感じるかもしれませんが、そもそもこの糸によって犍陀多が登り切れたとしたらどうしていたのでしょうか?
そこを考えると、そもそも犍陀多を天の国へあげる気はさらさらなく、どのタイミングで糸が切れるのかを単純に推測っていただけのようにも感じます。
なので、蜘蛛の糸は切れたのでもなく切ったのでもなく、切れるようにできていたが私の中での答えです。
ただそれだけの話

そもそもお釈迦様からすれば、この一つの話もただの時間つぶしに過ぎないのです。
これにはどんな感情が湧けばいいのでしょうか。
所詮、人間のことなぞお釈迦様は気にすらならない?
だから、好き勝手やればいい?
犍陀多という人間はそれほどまでに小さな存在ということの示唆?
どれもスッキリはしないですが、これは全て夢でした、チャンチャン的な雰囲気を感じます。
結局のところ、その一部始終をお見せしましたが、これをどう捉えるもあなた次第ですよ。
ということなのでしょうか?
何とも不思議な、そしてこれを子供向けとして世に出した芥川龍之介の思考にもっと触れてみたいと思えた話でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
