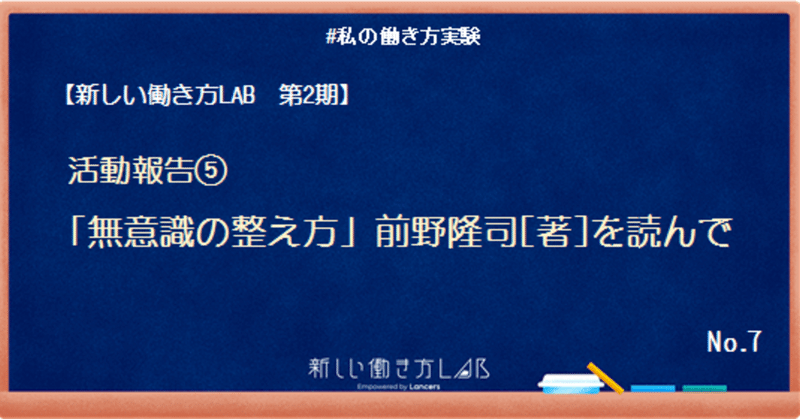
【幸福学】活動報告⑤:「無意識の整え方」前野隆司[著]を読んで
本記事は、ランサーズ新しい働き方LABの「研究員制度」の活動の一環として、私個人が行う「働き方実験」についてまとめたものです。
本を読んだきっかけ
指定企画『幸福学』の課題図書、『幸せのメカニズム』『幸せな職場の経営学』『ウェルビーイング』を読み進めていくうちに、そのほかの前野隆司教授の著書も読んでみたいと思いました。
『感動のメカニズム』『錯覚する脳 「おいしい」も「痛い」も幻想だった』 などとともに借りたのがこちらの『無意識の整え方』です。
手元に本が届くとなぜか「無意識」というキーワードにものすごく惹かれて、『感動のメカニズム』をまだ読み終えていなかったのですが、先に読んでしまいました。
下記はそのときの気持ちです。
・「無意識を整える」というワードの意味を知りたい!
・対談形式で読みやすそうだし面白そう!
・「氣」「仏教」「森」「医」など、対談している方たちのプロフィールが気になる!
本を読んでいて、気になった言葉たち。
本を読み進めながら、気になった言葉たちを書き出してみました。
・「真剣」であっても「深刻」になりすぎない。「これでいいのだ」と思う
・無意識の鍛錬
・元の場所に戻す
・自然で安定した姿勢
・「集中」するが「執着」はしない
・森に入って感覚を開く
・ゆっくり行動する
・感覚を開くと無意識にアクセスしやすい、ひらめきやすくなる
・感覚は無意識に任せて、ただ受け止めることが大切。あとで、ひも解かれるもの
・仮説は持ちすぎずに感覚をとがらせて、ただ受けとめる
・五感が開く、無意識にあるものを出しやすくする
・無意識へと開いている部分を閉じないようにする
・「みずから」と「おのずから」のあわい
・ゆっくりすることで普段切り捨てていることに気付ける
・理論的な意識付けをあえて避ける
・根拠のない大丈夫感
・自然に触れることは医療
・言葉にならないもの、子どものときの宿題を追求する
ワニ・プラス
とくに気になったのが、次の3つです。
・「集中」するが「執着」はしない
「集中」というのは感覚が研ぎ澄まされて周りもよく見えている状態。そのことだけしか頭にないのは「執着」であって、「執着」してしまうとうまくはかどらなくなる。
・感覚を開く
感覚が開きやすい場所=森
・感覚はただ受け止めることが大切
考えすぎずにそのときの感覚を大事にする。感じたまま受け止めていると、あとから思いもよらないひらめきにつながる。

読んだ感想
正直、「氣」「仏教」「医」の対談は、壮大すぎて、ことばの意味の理解も追いつかないまま読み進めていました。
同時に、自分の「考えてみる」がものすごく狭く小さな世界の中でしか行われていないことに思えて恥ずかしくなりました。
深いだけじゃなく、広い。
自分の考えの芯を持ちながらも多様な考え方に興味を持ち、広く受け入れている。知識も技術も人間性も高くて視野も器も広い。この本に登場する全員が超越した存在という感じがしました。
幸せの4つの条件にまさに当てはまる方々だそうです。
話がすーっと入ってきたのは「森」でした。自然の中にいる自分を想像しやすかったからかなと思います。五感が研ぎ澄まされる感じ、普段気づかずに通り過ぎているものにも気づきやすい自然の壮大さがイメージできました。
また、「氣」「医」を読んでいて、病院勤務時代に関わらせていただいたマイクロスリップの研究を思い出しました。
日常的な動作を遂行する中でみられる”小さなよどみ”であるマイクロスリップ。無意識で行われる躊躇や軌道の変化、修正、手のかたちの変化。
無意識の中で私たちは周囲の環境を感じとり、微細な修正や調整を繰り返しながら行為を遂行している。
やはり、意識の周辺で無意識がはたらいているんだなと思いました。
自分なりの「無意識の整え方」
無理に意味づけしようとせず、自分の感じたままの感覚を大切にしていきたいと思いました。そして、無性に禅が組みたくなりました。
自然の中に出かけて、感覚が開く感じを味わいたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
