
6月は虫歯予防月間!虫歯をなくす方法に真剣に向き合ってみる!
皆さんこんにちは。
今日も少し健康について考えていきたいと思います。
6月といえば、日本歯科医師会が6(む)と4(し)の語呂合わせにちなんで、6月4日を「むし歯予防の日」と提唱しています。
ですので今回は、虫歯についてまとめていこうと思います。
100歳まで自分の歯で美味しいものを食べたいですものね。
虫歯に気付きたい!セルフチェックの仕方

· 歯と歯茎の境目が白くなっている
· 冷たいもの・熱いものがしみる
· 歯に穴が空いている
· 歯に黒い部分がある
· 噛むと痛みを感じる
· 何もしていなくても歯が痛い
以上の症状が当てはまる方は、虫歯の可能性を念頭に入れてみてください。
虫歯の発見方法

鏡で確かめる
まず、虫歯の発見には鏡を使用して自分の歯をよく観察しましょう。歯の表面や歯茎の状態を確かめることで、虫歯の初期症状を見逃すことなく発見できます。特に歯の裏側や奥歯の溝など、見えにくい箇所にも注意しましょう。
デンタルフロスを使用する
虫歯は歯と歯の間や歯と歯茎の間にできることがあります。
虫歯によって歯の組織が弱くなり、フロスの摩擦や圧力によって切れやすくなることがあるので、このような場合、虫歯の進行を疑ってみましょう。
歯医者に検診に行く
定期的な歯科検診は虫歯の発見において非常に重要です。専門家の目で虫歯の有無や進行度を確認してもらいましょう。歯医者の検診では、レントゲンや特殊な器具を使って細部まで確認できます。早期発見により、適切な治療を受けることができるので、歯科検診を定期的に行いましょう。
虫歯の見分け方を知ろう
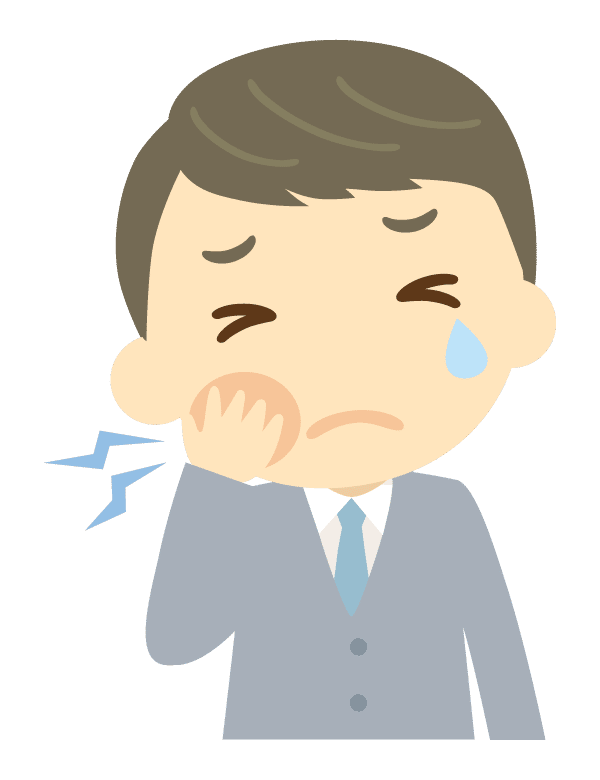
虫歯を見つける方法は、痛みによる自覚と見た目による判別で
大きく分けると2つの方法があります。
1.痛みによる見分け方
虫歯は、初期段階では痛みがないこともありますが、
症状が進行するにつれて痛みや違和感が現れやすくなります。
痛みを感じるのであれば虫歯を疑うべきですが、知覚過敏である可能性も否めないのです。
痛みを感じる点では、虫歯と同じため、見極めが難しいものですが、痛みがすぐに引く場合は知覚過敏である可能性が高いといえます。
2.見た目による見分け方
虫歯の初期症状では、歯の表面に斑点が現れることがあります。
この段階では虫歯菌が歯の表面に付着しているだけで、歯質自体はまだ健康です。
しかし、このまま放置すると虫歯は進行していき、茶色っぽい色素が付着し始めます。最終的には黒っぽい穴が開いたような形状に変化します。
歯の色や形が変化している場合は、虫歯の可能性が高いので注意が必要です!
虫歯と知覚過敏の違い

知覚過敏は、冷たいものがしみるという以外に、歯自体に目で見てわかる症状はあまりないのが特徴です。
歯というよりも、歯と歯茎の境目に注目します。
・歯の根元が露出している
・歯茎が下がっている
・歯自体には穴などの症状がない
歯茎が下がることによって、歯が長くなったように見えます。以前より歯が長くなったと感じる方は要注意です。
一方、虫歯は歯の一部が変色したり表面に小さく穴があいていたりなど、歯自体の見た目に症状が現れることもあるため、見た目の違いで知覚過敏と見分けることができます。
知覚過敏と虫歯は、痛みを感じる長さに違いがあります。
知覚過敏は、冷たいものを飲んだり食べたりした瞬間だけ、一時的な痛みを感じるのが特徴です。個人差はありますが、痛みの長さは長くても10秒程度でおさまりますので、それ以上続くようであれば虫歯を疑った方がよいでしょう。
また、知覚過敏は時間がある程度経っても痛みの程度が進行しません。
虫歯の場合は、時間が経過するごとに痛みが強くなり、ひどくなって神経が死んでしまうと逆に痛みがなくなります。
しかし、知覚過敏にせよ虫歯にせよ、歯科医院で診断を受けて適切な処置を行ってもらうことに変わりはありませんので、自分だけで判断せずに歯科医院へ相談するのがおすすめです!
虫歯になりやすい環境
以下、虫歯になりやすい口内環境についてまとめてみました、
以下のことを注意しながら生活を見直してみてください。
▼口がよく乾く
口の中の乾燥は虫歯になるリスクが高まる
▼歯並びが悪い
歯ブラシの毛先が隅々まで行き届かず、磨き残しをするリスクが高まる
▼歯周病である
歯肉が歯周病の影響で衰退することで歯と歯に隙間ができ、
磨き残しが多くなる
▼治療済みの歯が多い
二次虫歯を引き起こすリスクも高く、
進行していることに気づかないことも多い
虫歯の進行具合と治療方法
進行度 症状
C0 ・歯の表面のエナメル質が溶け始めている状態(脱灰)
・虫歯の穴はまだ空いていない
・痛みがなく自覚症状も少ない
C1 ・歯に穴が空きはじめている段階
・歯の表面に茶色いシミができることがある
・甘いものがしみやすくなる
C2 ・歯の内部の「象牙質(ぞうげしつ)」まで
虫歯が進行している段階
・噛むと痛みを感じたり冷たいものがしみたりする
・象牙質まで達した虫歯は進行が早い
C3 ・虫歯が神経にまで達した段階
・熱いものがしみる
・何もしていなくても激しく痛む
C4 ・歯茎の外に出ている部分がほとんど失われた段階
・何もしていなくても激しく痛む
・神経が死んで逆に痛みを感じなくなることがある
虫歯を予防するためにしたいこと!
1.食後は、むし歯菌による酸の発生が多いため、必ず歯ブラシをする
2.デンタルフロスや歯間ブラシを使用する
3.間食は口の中が常にむし歯になりやすい状態になるため、極力控える
4.フッ素入りの歯磨き粉で歯磨きを行う
5.フッ素入りのマウスウォッシュで口をゆすぐ
6.栄養バランスの取れた、規則正しい食生活をすること
正しい歯磨きの仕方

①ひと筆磨き
磨き残しが多い方の特徴としてよくあるのは磨く順番がバラバラで
あることです。磨きやすいところだけ磨いて、磨きにくいところが
おろそかになっていませんか?
歯ブラシを当てる位置があっちこっちにとばないように一線で磨く
ように心がけてください
②歯ブラシを当てる位置
歯ブラシを当てる位置は歯と歯茎の間の境目あたりです。
歯の先端は唾液の流れや唇の動きで歯垢はある程度取れています。
歯周病の原因になり虫歯に最もなりやすい歯と歯肉の間にしっかり
当てるようにしてくださいね。
当てる角度は歯の面に対して45度から90度です。
③歯ブラシの動かし方
横刻みに細かく動かしてください。
歯1〜2本程度の幅で動かすように意識していただければちょうど
よいです。
前歯の裏だけは歯ブラシの先端やかかとの部分を使い、かき出すよう
に磨いていただければキレイに取れます。
④歯ブラシの持ち方
歯ブラシはぐっと握りしめてしまうと力が入りすぎてオーバーブラ
ッシングをしてしまう傾向があります。
ペングリップ法といって鉛筆を持つ持ち方で磨いてみてください。
これで力が頼りなく感じる方は普段から強く磨きすぎです。
歯垢はそれほど強く磨かなくてもきちんと当たっていれば取れます。
⑤最後のチェック
歯ブラシが終わったら歯垢がきちんと取れているか舌でチェック
してみてください。ツルツルとした面は磨けていますし、
ザラザラの面は再度磨く必要があります。
虫歯になりやすい習慣
以下に注意することで、虫歯リスクを大幅に下げることにつながります。
▼歯磨きは1日に1回以下
毎食後歯磨きをすることが理想でありますが、外出時のうがいも有効です。
▼時間を決めず、ダラダラと食べ続ける
食べ物が口の中に存在する時間が長ければ長い程、虫歯リスクは上がります。
▼甘い食べ物を良く食べる
虫歯の原因菌は、糖分を栄養にするため、過度に甘い物を食べることは避けましょう。
▼甘い飲み物をだらだら飲んでしまう
コーヒーや紅茶、ジュースやスポーツドリンクなど甘い飲み物をだらだら飲んでしまうのも虫歯の原因になります。
▼歯医者さんにはしばらく行っていない
歯磨きでは落としきれない汚れなどが蓄積し、虫歯菌を呼び寄せるリスクがあります。
今回は虫歯と虫歯予防についてまとめてみました!
最近なんだか歯に違和感があるなと感じたり、メンテナンスがしたいと感じたら6月の虫歯予防月間をきっかけに歯科検診に行ってみるのもおすすめです。
健康な歯で心も体も元気に過ごしましょう!
では、今回はこの辺で。
皆さんの毎日が健康でありますように!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
