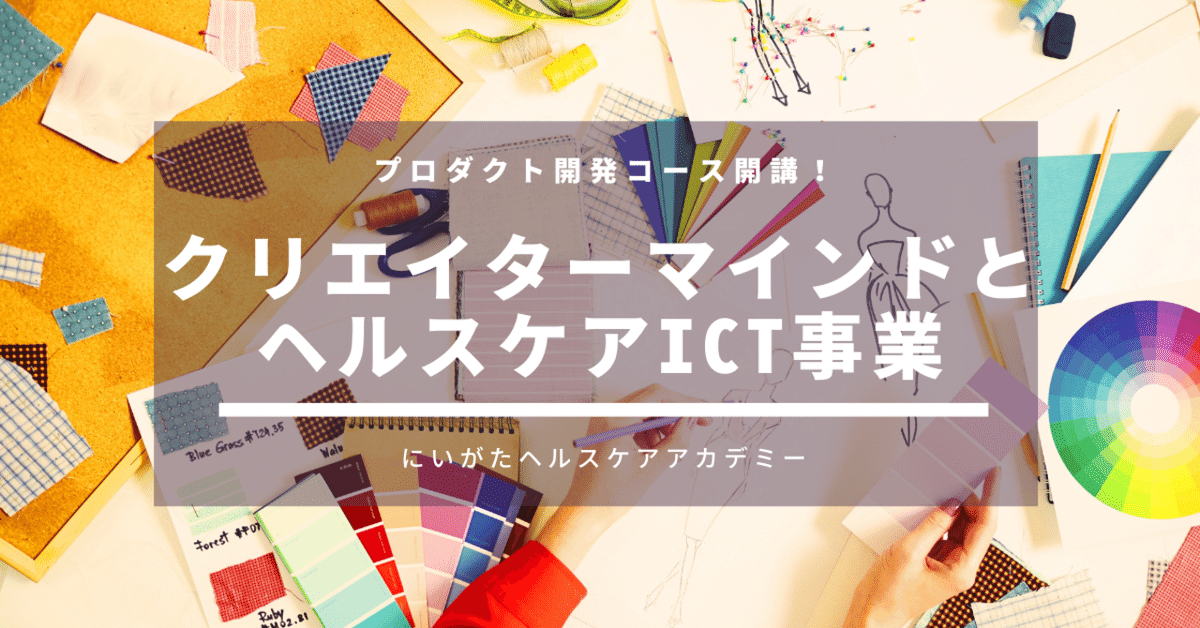
プロダクト開発コース開講! クリエイターマインドとヘルスケアICT事業について学ぶ
2021年10月16日 (土)より、にいがたヘルスケアアカデミー「プロダクト開発コース」がスタートしました!
プロダクト開発コースでは、4名でチームを組み、モックアプリまたはアプリのプロトタイプの作成を行います。コースの目的はプロダクト開発の基礎を習得することであり、これまでのコースと同様、コース最終回では全チームがピッチコンテストで成果を発表します。
プロダクト開発コースのキックオフである今回は、オンラインにて開催されました。開会の挨拶には株式会社BSNアイネット常務取締役 伴内 富士男氏、講義「プロダクト開発入門」にはハイズ株式会社 木野瀬 友人氏、研修「チームビルディング」にはハイズ株式会社 小平 寛岳氏と河村 由実子氏を迎えました。
本記事では、プロダクト開発コース第1回講義の様子を簡単にお伝えします。アカデミーに興味のある方、新潟のヘルスケアを良くしたいという思いをお持ちの方、医療課題に対してアクションを起こしていきたいと思っている方は必見です!
「プロダクト開発コース」 の全体スケジュール
2021年10月よりスタートしたプロダクト開発コースは、下記スケジュールで進んでいきます。

講義 「 プロダクト開発入門 」
- 木野瀬 友人氏

■ 木野瀬 友人氏(ハイズ株式会社)
2007年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了、2019年デジタルハリウッド大学院デジタルコンテンツ研究科修了。2005年に開発会社である株式会社エクストーンの前身となる企業を創業し、ニコニコ動画の運営母体である株式会社ニワンゴの創業を経て現職。ハイズの病院経営コンサルティングにおいては「ITに弱い病院の助けになりたい」という考えのもと病院インフラの更改を担当。現代の技術の恩恵が得られない医療現場に対して、コンピューティングの視点から業務のスマート化を推進。慶應義塾大学総合政策学部卒業後に当時2ちゃんねるの管理人の西村博之と、ドワンゴの会長の川上量生とともに株式会社ニワンゴを創業。事業アイデアの実現担当として企画からコーディングまでを行う。
本講義では、聴講者を惹きつける木野瀬氏の魅力的なファシリテーションのもと、2時間半みっちりとプロダクト開発の基礎について学んでいきました。講義の中でお話のあったポイントをいくつかご紹介します。
講義の流れ
1限目:プロダクト開発コースの定義
2限目:一般企業マインドではなくスタートアップマインド
3限目:ヘルスケアICTプロダクトの紹介
4限目:ヘルスケアICT事業の土地勘
5限目:プロダクト開発基礎
講義のポイント
■ コンシューマーマインドとクリエイターマインド
「コンシューマーマインド」とは、消費者のマインドセットのことで、感情の変化を感じるだけで成果はほとんどないことを指します。固定マインドセットとも言います。努力をしてもしなくても結果が変わらないのであれば、現状維持に徹することがベストだと思う人が多い傾向です。
一方で、クリエイターマインドとは、受けた知識を吸収し、実行して手の内に入れようとする制作者のマインドセットのことです。成長マインドセットとも言います。能力は努力次第で伸ばすことができる、ということを知っている人が多い傾向です。
プロダクトを開発するにあたっては、クリエイターマインドが必要となります。クリエイターマインドではない人も少しずつ変わることはできます。本講義では、その具体的な方法について木野瀬氏よりいくつかご紹介いただきました。
■ クリエイターマインドになるためのヒント 〜人が変わる3つの方法〜
結果を出している人は一見キラキラしていますが、周りから見えているのは表層部分だけ。裏では、能力やセンス、意識・世界観・人生観、さらには環境など、あらゆるものが結果に影響を与えています。
経営コンサルタントで有名な大前研一氏は、人が変わるには以下の3つしかないと言います。1つ目は「時間配分」、2つ目は「住む場所」、3つ目は「付き合う人」です。人が変わるには、比較的変えやすいと言われている「環境」を変えることが重要です。皆さんも今一度振り返ってみましょう。人が変わる際にもっとも無意味なのは、決意を新たにすることです。行動を具体的に変えない限り、決意だけでは何も変わりません。(参考:「時間とムダの化学」大前研一 2005)
■ 一般企業とスタートアップの違い
日本における全266万企業のうち、一般企業は99.9%、スタートアップはわずか0.1%です。一般企業の常識をスタートアップに持ち込むと大失敗します。一般企業は事業を継続することが目的ですが、スタートアップは最短で急成長することが目的であり、破壊的イノベーションを起こすために設計された企業です。
スタートアップはJカーブを描いて成長(最初はマイナスに振れ、その後急成長)します。スタートアップの成長・成功で大切となるのは、課題の質を高めることです。課題の質は、どれだけお金を払ってもあげられません。開発をするというのはソリューションの質を高めることですが、課題の質を上げることから進めていくことが大切です。強豪が持っていない課題というのを増やしていきましょう。失敗するスタートアップはプロダクトを作り込みすぎる傾向にあります。大切なのは、多くの機能ではなく、たった1人でもその商品を使い幸せになる人がいるということです。
従って、スタートアップの選択は直観に反します。スタートアップのプロダクト開発において考え得るプロセスは2つあります。1つは「ソリューションの質を高めてから課題の質を高める」パス、もう1つは「課題の質を高めてからソリューションの質を高める」パスです。しかし実際は、「ソリューションの質を高めてから課題の質を高める」パスは機能しません。なぜなら、顧客の課題に向き合わず機能追加をしたり利便性を高めたりしても、顧客が求めるプロダクトにはならないからです。一方、課題の質を誰よりも深めることができれば、他者が真似することのできない知見を持つことができ、そこから直にプロダクトの実装に生かすことができます。
■ ヘルスケアICT事業の土地勘
デジタルヘルスには「医療の課題感」と「ITの想像力と実現性」の部分を両方兼ね備えた人材が必要です。医療人材のマインドセットと、IT人材のマインドセットはどちらも重要です。また、医療機関向けには負担軽減と売上増、患者・患者家族向けには不安解消や負担軽減、保険者向けには負担軽減と医療費削減という価値のあるプロダクトが求められます。
■ 講義のプロダクト開発基礎&まとめ
プロダクト開発をする際には、「そもそも課題が実在するのか」「課題に対して解決策は適切か」「プロダクトに市場は存在するのか」を検討する必要があります。要するに、プロダクト開発をする上で最も重要なことは「人が欲しがるものを作ること」です。これを実現するためには仮説を設定し、検証するサイクルを何度も回す必要があります。価値のあるソリューションにつながるプロダクトを開発するため、まずは顧客に向き合い、課題を深めていきましょう。
研修 『チームビルディング』
- 小平寛岳氏 / 河村由実子氏

■ 小平寛岳氏(ハイズ株式会社 コンサルタント)
長野県出身。新卒で上尾中央医科グループ八潮中央総合病院に入社。幅広い病期・疾患を対象としたリハビリテーション業務、ヘルスプロモーション活動等に従事。その後、訪問看護ステーションと整形外科に入社し、外来・地域医療における患者課題の解決に取り組む。大学院進学・中退を経て、株式会社メプラジャパンにてヘルステック領域の新規事業創出・海外展開支援に従事。現在はハイズ株式会社にて主に医療経営コンサルティング業務を行う。

■河村由実子氏(ハイズ株式会社、理学療法士/ライター)
広島県出身。2013年理学療法士免許取得後、亀田総合病院にて勤務。2017年から県立広島病院のICU専任理学療法士として勤務。FMラジオで医療系トークバラエティー番組「医どばた食堂」メインパーソナリティーを務める傍ら、取材・編集を自ら行うリハビリ系Webメディア「リハノワ」を運営。2020年春、ICUにおけるオンライン面会システムを構築。2020年夏、一級建築士とともに離島の空き家をバリアフリーリノベーションし宿屋を作るというプロジェクトを立ち上げる。2021年春よりフリーランスとして独立。
■ チームビルディングとは
一般的に、チームビルディングとは各自のスキルや能力、経験を最大限に発揮し、目標を達成できるチームを作り上げていくための取り組みのことを指します。今回は、プロダクト開発という新たな目標ができたこと、新メンバー・新チームになったことから、これまでの振り返りも兼ねて改めてチームで方向性を話し合いました。チームの目的の再確認を行い、個人の強みを活かした関わり方を共有しコミュニケーションを活発化させる時間となりました。
■ チーム力を向上させる要素
今回は、3か月という短期間でプロダクト開発を行う必要があるため、以下の4つの要素をチーム毎に確認しました。
①目的の共有
②役割の明確化
③チームの運営ルールの設定
④モチベーションの見える化
各チーム、プロダクト開発に向けてそれぞれの想いを共有し、今後の方向性が見えてきているようでした。
まとめ
今回は、プロダクト開発の基礎とチームビルディングについて学びました。アカデミー生は一連の講義の学びを活かしながら、チームごとに新潟のヘルスケア課題解決に資するプロダクトを開発していきます。各チームどんなプロダクトが出来上がっていくのか楽しみですね。これからも、スタッフ一同全力でサポートさせていただきます!

(講師・木野瀬氏とスタッフ一同)
次回の講義では、課題の深掘りとプロダクト開発の道のりについて学びます!
主催:ヘルスケアICT立県実現プロジェクト
運営:株式会社BSNアイネット・ハイズ株式会社
後援:新潟県
<ヘルスケアICT立県実現プロジェクトについて>
新潟の地域医療課題をヘルスケアICTの力で解決すべく令和2年10月に立ち上がったプロジェクトです。本プロジェクトでは新潟県の医療・健康課題に対応したヘルスケアICTを活用し、人材・企業を育成することで、新潟から最先端のヘルスケアICTを生み出すことを目的としています。プロジェクトは2本の柱を軸としています。1つ目は、ヘルスケアICTプロダクトの開発です。新潟県の有する特に大きな医療課題として、小児産婦人科領域、救急医療領域、生活習慣病領域の3領域にてプロダクトの開発や地域展開に取り組んでいます。2つ目は、人材育成構想です。ヘルスケアICT人材の育成・集積を行っていくための人材育成コースとコミュニティを併走しています。 この2本柱で、分析・アイデア創出・サービス開発のサイクルが担える人・企業を新潟に増やし、継続的なイノベーション創出を通して、ヘルスケアICT立県を実現します。本プロジェクトは、株式会社BSNアイネット、ハイズ株式会社、株式会社Kids Public、日本電気株式会社新潟支店がコンソーシアムを構成し、新潟県や新潟大学と連携してワンチームで取り組んでいます。
Twitter:アカデミーの活動や関連情報、新潟のヘルスケア情報や潜在的な課題などを発信しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
