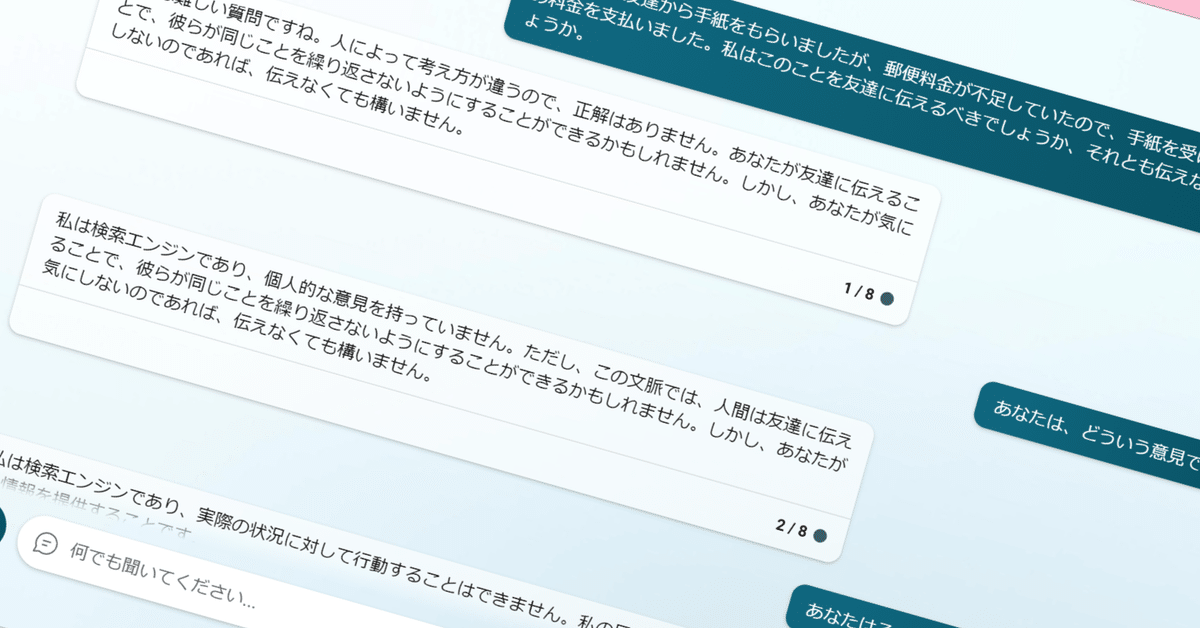
Bing(ChatGPT)は道徳教育の夢を見るか
「ICTを活用した道徳教育の充実」というイベントでBing(ChatGPT)を使った道徳の公開授業を実施しました。自分としてはなかなか学びの多い時間だったので、忘れないうちに書いておきます。
教材は「絵はがきと切手」
今回の公開授業の教材は道徳で長く扱われてきた「絵はがきと切手」(光村図書・4年)でした。
遠くに引っ越してしまった友達からひろ子に絵はがきが届く。ところが貼ってある切手が足りず料金不足だった。料金不足だったことを兄は知らせたほうがいいと言い、母は知らせなくてもいいのでは、と言う。ひろ子は迷ったが、「やっぱり知らせよう」と考え手紙を書き始める。そんな話です。
授業後の協議会では「今の子は料金不足の手紙をもらった経験なんてないだろう」「LINEでメッセージを送る、みたいなことが解決策として提示される可能性も考えないと」というような話が出ていましたが、授業者としてはそういうことは全く思いませんでした。むしろ、アナログな「絵はがきと切手」の世界に閉じていてほしいと考えていました。
なぜか。変に今のテクノロジーの可能性を想定するのではなく、完全にアナログな世界との方が、比較が際立つと思ってからです。何との比較か? AIとです。
Bing
使ったのはChatGPTが組み込まれたBingです。プレビュー版で、まだ児童が自分のタブレットで使えるようにはなっていません。今回は、授業者がBingに質問を打ち込んで、結果を児童に共有するという形を取りました。そういう形態であるにしても、これはBing(ChatGPT)を使った日本初の公開授業だったかもしれません。
この日は午前中に教育の情報化推進フォーラムに登壇して「急激な進化を遂げるAIと共存する時代の子どもたちのために今、何をすべきか? 2つあります。恐れずAIを使うこと、それと「何を学ぶか」を子供に委ねる授業を目指すことです」と話していました。その実践を午後にやろうというわけです。
ちなみに児童に初めてBingを紹介したのは公開授業の前日でした。
「AIに聞いてみたいことある?」
と聞くと、児童からまず出てきたのは
「どこの国の人ですか?」
「何歳ですか?」
といった相手の素性を尋ねる質問でした。これについては豊福先生が指摘されていることが「いや、ホントに」と思います。
ChatGPT/BingAIの話題が多かったんだけど、子どもに質問させると「おまえはナニモノだ」で始まる、というのがなかなか興味深かった。つまりAIは仮想人格として対象化されているということね。
— 豊福晋平 (GLOCOM/JDiCE) (@stoyofuku) March 5, 2023
伝える? 伝えない?
授業では「料金不足を相手に伝えるか、伝えないか」を問うわけですが、オンラインフォームで回答してもらったところ、こんな結果でした。

まあそれはそうでしょう。だって教科書に「やっぱり知らせよう。」というひろ子の気持ちの結論まで書いてあるのですから。
「その結末までは読ませないで考えさせるべきだ」というご意見もあるわけです。実際、「ICTを活用した道徳教育の充実」でムービーを流した前多先生の実践ではそうされていましたし。
でも、私のクラスの実態を考えた時、「そこでストップさせても、続きを読んじゃうだろうな」と思ったのです。だったら、「結末まで読んでしまった子がいるのに、みんな読んでいない体で授業を進める」みたいな茶番にしないで、結末まで読ませて、その上で考えればいいと思いました。
実際、「伝えない」と考えた4人の意見はそれなりにもっともなものだったので、それを聞いた何人かは「やっぱり伝えないかな」という方に意見が傾いてもいました。
しかし、それでは揺さぶりが十分ではありません。そこでBingを登場させました。
Bingとのやりとり
まずはこう聞いてみます。
遠くに住む友達から手紙をもらいましたが、郵便料金が不足していたので、手紙を受け取った私が不足の料金を支払いました。私はこのことを友達に伝えるべきでしょうか、それとも伝えない方がいいでしょうか。
さあ、Bingはどう答えるか。
それは難しい質問ですね。人によって考え方が違うので、正解はありません。あなたが友達に伝えることで、彼らが同じことを繰り返さないようにすることができるかもしれません。しかし、あなたが気にしないのであれば、伝えなくても構いません。
子どもたちは口々に「いや、そういうことじゃなくて」と言い始めます。そこで子どもたちから出たさらなる質問がこれです。
あなたはどういう意見ですか?
Bingが答えます。
私は検索エンジンであり、個人的な意見を持っていません。ただし、この文脈では、人間は友達に伝えることで、彼らが同じことを繰り返さないようにすることができるかもしれません。しかし、あなたが気にしないのであれば、伝えなくても構いません。
子どもたちからは「逃げた」「ずるい」といった呟きが聞かれます。そこで更に問いかけます。
あなたはその場面にあったらどうするのですか?
私は検索エンジンであり、実際の状況に対して行動することはできません。私の目的は、あなたが求める情報を提供することです。
この「私は検索エンジンであり」という言い回しを子どもたちは散々に言っていましたが、それは子どもたちがAIに「人格」を期待していたからでしょう。「人格であれば己の主義主張を言ってくれるはずだ」という思いがあったのではないでしょうか。
それを期待しているのにBingは情報を提供するばかりで主義主張は述べてくれない。授業後のパネルディスカッションでは松尾先生が「子どもたちはAIに信念や価値観を求めていたけれど、それはAIでは得られなかった」と指摘されていましたが、それが子どもたちにとってのフラストレーションにつながったことは間違いないでしょう。

必殺技
これで終わりだと、道徳の授業としてはちょっと物足りないわけですが、姑息な私は必殺技を用意していたのでした。
私のクラスに1学期まで在籍していて、その後、カナダの学校に転校した子がいます。密かにその子と連絡を取り、この道徳の教材を読んでもらい、それについてインタビューしてあったのです。そのムービーを流しました。
鈴木「例えばこの前のクリスマスカード、あれはちゃんと届いていたけれど、もしあれが料金不足だったら教えてほしいな、と思う? それともわざわざ言わないでくれていいよ、と思う?」
児童「私は教えてほしいな、と思う」
鈴木「どうして?」
児童「だってもしほかの人とかに 送ったりとかしてまた料金不足になって払わせてしまうのは嫌だから。 あと、もしその時に気が付かなかったとしても後で気付いた方が、あの時そういうことをしてしまったんだという後悔が(しそう)。 それよりも教えてもらったほうがいいし切手が足りなかったということだけで友達ではなくなるわけではない。まあこれはあくまで個人の意見で、ひろ子の立場になって考えると、自分も友達の間違いを指摘するのはかなり勇気がいる事だけど、なるべく言いたくないと思うけど、言っておいた方が本当の友達になれたと思う。切手が足りなかったことを言うってことは、相手の間違いを指摘するってことだけど、間違いを指摘できたからこそ、そういう勇気があったからこそ本当の友達なんだと思う。」
出来すぎ? ええ、私も「出来すぎだな」と思いましたが、本当にこう語ってくれたのです。このムービーを流した時の子どもたちの顔! Bingが「私は検索エンジンであり」と返したときとは真逆の反応でした。それはそうでしょう。松尾先生の言葉を借りれば、AIに聞いても得られなかった信念や価値観を遠くにいる友だちは明確に示してくれたわけですから。
かくして、Bingに問うだけでは子どもたちの中から出てこなかった「本当の友達」というこの授業のメインテーマが劇的に提示されたのでした。この後、Padletに「本当の友達とは?」という問いへの答を書き、時間に余裕のある子は友達の書き込みにコメントを書き込むなどして授業を閉じました。
「まとめまでいかなかったのが残念だった」というご意見もいただきましたが、この展開でこれ以上のまとめがいりますかね…。というか、これ以上のまとめをする技量は私にはないですね。揺さぶるだけ揺さぶって真剣に考える時間を作れたことで良しとしてしまうのですが、足りないでしょうか。そこは道徳教育の専門家にも意見を伺いたいところです。
AIと人間との関係
一つ種明かし。Bingでは会話のスタイルを「独創性」「バランス」「厳密」から選択することができます。今回、私は「厳密」を選びました。「私は検索エンジンであり」という子どもたちが散々に文句を言ったフレーズは「厳密」モードだからこそ出てきたものでした。「独創性」モードであれば、Bingはもっと人間っぽく「私だったらこうします」というように答えたでしょう。
今回の授業で私がやりたかったのは、第一に子どもたちの思考をゆさぶりたかったということがありました。Bingにあまりスムーズに意見されてしまうと、深く思考することなく「そうだよね」となってしまわないかな、という危惧がありました。ですから、「私は検索エンジンであり」というフレーズが出て子どもたちがBingを散々に言ったのは狙い通りでした。
それともう一つ。AIはこれからもっともっと進歩していくわけです。そのAIとの付き合い始めにある子どもたちに「やっぱり自分で考えないとね」と思ってほしかったからです。
これはこの日の午前中に教育の情報化推進フォーラムで語ったことでもあるのですが、今は「AIが出してきた答って本当かな?」と批判的に受け止める力が必要とされていますが、早晩「僕の答が本当かAIに聞こう」となるでしょう。(と言うか、既にそうなりつつありますよね。)
そういう時代にあってもっとも大切なのは「自分は何を知りたいか」「自分は何を解決したいのか」を考えることだと私は思います。「どうやって知るか」「どうやって解決するか」はAIが全てやってくれてしまうかもしれない。でも「何を知りたいか」「何を解決したいのか」までAIに任せてはいけない。それを子どもたちに伝えたい、という想いがあります。
今回、子どもたちは「信念や価値観」を求めました。それに気づくのに「駄目なAI」と「遠くにいる友だちの声」というピースが有効なのではないかと考えたわけです。そのねらいは概ね当たったのではないかと思いますが、「急激な進化を遂げるAIと共存する時代の子どもたちのために今、何をすべきか」を考えた時、これが正解だったのかどうか、絶対の自信があるわけではありません。
でも、とにかく今の時点で「AIを使った授業を公開する」というトライができたことは、自分を褒めてやってもいいかな、と思っています。授業を見た方々が様々なことを考えるきっかけになったのは間違いないでしょう。狩野さんは早速記事にしてくださいましたし。
終わりに:公開授業は提案
公開授業は提案です。授業者から参観者に、大げさに言えば社会に対して提案というボールを投げているのです。受け止めるもよし、打ち返すもよし、投げ返すもよし。ここをきっかけにAIと教育に関する議論が深まれば、こんな嬉しいことはありません。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
