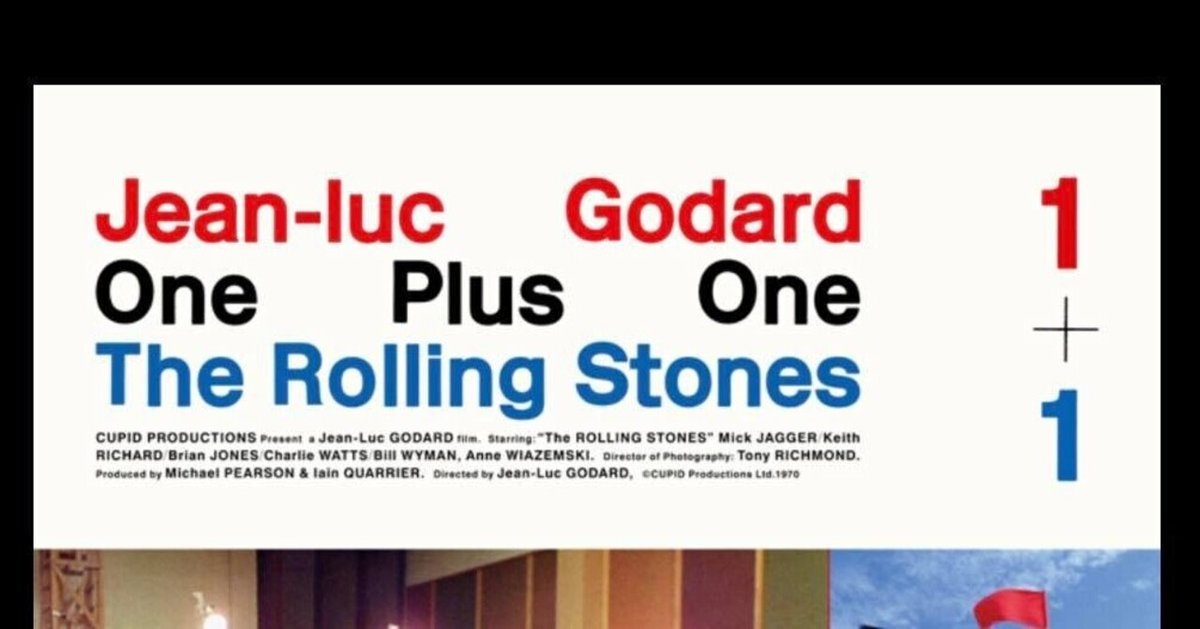
ゴダールよ永遠に(チューリヒの宿にて書く)/一日一微発見335
小鳥たちが小さな庭で騒いでいる。
ここはヒッピーぽいオープンな飲みの場所で、僕ら(僕と妻)はさっき5時ギリギリにギャラリーであるEVA PRESENPHUBERとKILHIMMANに駆け込んで、駆け込んだわりには作品はピンとこなくて、その近くの飲み屋にしけこんだというわけ。
さっきまで小雨が降りしきっていたのに、夕方になって晴天が広がり陽が射しはじめた。
ああ、なんという平和。
すでに隣のクラブからはグルーヴィーな音楽が流れ、この日の仕事をはやばやと終えた連中が飲みにやってくる。
安あがりなオーガニックなアーバンフォーミング。でも小鳥のエサは食べ残しのポテトチップス。
夕日の中での脳裏をさらないのは、さっき見たピンとこないアートのことではなく、13日に自死 (安楽死)を選んだこの国(スイス)の人、ジャン・リュック・ゴダールのことだ。
彼は13日に死んだがその2日前にウィリアム・クラインも死んだ。この2人にはひとかたならぬ感謝を捧げたい。
多くの人もそうだろうか、この2人に出会わなかったら今の自分はなかったな、と思うからだ。
大阪から京都の大学に逃げて、高校生の時に描いていた絵は(大きいから)諦めて、8ミリ映画にシフトして旅して今からすればロードムービーもどきを撮っていた。
やさぐれた仲間とサークルをやり、学生会館(当時は自主管理下にあった)で映画を興行的に上映していた。
ロマンポルノ、ヤクザ映画、実験映画の季節。
鈴木清順、田中登の「色情めす市場」、長谷川 和彦「青春の殺人者」などを上映して活動資金と称した泡銭をこしらえた。フィルムは当時の京一会館の人から横流ししてもらった。
同時に上映したのがクラインの『ポリーマグお前は誰だ』やゴダールの『ウイークエンド』『中国女』『東風』だった。
クラインが写真家だとは全く知らなかった。
この2人との出会いがなければ、今にいたる「編集人生」はなかっただろう。はっきり言える。
ウィリアム・クラインは僕にとって、まずは強烈に映画の人だった。映像における虚と実、偶然と必然を植え付けられた。
その後、90年代に渋谷のPARCOがやっていたギャラリーThe EXPOSERでクラインの展覧会が開催されたときに、彼にインタビューした時に因果は巡ると思った。
ここから先は
¥ 150
応援よろしくね~
