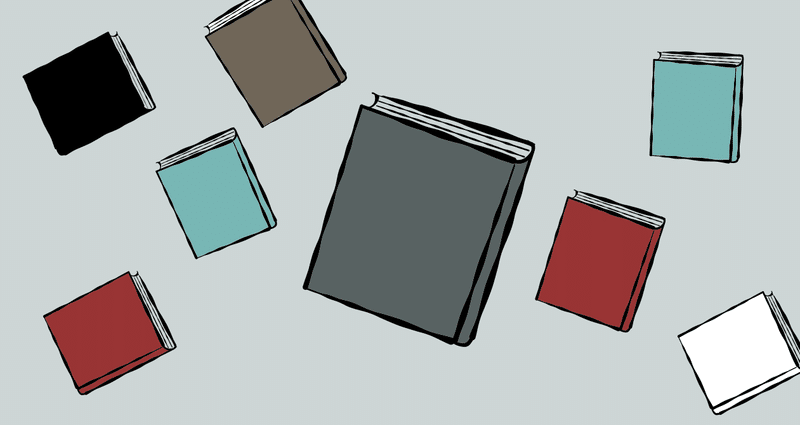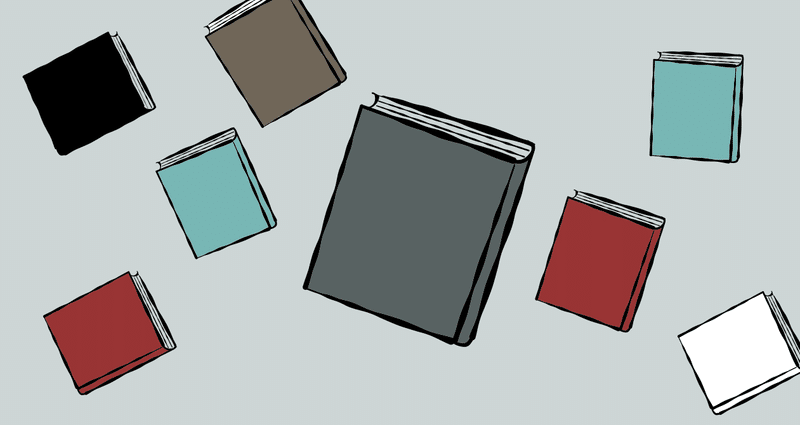文学フリマ東京に出展した感想など。
5月19日に仲間で文学フリマ東京に出展してきました。
12時から17時とたった5時間ですが、静かなる熱狂の時間でした。
この時間で、1800店舗以上が出展し、1万2千人以上が参加したそうです。普通だったらこの規模のフェスだとウワ〜っ!!と喧騒になりそうですが、そこは文学好きが集まるからか、出展者のお店の呼び込みもうるさくなく、全体的に静かで、お客さんも静かに目利きの目を光らせてハンティングしていくのが面白いなあと思いました。
ジャンルも幅広いけれど、大衆向け小説や詩が置いて