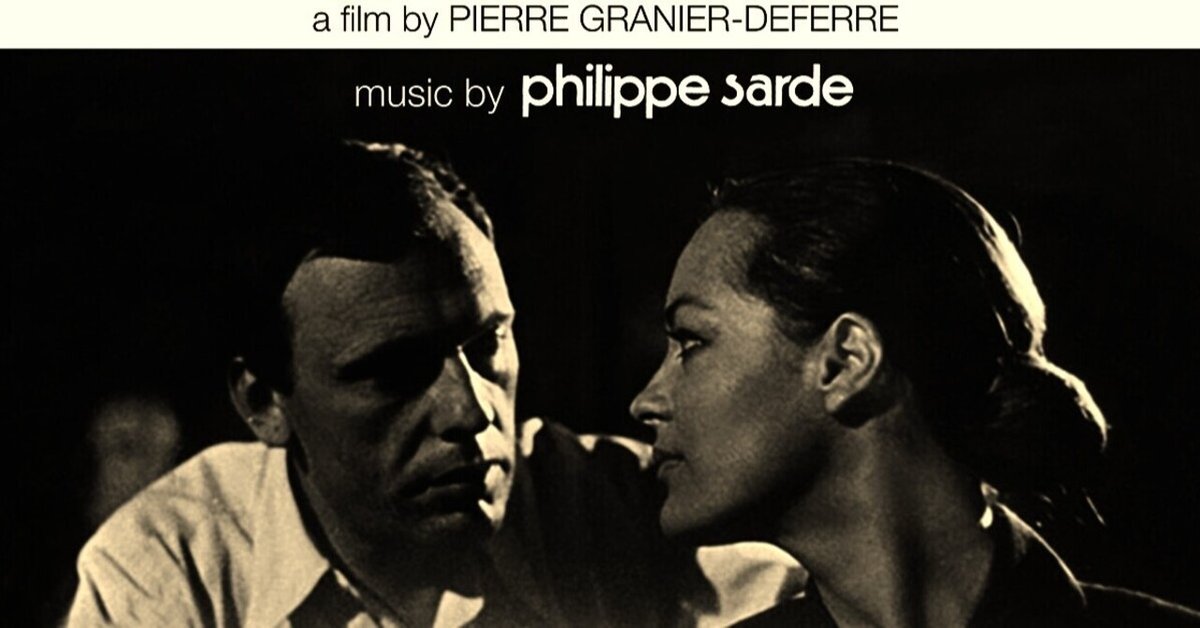
心を動かされる珠玉のサントラ盤(7):「離愁」他(フィリップ・サルド)
「ドラマティック・アンダースコア」のサントラ盤を毎回紹介しています。
「ドラマティック・アンダースコア」とは、映画の中のアクションや、特定のシーンの情感・雰囲気、登場人物の感情の変化などを表現した音楽のことで、「劇伴(げきばん)音楽」と呼ばれたりします。
今回ご紹介するお薦めのサントラ盤は――
---
(未公開)LE CHAT
離愁 LE TRAIN
作曲:フィリップ・サルド
Composed by PHILIPPE SARDE
指揮:カルロ・サヴィーナ
Conducted by CARLO SAVINA (LE TRAIN)
演奏:サンタ・チェチリーア管弦楽団
Performed by Orchestra di Santa Cecilia di Roma (LE TRAIN)
(スペインQuartet Records / QR447)
「個人生活」「限りなく愛に燃えて」「(TV)新・メグレ警視/ローソク売り」のフランスの映画監督ピエール・グラニエ=ドフェール(1927~2007)とフランスの作曲家フィリップ・サルド(1948~)とのコラボレーション作品2本のスコアをカップリングにしたCD。いずれも「メグレ警視」シリーズや「モンパルナスの夜」「仕立て屋の恋」「倫敦から来た男」等の原作で知られるベルギー人作家ジョルジュ・シムノン(1903~1989)の小説を映画化したもの。
LE CHAT(猫)
「(未公開)LE CHAT」は、1971年製作のフランス=イタリア合作映画で、日本では劇場未公開(“LE CHAT”はフランス語で“猫”のこと)。出演はジャン・ギャバン、シモーヌ・シニョレ、アニー・コーディ、ジャック・リスパル、ニコール・ドゥサイー他。フランス中央部の町クールブヴォアで、もうすぐ取り壊される予定の小さな家に暮らす印刷工だったジュリアン(ギャバン)と、サーカスの団員だった妻のクレマンス(シニョレ)、そしてジュリアンが妻よりも愛情を注ぐ一匹の猫グルフィエを描いたドラマ。フランスが誇る名優であるギャバンとシニョレは、この作品で1971年度ベルリン国際映画祭の最優秀男優賞、女優賞を受賞している。
フィリップ・サルド作曲のスコアは、冒頭のメインタイトル「Le chat (Générique debut)」が、サルド自身の演奏によるピアノ・ソロとストリングスによるメランコリックで美しい曲。「Le Temps des souvenir」は、2人の若き日の幸せな結婚生活を描写した、ジャン・サブロンのヴォーカルによるジェントルでノスタルジックなシャンソン(エディ・マルネイとサルドが作曲)。更に、明るく快活なマーチ「Le cirque」や、ダイナミックなサスペンス音楽「Le chat (Suspense 1)」と展開し、最後はメインの主題によるエンドタイトル「Le chat (Générique fin)」でしっとりと締めくくる。
離愁
「離愁」は、1973年製作のフランス=イタリア合作映画(日本公開は1975年)。出演はジャン=ルイ・トランティニアン、ロミー・シュナイダー、モーリス・ビロー、ポール・アミオ、ニケ・アリギ他。第二次大戦中、ナチスドイツ占領下のフランスを舞台に、他国へと逃亡を図るユダヤ人たちが乗った列車内での、ともに家族のある行きずりの男女の束の間の愛情を描くドラマ。フランス北部のフメイでラジオの修理屋を営んでいたジュリアン(トランティニアン)は、幼い娘と妊娠中の妻モニーク(アリギ)を客車に乗せ、自分は家畜車に乗って村から脱出した。ドイツ軍の攻撃が激しさを増す中、駅に列車が停車したとき、ジュリアンは列車に乗ろうと駆けて来たユダヤ人女性アンナ(シュナイダー)を見つけ、家畜車に乗せてやった。2人は身動きできない貨車の中で寄り添うようにしながら旅を続け、やがて惹かれ合うようになる……。
フィリップ・サルドは、撮影が始まる前に脚本だけを基に9楽章からなる交響組曲を作曲し、グラニエ=ドフェール監督はこの音楽を撮影のセットでかけて、その雰囲気、リズム、テンポをベースに演出したという(この点はフランソワ・トリュフォー監督作品でのジョルジュ・ドルリューのスコアと同様)。
このスコアでは、何といっても悲哀に満ちたアンナの主題「Anna」がこの上なく美しい。ここまで切なく情感豊かな音楽はあまりないだろう。この主題のバリエーションは「La guerre」「Julien」でもドラマティックに展開する。冒頭の「L'attaque」「L'exode」は、激しく緊迫したサスペンス音楽。「Le train」「La traversée」も、不吉なタッチで緊張感を盛り上げる。短くコンパクトにまとまったスコアだが、極めてエモーショナルで感動的な音楽。
あまりの若さに驚く
ピエール・グラニエ=ドフェール監督は、フィリップ・サルドが音楽を担当した「すぎ去りし日の…」を見てそのスコアに感銘を受け、監督のクロード・ソーテに電話してサルドを紹介してもらったという。グラニエ=ドフェールはソーテから「彼はすごく若いよ」と予め言われていたが、実際に会ってみてあまりにも若いのに驚いたらしい(サルドは当時23歳だった)。彼らが最初に組んだ作品が「LE CHAT」で、録音スタジオでミュージシャンたちを統率するサルドを見て、グラニエ=ドフェールは「自分の作曲家を見つけた」と感じたという。
フィリップ・サルドは、グラニエ=ドフェール監督の「帰らざる夜明け」「個人生活」等にもスコアを提供しているほか、クロード・ソーテ監督の「すぎ去りし日の…」「夕なぎ」「友情」「ギャルソン!」や、アンドレ・テシネ監督の「バロッコ」「ブロンテ姉妹」「海辺のホテルにて」、ベルトラン・タヴェルニエ監督の「判事と殺人者」「田舎の日曜日」「ソフィー・マルソーの三銃士」、ジョゼ・ジョヴァンニ監督の「暗黒街のふたり」、ジョルジュ・ロートネル監督の「愛人関係」、マルコ・フェレーリ監督の「ひきしお」「最後の晩餐」といった数多くの作品を手がけている。
テス
サルドと「(未公開)LOVESICK」「(未公開)マンハッタン・プロジェクト」「(未公開)SISTER MARY EXPLAINS IT ALL」で組んでいるブラジル出身の監督マーシャル・ブリックマンは、もともとサルドの音楽の大ファンで、彼がロマン・ポランスキー監督の「テス」(1979)に作曲したスコアを聴きながら「LOVESICK」(1983)の脚本を執筆していた。
この音楽に惚れ込んでしまったブリックマンは、サルドのパリの住所に脚本を送って作曲の依頼をした。脚本を読んで気に入ったサルドは、パリからニューヨークのブリックマンに電話して「そっちで会おう」と言ってきた。ニューヨークのカフェでサルドと会う約束をしたブリックマンは、眼鏡をかけ口髭をはやし、完璧にスーツを着こなした中年の欧州紳士がやってくると予想していた(その時点でサルドは150本以上の作品を手がけていた)が、彼の前に現れたのは眼鏡も口髭もない長髪にレザージャケットの30歳そこそこの男だった。
ブリックマンは、「きっとサルドは自分でやる気がなくなったので弟子をよこしたんだ」と思った。ところが、彼の前に座って話をはじめた男の声は、電話で聞いたサルド本人のものだった。ブリックマンは「この若者が一体いつ150本もの映画音楽を作曲したんだろう」と非常に驚いたという。
そんなサルドも今年(2022年)で74歳になるが、最近でもジャック・ドワイヨン監督の「ロダン カミーユと永遠のアトリエ」(2017)や、ルイ・ガレル監督の「パリの恋人たち」(2018)といった作品にスコアを提供し続けている。
映画音楽作曲家についてもっと知りたい方は、こちらのサイトをどうぞ:
素晴らしき映画音楽作曲家たち
