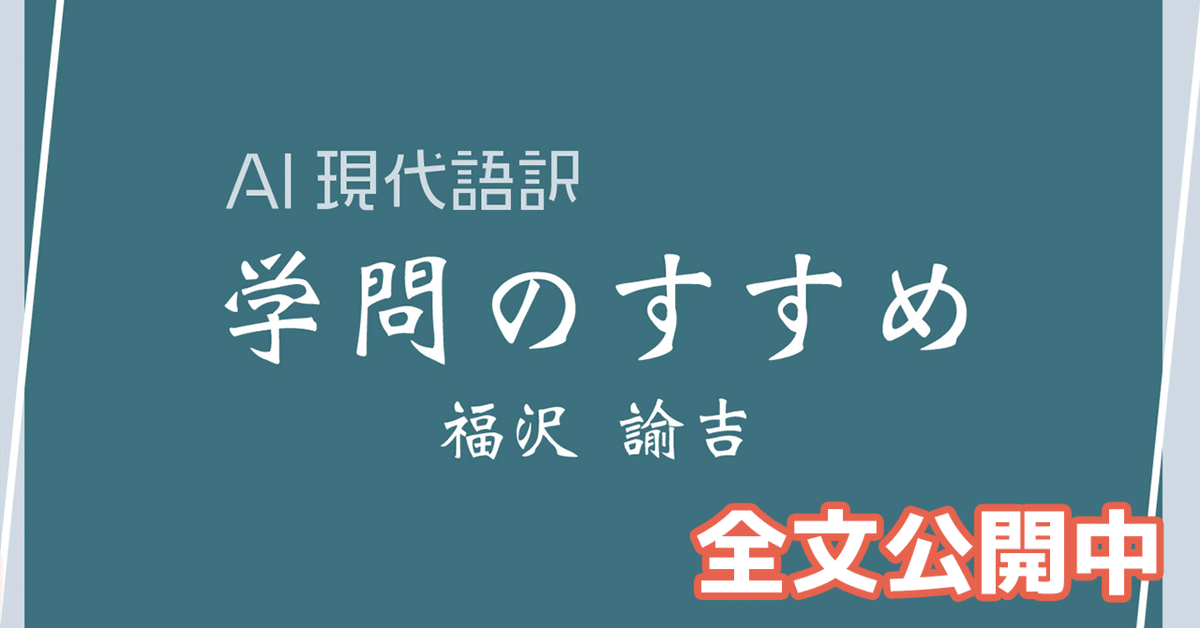
【全文公開】ChatGPTを使って『学問のすすめ』を現代語訳してみた
話題のChatGPT(GPT-4)を使って『学問のすすめ』を読みやすく現代語訳してみました。冒頭を比較してみるとこんな感じです。
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と言えり。されば天より人を生ずるには、万人は万人みな同じ位にして、生まれながら貴賤上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろずの物を資り、もって衣食住の用を達し、自由自在、互いに人の妨げをなさずしておのおの安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と言われています。だから、天が人を生み出すとき、みんな同じ立場で、生まれつきに貴賤や上下の違いはありません。すべての人は、物質や精神の力を使って、世界中のものを利用して生活し、自由に暮らして、人々が邪魔しあわずに安らかにこの世を過ごすことが目的です。
原文と比べて非常に分かりやすくなった思います。これフリガナ以外はChatGPTの出力そのままです。やばいですよね。本文も99%はChatGPTのものをそのまま使っています。
続きも全て無料で読めるのでぜひ読んでみてください。
Kindleで読みたい人はこちらもどうぞ(内容は同じです)。
初編
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と言われています。だから、天が人を生み出すとき、みんな同じ立場で、生まれつきに貴賤や上下の違いはありません。すべての人は、物質や精神の力を使って、世界中のものを利用して生活し、自由に暮らして、人々が邪魔しあわずに安らかにこの世を過ごすことが目的です。しかし今、人間の世界を見ると、賢い人もいれば、知らない人もいて、貧しい人もいれば、裕福な人もいて、高貴な人もいれば、卑しい人もいるので、その違いは雲と泥との違いのようです。その理由はとても明白です。『実語教』に、「人が学ばなければ知恵がなく、知恵がない者は愚か者である」とあります。だから、賢い人と愚かな人の違いは学ぶか学ばないかで決まります。また、世の中には難しい仕事もあれば、簡単な仕事もあります。難しい仕事をする人は高い身分の人と呼ばれ、簡単な仕事をする人は身分が低いと言われます。心を使って考える仕事は難しく、手足を使う力仕事は簡単です。だから、医者や学者、政府の職員、大きな商売をする町人、たくさんの働き手を使う大農家などは、身分が高くて貴いと言われます。
身分が高くてお金持ちの家でも、普通の人たちから見ると手が届かないように見えますが、それはただその人が勉強をしているかしていないかで違いが出来ただけで、天から決まったわけではありません。ことわざでは、「天はお金や地位を人に給わず、その人が頑張ったことに報いるだけだ」と言います。だから前にも言ったように、人は生まれた時にはみんな同じで、貧富や地位の差はありません。ただ勉強をして物事をよく知る人は立派な人やお金持ちになり、勉強をしない人は貧乏人や下の立場の人になるだけです。
学問とは、ただ難しい字を覚えたり、古文を読んだり、和歌を楽しんだり、詩を作るだけの高尚なものではありません。これらの文学も自然に人の心を喜ばせる良いものではあるけれど、昔から世間で言われている儒者や和学者のように尊ばれるべきものではありません。昔から漢学者の中にはうまく家庭を持つ人も少なく、和歌が上手で商売も巧みな人は珍しいです。だから心ある町の人や農民は、子どもに勉強をしてもらうことで財産がなくなるのではないかと親の気持ちで心配する人もいます。それは無理はありません。結局、その勉強の成果が遠くて日常生活に役立たないことがわかります。
だから、こんな難しい学問ばかり学ばず、むしろ私たちの生活に直接関係する実用的な学問をもっと大事にしましょう。例えば、いろは四七文字を覚えて、手紙の書き方、お金の計算の仕方、そろばんの練習、天秤の使い方などを学びましょう。さらに進んで学ぶべき点もたくさんあります。地理学とは日本や世界中の国々の風土や道案内を学ぶことです。科学とは、自然界の法則を調べて、物体の性質や働き方を理解する学問です。歴史とは、各時代や国々の出来事を研究する学問です。経済学とは、個人や家庭のお金の管理から国家の経済までを考える学問です。道徳教育とは、自分の行動をよくし、他人とうまく付き合い、この世界でうまく生きていくための基本的なルールを学ぶものです。
このような学問を学ぶ時には、欧米の本を読んだり、日本語になった資料を使って勉強しましょう。特に才能がある子どもたちには、外国語も教えて、彼らが専門的な知識を身につけるために研究することが大事です。こうした教育は実践的で、何か問題があればそれに対応して解決策を見つけられるようになるはずです。これが私たち一般人に必要な知識であり、すべての人が知っておくべきことです。その知識があれば、士農工商の四民はそれぞれの仕事を上手にやり、皆それぞれの立場で独立し、国全体も繁栄します。
勉強する際には、自分の立場や限界を理解することが重要です。人間は、生まれたときから自由で縛られない存在ですが、ただ単に自由だけを考えて、周りに迷惑をかけないようにすることが大切です。自分の自由と他人に迷惑をかけない範囲を知ることで、わがままにならずに済みます。例えば、自分のお金を使って楽しむことは悪くありませんが、それが他人に悪影響を与える場合はダメです。
また、自由と独立は人それぞれにあるだけでなく、一国全体にもあるものです。私たちの日本はアジアの東にある島国で、昔から外国とあまり交流を持たず、自分たちの国のものだけで生活していましたが、困っていることはありませんでした。しかし、嘉永年間にアメリカ人が来て外国との取引が始まり、今のようになりました。その後も、いろいろな意見があり、国を閉ざして外国人を追い出そうとする人もいましたが、その考え方はとても狭いもので、「井の中の蛙」という言葉がぴったりで、役に立ちません。日本も西洋の国々も同じ世界にあり、同じ太陽の光を浴び、同じ月を眺め、海や空気を共有し、感じ方も同じ人々ですから、お互いに余っているものを交換し、お互いに教え合い、学び合い、恥ずかしがらず、誇らず、便利さを追求し、幸せを願い、天理と人道に従って交流を深めなければいけません。真理のためにはアフリカの奴隷にも敬意を払い、正義のためにはイギリスやアメリカの軍艦も恐れず、国の名誉のためには日本の人々みんなで命を捨ててでも守らなければなりません。これこそが一国の自由と独立だと言えます。
しかしながら、中国の人々のように、自分たちの国以外に他の国がないかのように考え、外国人を見るとすぐに「異民族」と呼び、彼らを動物のように見下し嫌う態度は、自分たちの力を計り知らずに無理に外国人を追い出そうとする様子は、国の立場を理解せず、個人の自由を大切にせず、わがままで無鉄砲な人と言えるでしょう。明治時代になってから日本の政治は大きく変わり、外国との関係では万国公法に従い、国内では人々に自由と独立の考え方を示しました。普通の人にも名字や馬に乗ることを許すようになったり、士農工商の四つの身分を同じように扱うようになったりしたことは、日本の歴史の中で素晴らしい出来事だと言えます。
これからは、日本のみんなにとって、生まれたときから持っている立場とか言うのはほとんどなくなるでしょう。ただ、その人の才能や性格、そして住んでいる場所によって立場が変わるのです。例えば、政府の役人を大切にするのは普通ですが、それは役人自身がすごいからではなく、役人が持っている才能や性格で仕事をがんばり、国のために大切な法律を扱うからです。人がすごいわけではなくて、法律がすごいのです。
昔の時代に、東海道でお茶壺が通るという話は、みんなが知っていることでした。他にも、政府が使う鷹は人よりも大切で、政府が使う馬のために旅行者は道を譲ったりしました。全部、「御用」という言葉がついているものだけ、みんなが怖くて大切だと思っていたんです。でもこれはみんな、何千年も前から嫌がりながらも、自然に慣れてしまって、上下の間に見せかけだけの風習ができてしまいました。結局、それらは法律のためでも品物のためでもなく、ただ政府が威力を見せて、人々をおびえさせて、自由を邪魔する卑怯な方法でした。これを「虚偽の威力」と言います。
今日になって、もう日本中にはそんな恥ずかしい制度や風習はなくなったはずです。みんな安心して、もし政府に対して不満があるなら、隠さずに遠慮しないで意見を言うべきです。それが天理と人情に合っていることなら、命をかけて争うべきです。これが日本の国民としての役割だということです。
前に言った通り、人の一人も国も、天の道理に基づいて自由なものですから、もしこの国の自由を邪魔する人がいたら、世界中の国々を敵にしても怖くありませんし、この一人の自由を邪魔する人がいたら、政府の役人も気にしないで済みます。特に最近は、すべての人が同じように扱われる考えが広まっているので、みんな安心して、ただ天の道理に従って思う存分に仕事をするべきだと言いますが、それでも人間はそれぞれの立場があって、その立場に合った才能や徳を持っていなければなりません。才能や徳を身につけるためには、物事の理由を知らなければならず、物事の理由を知るためには、文字を学ばなければなりません。これが学問がとても大切な理由です。
最近の様子を見ると、農業や工業、商業を営む人たちは、以前よりもずっと立場が良くなって、もうすぐ士族と同じような位置になりそうです。今日では、農業や工業、商業の人たちの中にすごい人がいれば、政府がその人を使う道がもう開かれています。だから、自分の立場を大切にして、自分の立場を重要だと思って、悪いことはしないでください。世の中で、知識がなくて文字が読めない人ほど、かわいそうで、嫌なものはありません。賢さがないせいで、恥を知らなくなって、自分が無知で貧しい生活を送っているのに、自分のせいだと思わず、お金持ちの人をうらやんで、困ったことには仲間を集めて強訴や一揆などで乱暴なことをすることがあります。恥を知らないと言えば、法律を恐れないと言えます。国の法律を頼りに自分の安全を守り、家族を養っているのに、その法律を頼りにしているだけで、自分の欲望のためにはまた法律を破ろうとします。前後のつじつまが合わないことですね。また、たまたま家が裕福で適切な財産がある人も、お金を貯めることは知っていても、子どもたちに教えることは知らないのです。教えられない子どもたちは、その愚かさも当然だと思われます。結局は怠け者になって遊び歩き、先祖から受け継いだ家の財産を一瞬で失うことが少なくありません。
かかるばかな人たちを支配するには、とても道理を使って教える方法がなければ、ただ力を使って怖がらせるだけです。西洋のことわざに「ばかな人たちの上に厳しい政府がある」というのは、このことです。これは政府の厳しさではなく、ばかな人たちが自分たちで災いを呼ぶことです。ばかな人たちの上に厳しい政府があれば、良い人たちの上には良い政府があるのです。だから今、私たちの日本国にも、この人々がいてこの政治があります。もし人々の徳義が今日から衰えて、さらに無学で文字が読めない状態になることがあれば、政府の法ももっと厳しくなるでしょう。もしまた、人々みんなが学問に励んで、物事の理由を知り、文明の風に進むことがあれば、政府の法もさらに寛大になるでしょう。法が厳しくなったりやさしくなったりするのは、ただ人々の徳が良いか悪いかによって変わるだけです。誰が厳しい政治を好んで良い政治を嫌うでしょうか。誰が自分の国が豊かで強いことを願わないでしょうか。誰が外国に侮られることを許すでしょうか。これは人である者の普通の気持ちです。今の世に生まれ、国に尽力する心がある人は、必ずしも自分を苦しめるほどの心配はありません。ただ大切な目標は、この人間の気持ちに基づいて、まず自分の行いを正しくし、学問に励み、たくさんのことを知り、それぞれの立場に合った知恵や徳を身につけて、政府が政治をするのが楽になり、人々が支配を受けて苦しみがないように、お互いに適切な位置を見つけて、一緒に全国の平和を守ろうとすることだけです。今、私たちが勧める学問も、この一つのことを目的にしています。
端書
このたび、わたしの故郷である中津で学校を開くことになりました。学問の大切さを伝えるために、昔から仲良くしている同じ町の友達に見せるために、一冊の本を作りました。それを見た人が、「この本を中津の人だけに見せるより、たくさんの人に知らせたほうがもっといいことになる」と言ってくれたので、慶応義塾の印刷機を使って、たくさんの人に見てもらえるようにしました。
明治四年未十二月
福沢諭吉
記
小幡篤次郎
二編
端書
学問とは広い言葉で、形のない学問もあれば、形のある学問もあります。心学、神学、理学などは形のない学問です。天文、地理、物理、化学などは形のある学問です。どちらにしても、みんな知識や見聞を広げて、物事の道理をわかり、人が持つ役割を知ることです。知識や見聞を広げるためには、人の言葉を聞いたり、自分で考えたり、本を読んだりしなければなりません。だから、学問には文字を知ることが必要ですが、昔の人が思うように、ただ文字を読むだけを学問とするのは大きな間違いです。
文字は学問をするための道具で、例えば家を建てる時にハンマーやノコギリが必要なようなものです。ハンマーやノコギリは家を建てるために欠かせない道具ですが、その道具の名前を知るだけで家を建てる方法を知らない人は大工とは言えません。まさにこの理由で、文字を読むことだけを知って物事の道理をわからない人は学者とは言えません。いわゆる「論語を読んでいるのに論語が分からない」ということです。日本の『古事記』を覚えていても、今日の米の値段が分からない人は、家庭の学問に詳しくない人と言われます。経典や歴史の奥義に詳しくても、商売のルールを知らずに正しく取引ができない人は、お金の計算が苦手な人と言われます。何年も勉強して、たくさんのお金を使って洋学を学んでも、まだ自分の生活費を稼げない人は、時代の学問に疎い人です。これらの人たちは、ただ文字の問屋と言われるだけです。その役割は、ご飯を食べるための字引きと変わりません。国のためには無用の長物で、経済を邪魔する食客と言えます。だから、家庭のことも学問ですし、お金の計算も学問ですし、時代を読むこともまた学問です。どうして必ず和漢洋の本を読むだけを学問と言えるのでしょうか。
この本のタイトルは『学問のすすめ』と名付けられていますが、決して文字を読むことだけを勧めるわけではありません。本の中に書かれていることは、西洋の本からその文章を直接訳したり、その意味を訳したりして、形のあることでも形のないことでも、一般の人が知っておくべき事柄を紹介し、学問の大切さを示しています。最初に出版された一冊目を第一編とし、その考えを広げて今回の第二編を書き、次に第三編、第四編も書く予定です。
人はみんな同じように生まれる
最初の部分で、人はみんな同じ立場で生まれて、上下の違いがなく自由に生きられると書いてあります。今、この考えを広げて言いたいことがあります。人が生まれるのは、天が決めたことで、人間の力ではありません。人々がお互いに尊敬し愛し合い、それぞれの仕事を果たして、お互いに邪魔しない理由は、もともと同じ人間で、一緒に天を共有し、天地の間のものを作り出すからです。例えば、家族の中で兄弟が仲良くするのは、同じ家族で、一緒に一つの親を持っている大切な関係だからです。
だから、今、人と人とのバランスを考えると、みんな同じだと言わざるを得ません。ただ、その同じというのは、見た目や状況が同じという意味ではなく、正しい道徳が同じという意味です。見た目や状況を考えると、貧乏と金持ち、弱い人と強い人、賢い人とおろかな人の違いは大きく、たとえば大名やお金持ちで、お城に住んで、きれいな服を着て、おいしいものを食べる人もいれば、貧しい人で、小さな家に住んで、今日のご飯に困る人もいます。また、頭が良くて力強い人が役人や商人になって、世の中を動かす人もいれば、知恵がなくて一生、飴やおこしを売る人もいます。また、強い相撲取りがいれば、弱いお姫様もいます。これは雲と泥の違いですが、一方で、その人々が持つ正しい道徳を考えると、みんな同じで、少しも違いがありません。つまり、その正しい道徳とは、人々が命を大切にし、自分の持ち物を守り、名誉を重んじる大事な考えです。天が人を生み出す時、体と心の働きを与えて、人々がこの道徳を実現する仕組みを作りました。だから、どんなことがあっても、人間の力でこれを傷つけてはいけません。
大名の命も貧しい人の命も、命の大切さは同じです。お金持ちがたくさんのお金を持っていても、飴やおこしを売る人が少しのお金を持っていても、自分のものを守る気持ちは同じです。世の中には、「泣く子と地頭には勝てない」とか、「親と主人は無理を言うもの」という悪い考え方がありますが、これは見た目や状況と道徳を間違えて考えている意見です。地頭と百姓は、見た目や状況が違っても、正しい道徳は同じです。百姓にとって痛いことは地頭にとっても痛いはずで、地頭が口に入れる甘いものは百姓にも甘いはずです。痛いものを遠ざけて甘いものを手に入れるのは人間の欲求で、他の邪魔がなくて達成できることは、人間の正しい道徳です。この道徳に関しては、地頭も百姓も全く違いがありません。ただ、地頭はお金持ちで強く、百姓は貧乏で弱いだけです。貧乏とお金持ち、弱い人と強い人は、見た目や状況ではもともと同じになれません。
しかし、今、お金持ちで強い人が、貧乏で弱い人に無理を押し付けることは、見た目や状況が違うからと言って、他の正しい道徳を傷つけていいわけではありません。これを例えると、力士が自分に力があるからと言って、その力で隣の人の腕をねじ曲げるようなことです。隣の人の力はもともと力士より弱いかもしれませんが、弱いからと言って、その腕を使って自分の便利を図ることに問題がないはずです。それなのに、理由もなく力士に腕を折られるのは、とても迷惑なことです。
また、この考えを世の中のことに当てはめてみましょう。昔の幕府の時代には、武士と庶民の区別が大きく、武士は勝手に権力を振りかざして、百姓や町人を罪人のように扱っていました。そして、「切り捨て御免」という法律がありました。この法律によれば、庶民の命は自分の命ではなく、借り物のようなものです。百姓や町人は、関係もない武士に頭を下げて、道路を避けたり、席を譲ったりしなければならず、自分の家で飼っている馬にも乗れないほどの不便さを受け入れなければならなかったのは、とてもおかしいことです。
右は、武士と平民が一人ずつ対立しているのは不公平ですが、政府と人々の関係ではもっと見苦しいことがあります。幕府はもちろん、三〇〇の大名の領地にもそれぞれ小さな政府があり、農民や町人を勝手に扱っています。時々、慈悲に似たことがあるけれど、本当は人々に持っている権利を許さず、本当に見ていられないことが多いです。そもそも、政府と人々の関係は、前にも言ったように、ただ強いか弱いかだけで、権利に違いはありません。農民はお米を作って人々を養い、町人は物を売買して便利にしています。これは農民や町人の仕事です。政府は法律を作って悪い人を止め、良い人を守ります。これは政府の仕事です。この仕事をするにはたくさんのお金が必要ですが、政府にはお米もお金もないので、農民や町人から年貢や運上を出してもらって政府のお金をまかないます。これは政府と人々の約束です。だから、農民や町人が年貢や運上を出してちゃんと国の法律を守れば、その仕事を果たしたと言えます。政府が年貢や運上をもらって正しく使って人々を守れば、その仕事を果たしたと言えます。両方がちゃんと仕事をして約束を守れば、もう何も文句はありませんし、それぞれの権利を大切にして邪魔することはありません。
しかし、幕府の時代には政府のことをお上様と呼び、お上の用事があると威張っていました。道中の旅館ではただで食べたり、川でお金を払わなかったり、人足にお金を払わなかったり、ひどい場合は旦那が人足を脅してお酒代を取ったりしました。とてもひどいことです。また、大名が建物を作ったり、役人が無駄なことをしたりしてお金が足りなくなると、いろいろな言い訳をして年貢を増やしたり、お金を出させたりしました。これを国の恩に報いると言っていました。でも、本当の国の恩とは何でしょうか。農民や町人が安心して仕事ができて、泥棒や殺人がなくて暮らせることが政府の恩です。もちろん、安心して暮らせるのは政府の法律があるからですが、法律を作って人々を守るのは政府の仕事です。これを恩とは言えません。政府が人々に対してその保護を恩とするならば、農民や町人は政府に対してその年貢や運上を恩と言います。政府が人々の公事訴訟をお上の面倒と言うならば、人々も言います。「一〇俵のお米の中から五俵の年貢を取るのは農民にとって大変な面倒です」と。言い返すことが終わらなくなります。とにかく、恩があるのなら、一方だけが礼を言うのではなく、両方が礼を言うべきです。
悪い風習がどうして始まったか調べると、その根本は、人間みんな同じ大切さを間違えて、お金持ちと貧しい人、強い人と弱い人の違いを悪い道具に使って、政府の力を使って貧しい弱い人々の正しい考えや意見を邪魔することになったからです。だから、人間はみんな同じ大切さを忘れてはいけません。これが人間の世界で一番大切なことです。西洋の言葉では、これをレシプロシチ(互恵)またはエクウオリチ(平等)と言います。つまり、最初に言った「みんな同じ立場」というのは、このことです。
これは、農民や町の人々に、思い通りに力を使ってもらうという意見ですが、他の面から見ると、別の考え方もあります。人と関わるときは、相手の性格や立場によって、自然にその扱い方も変わるべきです。もともと、人々と政府の関係は、同じ立場で役割を分けて、政府は人々の代表として法律を作り、人々はその法律を守ると約束したものです。例えば今、日本中で明治の年号を使っている人たちは、今の政府の法律に従うことを約束した人々です。だから、国の法律が決まったら、たとえそれが一人のために不便でも、改善するまでは動かせません。慎重に守らなければいけません。これが人々の役割です。しかし、無学で文字が読めず、正しい考え方もわからず、身につけている技術は食べたり飲んだり寝たり起きたりするだけで、その無知なくせに欲望は強く、目の前の人をだますのが上手で、政府の法律を逃れるのが巧みで、国の法律が何なのかもわからず、自分の役割が何なのかもわからず、子どもをたくさん生んでもその子どもに教える方法も知らず、恥や法律も知らない馬鹿者で、その子孫が増えると国に利益はなく、かえって害を与える者がいないわけではありません。そんな馬鹿者を扱うには、道理だけでは無理で、仕方なく力を使って脅かし、一時的な大きな害を抑えるしか方法がありません。
これが世の中に横暴な政府がある理由です。ただ日本の旧幕府だけでなく、アジアのいろいろな国も昔からそうです。だから、一国の横暴な政治は、横暴な王や役人のせいだけではなく、実際には、人々の無知さが自分たちで災いを招いているのです。他人にそそのかされて暗殺を企む人もいれば、新しい法律を誤解して暴動を起こす人もいるし、強訴という名目で金持ちの家を壊したり、お酒を飲んでお金を盗む人もいます。その行動はほとんど人間らしくありません。そんな悪い人々を扱うには、釈迦も孔子も良い方法がないので、必ず厳しい政治を行わなければなりません。だから、人々が横暴な政府を避けたいなら、早く勉強に励んで自分の才能や徳を高め、政府と対等な立場に立たなければなりません。これが私たちが勧める学問の意味です。
三編
国は同等なること
おおよそ、人として名前があるなら、お金持ちでも貧しい人でも、強い人でも弱い人でも、国民も政府も、その権利に違いはありません。これは、第二編に書かれています。今、この権利を広げて、国と国の関係を考えます。国とは、人々が集まったもので、日本は日本人が集まったものですし、イギリスはイギリス人が集まったものです。日本人もイギリス人も、みんな天地の間の人ですから、お互いにその権利を邪魔する理由はありません。一人が一人に向かって害を与える理由がなければ、二人が二人に向かって害を与える理由もありません。百万人も千万人も同じことで、物事の道理は人数の多少によって変わりません。
今、世界中を見渡すと、文明開化で文学も武器も盛んで富んでいて強い国がありますし、まだ野蛮で未開で文武どちらもできなくて貧しくて弱い国もあります。一般にヨーロッパ・アメリカの国々はお金持ちで強く、アジア・アフリカの国々は貧しくて弱いです。でも、この貧富や強弱は国のあり方だから、最初から同じではありません。しかし、今、自分たちの国がお金持ちで強いからといって、貧しい弱い国に無理を押し付けるのは、力持ちが病気の人の腕を握りつぶすようなもので、国の権利では許されないことです。
最近、私たちの日本でも、今の状況では西洋の国々の富や強さには及ばないところがありますが、一国の権利においてはちょっとした違いもありません。道理に戻って曲がりを正す日が来れば、世界中を敵にしても怖くありません。「日本中の人々がみんな命を捨てても国の威光を守る」というのは、この場合です。それだけではなく、貧富や強弱のあり方は自然の決まりではなく、人々の努力や怠けによって変わるものです。今日の愚か者も明日は賢者になれますし、昔の富強も今の貧弱になれます。古今、その例はたくさんあります。私たち日本人も、これから学問に励んで気力をしっかり持って、まず自分一人の独立を考え、それから一国の富強を目指すことができれば、西洋人の力を恐れる必要はありません。道理あるものはそれに従い、道理ないものは打ち払うだけです。自分一人が独立して、一国が独立するというのは、このことです。
自分一人が独立して一国が独立すること
前の文章で言ったように、国と国は同じ権利を持っていますが、国の中の人々が独立の気力がないときは、一国が独立の権利を守ることができません。そのために、次の三つの項目があります。
第一条 独立の気力がない人は国を大切に思わない。
独立とは、自分で自分の身を支配し、他人に頼らない心のことです。自分で物事の正しいか間違いかを判断して、失敗しない人は、他人の知恵に頼らない独立です。自分で心身を働かせて、自分の生活を立てる人は、他人のお金に頼らない独立です。人々がこの独立の心を持たずに、ただ他人の力に頼ろうとするだけなら、全国の人はみんな、頼る人ばかりで、引き受ける人はいません。これは、盲目の人が手引きがなくて進むようなもので、とても困ります。ある人が言います、「人々はこれに頼るべきで、これを知る必要はありません。世の中は目の見えない人が多くて、賢い人が上にいて、みんなを支配して、上の意見に従わせることができます」と。この意見は、孔子の考え方ですが、実際には間違っています。一国中で、人々を支配するほどの才能や徳を持った人は、千人の中で一人にすぎません。
仮にここに人口百万人の国があるとしましょう。その中で千人は賢い人たちで、残りの九十九万人は知識がない普通の人たちです。賢い人たちがその普通の人たちを支配して、子どものように愛したり、羊のように育てたり、怖がらせたり、優しくしたりして、どうすべきか教えることができれば、普通の人たちも上の人の言うことに従って、泥棒や殺人がなく、国は平和になるでしょう。しかし、この国の人々は主人と客の二つに分かれていて、主人は千人の賢い人たちで、自由に国を支配しています。残りの人たちは何も知らない客の立場です。客の立場だから心配事も少なく、ただ主人に頼って生活しているだけで、国の問題に悩むことはありません。これは当然のことで、実際に面倒な状況です。国内のことはまだしも、外国と戦争が起こったら、その問題がどれだけ大変か想像してみてください。知識がなく力もない普通の人たちは、槍を逆さに持つことすらできないでしょう。しかし、「私たちは客だから、命を捨てるのはやりすぎだ」と逃げ出す人が多くなるでしょう。そうなれば、この国の人口は名ばかり百万人でも、国を守るためにはその人数がとても少なく、一国として独立するのは難しいです。
このような状況だから、外国に対抗して自分たちの国を守るためには、自由で独立した気持ちを全国に広め、国中の人々、身分や立場に関係なく、その国を自分の身に引き受けるべきです。英国の人は英国を自分の国だと思い、日本の人は日本を自分の国だと思います。その国の土地は他人のものではなく、自分たちのものです。だから、国のためを思うことは家族のためを思うようなものです。国のためにはお金を失うだけでなく、命を捨てることも惜しくありません。これが国を助ける大きな理由です。
もちろん、国の政治を行うのは政府で、その支配を受けるのは人々ですが、これはただ便利のためにお互いの役割を分けているだけです。一国全体に関わることになったら、人々は政府だけに国を任せて、横で見ているだけではダメです。日本の人も英国の人も、自分たちの名前や肩書に国の名前があれば、その国に住んで、生活し、自由に行動する権利があります。その権利があるからこそ、それに伴う責任も持たなければなりません。
昔、戦国時代に駿河の今川義元が何万人もの兵士を率いて織田信長を攻めようとしたとき、信長の策で桶狭間に兵士を隠して、今川の陣地に近づいて義元の首を取りました。その結果、駿河の兵士たちは蜘蛛の子が散るように逃げ出し、戦わずして敗れました。当時有名だった駿河の今川政府も一瞬で滅び、跡形もありません。それに比べて、数年前のフランスとプロイセンの戦争では、両国が戦い始めたばかりで、フランス皇帝ナポレオンはプロイセンに捕まってしまいました。しかし、フランス人はそれでも希望を失わず、ますます怒って防戦し、骨を見せるほど血を流して何ヶ月も城を守りました。最後に和平が成立しましたが、フランスは今も昔も変わらないフランスです。今川の話と比べると、全く違う話です。その理由は何でしょうか。駿河の人々はただ義元一人に頼っていて、自分たちは客だと思っていて、駿河の国を自分の国だと思っていませんでした。一方、フランスには国を助ける人々がたくさんいて、国の危機を自分の問題として受け止め、誰かに言われるまで待たずに自分たちの国のために戦っていました。だから、こんな違いがあるのです。これを考えると、外国に対抗して自分たちの国を守るためには、その国の人々が独立した気持ちで国を大切に思うことが重要で、そうでない人たちはそれほど大切に思わないことが分かります。
第二条 家の中で自立できない人は、外で外国人と接する時も、自立できない。
自立できない気持ちがない人は、必ず他の人に頼ります。他の人に頼る人は、必ず他の人を怖がります。他の人を怖がる人は、必ず他の人におべっかを使います。いつも他の人を怖がっておべっかを使う人は、だんだん慣れて、顔の皮が鉄のようになります。恥ずかしいことを恥ずかしく思わず、言うべきことを言わず、人を見るだけでただおじぎをするだけです。いわゆる「習慣が性格になる」ということで、慣れたことは簡単に直すことが難しいものです。例えば今、日本では一般の人に名字や馬に乗ることを許して、裁判所の様子も変わって、表向きは士族と同じようになっていますが、その習慣はすぐに変わらず、一般の人の性格は昔の一般の人と変わりません。言葉も汚く、おもてなしも汚く、目上の人に会えば一言半句の理屈を言うことができず、立てと言われれば立ち、踊れと言われれば踊ります。その従順さは家で飼っている痩せた犬のようです。本当に無気力で厚かましい顔だと言えます。
昔、鎖国の時代に旧幕府のような窮屈な政治を行っていた時代では、国民に気力がなくても政治に影響しないどころか、むしろ便利だったので、わざと国民を無知にして、無理に従順にさせることが役人の得意だったのですが、今、外国と交流する時代になって、このために大きな弊害があります。例えば田舎の商人たちが、恐れながら外国との取引に挑戦して横浜などに来ると、まず外国人の体格がたくましいのを見て驚き、お金がたくさんあるのを見て驚き、商館が大きいのを見て驚き、汽船が速いのを見て驚きます。すでに胆を落として、次々に外国人に近づいて取引をすると、その交渉の鋭さに驚きます。時々無理なことを言われることがあっても、ただ驚くだけでなく、その威力に震えて怖がり、無理だとわかっていても大きな損失や恥を受けることがあります。これは一人の損失ではなく、一国の損失です。一人の恥ではなく、一国の恥です。本当に馬鹿らしいようですが、先祖代々自立しない町人の性格は、武士に困らされ、裁判所に叱られ、一人で生活費を稼ぐ足軽に会ってもお旦那様と尊敬する心は腹の底まで腐っていて、一朝一夕に洗い流すことができません。こんな臆病な神の手下たちが、あの大胆で恐れ知らずな外国人に会って、胆を抜かれるのは仕方がないことです。これは家の中で自立できない人が、外で自立できない証拠です。
第三条 自立する気持ちがない人は、他の人に頼って悪事をすることがある。
旧幕府の時代に、名目金というものがありました。それは御三家などという権威のある大名の名前を借りてお金を貸し、かなり無理な取引をしていたことがあります。そのやり方はとても悪いです。自分のお金を貸して返してもらえない人がいれば、何度も力を尽くして政府に訴えるべきです。しかし、この政府を怖がって訴えることを知らず、汚い方法で他の人の名前を借りて他の人の暴力でお金を返させるのは卑怯な行動ではありませんか。今日では名目金の話は聞かれませんが、世間に外国人の名前を借りる人はいないでしょうか。私たちはまだその確証を得ていないので、ここで明らかに論じることはできませんが、昔のことを考えると、今の世の中にも疑いがないわけではありません。これからもし外国人と混ざって暮らすような場合があって、その名前を借りて悪いことをする人がいたら、国の災いで、本当に言ってはいけないことです。だから、国民が自立できない気持ちがあると、その取り扱いが便利だと思って油断してはいけません。災いは思わぬところから起こるものです。国民がますます自立できない気持ちが少なくなれば、国を売る災いもまたますます大きくなるでしょう。つまり、他の人に頼って悪いことをするというのは、このことです。
これらの三つの条文で言っていることは、すべて国民が自立しない心から生じる災害です。今の世に生まれて、愛国の気持ちがある人は、官民問わず、まず自分自身の自立を考え、余力があれば他の人の自立を助けるべきです。親は子どもに自立を教え、先生は生徒に自立を勧め、士農工商の人たちも自立して国を守らなければなりません。一言で言えば、人を縛って一人で心配を求めるより、人を放って一緒に苦楽を共有する方が良いです。
四編
学者の仕事について話す
最近、こっそり賢い人たちの話を聞くと、「これから日本が栄えるか衰えるかは、人々の知恵で明らかに計り難しいけれども、結局、独立を失う心配はないだろう。今見ている勢いで少しずつ進歩していけば、必ず文明が盛大なところに行くだろう」と言って、これについて質問する人がいます。また、「その独立を守るべきかどうかは、今から二、三十年後になれば明らかにわかるだろう」と言って、これを疑う人がいます。さらに、とても日本を見下した外国人の意見に従うと、「日本の独立は危ない」と言って、これを難しいと考える人がいます。もちろん、人々の意見を聞いてすぐに信じて希望を失うわけではありませんが、結局、これらの意見は私たちの独立を守るべきかどうかについての疑問です。疑いがなければ、質問が起こる理由もありません。もしイギリスに行って、「イギリスの独立は守るべきかどうか」と言って質問したら、みんなが笑って答える人はいないでしょう。答える人がいないのは、それを疑わないからです。だから、私たちの国の文明の様子は、今日も昨日に比べて進歩しているように見えるけれど、最後にはまだ疑いがあるところを免れないのです。せめてこの国で生まれて日本人の名前がある人は、これにがっかりしないわけにはいかないでしょう。今、私たちもこの国で生まれて日本人の名前があり、その名前があるからには、それぞれの役割を明らかにして尽くすべきです。もちろん、政治の仕事をするのは政府の任務ですが、人間の仕事には政府が関わらないものもたくさんあります。だから、一つの国の全体を整理するためには、国民と政府が協力して初めて成功を得られるもので、私たちは国民としての役割を果たし、政府は政府としての役割を果たし、互いに助け合って全国の独立を維持しなければならないのです。
すべてのものを維持するためには力が均等でなければなりません。例えば、人の体のように。これを健康に保つためには、食べ物や飲み物がなければならないし、空気や光も必要です。寒さや暑さ、痛みやかゆみ、外から刺激があって内からそれに応じることで、一つの体の働きを調和させます。もし急に外からの刺激をなくして、ただ生きる力だけで働かせて放っておくと、人の体の健康は一日も保てません。国も同じです。政治は一つの国の働きです。この働きを調整して国の独立を守るためには、内に政府の力があり、外に国民の力があり、内外が相応しく力を平均しなければなりません。だから、政府はまだ生きる力のようで、国民はまだ外からの刺激のようです。もし急にこの刺激をなくして、ただ政府の働きだけに任せて放っておくと、国の独立は一日も保てません。せめて人の体の理屈を明らかにし、そのルールを一つの国の経済の議論に適用することを知っている人は、この理屈を疑わないでしょう。
今、私たちの国の状況を見て、外国に及ばないものを挙げると、学問だとか、商売だとか、法律だとかがあります。世界の文明は主にこれら三つに関係していて、三つが揃わなければ国の独立を得られないことは、賢い人が待たなくても明らかです。しかし、今の日本には、まだ一つも整ったものがありません。
政府が新しくなってから、役所にいる人たちは、力を尽くしているし、その才能も悪くないと言えますが、仕事をする上でどうしても避けられない原因があって、思い通りにならないことが多いのです。その原因は、国民が無知で文字が読めないことです。政府はすでにその原因があることを知っていて、学問を勧めたり、法律を話し合ったり、商売の方法を示したりして、国民に説明したり、自分たちで先例を示したり、いろいろな方法を試していますが、今日まで実際に効果があることは見られず、政府はまだ独裁の政府で、国民はまだ元気がなくて力のない愚かな人々です。少し進歩したことがあっても、そのために努力したりお金を使ったりしたことと比べると、成果が少ないのはどうしてでしょう。やはり、一つの国の文明は、政府の力だけで進むものではありません。
人が言います、「政府は、しばらくこの無知な人々を治めるために一時的な方法を使って、その知恵や徳が進むのを待ってから、自分たちで文明の世界に入ろうとするんだ」と。この考えは言うべきだけど、実行すべきではありません。私たちの国の人々は何千年も専制政治に苦しめられてきて、みんな心に思っていることを表現できず、だますことで安全を手に入れ、うそをついて罪を逃れることが、人生で必要な道具になりました。不誠実さや不信は日常の習慣になり、恥ずかしいと思う人も疑う人もいなくて、自分の誠実さはもう消えてしまいました。こんな状態で、国を大切に思う余裕があるでしょうか。政府はこの悪い習慣を直そうとして、ますます威厳を見せつけて、人々をおどかしたり叱ったりして、誠実になるように強制しようとします。でも、それがかえってますます不信を引き起こし、火で火を消そうとするようなものです。結局、上下の間に隔たりができて、それぞれ独自の雰囲気が生まれました。その雰囲気とは、いわゆるスピリットというもので、すぐには変えられません。最近、政府の外見はだいぶ変わりましたが、専制的で抑圧的な雰囲気は今も残っています。人々も少しずつ権利を手に入れるようになりましたが、卑屈で不信の雰囲気は依然として変わらないままです。この雰囲気は形がなくて目に見えないけれど、世間全体の出来事に現れていて、それが虚しいものではないことが分かります。
試しに一つ例を挙げてみましょう。今、政府にいる人たちの中には、私が話を聞いたり行動を見たりすると、大抵は広い心を持った立派な人たちで、私たちが感心できるだけでなく、その言動に憧れるものもあります。また、一方で平民だとしても、みんなが無気力で愚かな人ばかりではなく、何万人に一人くらいは公平で誠実な良い人もいます。しかし、今、この立派な人たちが政府で政治を行っているのに、その政治の成果を見ると、私たちが喜べないことがたくさんあります。また、あの誠実な良い人たちも、政府と関わるとすぐに折れてしまい、うそやだましの手段で政府をだまして、恥ずかしいと思わないんです。この立派な人たちがこんな政治を行い、この人々がこんな低劣な状態に陥るのは何故でしょうか。まるで一つの体に二つの頭があるようなものです。私たちの中には知恵があるけど、政府の中には愚かさがある。これをばらばらにすると明るいけど、集めると暗くなる。政府は賢い人たちが集まる場所なのに、愚かな人の仕事をするものだと言えます。不思議ではありませんか。結局、その理由はあの雰囲気に支配されて、人々が自分たちで力強く働くことができないからだと思います。明治維新以来、政府が学問や法律や商売などの道を盛んにしようとしても効果がないのは、その病気の原因がここにあるからです。それなのに、一時的な方法で人々を支配して、知恵や徳が進むのを待つというのは、威圧で文明に迫ろうとするものか、だますことで善行に導く策なのでしょうか。政府が威圧を使えば、人々はだましで応じるでしょうし、政府がだましを使えば、人々は形だけ作って従うだけです。これを最善の策とは言えません。たとえその策が巧みでも、文明の実情に適用しても効果がないでしょう。だから言います、世の中の文明を進めるためには、ただ政府の力だけに頼るべきではありません。
右所論を考えると、今、わが国の文明を進めるには、まず人々の心に染み付いた悪い風習を一掃しなければなりません。これを一掃する方法は、政府の命令だけでは難しく、私の説教だけでも難しいです。必ず自分自身で行動して、人々に見本を示すことが大切です。今、その見本となるべき人物を探すと、農業や商業の中にはいませんし、和漢の学者の中にもいません。その役割を果たす人は、洋学を学んだ人たちだけです。
しかし、洋学者にも頼りきれない問題があります。最近、洋学者が増えてきて、外国の文章を読んだり、訳書を読んだりして勉強しているようですが、学者の中には、文字を読んで意味が分からない人や、意味が分かっても実際に行動しない人がいます。私が疑問に思うのは、この洋学者たちは、みんな官僚の立場しか考えず、民間の立場を考えないことです。結局、漢学者と同じ悪い習慣を持っていて、まるで中国の知識を身につけて洋服を着ているようなものです。
実際の証拠を挙げてみましょう。今、洋学者たちはほとんどが官僚であり、民間で活動している人はほんの少ししかいません。ただ、官僚になることだけが目的ではなく、昔からの教育で政府に目を向け、政府に関わらなければ何もできないと考えています。有名な先生でさえ、この範囲から抜け出せません。彼らの行いは見下されるかもしれませんが、悪意はなく、ただ世間の風習に流されて自分が何をしているのか分からないだけです。有名な人たちがこうなら、普通の人たちはその風習に従わざるを得ません。
若い学生は少し本を読むとすぐに官僚になりたがりますし、お金持ちの町人は少しの元手で商売を始めようとします。学校も政府の許可が必要で、説教も政府の許可が必要です。牛を飼ったり、蚕を育てたりすることも政府の許可が必要です。民間の仕事のほとんどが政府に関係しています。このせいで、人々はますます政府に頼り、政府を慕い、政府を恐れ、政府におべっかを使い、自立した心を持つ人がいなくなってしまいます。例えば、新聞や建白書もその一例です。新聞の内容は政府のタブーに触れないようにしており、政府の良い点があれば大げさに褒めるばかりで、まるで売春婦が客にへつらうようです。また、建白書を見ると、文章は卑屈で、政府を過剰に尊敬し、自分を罪人のように見下します。平気で恥ずかしい文章を使い、恥じることがありません。この文章を読むと、狂人だけがそんなことを言うだろうと思います。しかし、新聞を出版したり、政府に建白書を送ったりする人たちは、洋学者であり、実際には売春婦でも狂人でもありません。
それにしても、その不誠実さは、こんなにひどい状況になってしまった理由は、まだ世間に民権を大切にする実例がなくて、ただその卑屈な気風に支配されて、その気風に同じようになって、国民の本当の姿を見せられないんです。これを一言で言えば、日本にはただ政府があって、まだ国民がいないと言ってもいいんです。だから、人々の気風を変えて世の中の文明を進めるには、今の洋学者たちにも頼ることはできないんです。
前に書いた意見が正しいとしたら、私たちの国の文明を進めて独立を守るのは、ただ政府がうまくやることだけではありません。また、今の洋学者たちも頼りにするには足りません。必ず私たち自身がやらなければならないことで、まず私たちから始めて、愚かな人々の先頭に立つだけでなく、洋学者たちのためにも先導して、どこへ行くべきかを示さなければなりません。今私たちの立場を考えると、学問も確かに浅くて劣っていると言われますが、洋学を志すことはもう長い間で、この国では中くらいの地位にある人です。最近の世の中の改革も、もし私たちが主導して始めたことでなければ、暗にこれを助けたりしたものです。たとえ助ける力がなくても、その改革が私たちの喜ぶところだから、世の人々もまた私たちを見るときに、改革家たちの名前を持っていることが必要です。もう改革家の名前があり、その身分も中くらい以上の地位にあり、世の人々が私たちの行いを目標にする人がいるでしょう。だから、まさに今、人々に先んじて事を成すのは、これを私たちの使命と言うべきです。
そもそも事を成すには、これを命じることは、これを教えることと同じではありません。これを教えることは、私たちが実際の例を示すことと同じではありません。そういうわけで、政府はただ命じる権利があるだけで、これを教えて実際の例を示すのは私たちの仕事です。だから、私たちはまず個人として立場を占めて、学問を教えたり、商売に従事したり、法律を議論したり、本を書いたり、新聞を出版したりするなど、国民としての範囲を超えないことは遠慮せずに行い、しっかり法を守って正しいことを行い、政府の命令が信じられないときには、自分の立場を曲げずにそれを議論し、まるで政府の頭に針を刺すように、古い悪習を取り除いて民権を回復することが、今急いでやらなければならない仕事です。
もちろん、個人の仕事はたくさんありますし、それを行う人々にもそれぞれ長所がありますから、少数の学者だけで全部のことを成し遂げるわけではありません。しかし、私たちが目指すところは、事を行うのが上手なことを示すのではなく、ただ世の中の人々に個人の方向を知らせるだけです。一〇〇回の説明よりも、一回の実際の例を示す方が効果的です。今私たちが個人として実際の例を示し、「人間の仕事は政府だけの責任ではありません。学者は学者で、個人として事を行うべきです。町の人々は町の人々で、個人として事を行うべきです。政府も日本の政府ですし、人々も日本の人々です。政府は恐れずに近づくべきで、疑わずに親しくするべきです」という意味を知らせることができれば、人々はやっとどこへ向かうべきかを明らかにし、上下の固定した気風も次第に消えていって、初めて本当の日本の国民が生まれ、政府のおもちゃではなく政府の刺激になり、学問以下の三つのものも自然にそれぞれの持ち主に戻り、国民の力と政府の力が互いに平等になって、全国の独立を守るべきです。
これまで述べたことを要約すると、今の世の学者たちは、この国の独立を助けようとするとき、政府の範囲に入って官僚になって事を行うか、その範囲を離れて個人で行動するかの利益と損失を述べ、本論は個人の立場を支持するものです。すべての世の中のものを詳しく調べると、利益がないものは必ず損失があり、得がないものは必ず失があり、利益と損失、得と失が半々になるものはありません。私たちももちろん自分のためにすることがあって個人を主張するわけではありませんが、ただ普段の考えを証明してこれを論じているだけです。もし世の人々が確かな証拠を持ってこの意見を否定し、明らかに個人の不利益を述べる人がいれば、私たちは喜んでそれに従い、世の中に害を及ぼすことはありません。
付録
本論についての質問が二、三つあるので、これを最後に書きます。
一つ目の質問は、「物事を進めるのは、力のある政府がやるべきだと思わないですか」と言います。答えは、「文明を進めるのは、政府の力だけに頼るべきではありません。その理由は本文で説明しています。また、政府が物事を進めても、すでに数年間試してみたけれど、まだ成功していないことがあります。私たちのやり方も、成功するかどうか分からないかもしれませんが、議論で見込みがあると思ったら、試さないわけにはいきません。まだ試してもいないのに、最初からうまくいかないと疑う人は、勇気があるとは言えません」
二つ目の質問は、「政府が人手が足りなくて、有能な人が政府を離れたら、公務が滞ってしまうのではないですか」と言います。答えは、「そんなことはありません。今の政府は、官僚が多すぎるという問題があります。仕事をシンプルにして、官僚を減らせば、仕事はうまく整理され、人々は社会の役に立つことができます。一度に両方の問題が解決します。わざわざ政府の仕事を複雑にして、有能な人を使って無駄なことをさせるのは、策略が下手だと言えます。また、この有能な人が政府を離れても、外国に行くわけではなく、日本にいて日本のために働くだけです。何も心配することはありません」
三つ目の質問は、「政府以外の場所で、個人が集まったら、自然に政府のようになって、本来の政府の権力が弱まるのではないですか」と言います。答えは、「その考え方は、小さい考え方です。個人でやる人も、政府で働く人も、みんな日本人です。ただ、違う立場で物事を進めているだけです。実際には、お互いに助け合って、一緒に全国の便益を考える仲間です。敵ではなく、本当の友達です。そして、個人でやる人が法律を破ったら、罰することができます。全く恐れる必要はありません」
四つ目の質問は、「個人でやりたいと思う人がいても、政府の仕事を辞めたら、他に生活の道がないのではないですか」と言います。答えは、「その意見は、立派な人が言うべきではありません。すでに自分で学者だと言って、世の中のことを考える人は、決して無能な人ではありません。才能があれば、生活費を稼ぐのは難しくありません。また、政府で働いて公務を行うことも、個人で仕事をすることも、どちらも大変さは変わりません。もし政府の仕事が簡単で、利益が個人の仕事よりも多いなら、その利益は努力の結果に見合っていないと言えます。本当に価値がある利益を求めるのは、立派な人がすることではありません。無能で、運良く政府の仕事について、むやみに給料をもらって贅沢に暮らし、遊びながら世の中のことを話す人は、私たちの友達ではありません」
五編
『学問のすすめ』は、もともとみんなが読むための本や小学校で使う教える本だったので、最初から三つ目までの部分では、わかりやすい言葉を使って文章を書くことを目指していました。でも、四つ目の部分では、ちょっと文章の形を変えて、難しい文字を使うところもあります。五つ目の部分も、明治七年一月一日にみんなで話し合った言葉を文章にしたものなので、その文章の形は四つ目と同じで、ちょっと理解しづらいかもしれません。結局、四つ目と五つ目の二つの部分は、学者さんたちに向けて話をするものだから、こんな風になっています。
世の中の学者さんたちは、だいたい元気がなくて、力が足りないけど、文字を見る目はすごく鋭いです。どんな難しい文章でも困らない人がいないから、この二つの部分では、遠慮なく難しい文章を書いて、意味も高いものになっています。それで、もともとみんなが読むための『学問のすすめ』の目的を失ってしまって、初心者の人たちにはとても気の毒です。でも、六つ目以降の部分では、また元の形に戻って、わかりやすさを大事にして、初心者のために便利なものにしようと思っています。だから、この二つの部分だけで全部の難しさを評価しないでください。
明治七年一月一日の言葉
私たちは今日、慶応義塾にいて、明治七年一月一日を迎えました。この年号は、私たちの国が独立した年号です。この塾は、私たちの仲間が独立した塾です。独立した塾にいて、独立した新年を迎えることができるのは、本当にうれしいことです。でも、これを手に入れて喜ぶべきものは、これを失ったら悲しむことになるでしょう。だから、今日喜んでいる時に、他の日に悲しむ時があることを忘れないでください。
昔から、私たちの国の政治が良くも悪くも変わってきましたが、今日まで国の独立を失わなかった理由は、国民が鎖国の習慣に安心して、政治の良し悪しや外国と関わることがなかったからです。外国と関係がなければ、良い政治も悪い政治も、みんな国内だけの問題です。また、これまで独立を失わなかったのも、ただ国内だけの独立で、まだ他の国と争うことはありませんでした。これは、子どもが家の中で育って、まだ外の人に会ったことがない人のようなものです。その弱さは、もちろんわかっているはずです。
でも、今は外国との交流が急に始まり、国内の仕事も全部これに関わるものがありません。色々なことや物が、外国と比べて処理しなければならない状況になっています。昔から私たちの国の人たちが少しずつ達成できた文明の様子を、西洋の国々の様子と比べると、ただ三つ分譲るだけではなく、これに続いて、海を見てため息をつくことも免れません。ますます私たちの独立の弱さを感じることになります。
国の文明は、形だけで評価してはいけません。学校と言っても、工業と言っても、陸軍と言っても、海軍と言っても、みんなこれが文明の形だけです。この形を作るのは難しくありません。お金さえあれば買えると言っても、ここにまた見えない一つのものがあります。このものは、目で見ることも、耳で聞くこともできず、売ったり買ったりできず、借りたり貸したりできません。でも、国民みんなの間にあって、その働きはとても強いです。このものがなければ、学校以下の色々なことも本当の役に立ちません。これこそが、文明の精神と言うべき大切で重要なものです。でも、そのものは何でしょうか。それは、人民の独立の気力、つまりこれです。
最近、私たちの政府は、学校を建てたり工業をすすめたりして、海軍や陸軍の制度も大きく変わって、文明の形はだいたい整っています。でも、人民はまだ外国に対して、私たちの独立をしっかり守って先を争おうとする人がいません。ただ、これと争わないだけでなく、たまたまその事情を知ることができる機会を得た人でも、まだこれを詳しく調べずに、最初にこれを怖がるだけです。他の国に対してすでに恐れている心がある時は、たとえ私たちに少し得るところがあっても、これを外に出すことができません。結局、人民に独立の気力がなければ、あの文明の形も、とうとう役に立たないものになるでしょう。
まず、日本の人々が元気がない理由を考えると、昔から政府が国の権力をすべて持っていて、武器や勉強だけでなく、工業や商売まで、全部政府が関わっていました。人々は政府の言うことを聞いて動くだけでした。まるで国が政府のもので、人々は国のお客さんみたいなもんです。もうみんな、この国でちょっと食べ物をもらって生きているだけで、国を大事に思わず、自分たちの力を出すチャンスもなく、結局、みんなの元気がなくなりました。
それどころか、今の時代はもっとひどいことがあります。世の中のものは、進まないと後退しますし、後退しないと進みます。進まず後退せずで止まっているものは、ありえません。今、日本を見ると、文明の形は進んでいるようですが、文明の心である人々の元気は、日々後退しています。考えてみてください。昔の足利や徳川の政府は、人々を支配するために力だけを使っていました。人々は政府に従うのは、力が足りないからです。力が足りない人は心から従うわけではなく、ただ恐れて従う形を作るだけです。今の政府は力だけでなく、賢さもすごく速くて、何事も遅れることがありません。新しい時代が始まってまだ一〇年もたっていないのに、学校や兵器が改革され、鉄道や電信ができ、石の建物が作られ、鉄橋がかけられるなど、決断が早くて成功が美しいことに、本当に驚きます。しかし、これらの学校や兵器、鉄道や電信、石の建物や鉄橋は、全部政府のものです。人々はどう思うべきでしょうか。みんなが言います、「政府は力だけでなく、賢さもあって、私たちには敵わない。政府は空の上で国を支配していて、私たちは下で頼るだけ。国の問題は上の人の仕事で、下の人が関係ない」と。要するに、昔の政府は力を使っていて、今の政府は力と賢さを使っています。昔の政府は人々を支配する方法が少なくて、今の政府はそれが豊富です。昔の政府は人々の力を抑えていて、今の政府はその心を奪っています。昔の政府は人々の外側を攻撃していて、今の政府は内側を支配しています。昔の人々は政府を鬼のように見ていて、今の人々は神のように見ています。昔の人々は政府を恐れていて、今の人々は政府をあがめています。このまま何も変わらなければ、政府が何かを始めるたびに文明の形は徐々にできていくように見えますが、人々はますます元気を失って、文明の心は徐々に衰えていくだけです。
今、政府には常に兵隊がいて、人々はそれを国を守る兵士だと認めて、その活躍を祝って元気になるべきなのに、逆にそれを人々をおどす道具だと思って恐れるだけです。今、政府には学校や鉄道があり、人々はそれを国の文明の証として誇るべきなのに、逆にそれを政府の恩恵だと思って、ますます頼る気持ちが強くなるだけです。人々はもう自分たちの国の政府に対して怯えていて、どうやって外国と競って文明を争う余裕があるでしょうか。だから言います、人々に独立した元気がなければ、文明の形を作ることはただの無駄なものだけでなく、逆に人々の心をさらに萎縮させる道具になるでしょう。
これらのことから考えると、国の文明は上の政府から始まるわけではなく、下の小さい人々から生まれるわけでもありません。必ずその中間から興って、みんなが向かう方向を示し、政府と並んで立って初めて成功するはずです。西洋の国々の歴史を見ると、商売や工業の道は政府が作ったものではなく、全部中くらいの地位にいる学者のアイデアから生まれたものです。蒸気機関はワットさんが発明したもので、鉄道はスティーブンソンさんが工夫したもので、経済のルールを考えて商売の方法を変えたのはアダム・スミスさんのおかげです。これらの偉い人たちはいわゆる中くらいの立場にいて、国の政治には関わっていないし、力仕事をする小さい人々でもありません。彼らは国の中くらいの位置にいて、知恵を使って世界を導いていました。彼らのアイデアや発明は、最初は一人の心で生まれて、それをみんなに知らせて実際にやってみるために、個人が友達を集めて、どんどんそのことを大きくして、人々に幸せをたくさん残すんです。この間に当たる政府の仕事は、ただそのことを邪魔しないで適切に進めさせて、人々の気持ちを察して守るだけです。
ゆえに文明のことを進める人たちは、私たち一般の人々で、その文明を守る人たちは政府です。だから、国の人々はみんな、文明を自分たちのものだと思って、争いやうらやみ、誇りを持ちます。国で素晴らしいことがあれば、全国の人々が手を叩いて喜びます。ただ、他の国に負けないように頑張りたいだけです。だから、文明のものはみんな、人々の力を増す道具になります。どんなことでも、国の独立を助けるものはありません。この事情は、今の日本とは反対だと言えます。
今、日本ではミッヅル・カラッスの地位にいて、文明を進めて国の独立を守るべき人たちは、ただ一種の学者だけです。しかし、この学者たちは時代の変化に目を向けず、国の問題に真剣に取り組まないかもしれません。また、政府に頼って物事を進めるべきだと考えるかもしれません。大体、彼らは自分の地位に満足せず、官僚になって、些細な仕事に追われて、無駄に体と心を疲れさせます。彼らの行動は笑うべきものが多いですが、自分たちもそれを許し、他の人たちもそれを怪しまないでいます。特に、「野に遺賢なし」と言って喜ぶ人たちがいます。もちろん、これは時代のせいで、一人一人のせいではありませんが、国の文明のためには大きな災難だと言えます。文明を育てるべき学者たちが、その精神が衰えていくのを見て、それを悩む人がいないのは、本当に悲しいことです。
ただ、私たちの慶応義塾は、この災難から少し逃れて、数年間、独立の名を失わず、独立した塾で独立した気持ちを育てています。そして、目指すところは、全国の独立を守ることだけです。でも、時代の流れは、急な川や強い風のように強力です。この勢いに立ち向かってしっかり立つのは、もちろん簡単ではありません。非常な勇気と力がなければ、知らず知らずのうちに流されたり、倒れたりする恐れがあります。そもそも、人の勇気と力は、ただ読書だけで得られるものではありません。読書は学問の方法で、学問は物事を進める方法です。実際に物事に触れて慣れることがなければ、決して勇気と力を生み出すことはできません。私たちの仲間で、その方法を身につけた人たちは、貧しさや苦しみを耐えて、得た知識を文明の現実に使わなければなりません。その仕事はたくさんあります。商売や法律、工業や農業、本の執筆・翻訳・新聞の出版など、文明の出来事はすべて、自分たちのものにして、国民の先頭に立って政府と協力し、官僚の力と私たちの力を平等にして、国全体の力を増やし、弱い独立を動かさない基礎に置くことです。外国と争っても、少しも譲らないで、今から数十年後に、今日の状況を振り返って、今日の独立を喜ばずに、かえってこれを哀れんで笑う勢いになることは、一大快事ではないでしょうか。学者たちは、その方向をしっかり決めて、目指すところがあるべきです。
六編
国の法の大切さを語る
政府は、国民が選んだ代表で、国民の意見に従って仕事をするものです。その役割は、悪い人を捕まえて、いい人を守ること以外ありません。つまり、これが国民の考えで、この目的を達成すれば、国の中で便利になるはずです。もともと、悪い人とは悪者で、いい人とは善人です。もし悪者が来て、善人を困らせようとすることがあったら、善人自身がこれを防ぎ、自分の父母や家族を殺そうとする人がいたら捕まえて、その人を殺し、自分の財産を盗もうとする人がいたら捕まえて、その人をむちで打つことは、問題ない理由ですが、一人の力でたくさんの悪者に対抗して、これを防ごうとするのは、とても無理なことです。
たとえば、それを手伝うのにかかるお金がたくさんかかっても効果がないから、上のように国民が代表として政府を立てて、善人を守る役割を頼み、その代わりに役人の給料や政府のいろいろな出費を全部国民から支払うことを約束したのです。そして、政府はすでに国民の代表として仕事をする権利をもらったので、政府がすることは実際に国民がすることで、国民は必ず政府の法に従わなければなりません。これも国民と政府との約束です。だから、国民が政府に従うのは、政府が作った法に従うのではなく、自分たちが作った法に従うのです。国民が法を破るのは、政府が作った法を破るのではなく、自分たちが作った法を破るのです。その法を破って罰を受けるのは、政府に罰されるのではなく、自分たちが決めた法によって罰されるのです。この考え方を言葉で表すと、国民という人は、一人で二つの役割を果たすようなものです。つまり、その一つ目の役割は、自分たちの代表として政府を立てて、国中の悪者を捕まえて善人を守ることです。その二つ目の役割は、しっかり政府の約束を守ってその法に従い、守られることです。
上のように、国民は政府と約束して、政府に権力を任せたので、決してこの約束を破って法に反することはできません。人を殺す人を捕まえて死刑にするのも政府の権利ですし、泥棒を捕まえて牢屋に入れるのも政府の権利ですし、裁判を進めるのも政府の権利ですし、乱暴やけんかを止めるのも政府の権利です。これらのことに関して、国民はちょっとも手を出してはいけません。もし勘違いして自分で罪人を殺したり、泥棒を捕まえてむちで打ったりすることがあれば、それは国の法を破っているので、自分で他人の罪を決める人になってしまい、それを私裁(しわい)と言って、その罪は許されません。この部分では、文明国の法律はとても厳しいです。いわゆる、威厳があって怖いものです。私たちの日本では、政府の権力が強いように見えますが、人々はただ政府の偉さを恐れて、その法の大切さを知らない人もいます。今ここで、私裁が良くない理由と国の法の大切な理由を説明することは、上のようなことです。
例えば、自分の家に強盗が入ってきて、家の中の人たちをおどかしてお金を奪おうとすることがあるでしょう。この時、家の主人がすべきことは、この事情を政府に訴えて、政府の対応を待つべきですが、事が急いで訴える時間もなく、その間に強盗はもう倉庫に入ってお金を持ち出そうとしています。これを止めようとすれば、主人の命も危険な状況ですから、仕方なく家の中で相談して自分でこれを防ぎ、その場の対処で強盗を捕まえておいて、後で政府に訴えるのです。この強盗を捕まえる時には、棒を使ったり、刃物を使ったり、強盗の体に傷をつけることもあるでしょうし、足を折ることもあるでしょうし、急いでいる時には鉄砲で撃ち殺すこともあるでしょう。しかし、結局、家の主人は、自分の命を守り、自分の財産を守るために一時的な対処をしただけで、決して強盗の悪さを責めて、その罪を罰する目的ではありません。
罪人を罰するのは政府がすることで、私の仕事ではありません。だから、私が力を使って強盗を捕まえた後、普通の人として彼を殺したり、打ち負かすべきではなく、指一本を賊に触れることも許されません。ただ政府に報告して、政府の判断を待つだけです。もし、賊を捕まえたあとで怒って彼を殺したり、打ち負かすことがあれば、それは無罪の人を殺したり、無罪の人を打ち負かすことと同じです。例えば、ある国の法律に、「金十円を盗む人は、その罰としてむちで一〇〇回たたかれる。また、足で人の顔を蹴る人もその罰としてむちで一〇〇回たたかれる」と書いてあります。そこで、盗賊が人の家に入って金十円を盗もうとして、家の主人に捕まって縛られた後、その主人が怒って足で賊の顔を蹴ることがあったら、その国の法律で考えると、賊は金十円を盗んだ罪でむちで一〇〇回たたかれ、主人も普通の人として賊の罪を判断して足で顔を蹴った罪でむちで一〇〇回たたかれるべきです。国の法律はこんなに厳しいので、みんなが恐れなければなりません。
この考え方で、敵討ちが良くないことも納得できます。私の親を殺した人は、その国で一人の人を殺した公の罪人です。この罪人を捕まえて罰するのは政府の仕事で、普通の人が関わることではありません。だから、殺された人の子供であっても、政府の代わりに私がこの公の罪人を殺す理由はありません。それは失礼な行動だけでなく、国民の仕事を間違えて、政府の約束に背いていると言えます。もし、政府の処置が悪くて罪人をひいきするようなことがあれば、その不正なことを政府に訴えるべきです。どんなに大変なことがあっても、自分で手を出してはいけません。たとえ親の敵が目の前に歩いていても、私に彼を殺す理由はありません。
昔、徳川の時代に、浅野家の家来が、主人の敵討ちとして吉良上野介を殺したことがあります。世の中では、これを赤穂の義士と言います。大きな間違いではないでしょうか。その時、日本の政府は徳川でした。浅野内匠頭も吉良上野介も浅野家の家来もみんな日本の国民で、政府の法律に従って守られるべきだと約束していました。しかし、ある朝、上野介が内匠頭に失礼なことをしたので、内匠頭は政府に訴えることを知らず、怒って私が上野介を切ろうとして、ついに両方が喧嘩になりました。徳川政府の裁判で、内匠頭に切腹を命じ、上野介には罰を与えず、この一つは本当に不正な裁判だと言えます。浅野家の家来たちがこの裁判を不正だと思ったら、どうして政府に訴えないのでしょうか。四七人の家来が一緒になって、それぞれの理由で法律に従って政府に訴え出たら、最初はその訴えを受け入れず、その人を捕まえて殺すこともあるでしょう。しかし、一人が殺されても恐れず、代わりに訴え出て、また殺されて、また訴え出て、四七人の家来が理由を訴えて命を失い尽くすと、どんな悪い政府でも最後にはその理由に従って、上野介にも罰を与えて裁判を正しくすることがあるでしょう。
そうして初めて本当の義士と呼べるはずですが、この理由を知らず、国民の立場にいながら国の法律の重さを考えずに勝手に上野介を殺したのは、国民の仕事を間違え、政府の権力を侵して、私が人の罪を判断したと言えます。幸いにも、その時、徳川の政府がこの乱暴な人を罰したので無事に治まりましたが、もし彼らを許していたら、吉良家の一族も敵討ちとして赤穂の家来を殺すことが必ずあったでしょう。そうなると、この家来の一族も敵討ちとして吉良の一族を攻めるでしょう。敵討ちと敵討ちで、終わりがなく、ついに両方の一族や友達が死に尽くすまで止まらないでしょう。これが無政府無法の世の中だと言えます。私が裁く国がこんなに害することです。気をつけなければなりません。
昔、日本では、農民や町人が、士分の人に失礼なことをしたら切り捨て御免という法律がありました。これは政府が公に私が裁くことを許したものです。これは間違っていることではないでしょうか。すべての国の法律はただ一つの政府で実行されるべきで、その法律が多く出てくるほど、その権力も弱くなります。例えば、封建時代に三〇〇人の諸侯がそれぞれ命を奪う権力があった時、政府の力もその比率で弱くなっていました。
私たちが一番悪いことをして、国の政治に大きな害を与えることは、人をこっそり殺すことです。昔から、人をこっそり殺すことがあって、それは自分が嫌いな人を殺すためだったり、お金を取ろうとするためだったりします。このようなことを考える人は、もともと悪いことをする覚悟がありますし、自分も悪い人だと思っています。でも、他にも違う種類のこっそり殺すことがあります。それは、自分のためではなくて、政治の敵を悪いと思って殺すことです。国のことについてみんなが違う意見を持っていて、自分の意見で他の人の悪さを決めて、政府の力を無視して勝手に人を殺します。それを恥ずかしく思わないどころか、自分が天罰を下すと言って誇らしげにしていることがあります。そして、人々はその人を国のために働く人と呼ぶことがあります。でも、本当に天罰とは何なのでしょうか。天の代わりに罰を下すというつもりなのでしょうか。もしそうだとしたら、まず自分の立場を考えるべきです。この国にいて、政府とどんな約束をしたのでしょうか。「国の法律を守って、自分の身を守る」と約束したはずです。もし国の政治について不満があって、国に害を与える人がいると思ったら、静かにそれを政府に訴えるべきです。政府を無視して、自分が天の代わりになって行動するのは、やり方が間違っていると言われるべきです。結局、こういう人たちは、正直で真面目だけど物事の理由が分からず、国が困っていることは知っていても、その原因を知らない人たちです。例えば、世の中には、こっそり殺すことで良いことが成し遂げられたり、幸せが増えたりしたことはありません。
国の法律の大切さを知らない人は、ただ政府の役人を怖がって、役人の前ではちゃんと振舞って、表向きは犯罪者ではないようにして、本当は悪いことをしても恥ずかしく思いません。それどころか、うまく法律を破って罪から逃れる人がいたら、その人の働きとして良い評判を得ることがあります。今、世間ではよく言われている話に、「これも上手な方法だ」「あれも政府の表向きのやり方だけど、このことをやる時に私に手伝ってもらえば、表向きの法律には問題がなくて、内側で手を打つ」と笑いながら話し、責める人もいません。それどころか、小さな役人と相談して、内側で手を打って、お互いに便利を得て、罪のない人のように振舞います。実際には、あの上手な方法というものは、あまりにも面倒くさいので、現実には使われないようになって、内側で手を打つことが行われるのです。でも、一国の政治を考えると、これはとても怖い悪い習慣です。こんな風に国の法律を軽んじて、人々はみんな不誠実になって、守るべき法律を守らずに、結局は罪を被ることがあります。
例えば、今道路でおしっこをするのは政府が禁じています。でも、人々はその禁止されていることの大切さを知らずに、ただ警察を怖がっているだけです。夕方など警察がいないときに法律を破ろうとして、思わず見つかってしまった場合、その罪に謝ると言っても、本当に大切な国の法律を破ったから罰せられるとは思わずに、ただ怖い警察に会ったのがその日の不運だと思っています。本当に悲しいことではありませんか。だから、政府が法律を作るときは、できるだけ簡単なものが良いとされています。それを法律にすると決めたら、必ずその意味をちゃんと伝えなければなりません。人々が政府が作った法律を見て、不便だと思ったら、遠慮なくそれを議論して訴えるべきです。すでにその法律を認めて、その法律の下にいるときは、自分でその法律を良し悪しを決めずに、ちゃんと守らなければなりません。
近くは先月、わが慶応義塾にも一つの出来事がありました。華族の太田資美さんは、一昨年から自分のお金を使ってアメリカ人を雇い、義塾の先生にしていましたが、今回先生を交代する時期になり、別のアメリカ人を雇おうとして、その人との話がすでにまとまったところで、太田さんから東京府に手紙を出して、このアメリカ人を義塾に入れて文学・科学の先生にしたいとお願いしました。しかし、文部省のルールでは、「自分のお金で私立学校の先生を雇って、自分で人を教える場合でも、その先生になる人は、本国で学問を終えた証明書を持っていなければ雇うことが許されない」という項目があります。それで、今回雇おうとしているアメリカ人は、その証明書を持っていないため、ただ語学の先生だったら問題ないのですが、文学・科学の先生としてはお願いを聞いてもらうのが難しいということで、東京府から太田さんに連絡がありました。
そこで、福沢諭吉が東京府に手紙を出して、「この先生は証明書を持っていなくても、その学力は当塾の生徒を教えるのに十分だから、太田さんのお願い通りにしてほしい。もしくは、語学の先生と言えばお願いも叶うはずだけど、もともと生徒たちは文学・科学を学ぶつもりだから、語学と偽って役所をだますことはあえてしない」とお願いしました。しかし、文部省のルールは変えられないため、諭吉のお願いもまた返されました。このせいで、すでに話がまとまった先生を雇うことができず、去年の一二月の終わりに、その人は帰国してしまい、太田さんの思いも一時的に無駄になり、何百人もの生徒たちも期待を失いました。本当に悲しいことですが、国の法律は大切だから、どうしようもありません。近いうちにもう一度お願いするつもりです。今回の問題については、太田さんをはじめみんなで集まって話し合い、「文部省の私立学校の先生に関するルールは大事な法律だから、ただ文学・科学という言葉を消して語学と書けば、お願いも叶い、生徒たちにとっても幸せになる」と何度も話し合いました。しかし、結局のところ、今回の先生がいなくても、生徒たちの勉強が少し後退するかもしれないけど、役所をだますことは恥ずかしいことだから、きちんと法律を守り、国民としての立場を間違えない方が、最善の策だと考え、この結果に至りました。もともと一つの私立学校の問題で、このことは小さなことに見えますが、議論の意味は世の中の教育にも関係するべきことだと思い、ついでにこれを書いておきます。
七編
国民の仕事について
第六編では、国の法を大切にすることを話し、「国民は一人で二つの役割を果たすものだ」と言いました。今度はその役割や仕事について、もっと詳しく説明して、六編の補足にします。
国民は一人の身で二つの勤めがあります。一つ目の勤めは、政府の下で働く一人の人々で、これを客と考えます。二つ目の勤めは、国の中の人々が一緒になって、一つの国という会社を作り、その会社の法を決めて実行することで、これを主人と考えます。例えば、百人の町の人が商社を作り、みんなで相談して社の法を決め、それを実行する場合、百人の人はその商社の主人です。すでにその法を決めて、社の中の人がみんな従っているところを見れば、百人の人は商社の客です。だから、一つの国は商社のようで、人々は社の中の人のようで、一人で主人と客の二つの仕事を果たすべきです。
まず、客としての仕事を考えると、一国の人々は国の法を大切にし、人間みんなが同じだという考えを忘れてはいけません。他人が来て自分の権利を害することを望まないなら、自分も他人の権利を邪魔してはいけません。自分が楽しむものは他人も楽しむから、他人の楽しみを奪って自分の楽しみを増やしてはいけません。他人のものを盗んで自分の富にしてはいけません。人を殺してはいけません。人を悪く言ってはいけません。国の法を守って、みんなが同じだという大きな理由に従うべきです。また、国の政治によって決まった法は、たとえそれが愚かだったり、不便だったりしても、簡単には破ってはいけません。戦争を起こしたり、外国と条約を結んだりすることは政府の権利であり、その権利は元々約束で人々から政府に与えられたものです。だから、政府の政治に関係ない人は、決してそのことを議論してはいけません。
人々がこの考えを忘れて、政府のやり方に自分の意見が合わないと言って勝手に議論を起こしたり、条約を破ろうとしたり、戦争を起こそうとしたりすると、国の政治は一日も持たなくなります。これは、百人の商社がみんなで相談して、社の中から十人を選んで会社の支配人にし、その支配人のやり方について、残りの九十人が自分の意見が合わないと言ってそれぞれ商法を議論し、支配人がお酒を売ろうとすると、九十人がぼたもちを仕入れようとし、その議論がいろいろあって、最悪の場合、一人が勝手にぼたもちの取引を始めて、商社の法に反して他人と争いになるようなことがあったら、会社の商売は一日も続かなくなります。結局、その商社がバラバラになったら、その損失は商社の百人がみんなで受け止めなければなりません。愚かだと言わざるを得ません。だから、国の法が不正や不便だと言っても、それを口実にして破る理由はありません。もし本当に不正や不便な部分があれば、一国の支配人である政府に説明して、静かにその法を変えてもらうべきです。政府が自分の説明に従わないなら、力を尽くしながら我慢して時期を待つべきです。
次に、主人としての仕事を考えると、一国の人々はつまり政府です。その理由は、一国の中の人々がみんなで政治をするわけではなく、政府というものを作って国の政治を任せ、人々の代わりに仕事をする約束を決めたからです。だから、人々は家の主であり、主人です。政府は代わりの人であり、支配人です。例えば、商社の百人の中から選ばれた十人の支配人は政府で、残りの九十人の社の中の人は人々のようです。この九十人の社の中の人は、自分で仕事をするわけではありませんが、自分の代わりに十人の人に仕事を任せたので、自分の立場を考えると、商社の主人と言わざるを得ません。また、その十人の支配人は現在の仕事をしていると言っても、元々社の中の人たちから頼まれて、その意見に従って仕事をする約束をした人たちなので、実際には私ではなく、商社の公の仕事をする人です。今、世間では政府に関わることを公務や公用と言いますが、その言葉の由来を考えると、政府の仕事は役人の個人的なことではなく、国民の代わりに一つの国を支配する公の仕事だという意味です。
右の次第をもって、政府は人々からのお願いを受けて、約束に従って国の人たちをみんな平等に大切にしなければならず、法律を正しく守り、罰を厳しくすることが大事で、自分勝手なことはしてはいけません。今、悪い人たちが集まって人の家に入って困らせる時、政府がそれを見て止めることができなければ、政府もその悪い人たちと同じだと言われてしまいます。政府が国の法律を守ることができず、人々に迷惑をかけることがあったら、どんなに大きいことでも小さいことでも、必ずそれを償わなければなりません。例えば、役人がちゃんと仕事をしなくて、国の人や外国の人に迷惑をかけて、三万円のお金を払わなければならないことがあるでしょう。政府には最初からお金があるわけではないので、そのお金は結局、人々から出てくることになります。この三万円を日本中の三千万人の人々に分けると、一人あたり一〇文ずつになります。役人がちゃんと仕事をしないことが一〇回もあれば、人々は一人あたり一〇〇文のお金を出さなければならず、家族が五人いる家だと五〇〇文になります。田舎の小さな農家に五〇〇文のお金があれば、家族みんなで集まって、普段は食べられないごちそうを作って楽しい夜を過ごせるはずなのに、ただ役人がちゃんと仕事をしないせいで、日本中のかわいそうな人々がその楽しい時間を失ってしまうのは本当に悲しいことです。人々としてはこんな馬鹿げたお金を出すべきではないと思うかもしれませんが、どうしようもなく、人々は国の大切な家元であり、最初から政府にこの国を任せて仕事をやってもらう約束をして、得るものも失うものも家元として受け入れるべきものなので、ただお金を失った時だけでなく、役人がちゃんと仕事をしないことについても文句を言ってはいけません。だから、人々はいつも気を付けて、政府のやり方が心配だと思うことがあったら、しっかりと伝えて、遠慮なく穏やかに話し合うべきです。
人々はすでに国の大切な家元であり、国を守るためのお金を出すのは当然の仕事なので、そのお金を出す時に不満そうな顔をしてはいけません。国を守るためには役人に給料を払わなければならず、海や陸の軍隊にもお金が必要で、裁判所や地方の役所にもお金が必要です。そのお金を全部集めてみると大きな金額に見えますが、一人あたりに分けるとどれくらいになるでしょうか。日本では年間の税金を全国の人々に分けると、一人あたり一円か二円になるでしょう。一年間にたった一、二円のお金を払って政府の保護を受けて、泥棒や強盗の心配もなく、一人で旅行しても山賊の恐れもなく、安心して暮らせるのはとても便利なことです。どんなにいい商売があっても、税金を払って政府の保護を受けるほど安いものはありません。世の中でお金を使う人たちの中には、家を建てるためや、きれいな服や美味しい食べ物にお金を使ったり、酒や女性のためにお金を無駄にして身を滅ぼす人もいますが、これらの出費を税金と比べると全然違う話で、無駄なお金だからこそ一文でも惜しむべきですが、道理に従って出すべきお金であり、それを出して安いものを買うお金だから、考えることもなく喜んで税金を払うべきです。
右のように人々も政府もそれぞれの立場で頑張ってお互いに助け合う時は問題もないのですが、時には政府がその立場を越えて横暴なことをすることがあります。ここで、人々がすべきことは三つだけです。つまり、我慢して政府に従うか、力を使って政府に反抗するか、正しい道を守って身を捨てるか、この三つです。
第一 自分の考えを曲げて政府に従うのは、とても良くないです。人間は、天が示す正しい道に従って生きることが仕事だと思います。でも、自分の考えを曲げて政府が作った悪い法律に従うのは、人間の仕事を壊すことだと言えます。そして、一度考えを曲げて不正な法律に従うと、後の世の子どもたちに悪い手本を残して、世の中全体の悪い風習を作り出すことになります。昔から日本でも、無知な人々の上に横暴な政府があって、政府が見せかけの力を強く使うと、人々はそれに怖がって従います。そして、政府のやり方が実際に無理だと思っても、その理由をはっきり言わないで、ただ怒られるのを恐れて、言うべきことも言わなくなります。その怖さは、俗に言う犬のフンに足を踏むようなもので、人々はただそれを避けて、どんな無理でも政府の命令に従うべきだと考えて、世の中全体の考え方ができあがり、ついに今日の情けない状況になってしまいます。これは、人々が自分の考えを曲げて、後の世に災いを残した一つの例だと言えます。
第二 力を使って政府に反対するのは、もちろん一人でできることではありません。必ず仲間を作らなければなりません。これは内乱と呼ばれる戦いです。けれども、これを最善の方法とは言えません。もう戦いを始めて政府に敵対する時には、その理由の正しさや間違いはあまり問題にせず、ただ力の強さや弱さだけを比べなければなりません。でも、昔から今までの内乱の歴史を見ると、人々の力はいつも政府よりも弱いものです。また、内乱を起こすと、今までその国で行われていた政治のしくみを一度壊すことになります。でも、その壊れた政府であっても、たとえどんな悪い政府でも、それ自体には少し良い政治や法律があるわけで、政府としての名前を持って少しの間生き延びる理由があります。
だから、一朝の勢いでそれを倒しても、暴力で暴力を代え、愚かさで愚かさを代えるだけです。また、内乱の始まりをたどれば、もともと人々が不親切なことを憎んで起こしたものです。しかし、人間の世界で内乱ほど不親切なものはありません。友達同士の関係を壊すだけでなく、ひどい場合は親子が互いに殺し合い、兄弟が互いに敵になり、家を焼いて人を殺し、その悪事に終わりがありません。こんな恐ろしい状況で人々の心はますます残酷になり、ほとんど野獣のような行動をしながら、逆に昔の政府よりも良い政治を行い、寛大な法律を施して世の中の人々の気持ちを厚く導こうと思うでしょうか。それは無理な考えだと言えます。
第三 正しい理由を守って命を捨てるとは、天の道理を信じて疑わず、どんな暴力的な政府の下でも、どんな厳しい法律に苦しめられても、その苦しみを我慢して自分の意志をくじかれることなく、武器も持たず力も使わず、ただ正しい理由を唱えて政府に訴えることです。この三つの方法の中で、この第三の方法が最も良い方法だと思います。理由を持って政府に訴えれば、その時その国にある良い政治や法律は、これがために少しも害を受けることがありません。その正しい議論は、使われないこともありますが、理由があるところでは、この議論によってすでに明らかになっていて、自然に人々の心がそれに従うことがありません。だから、今年に実現しなくても、来年を期待すべきです。また、力を使って政府に敵対する人は、一つ得るために百の害を受ける恐れがありますが、理由を唱えて政府に訴える人は、ただ除くべき害を除くだけで、他に問題を起こすことがありません。その目的は、政府の不正を止めることが目的なので、政府のやり方が正しくなれば、議論も一緒に終わるはずです。また、力を使って政府に敵すると、政府は必ず怒りを感じ、自分たちの悪さを省みず、かえってますます暴力を振るい、その非を押し通そうとする勢いになるでしょう。しかし、静かに正しい理由を唱える人に対しては、たとえ暴力的な政府でも、その役人たちも同じ国の人々なので、正しい理由を守って命を捨てる人を見て、必ず同情し、気の毒に思う心が生まれるはずです。もう他の人を気の毒に思う心が生まれたら、自然に過ちを後悔し、自然に勇気を失って、必ず改心するようになるでしょう。
このように、世の中で困っていて自分を苦しめたり命を失ったりする人たちを、西洋の言葉でマルチルドムと言います。失うものはただ一人の命ですが、その影響はたくさんの人を殺したりお金を使った内乱よりもずっと大きいです。昔から日本では、戦いで死んだ人も多く、切腹した人も多いです。どちらも忠臣義士として評判が高いですが、その命を捨てた理由を考えると、主君や政権を争う戦いに関係する人たちか、主人の敵討ちなどで華々しく命を投げ出した人たちばかりです。その姿は美しいように見えますが、実際には世の中に役立つことはありません。自分の主人のためだと言って、命を捨てることが良いと思うのは、昔の考え方ですが、今は文明の大義をもって考えると、これらの人たちはまだ命を捨てるべき場所を知らない人たちだと言えます。
元々、文明とは、人々の知恵や徳を伸ばし、自分自身をコントロールして世間と付き合い、互いに害を与えたり受けたりしないで、みんなが権利や義務を果たし、みんなが安全で豊かになることを言います。だから、戦いでも敵討ちでも、本当に文明の目的に合って、戦いに勝って敵を倒し、敵討ちを成功させて主人の面目を立てれば、必ずこの世界は文明に向かい、商売も行われ工業も発展し、みんなが安全で豊かになることが目的であれば、戦いで死んだり敵討ちしたりするのはもっともですが、それが目的ではありません。
昔の忠臣義士にも、そんな見込みはありません。ただ、因果関係で主人に対して責任を果たすことだけです。主人に対して責任を果たして命を捨てた人を忠臣義士と言うなら、今日も世の中にたくさんのそんな人がいます。権助は主人の使いで出かけて、一両のお金を落として困ってしまい、主人に申し訳ないと思って、決心して木の枝にふんどしをかけて首をくくることが珍しくありません。今、この義僕が自分で死を決める時の気持ちを考えて、その情けなさを察すると、哀れみを感じないわけにはいきません。使いに出かけてまだ帰らず、命を失ってしまいます。英雄たちも涙を流すでしょう。主人から頼まれて一両のお金を失ったことで、君臣の関係を果たすために死を選ぶのは、昔の忠臣義士に恥じないことです。その誠実さは日月と共に輝き、その名声は天地と共に永遠に続くはずですが、世間の人々は無情で権助を軽んじ、碑を建てて称える人もいなく、祭る人もいません。みんな言います、「権助の死はただ一両のためで、その事の大切さはとても小さい」と。
しかし、物事の重要さはお金の多少や人数では決められず、世の中の文明に役立つかどうかで決めるべきです。だから、昔の忠臣義士が一万人の敵を倒して死んだり、権助が一両のお金を失って首をくくったりしても、その死で文明に役立たないなら、どちらも同じで、どちらを軽く見るべきか決められません。義士も権助も、命を捨てるべき場所を知らない人たちと言えます。これらの行動はマルチルドムとは呼べません。私たちが聞いたことがある中で、人々の権利や正義を主張し、政府に迫り、命を捨てて成功する人で、世界中に対して恥じることがない人は、昔からただ一人の佐倉宗五郎さんだけです。ただし、宗五郎さんの話は、一般に伝わる物語だけで、まだ詳しい正確な歴史は分かりません。もし分かることがあれば、いつかそれを書いてその功徳を表し、みんなの手本にしたいです。
八編
他の人の体を自分の気持ちで動かしてはいけない
アメリカのエイランドという人が書いた『モラル・サイヤンス』という本に、人の心と体の自由について話されています。その話の大事なところは、人はそれぞれ独立した全体であり、自分の体を使い、自分の心を使って、自分一人を支配し、やるべき仕事をやるものです。だから、まず、人にはそれぞれ体があります。体を使って外の物と触れ合い、その物を手に入れて欲しいものを得るんです。例えば、種をまいてお米を作ったり、綿を取って服を作るようなことです。次に、人にはそれぞれ知恵があります。知恵を使って物の理由を見つけ出し、間違わないように物事を進めるんです。例えば、お米を作る時に肥料の方法を考えたり、木綿を織る時に機の工夫をするようなことです。これらはみんな知恵と判断力の働きです。
そして、人にはそれぞれ感情や欲望があります。感情や欲望を使って心と体の働きを起こし、それを満たして自分の幸せを作るんです。例えば、人はみんな美味しいものや綺麗な服が好きです。でも、これらは自然にできるものではありません。これらを手に入れるためには、人が働かなければなりません。だから、人が働くのは感情や欲望が促すからです。感情や欲望がなければ働かず、働かなければ安楽な幸せがありません。禅僧などは働かずに幸せがないものだと言えます。
次に、人にはそれぞれ真心があります。真心を使って感情や欲望を抑え、正しい方向に進めて止まるところを決めるんです。例えば、感情や欲望には限りがなく、美味しいものや綺麗な服もどれだけあれば十分かわかりにくいです。もし、やるべき仕事を放っておいて、ただ自分の欲しいものだけを手に入れようとすると、他の人を困らせて自分だけが得をする方法しかありません。これは人間らしい行いではありません。この時に欲望と道理を分けて、欲望から離れて道理の中に入るのが真心です。最後に、人にはそれぞれ意志があります。意志を使って物事を成し遂げる決意を立てるんです。例えば、世の中のことは偶然で起こるものではありません。良いことも悪いことも、みんな人がやろうと思ったから起こるんです。
これら五つのものは人が持っていなければならない性質で、この性質を自由に使って、自分一人の独立を作るものです。独立と言っても、一人で変わった人や世間と関わりのない人のように聞こえますが、そんなことはありません。人として世の中にいるなら、友達がいるのは当然です。でも、その友達も自分に関わりを求めるのは、自分が友達を大切にするのと同じです。だから、世の中の付き合いはお互いのことです。ただ、これら五つの力を使う時には、天が決めた法に従って、範囲を越えないことが大事です。つまり、その範囲とは、自分もこの力を使い、他の人もこの力を使って、お互いに邪魔しないことです。こうして、人が範囲を守って世の中を渡る時には、他の人に責められたり、天に罰せられたりすることはありません。これを人間の権利と言います。
この話からわかるように、人は他の人の権利を邪魔しなければ、自由に自分の体を使うことができます。好きなところに行ったり、欲しいところに止まったり、働いたり、遊んだり、この仕事をしたり、あの仕事をしたり、昼夜勉強したり、気に入らなければ何もしないで一日中寝ていても、他の人に関係ないことなら、他の人がそれをどうこう言う理由はありません。
もし、前の話に反して、「人は他の人の気持ちに従って物事をやるもので、自分の意見を出すのは良くない」という意見を持つ人がいたとします。その意見は本当に正しいのでしょうか。もし正しいなら、人が住んでいる世界ではどこでも通用するはずです。例えば、天皇様は将軍様よりも偉いので、天皇様の気持ちで将軍様の体を勝手に動かし、行きたければ「止まれ」と言い、止まりたければ「行け」と言い、寝たり起きたり飲んだり食べたりすることができるはずです。将軍様も部下の大名を支配し、自分の気持ちで大名の体を自由に使うはずです。大名は家老の体を支配し、家老は用人の体を支配し、用人は徒士を支配し、徒士は足軽を支配し、足軽は百姓を支配するはずです。
さて、農民については、もう目下の人ではないので、少し戸惑いがあるけれども、もともとこの議論は人間の世界で通用すべき当然の理由に基づいているものだから、何百万回でも、考えれば元の考えに戻らざるを得ない。「農民も人です、天皇さまも人です、遠慮はありません」と許可をもらって、農民の気持ちで天皇さまの身を自由に扱い、行幸したいと思えば「止まれ」と言い、行在に止まりたいと思えば「還御」と言い、起居寝食、みんな農民の思い通りで、金の服や美味しい食事をやめて麦飯を進めるようなことになったらどうでしょう。こんなことが起こったら、日本中の人々は、自分自身を制する権利がなくて、かえって他人を制する権利がある。
人の身体と心は、まったく別の場所にあって、その身体はまるで他人の魂が宿る旅宿のようです。下戸の身体に上戸の魂を入れ、子供の身体におじいさんの魂を止め、泥棒の魂は孔子の身体を借りて、猟師の魂は釈迦の身体に旅宿します。下戸がお酒を飲んで楽しく過ごせば、上戸は砂糖水を飲んで満足を感じ、おじいさんが木に登って遊べば、子供は杖をついて人の世話を焼き、孔子が弟子たちと一緒に泥棒をするなら、釈迦如来は鉄砲を持って殺生に行くでしょう。不思議ですね、面白いですね、また考えられません。
これを天理人情と言いましょうか、これを文明開化と言いましょうか。三歳の子どもでも答えるのは簡単でしょう。何千年も昔から日本や中国の学者先生たちが、上下貴賤の名分として騒がしく言っていたことも、結局は他人の魂を自分の身体に入れようとする考えだったのです。これを教えて、これを説いて、涙を流してこれを諭し、今日に至ってはその功徳もようやく現れ、大きな人が小さな人を制し、強い人が弱い人を圧迫する風習になったので、学者先生たちも得意げな顔をして、神代の神々や周の時代の聖人たちも、草の陰で満足していることでしょう。今、その功徳の一つ、二つを挙げて示すことは左様です。
政府が強くて小さな民を支配する議論は、前の部分でも書いたので、ここでは省略しましょう。まず、人間の男性と女性の関係について話しましょう。そもそも世に生まれた人は、男性も人ですし、女性も人です。この世で欠かせない役割を果たすという点では、世界は一日も男性がいなければならないし、また女性がいなければならない。その能力は確かに同じですが、ただ違うところは、男性は強く、女性は弱いです。大きな男性の力で女性と戦えば、必ず勝つでしょう。これが男性と女性の違いです。今、世間を見ると、力ずくで人のものを奪ったり、人を恥ずかしめたりする人がいれば、それを罪人と呼んで罰を与えることがあります。しかし、家の中では公然と人を恥ずかしめて、それを責める人がいないのはどうしてでしょう。
『女大学』という本に、「女性には三つの従う道があります。子供の時は両親に従い、結婚して夫に従い、年を取って子供に従うべきです」と書いてあります。子供の時に両親に従うのはもっともですが、結婚してから夫に従うとはどういうことでしょうか。その従う方法を問わなければなりません。『女大学』の文章によれば、主人がお酒を飲んで、女性に夢中になって、奥さんをののしったり子供を叱ったりして、放蕩淫乱を極めても、女性はそれに従い、そのような夫を天のように敬い尊み、顔色を和らげて、喜ばしい言葉で意見すべきだけです。その先の結末は書かれていません。ですから、この教えの趣旨は、淫乱な夫でも悪い夫でも、もう自分の夫と約束した以上は、どんな恥辱を受けても従わざるを得ず、ただ心にも思わない顔色を作って諫める権利があるだけです。その諫めに従うか従わないかは、淫乱な夫の気持ち次第で、つまり、淫乱な夫の気持ちはそれを天命だと思うしか方法がないのです。
仏教の本には、女性が罪が深いと書いてあることがあります。本当にこのような状況を見ると、女性は生まれたときから大きな罪を犯したとが人と変わらないですね。また、一方で女性を責めることは厳しすぎると、「女大学」では女性の悪い行いの七つの理由が書かれています。「淫乱だから悪い」とはっきりその判断が記されています。男の子にとってはとても便利ですね。こんな偏った教えではないでしょうか。結局、男の子は強く、女性は弱いという考えから、腕力を基本にして男女の上下関係を作った教えだと思います。
これは不倫をしている男女の話ですが、ここで愛人の問題が出てきます。世の中に生まれる男女の数は同じような理由で決まっています。西洋の人たちの実験によると、男の子が生まれることは女の子よりも多くて、男の子二二人に対して女の子二〇人の割合だそうです。だから、一人の男性が二人、三人の女性と結婚することはもともと自然に反していることが明らかです。これを獣と言っても問題ありません。父親と母親が同じ子どもたちを兄弟と呼び、父母と兄弟が一緒に住む場所を家と呼びます。しかし今、兄弟たちが同じ父親を持ちながら違う母親を持っていて、一人の父親だけでたくさんの母親が集まっています。これを人類の家と言えるでしょうか。家という言葉の意味が成り立ちません。たとえその建物が大きくて立派でも、その部屋が美しくても、私が目で見てもそれは人の家ではなく、動物の小屋と言わざるを得ません。妻と愛人が一緒に暮らして家族が仲良くやっている例は、昔から今まで聞いたことがありません。愛人だと言っても、彼女たちは人類の子どもです。一時的な欲望のために人の子を獣のように使い、家族のしきたりを乱して子どもたちの教育を損ない、災いを世界中に広めて毒を未来の世代に残す人たち、これを罪人と言わないわけにはいきません。
人々は言います、「愛人を養っても、その扱いが適切であれば人間関係を害することはありません」と。これは先生自身が言った言葉です。もし本当にそうだとしたら、一人の女性がたくさんの男性を養い、彼らを男の愛人と呼び、家族の第二等親の位置に置くのはどうでしょうか。このようにして家をうまく管理し、人間関係の大義に全く害を与えないのであれば、私はもう議論をやめて口を閉じて言わないでしょう。世界中の男性たちは自分自身を見つめ直すべきです。また、ある人は言います、「愛人を養うのは子どもを後に残すためで、孟子の教えでは不孝に三つあり、子どもがいないことが最も大きい」と。私は答えます、天理に戻ることを唱える者は孟子でも孔子でも遠慮なく、これを罪人と言っていいです。妻と結婚して、子どもが生まれなくても、それを大きな不孝とはどういうことでしょうか。逃げ口上と言ってもあまりに無理がありすぎます。
せめて人間らしい心を持っている人なら、誰が孟子の間違った言葉を信じるでしょうか。そもそも不孝とは、子どもが理に反したことをして親の心身を喜ばせないことを言います。もちろんお年寄りの心では孫が生まれるのは喜びですが、孫が生まれるのが遅いからといって、それをその子の不幸とは言えません。試しに世界中の親に聞いてみましょう。子どもが良い結婚相手を見つけて素晴らしい家庭を築いていても、孫が生まれないからといって怒って、その嫁を叱って、その子をムチで打って、勘当しようと思う人がいるでしょうか。世界は広いと言っても、こんな変わった人は聞いたことがありません。これらはもともと空論で、弁解する価値もありません。人々は自分の心に問いかけて、自分で答えるべきです。
親に孝行するのはもちろん人間として当然のことで、お年寄りであれば他人でも丁寧に扱うべきです。ましてや自分の父母に対しては愛情を尽くさなければなりません。利益のためでも名誉のためでもなく、ただ自分の親だと思って、天から与えられた誠実さで彼らに孝行すべきです。昔から日本や中国では孝行を勧める話がたくさんあります。「二十四孝」をはじめ、他にもたくさんの本が書かれています。しかし、これらの本を読むと、一〇冊のうち八、九冊は人間にできないことを勧めたり、愚かで笑うべきことを説いたり、理に反したことをほめて孝行だと言ったりするものがあります。
寒い中で、裸のまま氷の上に寝て、溶けるのを待つなんて、人間にはできないことです。夏の夜に、自分の体にお酒をかけて、蚊に刺されないようにするよりも、そのお酒のお金で虫よけの紙を買った方が賢いじゃないですか。お父さんやお母さんを助ける仕事もなくて困っているのに、悪くない子どもを生きたまま穴に埋めようとする心は、鬼だと言えますし、蛇だとも言えます。天理人情を害する最悪のことだと言えます。不孝の一番悪いことは、子どもを作らないことだと言われていますが、ここではすでに生まれた子どもを穴に埋めてしまおうとしています。どちらが孝行だと言えるのでしょうか。前後のつじつまが合わない考えではないでしょうか。結局、この孝行の考えも、親子の関係を大切にし、上下の違いをはっきりさせようとして、無理に子どもを責めるものだと思います。その理由を聞くと、「お母さんが妊娠して苦しんだり、生まれてからは三年間お父さんやお母さんのそばを離れない。その大きな恩はどうするの?」と言われます。しかし、子どもを作って育てることは人間だけでなく、動物たちも同じです。人間の親と動物の親が違うところは、子どもに服や食べ物を与えるだけでなく、教育して人間の付き合い方を教えることが一番大事だということです。
それなのに、世の中のお父さんやお母さんは、子どもを作ることはできても、子どもを教育する方法を知らないまま、自分たちは悪いことをして子どもに悪い見本を見せてしまいます。家を汚して財産を失い、貧しくなってしまい、元気がなくなって家のものがなくなると、悪いことをやめて頑固になります。そして、その子どもに向かって孝行を求めるとは、どんな心なのでしょうか。どんな厚かましい顔をして、こんな恥ずかしいことができるのでしょうか。お父さんは子どものお金を欲しがり、お姑さんはお嫁さんの心を悩ませます。お父さんやお母さんの気持ちで、子どもたちや夫婦の生活を制限してしまい、お父さんやお母さんが正しいと思って、子どもたちの意見は全く聞かない。お嫁さんはまるで餓鬼地獄に落ちたようで、起きている時間も寝ている時間も食べている時間も自由がありません。一つでも舅姑の考えに反すると、すぐに不孝者だと言われますし、周りの人たちもそれを見て、自分ではないからと親の側に立って子どもを責めることがあります。また、通りすがりの人の話に従って、親をだます方法を教えてもらうこともあります。これが人間の家庭の道だと言えるでしょうか。私は以前こんなことを言いました。「お姑さんの鏡はお嫁さんの時にある」と。お姑さんがお嫁さんを困らせたいなら、自分が昔お嫁さんだった時を思い出すべきです。
これは、上下や立場の違いから生じる悪い習慣で、夫婦や親子の二つの例を示しました。世間ではこのような悪い習慣がたくさんあり、どんなことでも人間の付き合いに影響しています。その他の例は次の話で書くことにします。
九編
学問のすすめを二つに分けて、中津の昔の友達に送る手紙
人の心と体の働きを細かく見ると、これを分けて二つに区別するべきです。第一は一人でいる時の働きです。第二は人間が仲間と一緒にいて、その仲間との関係での働きです。
第一 心と体の働きで、服や食べ物や家などの安らぎを得るもの、これを一人の身についての働きと言います。でも、実際には、世界にあるすべてのものは、人に役立つものばかりです。一粒の種をまけば、二、三百倍の実ができますし、山の木々も、育てなくてもよく成長します。風は車を動かす力になりますし、海は物を運ぶのに便利です。山から石炭を掘り出し、川や海から水を汲み、火を使って蒸気を作れば、大きな船や車を自由に動かせます。このように、自然の素晴らしい仕組みはたくさんあります。人はただ、この自然の仕組みを利用し、ちょっとした工夫で自分のために使うだけです。だから、人間が服や食べ物や家を手に入れることは、もう自然が九九%作ってくれているものに、人間が一%だけ加えるだけのことです。だから、人はこれらのものを作るとは言えません。実際には、道ばたに捨てられたものを拾うようなものです。
だから、人間が自分で服や食べ物や家を手に入れることは難しくありません。このことができても、特別に誇るべきではありません。もちろん、自立して生活することは人間にとって大切なことで、「あなたの額の汗をもって、あなたのご飯を食べなさい」というのは昔の人の教えですが、私の考えでは、この教えを実践しただけでは、まだ人間としての役割を果たし終えたわけではありません。この教えは、ただ人間が動物より劣らないようにするだけです。試しに見てください。鳥や獣や魚や虫は、自分で食べ物を手に入れることができます。それだけでなく、アリのように遠い未来を考えて、穴を掘って住む場所を作り、冬のために食べ物をため込むこともあります。
しかし、世の中には、このアリのやり方で自分を満足させる人がいます。今その一例を挙げましょう。男の子が大人になって、仕事に就いたり、商売を始めたり、役所で働いたりして、やっと親戚や友達に迷惑をかけずに、ちょうど良い服や食べ物を手に入れ、他人に失礼なこともなく、借りた家ではなく自分で簡単に家を建て、家の中のものはまだ整わなくても、奥さんだけはとりあえず手に入れ、望み通りに若い女性と結婚し、身の回りのことも整い、節約を守り、子供たちがたくさん生まれても教育はそれなりにできるからお金もそんなにかからず、病気などの急な出費に三〇円や五〇円のお金がいつも使えるようにして、細かく長い間の計画を心配し、とにかく一つの家を守る人がいれば、自立した生活を手に入れたと得意そうにして、世の中の人もこれを見て、ちゃんと自立した人物だと言い、頑張って働いたことが評価されるような気持ちになりますが、実際には大きな間違いです。この人はただアリの弟子だと言えるだけです。一生の仕事はアリよりも優れているわけではありません。その服や食べ物を求め、家を建てる時には、額に汗を流すこともあったでしょうし、心配することもあったでしょう。昔の人の教えに対して恥ずかしいことはないと言えますが、その成功を見ると、すべての生き物の中で特別な人間の目的を達成したわけではありません。
上記のように、一人の身の服や食べ物や家を手に入れて満足するべきではない場合、人間の人生はただ生まれて死ぬだけで、死ぬ時の様子は生まれた時の様子と変わりません。このようにして子孫が続いていくと、何百代も経っても一つの村の様子は昔のままで、世界に新しい技術を生み出す人がいなくなり、船も作らず、橋もかけず、自分や家族以外のことはすべて自然に任せて、その土地に人間が生きた痕跡を残さなくなるでしょう。西洋の人が言ったことがあります。「世の中の人が皆、自分で満足することを知って小さな安らぎに甘んじていたら、今日の世界は最初にできた時の世界と変わらないだろう」と。これは本当にそうです。もちろん、満足には二つの種類があり、その境界を間違えてはいけません。一つ手に入れても、また二つ欲しくなり、足りると思ったらまた足りないと感じ、最後には満足することを知らないものは、欲と呼ばれたり、野心と呼ばれたりします。しかし、私たちの心と体の働きを広げて目指すべき目的を達成できないものは、愚かだと言われるべきです。
第二 人はみんなで暮らすのが好きで、一人でいることはできません。夫婦や親子だけでは、その気持ちを満たすことはできず、必ず広く他の人と関わり、その関わりが広ければ自分の幸せも大きくなると感じるものです。だから、人間の交流が始まるわけです。もう世の中にいて、その交流の中の一人になったら、その義務もあります。学問とか、工業とか、政治とか、法律と言うものは、みんな人間の交流のためにするもので、人間の交流がなければどれも役に立たないものです。
政府は、法律を作る理由は、悪い人を防いで良い人を守り、人間の交流を大切にするためです。学者は、本を書いたり人を教える理由は、後の世代の知恵を導いて、人間の交流を守るためです。昔、ある中国の人が、「天下を治めることは肉を分けるように公平であるべき」と言い、「庭の草を取り除くよりも、天下をきれいにしよう」と言ったのも、みんな人間の交流のために役立ちたいという気持ちを表しています。どんな人でも、少しでも自分に得るものがあれば、それを使って世の中に役立ちたいと思うのは普通のことです。自分では世のために何もしていないつもりでも、知らず知らずのうちに後の世代や子孫がその恩恵を受けることがあります。人にこの気持ちがあるからこそ、人間の交流の義務を果たせるのです。
昔からこんな人たちがいなかったら、私たちが今日生まれて、今の世界中にある文明の恩恵を受けることはできません。親から財産を受け継ぐことは遺物と呼ぶことができますが、その遺物はただ地面や家財などだけで、これを失えば跡形もなくなります。しかし、世の文明はそうではありません。世界中の昔の人たちを一つにまとめて、その一つの昔の人たちから今の世界中の私たちに譲り渡された遺物ですから、その大きさは地面や家財の類ではありません。でも、今誰に向かってこの恩を感謝すべき相手がいないのです。これは例えば、人生で必要な太陽の光や空気をお金を使わずに得るようなものです。そのものは大切だけど、持っている主人がいないのです。ただ、これを昔の人たちの陰徳恩賜と言うべきなのです。
最初のころは、人間の知恵はまだ開かれていませんでした。その様子を表現すると、まるで生まれたばかりの子供がまだ知識が出てこないようなものです。例えば、麦を作って粉にするためには、自然の石と石を使ってそれをつぶすことでした。その後、ある人の工夫で二つの石を丸く平らな形に作り、その中心に小さな穴を掘り、一つの石の穴に木か金の棒を差し込み、その石を下に置いてその上にもう一つの石を重ね、下の石の棒を上の石の穴にはめ込み、その石と石の間に麦を入れて上の石を回し、その石の重さで麦を粉にする工夫ができました。これがひき臼です。昔はこのひき臼を人の手で回すことが普通でしたが、時代が進むにつれて臼の形もだんだん変わり、水車や風車で動かしたり、蒸気の力を使ったりして、どんどん便利になっていきました。
何事もこのようにして、世の中の様子はだんだん進み、昨日便利だったものも今日は遠回りになり、去年の新しい工夫も今年は古くさいものになります。西洋の国々では、電信や蒸気やいろいろな道具が次々に出てきて、顔を変えていきます。新しいものが出るのは、形のある道具だけではありません。人間の知恵がどんどん開かれて交流が広がり、交流が広がれば人間の気持ちも和らぎ、万国公法の考え方が広まって戦争を起こすことが難しくなり、経済の話題が盛んになって政治や商売の風潮が変わり、学校の制度や本の形式、政府の商議、議会の政談がどんどん高まっていきます。その行く先の果ては予想できません。西洋文明の歴史を読んで、最初のころから一六〇〇年代までの巻を閉じて、二〇〇年間を飛ばして、一八〇〇年代の巻を開いてみると、誰もがその急速な進歩に驚愕するでしょう。ほとんど同じ国の歴史とは信じられないくらいです。このように進歩を遂げた理由の根本を探ると、みんな昔の人たちの遺物や先人たちの贈り物です。
わが日本の文明も、最初は朝鮮・中国から来ました。それから、日本の人たちが努力して、今のような姿になりました。洋学というのは、昔の宝暦年間から始まりました(『蘭学事始』という本を見てください)。最近、外国との交流が始まって、西洋の考え方が広まりました。洋学を教える人もいて、洋書を訳す人もいます。みんなの気持ちが変わって、政府も変わり、藩もなくなりました。これも、昔の人たちのおかげです。
昔から、力のある人たちが、心と体を使って世のために働く人がたくさんいました。今、その人たちの考えを思うと、きっとお金や家が豊かだけでは満足しないでしょう。人との付き合いを大切にして、高い目標を持っています。今の学者は、そんな人たちから文明を受け継いで、進歩の先頭に立っているんです。だから、どんどん進んでいかないといけません。これから何十年後の文明の世界になったら、後の人たちが、私たちの良いところを見上げるようになるはずです。だから、私たちの仕事は、今この世にいて、自分たちの生きた証を残して、後の世に伝えることです。それはとても大切なことです。
ただ学校の本を数冊読んで、商売や工場で働いたり、小さな役人になって、年に少しのお金をもらって家族を養うだけでは、満足できないでしょう。そんな人は、他人に迷惑をかけないだけで、他人を助ける人ではありません。時には、チャンスがあっても、力を発揮できないこともあります。昔も今も、そんな例はたくさんあります。私たちの知っている近くの町にも、すごい人たちがいました。今の文明の目で見ると、その人たちの言動や考え方が間違っていることもあるかもしれません。でも、それは時代のせいで、その人たちのせいじゃないんです。実は、彼らは物事を成し遂げる気力があったんです。ただ、運が悪くてチャンスに出会えず、宝を持っているのに一生を過ごしました。死んだり、老けたりして、世の中の人たちにその良さを伝えられなかったのは、とても残念です。
でも、今はそうではありません。前にも言ったように、西洋の考え方が広まって、ついに旧政府が倒れて藩もなくなりました。これは、戦争だけの変化ではありません。文明の力は、戦争だけで終わるものではありません。だから、この変化は戦争の変化ではなく、文明に影響された人々の気持ちの変化なんです。戦争の変化はもう七年前に終わって跡形もありませんが、人々の気持ちの変化は今も続いています。物事を動かすためには、導く人が必要です。学問の道をリーダーとして、みんなの気持ちを導いて、高い目標に向かわせるためには、今の時代がチャンスです。このチャンスに出会った人たちは今の学者です。ですから、学者は世のために勉強しないといけません。十編につづきます。
十編
前編のつづき、中津の旧友に贈る
前編では、学問の大切さを二つに分けて話しました。その話の要点は、「人はただ自分や家族の食べ物や服を手に入れるだけで満足してはいけない。人の本当の力はもっと高いところにあるから、人々と仲良くなって、その仲間と一緒に世のために頑張るべきだ」ということです。
学問をする時、目標を高く持たないといけません。ご飯を炊いたり、お風呂の火を焚いたりすることも学問です。世界中のことを考えることも学問です。でも、家族の生活を楽にすることは簡単で、世界中の経済を考えることは難しいです。世の中のもので、手に入れやすいものは大切ではありません。大切なものは、手に入れるのが難しいからです。私はこっそり考えていますが、今の学者は難しいことを捨てて、簡単なことに取り組むのが問題だと思います。
昔の封建時代には、学者がお金を持っていても、世界中のことを全部考えることは難しい状況でした。だから、学問をする場所がなくて、仕方なく勉強していました。その学問の方法は良くないと言われても、本を読んで勉強して、知識が豊富な人は今の人たちにはなかなかいません。今の学者はそうではありません。だから、勉強すればするほど、実際に使うべきです。例えば、洋学生は、三年間勉強すれば歴史や科学の本を知ります。そして、洋学の先生になって学校を開いたり、他の人に教えたり、政府で働いたりするべきです。それよりもっと簡単なことがあります。その時流行っている外国の本を読んで、世間を走り回って、内外のニュースを聞いて、チャンスがあれば役所について、すぐに立派な役人になります。こんな状況で、世の中の学問は高いレベルに進むことはありません。筆で書くことが少し下品だと言われても、お金の計算で説明しましょう。学校に入って勉強するのに一年間で一〇〇円しかかからないです。三年間で三〇〇円を使って、すぐに一ヶ月に五〇~七〇円の利益を得るのが洋学生の仕事です。耳で学んだ知識で役人になる人は、この三〇〇円を使わなくても、手に入れる月給は全部利益です。
世の中の商売でこんなに大きな利益を得るものはあるでしょうか。高利貸しでも、これよりもっと利益があると言えます。もちろん、物の値段は世の中の需要によって高かったり低かったりします。今、政府やいろいろな所で洋学者が急に求められているため、この相場の景気が良くなっています。だから、その人を悪いと言われても、買う人をばかだと言われても、私たちの考えでは、その人がもっと三~五年頑張って本当の学問を勉強してから仕事につけば、大きな成果があると思います。そうすれば、日本全国で知恵や徳が増えて、初めて西洋の国々の文明と競争できるようになります。
今の学者は何を目的にして学問をしていますか。自由で独立した大切な理念を求めると言い、自分たちの権利や自由を取り戻すと言うわけではありません。もちろん、自由や独立と言う時には、その言葉の意味にも義務があるはずです。独立とは、一つの家に住んで他の人から食べ物や服をもらわないだけではありません。それはただ内側の義務です。もっと外側の義務を考えると、日本に住んでいて日本人であることを恥ずかしく思わず、国中の人たちと力を合わせて、この日本を自由で独立した地位にすることが、内側と外側の義務を果たすと言えます。だから、一つの家に住んでちょっとだけ食べ物や服を手に入れる人は、一家の主人と言えますが、まだ独立した日本人とは言えません。
試しに見てみましょう。今の世界の状況では、文明という名前はあるけれども、まだその実を見ていません。外側の形は整っているけれども、内側の精神はなくなっています。今の日本の海軍や陸軍で西洋の国々の兵士と戦うことができるでしょうか。絶対に戦えません。今の日本の学問で西洋人に教えることができるでしょうか。絶対に教えられるものはありません。逆に、彼らから学んで、それでも足りないところを恐れるだけです。外国に留学生がいて、国内に雇われた先生がいて、政府の部署や学校から、いろいろな場所まで、ほとんど外国人を雇わないところはありません。私立の会社や学校も、新しく事業を始める時には必ず最初に外国人を雇って、高い給料を払って頼ります。彼らの長所を取り入れて、自分たちの短所を補うというのは人々の考えですが、今の状況を見ると、私たちは全部短所で、彼らは全部長所のようです。
もともと、数百年間の鎖国が終わって、急に文明の人たちと交流することになったので、その状況は火と水が触れ合うようなものです。この交流をうまくやるためには、外国の人を雇ったり、外国の道具を買ったりして、急いで欠けている部分を補う必要があります。それは仕方がないことだから、一時的に外国に頼ることは国の失敗ではありません。でも、他国のものに頼って自分たちの役に立てるのは、永遠に続く方法ではありません。それはただ、一時的な手段だと思って、自分たちを慰めるだけです。その一時的なものはいつ終わるのでしょうか。自分たちで用意できる方法はどうすればいいのでしょうか。それを考えるのはとても難しいです。
ただ、今の学者たちの成果を待って、学者たちが自分たちの国の役に立てるようにするしか方法はありません。だから、学者たちの仕事はとても重要だと言えます。今、日本に来ている外国人は、日本の学者たちがまだ未熟だから、しばらく代わりに働いている人たちです。今、日本で外国の道具を買っているのは、日本の工業がまだ下手だから、お金と交換して役に立てるものです。外国人を雇ったり、道具を買ったりするためにお金を使うのは、日本の学問がまだ外国に追いついていないから、日本のお金を外国に渡すことになります。それは国のために惜しむべきことです。学者になった人たちは恥ずかしいと思うべきです。そして、人間として将来の希望を持つべきです。希望があれば、世の中で頑張る人がいます。明日の幸せを願って、今日の不幸も慰めるべきです。来年の楽しみを願って、今年の苦しみも我慢するべきです。昔は、世の中のものごとが古い方法で制限されていて、志を持つ人たちにも目標を育てることができませんでしたが、今は違います。その制限を取り除いた後は、まるで学者たちのために新しい世界が開かれたように、どんな立場でも世の中で活躍する場所があります。
農業をやり、商売をし、学者になり、官僚になり、本を書き、新聞を書き、法律を教え、芸術を学び、工業も始めるべきです。議会も開くべきです。いろいろな仕事をやるべきではないものはありません。そして、この仕事を成功させて、日本中の兄弟たちが争わないようにすることが大切です。知恵を競う相手は外国人です。この知恵の戦いに勝てば、日本の立場を高くすることができます。負ければ、日本の立場を下げることになります。その希望は大きく、目指すところは明らかだと言えます。もちろん、世の中のことを実行するには、状況に応じて柔軟に対応する必要がありますが、絶対に欠かせない仕事は、今からみんなで研究しなければなりません。たとえ少しでも社会の義務を知る人たちは、この時代に当たってこの状況をただ見ているだけではいけません。学者たちは頑張らなければなりません。
これを考えると、今の学者さんたちは、普通の学校の教育だけで満足しちゃいけないです。もっと高い目標を持って、学問の本当の意味に達し、自分で立ち上がって他の人に頼らず、友達がいなくても一人で日本を守る力を育てて、世のために尽力しなければいけません。私たちも、古い日本や中国の学問で人々を治めることは知っていますが、自分で勉強することはあまり好きじゃありません。だからこそ、この本の最初から、みんなが同じ権利を持つことを主張して、自分で責任を果たして、自分の力で生きる大切さを話しています。でも、自分の力で生きるだけじゃ、まだ私たちの学問の目的は終わっていません。
これを例えると、ここに酒や女性に夢中で、だらしない子供たちがいます。どうやって彼らをちゃんとした人にするかというと、まずお酒を飲むのを禁じて、遊びに行くのを止めさせて、それからちゃんとした仕事につかせることです。お酒を飲まないで遊びに行かない間は、まだ家の仕事について話すことはありません。でも、酒や女性に夢中にならなくても、それだけでその人が良い人だとは言えません。ただ世の中に迷惑をかけないだけで、まだ役に立たないものの名前は免れません。お酒を飲まないで遊びに行かない上で、ちゃんとした仕事について、自分や家族を支えることがあって、初めて普通の子供だと言えます。自分の力で生きることも同じです。
私たちの国の士族以上の人たちは、何千年もの昔からの習慣に慣れて、どんな服を着てどんなご飯を食べるかも知らなくて、お金持ちになった理由もわからなくて、自分たちが何もしなくてもご飯が食べられるのは当然だと思っています。そんな人たちは、酒や女性に夢中になって、前後のことを忘れてしまう人たちと同じです。こんな時に、こんな人たちにどんなことを言ってもいいでしょうか。ただ自分の力で生きることを言って、彼らの夢から目覚めさせるしか方法はありません。こんな人たちに向かって、高い学問を勧めることはできません。世の中を良くする大きな理由を話すこともできません。たとえそんなことを言っても、夢中で学問を始めても、その学問もまた夢の中の夢だけです。だから私たちは、ずっと自分の力で生きることを主張して、まだ本当の学問を勧めていません。だからこの話は、みんなが何もしないでご飯を食べる人たちに言うべきで、学者さんたちに教えるべき言葉じゃありません。
でも聞いたことがあるんです。最近、古い友達や勉強を始めた人たちの中に、まれにまだ勉強が終わっていないのに、早く生活の道を探す人がいます。もちろん、生活は大事です。その人の才能に長所と短所があるから、これからの方向を決めるのはいいことだと思います。でも、もしこの考え方がみんなに広がって、ただ生活を競うだけになったら、すごい子供たちがまだ実力を出し切れないかもしれません。それは本人にとっても悲しいことで、世の中にとってももったいないことです。生活が大変だと言っても、家族の生活をちゃんと考えれば、お金をすぐに使って安心を買うより、一生懸命働いて節約して成功する時を待つ方がいいです。勉強を始めたら、しっかり勉強しましょう。農業をやるなら、大きな農業を目指しましょう。商売をするなら、大きな商売を目指しましょう。学者さんたちは、ちょっとした安心に満足しちゃダメです。簡単な服を着て簡単なご飯を食べて、寒さや暑さに怯えず、米をついて、薪を割りましょう。勉強は、米をつきながらもできることです。人間のご飯は、洋食だけじゃなくて、麦ご飯を食べて味噌汁をすすって、文明のことを学ぶべきです。
十一編
名分で偽りの良い人が生まれる話
第八編では、上下貴賤の名分から夫婦・親子の間に起こる問題の例を示し、「その問題が広がるところは、他にもたくさんある」と書きました。そもそもこの名分が引き起こす問題を考えると、それは強い力を持って弱い人を支配する意味で間違いないと言えますが、その本当の意味は悪い考えから生まれたわけではありません。結局、世の中の人々を全て無知で善良だと思い、助けたり、導いたり、教えたり、助けたりするために、ただ上の人の命令に従って、自分の意見を出さないようにし、上の人は自分が気づいた方法でうまくやりくりし、国の政治も、村の支配も、お店の始末も、家庭の生活も、上下が心を合わせて、まるで世の中の人間関係を親子の関係のようにしようとする考えです。
例えば、一〇歳くらいの子供を扱うときは、もちろんその子供が意見を出すべきではありません。親がうまくやりくりして食べ物や服を与え、子供はただ親の言うことに逆らわず、指示に従えば、寒い時にはちょうどあたたかいものが用意されていて、お腹が空いた時にはご飯ができていて、ご飯や服はまるで空から降ってくるように、自分が欲しいと思った時に手に入り、何も困らないで家にいられます。親は自分の大切な子供だから、教えたり、諭したり、ほめたり、しかったりするのも、すべて本当に愛情からで、親子の間は一つになって、その楽しさは言い表せません。これが親子の関係で、そのときは上下の名分もあって、問題が起こることはありません。名分を主張する人は、この親子の関係をそのまま人間関係にしようと考えていて、面白い工夫のようですが、ここに大きな問題があります。親子の関係は、知恵がある本当の親と一〇歳くらいの本当の子供の間でしか成り立ちません。他人の子供に対してはもちろん無理です。たとえ本当の子供でも、もう二〇歳以上になったらだんだんその考えを変えなければなりません。ましてや、もう大人になった他人同士の間ではどうでしょう。この方法で関係が成り立つわけがありません。言わば、望んで実現できないものがこれです。
さて今、国と言い、村と言い、政府と言い、会社と言い、すべて人間関係と呼ばれるものはみな大人と大人の仲間です。他人と他人の付き合いです。この仲間付き合いに親子の方法を使おうとするのは難しいことでしょうか。しかし、実際には実現できないことでも、それを実行してうまくいくと想像する人は、その想像を実現したく思うのも人情です。これが世に名分というものが生まれ、専制が行われる理由です。だから、名分の根本は悪い考えから生まれたわけではなく、想像によって作られたものです。
アジアの国々では、国王のことを民の親と言い、人々のことを子どもや赤ちゃんと言い、政府の仕事を人々を世話する仕事と言って、中国では地方の役人のことを何州の牧と呼んでいます。この牧という字は動物を飼う意味なので、一つの州の人々を牛や羊のように扱うつもりで、その名前を堂々と看板に掛けているわけです。失礼な方法ではありませんか。人々を子供のように、牛や羊のように扱うと言っても、前にも言ったように、最初の本当の意味は悪くありません。本当の親が本当の子供を育てるような考えで、まず国王を賢明な人と決め、賢い正直な人を選んで助けさせ、自分の欲望を持たず、心が清くまっすぐで、自分の気持ちを他人に伝え、人々に優しく接して、飢饉の時には米を与え、火事の時にはお金を与え、助け教育して生活が安楽になるようにし、上の人の徳は暖かい南風のように、人々がそれに従うのは草が風になびくように、柔らかさは綿のようで、無心さは木や石のようで、上下が一つになって平和を歌おうとする計画です。まるで極楽の様子を真似したようなものです。
しかし、事実をよく考えると、政府と人々はもともと親子の関係ではなく、実際には他人同士です。他人同士の関係では、感情だけではうまくいかず、必ずルールや約束が必要で、お互いにそれを守って細かい違いを争い、両方とも円くうまくいくことが、国の法律ができた理由です。しかし、どんな学校に入っても、こんなに完璧な聖人や賢者を作り出す方法はなく、どんな教育をしてもこんなに素晴らしい人々を得る方法はなく、昔から中国の人々も心配してきましたが、今日まで一度もうまくいったことはありません。結局、今のように外国人に押し付けられているわけではありません。
この意味を知らずに、効かない薬を何度も飲むように、小さな工夫の仁政を使い、神じゃない人が無理にその仁政を調整して恩恵を受けようとし、恩恵が迷惑に変わり、仁政が厳しい法律に変わり、それでも平和を願うのでしょうか。願うなら一人で願ってください。これを解決する方法はありません。その考え方はとても遠回りです。本当に隣にいるのに笑いをこらえるのが難しいほどです。
この習慣は政府だけでなく、商家や学校、宮殿や寺院でも行われています。今、その一例を挙げてみましょう。店の中で店主が一番物知りで、元帳を扱うのは店主一人です。だから番頭や手代がいて、それぞれが自分の仕事をしていますが、番頭や手代は商売全体の仕組みを知らず、ただうるさい店主の指示に従って、給料も指示によって、仕事も指示によって、商売の損益は元帳を見てもわからず、朝晩店主の顔色をうかがい、その顔に笑みがあるときは商売がうまくいっていると推測し、眉間にしわが寄っているときは商売がうまくいっていないと推測するくらいです。心配することは何もありません。
ただ一つ心配なのは、自分が預かっている帳面に筆を使って極内の仕事をすることだけです。鷲のような店主の目力もそれまで及ばず、真面目な忠助が思いがけず倒れたり急死した後で帳面を調べると、大きな穴が開いていて、初めて人間に頼るのが難しいことにため息をつくだけです。しかし、これは人間に頼るのが難しいわけではなく、専制に頼るのが難しいのです。店主と忠助は赤の他人ではありません。その忠助に商売の割合を約束せずに、子供のように扱おうとするのは店主の無理解と言えます。
このような上下や貴賤の名分を正しくし、ただその名前だけを主張して専制の権力を行使する原因から、その毒が出るところは人間が行う詐欺や策略の姿です。この病気にかかる人を偽善者と呼びます。例えば、封建時代の大名の家来は表向きみんな忠臣だと思っていて、その形を見ると君主と臣下の名分が正しく、挨拶をする時も敷居の一本の内外を争い、亡くなった君主の夜には精進を守り、若殿が生まれると上下を着せ、年始の祝いやお墓参りには一人も欠けることがありません。口から出る言葉は、「貧しさは士の常であり、尽力して国に報いる」や、「その食べ物を食べる者はその仕事で死ぬ」と言ったり、とても立派そうに言って、すぐに戦死する勢いで、一見すると騙されそうな様子ですが、こっそり片側から見ると、やはり偽善者です。
大名の家来が良い役割を果たす者がいれば、その家にお金ができる理由は何でしょうか。決まった俸禄と役料で余分なお金は入らないはずです。しかし、出入りの差し引きで余るのはとても怪しいです。役得だろうが、賄賂だろうが、大名の物を取ることに違いありません。その最も典型的な例を挙げると、普請奉行が大工から割前をせしめたり、会計の役人が出入りする町人からお礼を受け取るようなことは、三百諸侯の家にほとんど定石のようなものです。大名のためには馬の前で戦死さえすると言っている忠臣義士が、買い物の時に値切るのはあまりにも不都合ではありませんか。金箔付きの偽善者と言えます。
まれに正直な役人がいて、賄賂の話も聞こえないけど、それはただお金を盗まないだけです。人が盗まないからといって、すごいと思うべきではありません。ただ、偽りの良い人たちの中で普通の人が混ざっているだけで、特別目立つわけではありません。結局、偽りの良い人たちが多いのは、昔の人たちがみんな良い人だと思い込んでいたからで、それが悪いことになってしまいました。本当に頼りにならないものは名分です。一番大きな毒は専制抑圧です。それは怖いことです。
ある人が言います、「人々の悪い例ばかり挙げても限りがないけど、日本は義の国で、昔から君のために命を捨てる義士がたくさんいました」と。答えて言います、「本当にそうですが、義士は少なくて、数が合わないんです。元禄年中は義気が盛んな時代でした。その時、赤穂七万石の中に義士四七人がいました。七万石の土地にはおおよそ七万人が住んでいたはずです。七万人の中に四七人がいれば、七百万人の中には四千七百人がいるはずです。時代が変わって、人々の気持ちは薄くなり、義気も衰えていくのは普通のことです。だから、元禄年中から義気を三割減らして七割にすれば、七百万人について三千二百九十人の割合になります。今、日本の人口は三千万人で、義士の数は一万四千百人になるはずです。この人数で日本を守れるでしょうか。三歳の子どもでも計算できることです」
この話によると、名分は意味がないようですが、念のためにもう一言付け加えましょう。名分とは見せかけの名前のことです。虚名と言えば、上下関係に関係なく無用のものですが、見せかけの名前と実際の仕事を入れ替えて、仕事をちゃんとやれば、名分も問題ありません。政府は国を運営する場所で、人々を支配する仕事があります。人々は国のお金を出す立場で、国のために働く仕事があります。文官は政治や法律を決める仕事があります。武官は命じられた場所に行って戦う仕事があります。他にも、学者や町人にもそれぞれ決まった仕事があります。
しかし、ちょっとした知識を持った人が、名分は無用だと聞いて、すぐに自分の仕事を忘れてしまいます。人々の立場で政府の法を破ったり、政府の命令で人々の仕事に手を出したり、兵隊が政治を議論して戦争を起こしたり、文官が武官に従ったりすることがあれば、それは国が大変なことになります。自由すぎて、無秩序な騒ぎになるでしょう。名分と仕事は文字が似ていますが、意味は全く違います。学者はこれを間違えないでください。
十二編
演説の方法をすすめる話
演説とは英語でスピーチと言い、たくさんの人が集まって意見を話し、自分の考えを伝える方法です。日本では昔からあまり聞かないけれど、お寺のお話しすることはちょっと似ています。西洋の国では演説がとても盛んで、政府の議会や学者の集まり、商人の会社、市民の集まりから、結婚式や葬式、新しく始める仕事やお店まで、たった一〇人ぐらい集まっても、必ずその場で、何か意味のあることを話したり、普段の考えを話したり、その場で思いついたことを話してみんなに見せる風習があります。この方法が大切だということはもちろんわかります。例えば今、世間で議会の話があっても、最初に意見を話す方法がなければ、議会も役に立たないでしょう。
演説で物事を話すと、その内容が大切かどうかは一旦置いておいて、ただ話すだけで面白さが生まれます。文章で書くと意味がなさそうなことでも、言葉で話すと簡単に理解できて感動するものがあります。昔から有名な詩や歌もそうで、普通の文章に訳すと面白くないけれど、詩や歌の形で表現すると素晴らしい雰囲気が生まれてみんなを感動させます。だから一人の考えをたくさんの人に伝える方法は、どのように伝えるかがとても大切です。
学問はただ本を読むだけではないということは、もうみんなが知っているので今それを説明する必要はありません。学問の大事なことは実際に使えることです。使えない学問は無学と同じです。昔、ある朱子学の学生が何年も江戸で勉強して、有名な先生の意見を書き写して、毎日頑張って数年間でたくさんの本を作りました。もう学問ができたと思って故郷に帰ろうとして、自分は陸路で帰り、書いた本は船で送りました。しかし遠州の海で船が難破してしまいました。その災難で、学生は無事に帰れたけれど、学問は全部海に流れてしまって、何も残らなかったという話があります。
今の洋学者にも同じ心配があります。今日都会の学校で本を読んだり講義を聞いたりする様子を見ると、それを評価して学者と言わざるを得ません。でも、急にその本を取り上げて田舎に追い出すことがあったら、「僕の学問は東京に置いてきた」と言い訳するような変な話もあるでしょう。
だから学問の本当の意味は本を読むだけではなくて、心の働きにあります。その働きを実際に使って現実に活かすにはいろいろな工夫が必要です。オブセルウェーションとは物事をよく見ることです。リーゾニングとは物事の理由を考えて自分の意見を作ることです。この二つだけではまだ学問の方法を全部使ったとは言えません。もちろん本を読まなければいけないし、本を書かなければいけないし、人と話さなければいけないし、人に向かって意見を話さなければいけません。これらの方法を全部使って初めて学問を勉強する人と言えます。つまり、物事を見たり考えたり本を読むことで知識を集め、人と話すことで知識を交換し、本を書いたり演説したりすることで知識を広げる方法です。そうしてこの方法の中には、一人でできることもあるけれど、話すことや演説することは必ず人と一緒にしなければいけません。演説会が大切だということを知るべきです。
今日、日本の国民が一番心配なことは見識が低いことです。それを高めて進歩させるのは今の学者の仕事ですから、その方法があるなら頑張って取り組まなければいけません。しかし、学問の道で話すことや演説することが大切だということはもう明らかですが、今日実際にそれをやっている人がいないのはどうしてでしょう。学者の怠け心だと言えます。人間のことには内側と外側の両方があり、両方を大切にしなければいけません。今の学者は内側のことだけに専念して、外側の仕事を知らない人が多いです。これを考えなければいけません。自分の中で深く考えることは深い池のようで、人と接して活発にすることは飛ぶ鳥のようで、その密度が内側にないかのようで、その大きさが外側にないかのようで、初めて本当の学者と呼べるのです。
人の行いは、立派でなければならない理由
前の文章では、「今、私たちの国で一番心配すべきことは、人々の考え方がまだ立派でないことです」と言いました。人の考え方や行いは、難しい話をするだけで立派になるわけではありません。禅の家には、道を悟るということがありますが、その理由はとても奥深いです。しかし、その僧侶の行いを見ると、遠回りで役に立たず、実際には何の考え方もない人と同じようです。
また、人の考え方や行いが、たくさんのことを聞いたり見たりするだけで立派になるわけではありません。たくさんの本を読んで、世界中の人と交流しても、自分だけの意見がない人がいます。昔ながらの習慣を守る儒教の学者のような人たちです。ただ、儒教の学者だけでなく、洋学者もこの問題を免れません。今、西洋の新しい学問に興味を持ち、経済の本を読んだり、人間修養の話をしたり、理学や知識を学ぶことに一生懸命ですが、その人の私生活を見ると、全然違います。経済の本を読んでいる目で、家族のお金のやりくりを知らず、口で人間修養の話をして、自分の良い行いを知らない。その考え方と行いを比べるとき、まるで二つの人がいるかのようで、一貫した考え方が見られません。
結局、このような学者たちも、口で話したり、目で見たことを否定するわけではありませんが、物事を正しいと思う心と、その正しいことを実際に行う心は、全く別のものです。この二つの心は、時々一緒に行動することがありますが、時々そうではありません。「医者が自分の健康を気にしない」と言ったり、「論語を読む人が論語を知らない」ということわざも、これを言っているのです。だから、人の考え方や行いは、難しい話をするだけで立派になるわけではなく、また、たくさんのことを聞いたり見たりするだけで立派になるわけでもありません。
では、人の考え方を立派にし、その行いを良くする方法は何でしょうか。そのコツは、物事のありさまを比べて上流に進み、自分が満足しないことにあります。ただし、ありさまを比べるとは、ただ一つのことや物を比べるだけではありません。この一つのありさまと、あの一つのありさまを並べて、両方の良い点と悪い点を全部見極めなければなりません。例えば今、若い生徒たちがお酒や女性に夢中にならずに、真面目に勉強すれば、親や年配の人たちから叱られることはありません。それどころか、得意そうな顔をしているかもしれませんが、その得意な顔は、他のだらしない生徒と比べているだけです。真面目に勉強するのは人間の普通のことで、それをほめるほどのことではありません。人生の目標は、もっと高いものがあるはずです。昔の人々や今の人々を広く見て、誰と誰の功績が同じようなものを作れば、それに満足できるでしょうか。必ず上流の人物に向かわなければなりません。私に一つの良い点があっても、彼には二つの良い点があるとき、私はその一つの良い点に安心する理由はありません。ましてや、後輩は先輩より優れているべき約束ですから、昔の人々を空しく思って比べるべき人物がいないわけではありません。今の人々の仕事は、とても大切で重要だと言えます。
しかし、今、ただ真面目に勉強することだけで、人間の一生のことになるでしょうか。それを考えないのは、とても悲しいことです。お酒や女性に夢中になる人は、非常識な怪物と言われるべきです。この怪物と比べて満足する人は、両目が見えることを得意にして、盲人に自慢するようなものです。ただ愚かさを表すだけです。だから、お酒や女性の話をして、それを否定したり、是非を決める間は、どうしても低い話と言わざるを得ません。人の行いが少し進むとき、これらの汚い話はもう過ぎ去って、口に出すことさえ嫌われるようになるはずです。
今日の日本で学校を評価するとき、「この学校のしきたりはこんな感じです。あの塾のルールはこうだ」と言って、親たちはほとんどしきたりやルールに心配しています。そもそも、しきたりやルールって何を指すのでしょうか。厳しい塾のルールで生徒がふらふらしないように守ることを言うのでしょうか。これを学問の良い点と言うべきでしょうか。私たちはむしろ恥ずかしいと思います。西洋の国々のしきたりは必ずしも美しいわけではありませんし、醜い部分もたくさんあるけれど、その国の学校を評価するとき、しきたりが正しくてルールがちゃんと守られているから名誉があるということは聞いたことがありません。
学校の名誉は、教科が高尚で、教え方が巧みで、先生たちが品行方正で、議論が下品でないことによるだけです。だから、今の学校を運営している人たちや今の学校で勉強している人たちは、他の下手な学校と比べずに、世界中のトップの学校を見て良し悪しを判断しなければいけません。美しいしきたりやちゃんと守られているルールも学校の良い点だと言えますが、その良い点は学校として最も下に見るべき部分の良い点で、全く誇るべきではありません。トップの学校と比べようとするなら、別の努力をしなければいけません。だから、学校の急務としていわゆるルールのことを話す間は、たとえそのルールがちゃんと守られていても、決して満足してはいけません。
一つの国の様子を考えるのも同じです。例えば、ある政府があって、賢くて正直な人々が政治を任されて、国民の苦しみや喜びを察して適切な処置を行い、報奨と罰を必ず行い、恩恵と威厳を行使していて、みんなが幸せで平和を祝うような状況は、本当に誇るべきだと思います。しかし、その報奨や罰、恩恵や威厳、みんなのこと、平和というものは、すべて一つの国の中のことで、一人や数人の意見によるものです。その良し悪しは、その国の前の時代と比べたり、他の悪い政府と比べて誇るべきだけで、決してその国全体の様子を詳しく見て他の国と対比して、一から一〇まで比べたものではありません。もし一つの国を全体として一つのものと見なして、他の文明の国と比べて、数十年間で行われる両方の良し悪しを考えて、互いに足したり引いたり掛けたり割ったりして、実際に現れた損益を考えることがあれば、誇るべきものは決して誇るべきではないものでしょう。
例えば、インドの国家は古くありませんし、その文化の発展は西暦前数千年にあります。理論が精密で奥深いものは、おそらく今の西洋の国々の理学と比べて恥ずかしくないものがたくさんあるでしょう。また、昔のトルコの政府も、権威がとても強く栄えていて、礼儀や戦争の方法が整っていました。国王は賢明であり、宮廷の役人も正直でした。人口が多く、兵士が勇敢で、近くの国々と比べて類がなく、一時期その名誉が四方に輝いていました。だから、インドとトルコを評価すると、インドは有名な文化の国で、トルコは武勇の大国と言わざるを得ません。
しかし、今日この二つの大国の様子を見ると、インドはすでにイギリスの領土になっていて、その人々はイギリス政府の奴隷と変わりません。今のインド人の仕事はただアヘンを作って中国人を毒殺し、イギリス商人だけがその間に毒薬の売買で利益を得ることです。トルコの政府も名前は独立と言いますが、商売の権利はイギリスやフランスの人々が持っていて、自由貿易のおかげで国の物産は日に衰えていきます。織機を使う人もいなくて、道具を作る人もいなくて、汗をかいて土地を耕すか、手を袖に入れて暇に日月を過ごすだけです。すべての製品はイギリスやフランスから輸入され、国の経済を治めることができません。さすがに勇敢な兵士も貧しさに抑えられて役に立たないと言います。
このように、インドの文化も、トルコの武力も、かつてその国の文明に役立たないのは何故でしょうか。その国民の見方は一つの国の中に止まり、自分たちの国の様子に満足して、その様子の一部分を他の国と比べて、その間に優劣がないと見て騙されて、議論もそこで止まり、仲間もそこで止まり、勝ち負けや栄辱も他の全体の様子を目指すことを知らずに、みんなが平和を祝うか、または兄弟が壁に争っている間に、商売の権威に押されて国を失うのです。洋商が向かうところにはアジアに敵がいません。恐れるべきです。もしこの強敵を恐れて、その国の文明を尊敬するなら、内外の様子を比較して努力しなければいけません。
十三編
怨望が人間に害のあることを論ずる
およそ人間に悪いことがたくさんあるけれど、その中で一番大きな害があるのは怨望(妬み)です。貪欲、贅沢、悪口の類はみんな悪いことだけど、よく考えてみると、その働きの素質において悪いものではありません。これを使う場所や、その強さや弱さ、その向かう方向によって、悪いことから逃れることがあります。例えばお金を好んで満足しないことを貪欲と言います。でもお金を好むのは人の天性ですから、その天性に従って十分に満足させることは決して悪いことではありません。ただ理に反したお金を得ようとして場所を間違えたり、お金を好む心に限界がなくて理に反したり、お金を求める方向に迷ったりするときは、それを貪欲の悪いことと言います。だからお金を好む心の働きを見て、すぐに悪いことだと言わないでください。その良いことと悪いことの境にはちょっとした道理があって、その境の中にあるものは節約と言ったり、経済と呼んで、まさに人間が努めるべき美徳の一つです。
贅沢も同じようなものです。ただ自分の立場を超えるかどうかで、良いことか悪いことかを決めるべきです。暖かくて軽い服を着て快適な家に住むのが好きなのは人の性格です。天理に従ってこの欲求を満たすのに、なんでこれを悪いことと言わなければならないのでしょうか。お金を貯めて上手に使い、使っても限度を超えない人は、人間の素晴らしいことと言えるでしょう。
また悪口と反論は、その違いがわずかで区別することはできません。他人にうそをつくことを悪口と言い、他人の間違いを正して自分の真実だと思うことを反論と言います。だから世の中にまだ真実無妄の公道が見つからない間は、人の意見もまた、どれを正しいとしてどれを間違っていると言うべきか、それを決めることはできません。正しいか間違っているかがまだ決まらない間は仮に世界中の人々の意見を公道だと思っても、その人々の意見がどこにあるかをはっきり知ることはとても難しいです。だから他人を悪口する人を見て、すぐにその人を悪い人だと言わないでください。その悪口が本当に悪口なのか、それとも本当の反論なのかを区別しようとするには、まず世界中の公道を求めなければなりません。
この他にも、高慢と勇敢さ、粗野さと率直さ、固陋と実用的さ、浮薄さと利口さが対立するように、どれも働く場所や、強さや弱さ、向かう方向によって、時には悪いことになったり、時には良いことになったりするだけです。ただ働く素質が完全に悪い方に偏っていて、場所や方向に関係なく悪いことばかりの人は怨望の一つです。怨望は働きの陰で起こるもので、自分から取ろうとしないで、他の様子によって自分に不満を持ち、自分を見つめずに他人に多くを求め、その不満を満たす方法は、自分を助けることではなくて他人を傷つけることにあります。例えば他人の幸せと自分の不幸を比べて、自分に足りないところがあれば、自分の状況を改善して満足する方法を求めずに、逆に他人を不幸にし、他人の状況を下げて、自分と他人の平均を作ろうとするのです。これを憎んでその死を願うと言うのはこのことです。だからこのような人の不満を満たそうとすると、世の中全体の幸福を損なうだけで、少しも助けにならないでしょう。
ある人が言います、「詐欺やうそをつく悪いことも、その実質において悪いものだから、これを怨望と比べてどちらが軽いか重いかの違いはないはずだ」と。答えて言います、「確かにそう言えるけれど、事の原因と事の結果を区別すれば、自然に軽いか重いかの違いがあると言えません。詐欺やうそはもともと大きな悪いことですが、必ずしも怨望を生む原因ではなくて、たいていは怨望が原因で起こる結果です。怨望はまるで悪いことの母親のようで、人間の悪いことがこれによって生じないものはありません。疑いや嫉妬、恐れや臆病さは、みんな怨望から生まれるもので、その中で表に出るところは、内緒話や秘密の話、内輪の話や秘密の計画で、その外で壊れるところは、仲間や暗殺、一揆や内乱で、秋毫も国に利益をもたらさず、災いが全国に広がって主人も客も逃れることができません。これを公の利益を使って私を強くするものと言うべきです。
怨みや不満が人間関係に悪い影響を与えるのは、まるでこういうものです。今、その原因を考えてみると、ただ困っていることが一つの原因です。ただし、その困っていることはお金がないとか、貧乏などの困り事ではありません。人の話を遮ったり、人の仕事を邪魔したりするようなことで、自然に働く力を尽きさせることです。貧乏や困っていることを怨みや不満の理由にすれば、世界中の貧しい人たちはみんな不平を言い、お金持ちが怨まれる場所になり、人間関係は一日も続かないはずなのに、実際にはそうではありません。どんなに貧しくて立場が低い人でも、その貧しさや立場が低い理由の原因を知り、その原因が自分自身から生じていることを理解すれば、決して無闇に他人を恨んだり不満を持ったりするものではありません。その証拠はわざわざ説明する必要もなく、今日の世界中にお金持ちと貧しい人の差があっても、人間関係がうまく保たれていることを見れば、明らかにわかります。だから言います、お金持ちは怨まれる場所ではなく、貧しくて立場が低いことは不平の理由ではありません。
これを考えると、怨みや不満が生じるのは貧しさや立場の低さからではありません。ただ、自然に働く力を遮ぐことで、幸せや不幸が偶然に左右される状況では、怨みや不満が流行するだけです。昔、孔子が「女の子と小人は近づきにくくて、本当に困ったものだ」と嘆いたことがあります。今考えてみると、これは孔子自身が問題を起こして、その弊害を語ったものと言えます。人の心の性は男の子も女の子も違いはありません。また、小人とは下の立場の人と言うことでしょうか。下の立場の人から生まれた人が必ず下の立場の人になると決まっているわけではありません。下の立場の人も上の立場の人も、生まれたときの性格に違いはないことは、もちろん議論する必要はありません。それなのに、どうして女の子と下の立場の人だけが扱いにくいと言われるのでしょうか。普段から卑屈な考えをみんなに教え、弱い立場の女性や下の立場の人たちを縛り付けて、その働きに自由を与えないために、ついに怨みや不満の気持ちが生まれ、最後には孔子さえも嘆くことになりました。
元々、人の性格では働きに自由がなければ、その勢いで他人を恨んだり不満を持たざるを得ません。因果応報が明らかであることは、麦を蒔いて麦が生えるようなものです。聖人と呼ばれた孔子がこの理を知らず、別の方法も考えずにただ愚痴をこぼすのは、とても残念な話です。そもそも孔子の時代は、明治から二〇〇〇年以上前の野蛮草昧な時代で、教えの趣旨もその時代の風習や人情に従い、世界中の人々の心を保つためには、知っていてわざと縛る方法がなかったのです。もし孔子が本当の聖人であり、何万年も後のことを見通す明智さがあれば、当時の方法を心から良しとすることはありません。だから、後世の孔子を学ぶ者は、時代の考えを勘案して取捨選択しなければなりません。二〇〇〇年前に行われた教えをそのままに、模倣して明治時代に実行しようとする者は、物事の価値を話すべきではない人です。
また、近くの一例を挙げて示しましょう。怨みや不満が流行して人間関係を悪くしたものは、私たちの封建時代にたくさんいた大名のお殿の女中たちが最もです。そもそもお殿の大まかな様子を言えば、無知で無学な女性たちが集まって無知で無徳な主人に仕え、勉強をして褒められるわけでもなく、怠けて罰されるわけでもなく、叱られることもあれば、叱られないこともあり、言うのも良し言わないのも良し、嘘をつくのも悪し嘘をつかないのも悪し、ただ朝晩に臨機応変で主人の愛情を運よく得るだけです。
その状況はまるで的がない状態で矢を射るようなもので、当たるのも上手ではなく、当たらないのも下手ではありません。まさにこれを人間界外の一つの世界と言ってもいいでしょう。このような状況の中にいれば、喜怒哀楽の感情は必ず性格を変えて、他の人間社会とは違うものにならざるを得ません。たまたま仲間の中で出世する人がいても、その出世の方法を学ぶことができず、ただ羨むだけです。その羨みが強くなると、ただ妬むだけです。仲間を妬み、主人を恨むことに忙しくて、どうして家のためを考える暇があるでしょうか。忠誠や節義は表面上の挨拶だけで、実際には畳に油をこぼしても、人が見ていないところでは拭わずに放置するような態度です。最悪の場合、主人が命に関わる病気になっても、普段から仲間と睨み合いに巻き込まれて、思うように看病もできない人がたくさんいます。さらに一歩進んで怨みや嫉妬が極端になると、毒殺事件も珍しくありません。昔からこの大きな悪事について、その数を記録した統計表があります。お殿で行われた毒殺事件の数と、世間で行われた毒殺事件の数を比較すれば、お殿で悪事が盛んであることは明らかです。怨みや不満の災いは、どれほど恐ろしいことでしょうか。
右御殿女中の一例を見ても、大抵、世の中の様子は推し測ることができます。人間の最大の災いは恨みや妬みにありますが、それらの原因は困難な状況から生まれるものです。だから、人々の意見を尊重し、仕事を邪魔しないようにすべきです。たとえば、イギリスやアメリカなどの国々と日本を比べて、人間関係において、どちらが御殿のような状況を脱しているかと問われたら、私たちは今の日本がまったく御殿と変わらないとは言い切れませんが、その境界を越えるのが遠いか近いかという点では、日本はまだ近く、イギリスやアメリカは遠いと言わざるを得ません。イギリスやアメリカの人々も、欲深く贅沢を好むわけではなく、粗暴なわけでもなく、たまに詐欺師や騙す人がいることはありますが、ただ恨みや妬みを隠すことに関しては、必ず日本とは違う方法があるはずです。
今、世の賢い人たちには、国民が選んだ議員を持つ議会の考えがありますし、出版の自由についても意見があります。その良し悪しは一旦置いておいて、そもそもこのような考えが生まれる理由を考えると、賢い人たちは、現代の日本を古い御殿のようにさせず、現代の人々を古い御殿女中のようにさせず、恨みや妬みに負けない活動を促し、競争の勇気を励まし、幸福や不幸、評価や非難をすべて自分の力で手に入れ、全国の人々が自分の行いによって報われるようにしたいという考えがあるのでしょう。
人々の意見を尊重しないことや、仕事を邪魔することは、政府に関係することばかりではありません。一見、政治に限定された問題のように思えますが、この問題は政府だけでなく、人々の間でも起こり、毒を広めることが最もひどいものです。だから、政治だけを改革するのではなく、その根本を取り除くべきです。今後もう少し話しまして、政府以外のことについて考えてみましょう。
元々人は交流を好むものですが、習慣によって逆に嫌うこともあります。世の中には変わった人や珍しいものがあり、特に山村や遠い田舎で世間との交流を避ける人がいます。これらの人々を隠者と呼びます。また、本当の隠者ではないけれど、世間の付き合いが苦手で家に閉じこもり、俗世間を避けると言って得意げにする人もいます。このような人たちの気持ちを考えると、必ずしも政府の仕組みを嫌って身を引くわけではなく、心が弱くて物事に対する勇気がなく、度量が狭くて他人を受け入れることができず、他人を受け入れられないから他人も彼らを受け入れない。お互いに一歩ずつ距離を置いて、最終的には全く違う種類の人のようになり、最後には敵同士のようになって互いに恨み合うことがあります。これは世の中で大きな災いだと言えます。
また、人間関係において、相手の人を見ずにその行動を見るか、あるいはその人の言葉を遠くから聞いて、少しでも自分の意に沿わないものがあれば、必ず同情や共感の心を持たずに、逆に嫌悪の気持ちを抱き、悪く思って実際よりも悪い方に考えることが多いです。これは人の天性や習慣によるものです。物事の相談では伝言や手紙ではうまくいかないことも、直接話すことで円満に解決することがあります。また、人々はよく言います、「本当はこんな理由があるけど、顔を見てそんなこと言えない」と。つまり、これは人間の本質であり、我慢する心があるところです。すでに我慢する心が生まれたとき、お互いの気持ちが通じ合い、恨みや妬みの感情はすぐに消え去ることになります。古今に暗殺の例がいくつもあるとは言え、私たちがよく言うことがあります。「もし良い機会があって、殺す人と殺される人が数日間同じ場所にいて、お互いに隠すことなく本当の気持ちを話せるなら、どんな敵でも必ず仲直りするだけでなく、最高の友達になることもあるでしょう」と。
これらの事情を考えると、意見を尊重しないことや、仕事を邪魔することは、政府だけの問題ではなく、全国の人々の間で起こるもので、学者であっても免れることは難しいです。人々の活力は物事に関わらなければ生まれにくいです。自由に意見を言わせ、自由に働かせ、富も貧困もその人自身が手に入れることに任せ、他人が邪魔することがないようにすべきです。
十四編
心事の棚卸し
人が生きていく中で、考えているよりも意外と悪いことをしてしまい、考えているよりも意外とばかなことをやってしまい、考えているよりも意外とうまくいかないことがあります。たとえどんな悪い人でも、一生懸命悪いことだけをしようと思っている人はいませんが、物事にぶつかったり、関わったりすると、急に悪い考えが浮かんで、自分が悪いことをしていることを知りながら、いろいろな言い訳をして、無理やり自分を慰める人がいます。また、物事に取り組むときは、決して悪いことだと思わず、全く恥ずかしいところがないどころか、心から良いことだと信じて、他の人が違う意見を持っていたら、逆に怒ったり、恨んだりするくらいですが、時間がたって後で考えると、とても自分の行動が恥ずかしくなることがあります。
また、人それぞれ賢い人やばかな人、強い人や弱い人がいますが、自分は動物の知恵にも劣ると思う人はいけません。世の中のいろいろな仕事を見て、これなら自分でもできると思って、自分に合った仕事を引き受けることがありますが、その仕事をやっている間に、思っていたより失敗が多くて最初の目標を達成できず、周りに笑われたり、自分で後悔することがたくさんあります。世の中で成功しようとして失敗する人を見ていると、本当におかしくて笑いが止まらないくらいばかなことをやっているように見えますが、その失敗した人は必ずしもばかではなく、しっかりその理由を聞くと、実はもっともな理由があることがあります。結局、世の中の出来事は生き物であり、簡単に先の変化を予測できません。だから、賢い人であっても意外とばかなことをやってしまうことが多いです。
また、人が計画を立てるとき、いつも大きなことを考えて、その難しさや時間の長さを比べることはとても難しいです。フランクリンという人が言っていることがあります。「十分だと思ったときでも、実際にやってみると足りないことに気づく」と。この言葉は本当にその通りです。大工さんに家を建ててもらったり、洋服屋さんに服を作ってもらったりするとき、一〇回中八、九回は約束の日に間に合わせることができない人がいます。これは大工さんや洋服屋さんがわざと計画を破るわけではありません。最初に仕事と時間をちゃんと比べなかったため、思わず約束を破ってしまうだけです。さて、世の中の人は大工さんや洋服屋さんに約束を破ることを責めることが珍しくありませんが、それを責める理由もないわけではありません。大工さんや洋服屋さんはいつも恐れ入っていて、お客さんはちゃんと理解している人のように見えますが、そのお客さん自身が自分で引き受けた仕事を、ちゃんと約束通りにやり遂げたことがあるでしょうか。
田舎の学生が、東京に出てくるとき、苦労して三年で目標を達成しようと自分で決めた人が、本当にその約束を守ったでしょうか。無理な才能を持っていると思って、原本を求めて、三ヶ月で読み終わろうと約束した人が、本当にその約束通りにやったでしょうか。志を持った人が、「私が政府に出れば、この仕事はこうやって処理し、あの改革はこうやって処理し、半年で政府の顔を変える」と言って、何度も提案してやっと願いが叶って政府に出た後、本当に前日に考えたことに反らなかったでしょうか。貧しい学生が「私に一〇〇万円あれば、明日から日本中に学校を作って、家に勉強しない人がいなくなる」と言っている人が、今日良い縁があって三井や鴻ノ池の養子になったら、本当に言った通りになるでしょうか。このような夢を数えたらキリがありません。みんな、物事の難しさと時間の長さを比べずに、時間を計ることが甘く、物事を見ることが簡単すぎるせいです。
また、世間で物事を計画する人の言葉を聞くと、「一生のうちに」や「一〇年のうちにこれを成し遂げる」と言う人はとても多く、「三年のうちに」や「一年のうちに」と言う人は少し少なく、「一ヶ月のうちに」や「今日このことを計画して、今すぐやる」と言う人はほとんどいなくて、「一〇年前に計画したことを今やっと成し遂げた」と言うような人は私はまだその人に会ったことがありません。このように、期限が遠い未来にあるときは、大きなことを計画するようですが、その期限が近づいて今月や今日になると、はっきりと計画の内容を話すことができないのは、結局、物事を計画するときに時間の長さを考慮しないから起こる問題です。
以上のように、人生では、道徳や義理のことについて考えているよりも意外と悪いことをしてしまい、知恵のことについて考えているよりも意外とばかなことをやってしまい、考えているよりも意外と物事がうまくいかないことがあります。この問題を防ぐ方法はいろいろありますが、今ここで人があまり気にしない一つの方法があります。その方法とは何でしょうか。物事の成功や失敗について、時々自分の心の中でプラスとマイナスの計算を立てることです。商売で言えば、在庫を数える総勘定のようなものです。
商売では、最初から損失を狙う人はいけません。まず自分の才能とお金を考えて、世の中の流れを見て仕事を始めます。色々な変化に対応して、当たることもあれば外れることもあります。この買い物で損をしたり、あの売り物で利益を得たりします。一年や一ヵ月の終わりに全部の計算をするとき、予想通りになったこともあれば、大きく違ったこともあります。また、この商品は必ず利益があると思っていたのに、棚卸しの時に損益の表を見ると、意外に損失が出ていることもあります。買い物の時に品物が足りないと思っていたのに、棚卸しの時に残っている商品を見ると、売り物に時間がかかって、買い物が多すぎたこともあります。だから商売で大事なのは、普段の計算をしっかりして、棚卸しの時期を間違えないことです。
他の人のことも同じです。人間の人生の商売は一〇歳くらいから始めるものです。普段から知恵や徳の計算をしっかりして、損失を引き受けないように心がけなければいけません。「この一〇年間で何を損して何を得たか。今はどんな商売をしていて、どれくらい成功しているか。今は何を買って、どの時にどこで売るつもりか。一年中、自分の心のお店の管理がちゃんとできていて、遊びや怠けることで穴が開いていないか。来年も同じ商売で成功する見込みがあるか。もうこれ以上知恵や徳を増やす方法がないか」と、色々な計算をして棚卸しの全部の計算をすることが大事です。過去や現在の自分の行いについて、問題があることも多いでしょう。その例をいくつか挙げると、「貧乏でも忠誠を尽くす」と言って、無理に人々の米を食べて得意げにして、今日になって困っている人は、外国の銃があることを知らずに、刀や剣を買って、一時的な利益を得て、残った商品に後悔しているようなものです。日本や中国の古い本だけを勉強して、西洋の新しい学問を見ないで、昔のことばかり信じて疑わない人は、過ぎた夏の暑さを忘れずに冬に蚊帳を買うようなものです。若い学生がまだ勉強が十分でないのに急いで小さい役職を求めて、一生涯、外でうろうろするのは、半分作った服を質屋に入れて売るようなものです。地理や歴史の基本も知らず、普通の手紙を書くのも難しくして、無理に高尚な本を読もうとして、数ページ見てまた別の本を探すのは、元手がないのに商売を始めて毎日仕事を変えるようなものです。日本や中国や西洋の本を読んでも、世界や国家の状況を知らず、自分や家族の生活にも苦労する人は、そろばんを持たずに色々な商売をするようなものです。
世の中を治めることを知って、自分を直すことを知らない人は、隣の家の計算を助けて、自分の家に泥棒が入ることを知らないようなものです。口では新しい流行りを言って、自分がどんな人か考えない人は、売り物の名前は知っていても値段を知らないようなものです。これらの問題は今の世の中では珍しくありません。その原因は、ただ流れに任せてこの世を渡って、自分の身の有り様に注意しないで、生まれてから今日まで自分は何をしてきたか。今は何ができるか。これから何をすべきかと、自分自身をチェックしないからです。だから言います、商売の状況を明らかにして将来の見込みを決めるのは全部の計算です。自分の状況を明らかにして将来の方向を決めるのは知恵や徳の棚卸しです。
世話の字の意味
世話には二つの意味があります。一つは「保護」です。もう一つは「命令」です。「保護」とは、人のことを見守り、守ってあげたり、お金や物をあげたり、時間を使ってその人が利益や面目を失わないようにすることです。「命令」とは、人のために考えて、その人にとって便利だと思うことを指示したり、不便だと思うことには意見を言ったり、心を尽くして忠告することです。これも世話の意味です。
このように世話には、「保護」と「指図」の両方の意味があります。本当に良い世話をすれば、世の中は円く治まります。例えば、親が子供に食べ物や服を与えて保護の世話をすると、子供は親の言うことを聞いて指図を受け入れ、親子の関係に問題がありません。また、政府が法律を作って国民の命や面目、私有財産を大切に扱い、みんなの安全を考えて保護の世話をすると、人々は政府の命令に従って指図の世話に戻ります。そうすれば、公私の関係が円く治まります。
だから、「保護」と「指図」は二つあっても、その目的は同じで、ちょっとも違ってはいけません。「保護」が行き届くところは、「指図」も行き届くところです。「指図」が行き届くところは、「保護」も行き届かなければなりません。もし、この二つの目的が間違っていたり、少しでもズレていたら、すぐに問題が起こり、災いの原因になります。世の中には、こんな例がたくさんあります。それは、みんなが世話の意味を間違えて、「保護」だけだと思ったり、「指図」だけだと思ったりして、片方だけに偏って、文字の本当の意味を理解しないで、大きな間違いを犯しているからです。
例えば、親が子供にお金を与えて道楽息子を助けるのは、保護の世話はできていても、指図の世話はできていないことです。子供が勉強して親の言うことを聞くけれど、その子供に十分な食べ物や服を与えず、無学で文盲の苦しい状況に陥らせるのは、指図の世話だけをして保護の世話を怠っていることです。甲は不孝で、乙は不慈です。どちらも人間の悪い行為だと言われます。
昔の人が教えてくれた「友達に何度も会うと疎じゃれる」という言葉があります。その理由は、「私の忠告を使わない友達に対して余計なお世話をすると、相手が自分の気持ちを知らずに厚かましく意見を言って、最後には嫌われたり、恨まれたり、馬鹿にされたりして、実際には役に立たないから、大体のことを見計らってこちらから近づかないようにすべきだ」という意味です。この意味も、指図の世話が行き届かないところでは、保護の世話をするべきではないということです。
また、昔の田舎では、おじいさんが古い家の系図を持ち出して別家の中をかき回したり、お金のないおじさんが実家の姪を呼んで家事を指図したり、その冷たさを責めたり、その行儀の悪さをとがめたり、最悪の場合は、知らない祖父の遺言だと言って姪の家の私有財産を奪い去ろうとするようなことがあります。これは、指図の世話が過ぎて保護の世話が全くないことです。ことわざで言う「大きにお世話」とは、このことです。
また、世の中には貧しい人を助けるために、その人がどんな人かや、貧しくなった原因を調べずに、ただ貧しい姿を見てお金やお米をあげることがあります。寡婦や孤独で、本当に頼るところがない人には助けるのも当然ですが、五升の救済用のお米をもらって、三升分をお酒にして飲む人もいます。お酒を禁じる指示もできずにただお米をあげるのは、指示が行き届かず、保護が過ぎたものです。ことわざで言う「大変な苦労」はこのことです。イギリスなどでも、貧困を助ける法律が困難なのはこの理由だと言われています。
この考えを国の政治に広げて考えると、国民は税金を払って政府の必要なものを提供し、その生活を守るものです。しかし、専制政治では、国民の意見を全く使わず、その意見を述べる場所もないので、保護は一方的で、指示が進まない状況です。国民の状況は「大変な苦労」だと言えます。
このような例を探して挙げると、全部を数える暇がありません。この「世話」という考えは経済学で最も大切なポイントで、人間の生活の中で、仕事や事柄の違いや重要さに関わらず、常に注意しなければなりません。たとえこの議論が算盤を使って無情に見えても、薄くすべきところを無理に厚くしようとしたり、実際には薄いのに名前だけ厚くしようとすると、かえって人間の感情を傷つけて世の中の付き合いを苦々しくすることになります。名声を得ようとして実際の成果を失うものだと言えます。
上記のような議論を立てましたが、世間の誤解を恐れて、念のためここにいくつかの言葉を添えます。個人の道徳を修める教えには、経済の法則と相反するようなものがあります。しかし、一人一人の私的な道徳はすべて世界の経済に影響を与えるものではありません。知らない乞食にお金を投げたり、貧しい人を見かけたら、その人の来歴を問わずに少しの財産をあげることがあります。これらの行為は保護の世話ですが、この保護は指示と一緒に行われるものではありません。考え方を窮屈にして、ただ経済上の利益だけでこれを論じると不都合に見えても、個人の道徳で恵みの心は最も尊いもので、最も好ましいものです。例えば、世界中で乞食を禁止する法律は公平で正しいものですが、個人的に乞食に物をあげようとする心は非難されるべきではありません。人間のすべての事柄を算盤で決めるべきではなく、ただ使うべき場所と使ってはいけない場所を区別することが大切です。世の学者たちよ、経済の公論に酔って個人の仁恵を忘れないでください。
十五編
ものごとを疑って選び捨てること
信じる世界にうそが多く、疑う世界に真実がたくさんあります。試しに見てみましょう、世間のおろかな人々は、人の言葉を信じ、人の書いたものを信じ、小説を信じ、うわさを信じ、神や仏を信じ、占いを信じ、お父さんお母さんの大きな病気にマッサージの話を信じて草の根や木の皮を使い、お嬢さんの結婚話に家の形を見るのアドバイスを信じて良い夫を逃してしまいます。熱い病気で医者を呼ばずにお経を唱えるのは、阿弥陀如来を信じるからです。三日や七日の断食で亡くなるのは、不動明王を信じるせいです。このような人々の中で本当のことがどれだけあるか聞いてみると、答えは「たくさん」とは言えません。真実が少ないから、うそがたくさんあるわけです。しかし、このような人々はものごとを信じると言っても、その信じるものはうそを信じている人です。だから、「信じる世界にうそが多い」と言います。
文明の進歩は、天と地の間にある形あるものでも、形のない人間関係でも、その働きの意味を調べて真実を見つけ出すことです。西洋の国々の人々が今日の文明に達した理由を探れば、疑いの一つから始まったものばかりです。ガリレオは天文学の古い考え方を疑って地球が動くことを発明しました。ガルハニはカエルの足がちくじゃくすることを疑って動物の電気を発明しました。ニュートンはりんごが落ちるのを見て重力の理由に疑いを持ちました。ワットは鉄のやかんの湯気をいじって蒸気の働きに疑いを持ちました。どれもみんな、疑いの道を通って真実の奥に達したものと言えます。物事の理由を突き止める範囲を離れて、人間関係の進歩の様子を見ても同じです。奴隷売買の法律が良いか悪いか疑って、世界中の後世に悲しい毒を断ち切った人は、トーマス・クラレクソンです。ローマ教会の間違った考え方を疑って教えを少し変えた人はマルチン・ルターです。フランスの人々は貴族の横暴を疑って騒ぎを始めました。アメリカの州の人々はイギリスの成り立った法律に疑いを持って独立の成功を収めました。今日でも、西洋の偉い人たちが新しい考え方を唱えて人々を文明に導くのを見ると、その目的はただ昔の人が決めて反論できないとされる議論を反論し、世の中で普通に疑いを持たないとされる習慣に疑いを持つことだけです。
今の人間関係では男の子は外で働き、女の子は家の中で仕事をすると言ってその関係がほとんど自然だと思われていますが、スチュアルト・ミルは『女性論』という本を書いて、ずっと変わらないとされるこの習慣を壊そうと試みました。イギリスの経済の専門家たちに自由な法律が好きな人が多くて、これを信じる人たちはまるで世界中の決まりごとのように認めますが、アメリカの学者には保護法を唱えて自分たちの国だけの経済の考え方を主張する人がいます。一つの意見が出れば別の意見がそれを反論し、違う考え方が争ってどこまで行くか分からなくなります。これをアジアの国々の人々が、うその話や間違った考え方をすぐ信じて魔法や神仏に迷い込み、言われている聖人や賢人の言葉を聞いてただちに同意するだけでなく、何世も後になってもその言葉の範囲から抜け出せないものと比べれば、その品行や勇気の良し悪し、心の強さ弱さは、もともと年齢が同じでは話せないものです。
違う考え方が争うときに物事の真実を求めるのは、逆風に向かって船を進めるようなものです。その船の道を右にしたり、左にしたり、波にぶつかり風に逆らい、何十何百キロの海を通り過ぎても、そのまっすぐ進む道を計れば、進んだ距離はたったの三キロや五キロにすぎません。航海では時々順風があると言えども、人間関係では決してそんなことはありません。人間関係が進歩して真実に達する道は、ただ違う考え方が争うときに割り込む一つの方法があるだけです。そして、その議論が生まれる源は疑いの一つにあって存在するものです。「疑う世界に真実が多い」とは、まさしくこのことです。
それでも、物事を簡単に信じるべきではないことは確かですが、またそれを簡単に疑うべきではありません。この信じるか疑うかのときには、必ず選び捨てる明るさがなくてはなりません。学問の大事なことは、この明るい知恵を明らかにすることです。私たちの日本でも、国が開かれてから人々の考え方が変わり、政府を改革し、貴族を倒し、学校を作り、新聞局を開き、鉄道や電信や兵隊や工業など、いろいろな物事を一度に古い方法から変えたのは、みんな何千年も続いた習慣に疑いを持って、それを変えようと試みて成功したものだと言えます。
それでも、私たちの人々の心に、この数千年の習慣に疑いを持った原因を考えると、最初に国を開いて西洋の国々と交流し、その文明の姿を見て美しさを信じ、それに倣って古い習慣に疑いを持ったので、まさにこれを自分からの疑いとは言えません。ただ古いものを信じる信念で新しいものを信じ、昔は人々の心が東にあったものが、今日はそれが西に移っただけで、その信じることや疑うことの選び方については、本当に適切な明るさを保てないです。私たちはまだ学問が足りなくて、この選び方の疑問について、一つ一つ正しいかどうかを議論してすべてを挙げることができないので、もちろん自分で反省するべきです。しかし、世の中の変化の大きな流れを考えると、みんなの気持ちがこの勢いに乗って、信じるものは信じすぎて、疑うものは疑いすぎて、信じることも疑うことも適度な止まりどころを失っているのは明らかに見えます。以下にその理由を述べます。
東西の人々は、風習が違って感情も違い、何千年もの間、それぞれの国で行われてきた習慣は、利益や損害が明らかであっても、すぐに彼らに取ってこれに移すことはできませんし、ましてやその利益や損害がまだはっきりしないものについてです。これを採用しようとするには、たくさん考えて時間をかけて、その性質を明らかにして選ぶか捨てるかを判断しなければなりません。しかし、最近の世の中の様子を見ると、改革者や開化先生と呼ばれる人たちは、口を開けば西洋文明の美しさを称え、一人がそれを唱えればみんながそれに同意し、知識や道徳の教えから国を治めることや経済、衣食住の細かいことまで、みんなが西洋の風を慕ってそれに倣おうとする人がいないです。また、まだ西洋の事情についてほんの一部も知らない人でも、ただ古いものを捨てて新しいものを求めるようです。どうして物事を信じるのが軽々しく、疑うのがおろそかなのでしょうか。西洋の文明は私たちの国よりも優れていると言えますが、決して完全な文明ではありません。その欠点は数えきれません。彼らの風習はすべて美しくて信じるべきではなく、私たちの習慣はすべて醜くて疑うべきではありません。
例えば、ここに一人の子どもがいます。先生に会って心を打たれ、その風に倣おうとしてすぐに考え方を変え、本を買ったり、筆記用具を求めたりして、毎日机に寄りかかって勉強するのはもちろん悪いことではありません。これは美しいことだと言えます。しかし、この子どもが先生の真似をしすぎて、先生が夜遅く話すのに夢中になって朝寝する癖も学んで、とうとう体の健康を害することがあれば、これを賢い人と言えるでしょうか。この子どもは先生を見て完全な学者だと思い、その行動の良し悪しを考えずにすべて真似しようとして、この不幸に陥ったのです。
中国のことわざに、「西施のしかめっ面を真似る」という言葉があります。美しい人のしかめっ面は、そのしかめっ面の中に自然に魅力があるから真似するのですが、先生の朝寝にどんな魅力があるでしょうか。朝寝はただの朝寝で、怠け者で健康に気を使わない悪いことです。人を慕うあまりにその悪いことを真似するのは笑うべきことではないでしょうか。しかし、今の世の中の開化者たちの中には、この子どものような人たちがたくさんいます。
仮に今、東西の風習を比べて、先生たちがそれについて話すことを考えてみます。西洋人は毎日お風呂に入るけど、日本人は一か月に一、二回しか入らないとしたら、先生たちはこう言うでしょう。「文明の国の人たちはよくお風呂に入って、皮膚をきれいにして健康を守るけど、日本人はその大切さが分からない」と。
日本人は寝室に尿瓶を置いて、そこにおしっこをためるし、トイレから出たあと手を洗わないこともある。でも、洋人は夜中でも起きてトイレに行って、何かあったら必ず手を洗います。だから、先生たちはこう言うでしょう。「文明の国の人たちは清潔さを大事にするけど、日本人は汚れたままで、子どものようにまだ物事が分からない。でも、だんだん進んで文明の世界に入れば、きっと西洋の良い習慣を真似するようになるだろう」と。
洋人は鼻をかむときは毎回紙を使ってすぐ捨てるけど、日本人は布を使って洗濯してまた使います。そこで、先生たちはすぐに考えて、細かいことから経済の大切さにつなげて言うでしょう。「お金が少ない国では、人々は無意識に節約する方法を実践している。もし日本中の人々が鼻紙を使うようになったら、国のお金がどれだけ無駄になるか。だから、汚れた布を使い続けるのは、お金が足りないから節約しているんだ」と。
日本の女性は耳に金のピアスをつけて、お腹を締め付けて服を着飾ることがある。そんな時、先生たちは驚いて言うでしょう。「ひどいことだ。文明じゃない国の人たちは、自然に従うことが分からないばかりか、わざわざ体を傷つけて耳に荷物をかけたり、女性の大切なお腹を締め付けてハチのように細くしたりして、妊娠や出産が難しくなる。その結果、家族が不幸になったり、国全体の人口が減ったりする」と。
西洋人は家の中や外で鍵を使わないことが多く、旅行中に荷物を運ぶ人を雇っても、きちんと鍵をかけなくても盗まれない。また、大工や左官のような職人に仕事を頼む時も、約束事を書いた紙を使わずに、後で問題が起こることはめったにありません。でも、日本人は家の中の一部屋ごとに鍵をかけたり、手元の箱にも鍵をかけたりして、仕事の約束事を細かく書いても、それでも物が盗まれたり、契約違反などで裁判所に訴えることが多いです。そんな時、先生たちはため息をついて言うでしょう。「ありがたいキリスト教、かわいそうな異教の国の人々。日本の人たちはまるで泥棒と一緒に住んでいるみたいだ。西洋の自由で正直な風習と比べると全然違う。やっぱりキリスト教の国では道に落ちているものを拾わないって言うんだろう」と。
日本人がタバコを吸って、巻きタバコを使うのに対して、西洋人はパイプを使うなら、「日本人は道具の技術が足りなくてまだパイプを発明できないんだ」と言うでしょう。日本人が靴を履いて、西洋人が下駄を履くことがあれば、「日本人は足の指の使い方が分からないんだ」と言うでしょう。もし味噌が外国から来たものなら、こんなに軽んじられることはなかったでしょう。豆腐も洋人の食卓に出されたら、もっと評価が上がるでしょう。ウナギの蒲焼きや茶碗蒸しなどは、世界一美味しいものとして評判になるはずです。
これらの項目を全部挙げれば、きりがありません。今少し難しい話に進んで、宗教のことについて話しましょう。四〇〇年前、西洋では親鸞上人が生まれ、日本ではマルチン・ルーザが生まれました。上人は西洋の仏教を改革して、浄土真宗を広めました。ルーザは日本のローマ宗教に反対して、プロテスタントの教えを始めました。もしこれがあったら、人々はきっと言います、「宗教の大事な目的は、みんなを救うことで、人を殺すことではありません。この目的を間違えたら、他のことは見る価値がありません。西洋の親鸞上人はこの考えをよく理解して、野原で寝て、石を枕にして、たくさん苦労して、一生懸命働いて、その国の宗教を改革しました。そして今日、その国の人々の大半が教育を受けました。その教育が広がったことはこんなにすごいですが、上人が亡くなった後、その弟子たちは宗教のことで、他の宗教の人を殺したり、殺されたりすることはありませんでした。それは、彼らが宗教の徳を使って人々を教えたからです。日本の状況を見ると、ルーザが世に出てローマの古い教えに反対したけれども、ローマの信者は簡単に新しい教えを受け入れませんでした。古い教えは虎のようで、新しい教えは狼のようで、虎と狼が戦ってお互いに傷つけあいました。ルーザが亡くなった後、宗教のために日本の人々が殺され、日本のお金が使われ、戦争が起こり、国が滅びました。その災いは、筆で書くことも、口で話すこともできません。どんなに残酷なことか、野蛮な日本人は、みんなを救う教えで生き霊を苦しめ、敵を愛する教えで無実の同じ仲間を殺しました。今日、その結果はどうなっているかと問われれば、ルーザの新しい教えはまだ日本の人々の半分を教えることができないと言えます。東洋の宗教と西洋の宗教はこんなに違います。私たちはここで疑問を持って、もう長い間考えていますが、まだその原因がはっきりわかりません。こっそり考えると、日本のキリスト教も西洋の仏教も、その性質は同じですが、野蛮な国で行われると、自然に殺す気持ちが強くなり、文明の国で行われると、自然に優しい風が吹くのかもしれません。それとも、東洋のキリスト教と西洋の仏教は、最初から元々違うものなのかもしれません。それとも、改革の始祖である日本のルーザと西洋の親鸞上人の徳義に優劣があるのかもしれません。安易に浅い見方で決めつけるべきではありません。ただ、後世の賢い人たちの確かな説を待つだけです」と。
だから、今の改革者たちが日本の古い習慣を嫌って、西洋のものを信じることは、決して軽信軽疑の非難を避けられるものではありません。言われているように、古いものを信じる信念で新しいものを信じ、西洋の文明を憧れるあまり、そのしかめっ面や朝寝の癖も学ぶべきだと言います。それどころか、まだ新しいものを信じるべきものを見つけられないのに、早くも古いものを捨てて、自分が空虚なように感じて、安心できる立場を失って、結局は気が狂う人もいます。これは哀れです(医者の話を聞くと、最近は神経病や気が狂う病気の人が多いと言います)。
西洋の文明はもちろん憧れるべきです。これを憧れて、これに倣おうとして、日々足りないと言っても、軽々しく信じることは信じないことよりも劣っています。彼らの豊かさは本当に羨ましいと言えますが、その国の人々の貧富の差が大きいことも、真似するべきではありません。日本の税金は厳しいかもしれませんが、イギリスの貧しい人々が地主に苦しめられる姿を考えると、逆に私たちの農民の状況を祝福しなければなりません。西洋の国々では、女性を大切にする風習は人間の世界の美しいことですが、悪い奥さんが横暴に振る舞って夫を困らせたり、不従順な娘が親を軽んじて恥ずかしい行いをしたりする風習に心酔すべきではありません。
だから、今の日本で行われていることや物事は、本当に今のようにして正しいものなのでしょうか。商売や会社のルールは、今のようにして良いのでしょうか。政府の体裁は、今のようにして良いのでしょうか。教育の制度は、今のようにして良いのでしょうか。本の書き方は、今のようにして良いのでしょうか。それどころか、私たちの学問の方法も、今日のやり方で良いのでしょうか。これを考えると、たくさんの疑問が次々に生じて、まるで暗闇の中で物を探しているようです。この混乱の最中にいて、東洋と西洋の物事を比較して、信じるべきことを信じ、疑うべきことを疑い、取るべきことを取り、捨てるべきことを捨て、信じたり疑ったりする正しい方法を見つけるのは、やはり難しいことではありませんか。
そうなると、今この責任を負う人は、他にはいません。ただ、一種類の私たちの党の学者だけです。学者は努力しなければなりません。しかし、これを考えることは、これを学ぶことと同じくらい大切です。たくさんの本を読み、たくさんの物事に触れ、心を開いて冷静に、目を見張って、真実があるところを求めるなら、信じたり疑ったりすることはすぐに変わって、昨日の信念は今日の疑いになり、今日の疑いは明日解決することもあるでしょう。学者は努力しなければなりません。
十六編
手近く独立を守ること
不覊独立の言葉は最近みんなが話しているけれども、世の中の話にはたくさん間違いもあるから、みんなでその意味をちゃんと理解しないといけません。
独立には二つの種類があります。一つは目に見える形があるもので、もう一つは目に見えないものです。手っ取り早く言うと、物に関する独立と、心に関する独立と、二つに分けられます。
物に関する独立とは、みんながお金を持って、自分の仕事を頑張って、他の人に迷惑をかけないように、自分や家族の面倒を見ることで、簡単に言うと、人から物をもらわないという意味です。
目に見える独立は上のように分かりやすいけれども、目に見えない心の独立になると、その意味は深くて、関係が広くて、独立の意味とは関係ないように思えるけれども、この考え方を大切にして、間違えないようにしなければなりません。細かいことですが、次の例を見て説明しましょう。
「一杯、人、酒を飲み、三杯、酒、人を飲む」ということわざがあります。このことわざを解釈すると、「酒が好きな気持ちで人の本心を支配して、本心が独立できないようにする」という意味です。今日の世の中の人々の様子を見ると、本心を支配するものは酒だけではなく、いろいろな事物があって、本心の独立を邪魔することがたくさんあります。
この服が似合わないからあの羽織を作ったり、この服装がふさわしくないからあの煙草入れを買ったり、服が揃っているのに家が狭くて不便だと思ったり、家が建てられたらパーティーを開かないと困ると思ったり、うなぎご飯が洋食の仲介になったり、洋食が金の時計の手引きになったり、ここからあそこに移ったり、一から一〇に進んだり、どんどん進んで、どこまでも限りがありません。この考え方を見ると、家の中には主人がいないようで、自分の心の中には精神がいないようで、物が人に物を求めさせて、主人は物に支配されて、それに奴隷のように使われると言えます。
それよりもっとひどいことがあります。前の例では、物に支配される人だけれども、その物は自分の物だから、自分や家族の中で奴隷のような境地にいるだけですが、ここには他人の物に使役される例があります。あの人がこの洋服を作ったから私もこれを作ると言い、隣に二階建ての家を建てたから私は三階建てを建てると言い、友達の物が私の買い物の見本になり、同僚のうわさ話が私の注文書の下書きになり、色の黒い大きな男が変な姿で立っているその指に金の指輪は似合わないと自分でも分かっていながら、これも洋風だと言って無理に納得してお金を使い、暑い夕方、お風呂上がりには浴衣と扇子がいいと思うけれども、洋風の真似だから我慢して袖で汗をかき、ひたすら他人の好みに同じようにしようと心配するだけです。他人の好みに合わせることはまだ許せます。それが笑えるほど極端になって、他人の物を間違えて認めて、隣の奥さんがお召し縮緬に純金の簪をつけていると聞いて大変悩んで、急いで私も注文して後でよくよく調べたら、どうやら計画通りではなくて、隣の家の物は綿縮緬に金めっきだったそうです。こんなことでは、自分の本心を支配するものは自分の物でも他人の物でもなく、煙のような夢中の妄想に支配されて、自分と家族の暮らしは妄想の行き来に任せるものと言えます。精神の独立のあり方とはかなり距離があるでしょう。その距離の遠さや近さは、みんなで測るべきものです。
こんな夢中の世渡りで心を痛めて、身を使って、一年で一〇〇〇円の収入も、一か月で一〇〇円の給料も、使い果たしてその後が見えなくて、不幸にして家のお金や収入の道を失ったり、または給料から離れたりすることがあれば、気が抜けたようで、間抜けのようで、家に残るものは無駄な雑物だけで、身に残るものは贅沢の習慣だけです。かわいそうだと言うのはまだおかしくありませんか。お金を増やすのは自分の独立を求める基本だと思って心身を痛めながら、そのお金をどうするか決める時に、逆にお金のために支配されて独立の精神を失ってしまうのは、まさにこれを求める方法でこれを失うものです。私たちは、お金を大切にする人の態度をほめるわけではありませんが、ただお金を使う方法を工夫して、お金を支配してお金に支配されず、一つも精神の独立を害しないようにしたいだけです。
心の考えと働きがちゃんと合っているべき理由
みんなが、議論と実業の両方が大切だと言いますが、それを言うだけで、実際に行動する人はとても少ないです。議論とは、心で考えたことを言葉や文章で表すことです。まだ言葉や文章にしなくても、その人の心の中で考えていることを「心事」とか「志」と言います。だから、議論は外の物と関係ないと言えます。結局、心の中にあるもので、自由で、制限がないものです。実業とは、心で考えたことを外に出して、外の物に触れて何かをすることです。だから、実業には必ず制限があり、外の物に制限されて自由ではないものです。昔の人がこの二つを区別する時に、「言」と「行」や「志」と「功」と言ったりします。また、今日の俗語で言うところの「説」と「働き」も、これと同じです。
言と行が合わないとは、議論で言うことと実際に行動することが同じでないということです。「実際の仕事によって物を与えるべきで、その人がどんな風に考えていても形のない心事を賞するべきではない」という意味です。また、世間で、「あの人の説はいいけど、元々働かない人だ」と言って軽蔑することがあります。どちらも、議論と実業がちゃんと合わないことを問題にしています。
だから、この議論と実業はちょっとも違わないように正しく平均しなければならないものです。今、初めて学ぶ人が分かりやすくするために、人の心事と働きという二つの言葉を使って、お互いに助け合って平均を作り、人間の利益を生み出す理由と、この平均を失って起こる弊害を話します。
第一 人の働きには、大きさや重さが違います。芝居も人の働きですし、学問も人の働きです。人力車を引くことも、蒸気船を運用することも、農業をすることも、文章を書くことも、みんな人の働きです。でも、役者になるのではなくて学者になりたがり、車を引く仲間に入らずに航海の術を学び、農業の仕事に不満足で文章の仕事をする人は、働きの大きさや重さを見分けて、小さいものを捨てて大きいものに従う人です。人間の美しいことだと言えます。そんな風に、これを見分けるものは何でしょうか。その人自身の心です、また志です。こんな心や志がある人を「心事が高尚な人物」と言います。だから、人の心事は高尚でなければならず、心事が高尚でなければ働きも高尚になれません。
第二 人の働きは、難しさに関係なく、役に立つものが大きいものと小さいものがあります。囲碁や将棋などの技芸も簡単なことではありません。これらの技芸を研究して工夫を凝らす難しさは、天文学や地理学や機械や数学などの色々なことと変わりません。でも、役に立つ大きさに関しては、元々同じようなものではありません。今、役に立つかどうかを見て、役に立つ方に尽力する人は、心事が明らかな人物です。だから、心事が明らかでなければ、人の働きを無駄にして労力を使い果たすことがあります。
第三 人の働きには、ルールが必要です。働く時に場所や時期を考えなければなりません。例えば、道徳の話はありがたいけれど、宴会の最中に突然それを言うと、ただ人に笑われるだけです。学生の激しい議論も、時には面白くないことはありませんが、親戚の子供たちの集まりでそれを聞くと、変な人だと言われます。この場所や時期を見分けてルールを作るのは、心事が明らかな人です。人の働きが活発だけで賢くないと、蒸気機関がないようなもので、船にかじがないようなものです。ただ利益を出さないだけでなく、逆に害を与えることが多いです。
第四 前の項目では、人に働きがあって心事が行き届かない弊害を話しましたが、今度は逆に、心事だけが高尚で遠大で実際の働きがない場合も、とても困ることです。心事が高くて働きが足りない人は、いつも不平を感じることになります。世間を見て仕事を探す時、自分ができることは全部自分の心事より下のことだから、それに従事するのが嫌で、でも自分の心事を強くしたいけれど実際の働きが足りなくて仕事に当たれません。そこで、その罪を自分に責めずに他を責めたり、「運が悪い」と言ったり、「運命が届かない」と言ったりします。まるで天地の間にやるべき仕事がないかのように思い込んで、ただ悩んでばかりいます。口に文句を言って、顔に不平を表して、周りの人を敵だと思い、世の中が冷たいと感じます。その心の中を表現すると、金を貸さないのに返金が遅いことを怒るようなものです。
儒者は自分を知る人がいないことを心配し、書生は自分を助ける人がいないことを心配し、役人は立身の手がかりがないことを心配し、町人は商売がうまくいかないことを心配し、廃藩の士族は生計の道がないことを心配し、非役の華族は自分を敬する人がいないことを心配し、朝から晩まで心配があって楽しいことがありません。今日の世間にはこのような不満がたくさんあることがわかります。その証拠を得たいなら、普段の交流の中でよく人の顔色を見て知るべきです。言葉や態度が活発で、心の喜びが外にあふれるような人は、世の中にはとても珍しいです。私たちの実験では、いつも人が心配しているのを見て、喜んでいるのを見ません。その顔を借りたら、不幸なお見舞いなどがとても良いと思われるものが多いですが、気の毒な状況ではありません。もしこれらの人たちがそれぞれの仕事に励むことができれば、自然に活発な仕事の楽しさを得て、だんだんと事業が進んでいくはずです。そして、心の悩みと仕事のバランスが取れる場合もあるでしょう。しかし、ここでは気にせず、仕事のレベルは一で、心の悩みのレベルは一〇で止まり、一で一〇を望み、一〇で一〇〇を求め、これを求めて得られないで無駄に心配を買う人と言えます。これは石の地蔵に飛脚の魂を入れたようなもので、中風の患者に神経の敏捷を増したようなものです。その不満や不満足は推測してわかるでしょう。
また、心が高尚で仕事が少ない人は、人に嫌われて孤立することがあります。自分の仕事と他人の仕事を比べれば、当然及ぶべきではありませんが、自分の心の悩みを持って他の仕事を見ると、それに満足できず、自分でこっそり軽蔑の気持ちを持たずにはいられません。無分別に人を軽蔑する人は、必ずまた人から軽蔑されることが免れません。お互いに不満を持ち、お互いに軽蔑し合って、最後には変わり者や奇妙なものの笑いものになり、世間で立つことができなくなるものです。今日の世の中を見ると、傲慢で不遜で人に嫌われる人がいたり、人に勝とうとして人に嫌われる人がいたり、人に多くを求めて人に嫌われる人がいたり、人を誹謗して人に嫌われる人がいます。どれもみんな、人と比べるところを失って、自分の高尚な心の悩みを目標にして、それに照らして他の仕事を見て、その時に恍惚な想像を作り、人に嫌われる端を開いて、最後に自分で人を避けて一人で孤立した苦しい世界に陥る人です。試しに言いますが、後進の若い人たち、人の仕事を見て心に不満足だと思ったら、自分でその仕事をやってみるべきです。人の商売を見て下手だと思ったら、自分でその商売に当たってみるべきです。隣の家の家庭を見て管理が悪いと思ったら、自分でそれを自分の家で試すべきです。人の本を評価したいなら、自分で筆を持って本を書くべきです。学者を評価したいなら学者になるべきです。医者を評価したいなら医者になるべきです。大きなことから小さなことまで、他人の仕事に口を出したいなら、試しに自分をその仕事の立場に置いてみるべきです。もしその職業が全く違うものなら、その仕事の難易度や軽重をよく考えて、違う種類の仕事でもただ働きと働きを比べるだけで大きな間違いはないでしょう。
十七編
人望について
たくさんの人が見て、たくさんの人が指さして、「あの人はすごく頼りになる人ですね、信頼できる人物です。この仕事を任せてもきっと成功するでしょう」と、その人の性格を信じてみんなから期待される人を、人望がある人物と言います。人間の世界では、人望の大きさや軽重はありますが、せめて人に信じられる人でなければ、何の役にも立ちません。小さい例で言えば、一〇円を持たせて町へ行かせる人も、一〇円だけの人望があり、一〇円だけは人に信じられる人物です。一〇円より一〇〇〇円、一〇〇〇円より一〇〇〇〇円、一〇〇〇〇〇〇円、そして何百万円ものお金を集めた銀行の支配人になり、または一つの県や府の長官になって、ただお金を預かるだけでなく、人々の便利・不便を預かり、その貧富を預かり、その栄誉・恥辱をも預かることがある人は、そんな大きな仕事をする人は、普段から人望を得て、人に信じられる人でなければ、とても仕事を成功させることは難しいです。
人を信じないのは、その人を疑っているからです。人を疑うと、どこまでも疑いが広がります。目付けに目をつけるために目付けを置き、監察を監察するために監察を命じ、結局何の取り締まりにもならず、ただ人の気持ちを傷つける奇妙な話は、昔から今までたくさんあります。また、三井・大丸の商品は正札で大丈夫だからと言って、品質を確かめずに買ったり、馬琴の作品だから面白いに違いないと、タイトルだけを聞いて注文する人がたくさんいます。だから、三井・大丸の店はますます繁盛し、馬琴の著書はますます流行して、商売や執筆にとても都合が良いことがあります。人望を得ることの大切さを知るべきです。
「一六貫目の力がある人に一六貫目の物を任せ、一〇〇〇円の身代がある人に一〇〇〇円の金を貸すべし」と言うときは、人望も栄名もいらないで、ただ実物を信じて仕事をするようですが、世の中の人間関係はそんなに簡単で淡白なものではありません。一六貫目の力がない人でも座って数百万貫の物を動かすべし、一〇〇〇円の身代がない人でも数十万のお金を運用すべし。たとえば今、お金持ちで有名な商人の会計所に飛び込んで、一度に全部の帳簿を精算してみれば、出入りの差引きで何百何千円も足りない人がいるでしょう。この足りない分は、身代が〇円以下の足りなさだから、無一文の乞食より何百何千も劣るけれど、世間の人々がこれを乞食のように見ないのはなぜでしょう。それは、この商人に人望があるからです。だから、人望はもともと力量だけで得られるものではなく、またお金持ちだけで得られるものでもなく、その人の活発な才能と正直な心の徳義を積み重ねて得られるものです。
人望は智徳に属することが当然で、そうあるべきだと思われますが、世界中の古今の事実では、時々その反対のことが見られます。藪医者が玄関を広くして大繁盛し、売薬師が看板を金で作って大いに売り広め、山師の会計所に空っぽの金箱を置き、学者の書斎に読めない原書を飾り、人力車の中で新聞を読んで家に帰って昼寝をする人がいます。日曜日の午後に教会で泣いて、月曜日の朝に夫婦喧嘩する人がいます。どんどん広がる世界、真偽が入り混じり、善悪が混ざり合い、どれを正しくてどれを間違いとすべきか分からない。とてもひどい場合には、人望があるところを見て、本人の無知・無徳を占うべき人がいないわけではありません。ここで、少し見識の高い士君子は世間の栄誉を求めず、それを浮世の虚名だと思って、わざわざ避ける人もいて、それは無理もないことです。士君子の心構えにおいて、ほめるべき一つの考え方と言えます。
そうは言っても、どんな世の中の事物でも、極端な一方だけを論じれば弊害がないわけではありません。あの士君子が世間の栄誉を求めないのは大いにほめられるようですが、それを求めるか求めないかを決める前に、まず栄誉の性質を詳しく知るべきです。その栄誉というものが、本当に虚名の極みで、医者の玄関や売薬師の看板のようなものなら、最初からそれを遠ざけ、避けるべきだと言えますが、一方で社会の人間関係はすべて虚ろで成り立っているわけではありません。人の智徳は花木のようで、その栄誉・人望は花のようです。花木を育てて花を咲かせるのに、わざわざそれを避けることはないでしょう。栄誉の性質を詳しく知らずに、一概にそれを捨てようとするのは、花を払って木の存在を隠すようなものです。これを隠してその役割を増すわけではなく、まるで生き物を死んだもののように使うことと変わらず、世間のためを考えて不便利な大きなものだと言えます。
それでは、栄誉や人望は求めるべきものですか。答えは、そうです。これを求めなければいけません。ただ、それを求めるときには、適切な方法が大事です。心身の力を使って世間の人望を得るのは、米を計って人に渡すようなものです。上手な取りの人は、一〇合の米を一三合に計り出し、下手な人は九合七合に計り込むことがあります。私たちが言う適切な方法とは、計り出しもなく、計り込みもなく、ちょうど一〇合の米を一〇合に計ることです。ます取りには上手・下手があるけれど、それによって生じる差はわずか二、三分だけですが、才徳の力をます取りすると、その差は決して三分だけではなく、上手な人は正味の二倍、三倍にも計り出し、下手な人は半分にも計り込むことがあります。この計り出しの法外な人は、世間に法外な迷惑をかけるので、当然憎いいとされますが、しばらくそれを置いて、今ここでは正味の力を計り込む人のために少し考えてみましょう。
孔子が言った、「君子は自分を知らないことを心配せず、他人を知らないことを心配する」と。この教えは、当時世間で広まっていた悪い習慣を正すために言われたものだと思われますが、後世の無気力な学者は、この言葉をそのまま受け止めて、内向きにばかり考え込んで、その悪い習慣がどんどん増えて、ついには変わった人や無口な人、笑うことも知らず、泣くことも知らない木切れのような男を立派な先生だと称えるようになったのは、人間社会の一つの奇妙な話です。今、このださい習慣を捨てて活発な世界に入り、たくさんのものに触れて広く人々と交流し、他人も自分も理解し、自分の持っている正味の力をしっかり使って、自分のためにも、そして世のためにも役立てようとするには、
第一に、言葉を学ばなければいけません。文字で意思を伝えることは、もちろん有力な方法ですし、文章や執筆などの努力も大切ですが、近くの人と話して、すぐに自分の考えを伝えるには、言葉以外に有力な方法はありません。だから、言葉はできるだけ流暢で活発でなければいけません。最近、世の中に演説会が開かれています。この演説で有益なことを聞くのはもちろん利益ですが、それ以外にも、言葉の流暢さや活発さを身につける利益は、演説者も聞く人も共通です。
また、今日では、言葉が不足している人の話を聞くと、言葉が本当に少なくて不便そうです。例えば、学校の先生が翻訳した本の講義をするとき、「丸い水晶の玉」とあれば、わかりやすいことだと思って、全く説明しないで、ただ難しい顔をして子供たちを睨みつけ、「丸い水晶の玉」と言うだけですが、もし先生が言葉に豊かで表現が上手な人だったら、「丸いとは角がなくて団子のようなもの、水晶とは山から掘り出すガラスのようなもので、甲州などからたくさん出ます。この水晶で作ったごろごろする団子のような玉」と説明して聞かせたら、おばさんも子供も心の底からよくわかるはずです。使える言葉を使わずに不便にするのは、結局演説を学んでいないせいです。
また、ある学生が「日本の言語は不便で、文章も演説もできないから、英語を使って英文を書く」という馬鹿げたことを言う人がいます。考えてみると、この学生は日本で生まれて、まだ十分に日本語を使ったことがない人でしょう。国の言葉は、その国の物事が多いほど、徐々に増えて、全く不自由がないはずです。とにかく、今の日本人は、今の日本語を上手に使って話す力を身につけることを努力しなければいけません。
第二に、顔色や容姿を明るくして、一目見て人に嫌われないようにすることが大切です。肩をすぼめておべっかを使い、巧言令色でごますりをするような態度はもちろん嫌われるべきですが、苦虫を噛んで熊の胆を吸っているような顔や、黙って褒められて笑って損をしたような顔、一年中胸が痛むような顔、一生親の死を悲しむような顔もまた嫌われるべきです。顔色や容姿が活発で楽しいのは、人の徳義の一つであり、人間関係で最も大切なことです。人の顔色は家の門戸のようなもので、広く人々と交流し、客を自由に迎えるためには、まず門戸を開いて入口を掃除し、どんな人でも寄り付きやすくすることが重要です。
しかし今、人と関わろうとして顔色をなごやかにするのに意気込みを使わないだけでなく、逆に偽りの良い人を真似て、わざと厳しい様子を見せるのは、家の入り口に骸骨を下げて、門の前に棺桶を置くようなものです。誰がこんなところに近づきたいと思うでしょうか。世界中でフランスを文明の源と言い、知識が広まる中心と呼ぶのも、国民の態度がいつも元気で気軽で、言葉や態度も親しみやすく近づきやすい雰囲気があるから、その理由の一つだと言えます。
人は言うかもしれません、「言葉や態度は人々の生まれつきのものだから、どうしようもないし、これを議論することは結局無益だけだ」と。この意見は正しいように思えますが、人間の知恵や成長の理由を考えると、それは違うと分かります。人の心の働きは、進めるものと進めないものがありません。それは人の手足を使って筋肉を強くするのと同じです。だから言葉や態度も人の心身の働きなので、これを放っておいて上達する理由はありません。しかし昔から日本の習慣では、この大切な心身の働きを捨てて気にしない人がいるのは、大きな間違いではないでしょうか。だから私たちが望むのは、今日から言葉や態度を学ぶというわけではなく、この働きを人の徳義の一つとして軽視せず、いつも心に留めて忘れないことを願っています。
ある人はまた言います、「態度を良くするとは見かけを飾ることだ。見かけを飾ることが人間関係の要になるとしたら、ただ態度や顔色だけでなく、服装も飾り、食事も飾り、気に入らない客を招待して、自分に合わないご馳走をするようなことは、すべて虚飾で人と関わる悪いことだ」と。この意見も一理あるように思えますが、虚飾は人間関係の悪い点であり、その本質ではありません。物事の悪い点は、その本質に反するものが多いです。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とは、悪い点と本質が相反することを言っている言葉です。例えば食べ物の目的は体を養うことですが、食べ過ぎるとかえって栄養を損なうようなものです。栄養は食べ物の本質であり、食べ過ぎはその悪い点です。悪い点と本質が相反するものだと言えます。
だから人間関係の要は、和やすくて真面目な態度にあるだけです。その虚飾に流されるものは決して人間関係の本質ではありません。一般的に世の中で夫婦や親子ほど親しい人はいませんし、これを天下の最も親しい人と呼びます。この最も親しい人たちの間を支配するのは何かと言えば、ただ和やすくて真面目な心だけです。見かけの虚飾を取り除き、これを払い、これを完全に取り除いて初めて最も親しい人たちが存在するものを見ることができます。だから人間関係の親しさは、真面目な中にあって、虚飾と並んで立つべきではありません。
私たちはもちろん今の人々に対して、その人間関係が親子や夫婦のようになることを望んでいるわけではありませんが、ただその向かうべき方向を示すだけです。今日の世間で人を評価する言葉に、あの人は気軽な人だとか、気にかけない人だとか、遠慮しない人だとか、さっぱりした人だとか、男らしい人だとか、話が多いけれど良い人だとか、騒がしいけれど悪くない人だとか、無口だけど親切そうな人だとか、怖いようだけどあっさりした人だというような言葉は、まさに家族の関係を表して、和やすくて真面目な態度を称えているものです。
第三 「道が違うから一緒に考えない」と言います。世の中の人たちもこの教えを誤解して、学者は学者、医者は医者、少しでも仕事が違うと仲良くしないことがあります。同じ学校やクラスの友達でも、学校を卒業した後で、一人がお店の人になり、一人が役所の人になると、すごく遠く離れてしまい、関係がなくなることがあります。それは本当に間違った考え方です。人と仲良くするためには、昔の友達を忘れないだけでなく、新しい友達も作らないといけません。人類が互いに接しなければ、お互いの気持ちを伝えることができず、気持ちを伝えることができなければ、その人の性格を知ることができません。考えてみてください、世間の立派な人たちが、たまたま出会った人と一生の親友になることがあるでしょうか。一〇人に出会って一人の偶然に当たれば、二〇人に接して二人の偶然を得ることができます。人を知り、人に知られることの始まりは、たくさんこの辺にあって存在するものです。人気や名声などの話は一旦置いて、今日世間で友達が多いことは、便利さにつながらないでしょうか。昔、船で一緒だった人に、今日銀座でばったり会って、お互いに図らず便利なことが起こることがあります。今年お店に行く八百屋さんが、来年奥州街道の宿屋でお腹が痛くなった時に手伝ってくれることもあるでしょう。
人類はたくさんいますが、鬼でもなければ蛇でもなく、わざわざ私たちを傷つけようとする悪い敵はいません。怖がらず、心配事を全部出して、すぐに対応すべきです。だから、仲良くする範囲を広げるためには、この心配事をたくさん持って、色々な才能を持って偏らず、いろいろな方向から人に接することが大切です。学問で接したり、商売で交流したり、絵や書の友達がいたり、碁や将棋の相手がいたり、悪いことでなければ、友達を作る方法はたくさんあります。もし全く才能がない人でも、一緒にご飯を食べたり、お茶を飲んだりするのもいいです。さらに、体が丈夫な人は腕相撲や枕投げ、足相撲も楽しみとして交流の助けになるでしょう。腕相撲と学問は道が違うから一緒に考えないように思えますが、世界は広く、人間の交際はたくさんあって、ちょっとした違いが大きな影響を与えることがあります。人は人を嫌わないでください。
原文:青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)『学問のすすめ』
著:福沢諭吉
翻訳:GPT-4・ふーと
二〇二三年四月一〇日作成
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
