「学校読書調査」について〈勝手に図書館の本を紹介〉
会員のW辺です。
今回は1954年から(株)毎日新聞社と(公財)全国学校図書館協議会が共同で行っている「学校読書調査」について、広島大学図書館で調査する際にはどの資料を見れば良いか?という話題です。
動機
そもそもなぜ調べようと思ったか?という話ですが、端的に言えばライトノベルの代表作を読むためです。
なんだかんだ言って80年代末に"ライトノベル"という言葉が生まれて約30年、前史となるソノラマ文庫や集英社文庫コバルトシリーズ(後にコバルト文庫)が刊行され始めてからは約45年経過し、ジャンルとしても成熟してきて評論も出始めています。
現在では中古書店(例えばBookoff)などに行けば必ずライトノベルの棚があるぐらい、ある程度の作品にはそれほど困難ではなくアクセスできますが、果たして中古書店にある作品=代表作としてよいのかという疑問がつきまとっていました。
例えば大衆音楽だと、指標としてオリコンのランキングが1968年から集計されておりそれなりに信頼できるデータが存在していますが、書籍にはあまりそういうものがありません。書籍取次のトーハンが1990年より自社流通分のデータを公開していますが実売数は書いてない。頼みの綱の『出版指標年報』も広島大学図書館には2012年と2018年版しかない。
ということで、オリコンレベルとまでは行かなくても少なくとも定量的な評価があるものはないかと探していました。そんなとき『コバルト文庫で辿る少女小説変遷史』(嵯峨聖子)を読んでいると、この学校読書調査が引用されているではないですか。
早速資料にあたってみると数字(読者数)まで公開されています。最悪先述の『出版指標年報』のような一般書籍のランキングの中からライトノベルだけを抜き出すことまで考えていたので(その場合”ライトノベル”の定義をどうするかという超難問が……)、”青少年が読んだ本のみ”であることも嬉しい誤算でした。
ただ、問題点もあります。第一に調査期間が毎年5月の1ヶ月間のみであること。さすがに全数(学校)調査までは望みませんが、1年のうち1ヶ月間だけであることは痛い。爆発的な流行が捉えられてない可能性があります。そして、そもそも読書する人数が少ないため統計的に信頼できるデータか怪しいという最大の懸念点が挙げられます(平均して1位が20~30人程度)。ただ、他に当たるデータも見つかってないし論文を執筆するわけでもないので(もし参考にする方がいたらその部分には注意してください)、そこはしょうがないとあきらめてとりあえずこの調査を参考にすることにしました。
ということでずいぶん前置きが長くなりましたが、何を見れば良いか書いていきます。
※本稿では紹介の都合上以下の3つに勝手に分けました。
・第一期(1954~1979年分(第1~25回))
・第二期(1980~1993年分(第26~39回))
・第三期(1994年分~(第40回~))
読書世論調査
学校読書調査のデータは基本的には翌年発行の『読書世論調査』に収録されています。よってこれを参照する場合は発表年と調査年が1年ずれていることに注意してください。
掲載されている内容のうち特に必要としている具体的な本のタイトルについては、小学校4,5,6年、中学校と高校の全学年の男女についてそれぞれが読んだ本の上位おおむね10~20冊程度が載っています。また、基本的にはタイトルのみで作者は載っていないので各自調べて下さい。
もしこの『読書世論調査』が全年度所蔵されていれば一番良いのですが、そういうわけにはいきませんでした。(もし所蔵されていればこの記事は書いていません。)
現在広島大学図書館に所蔵されている巻は1950, 1951, 1953, 1971, 1973, 1988, 1989, 1999年版で、そのうち学校読書調査の結果が載っているのは1971, 1973, 1988, 1989, 1999年版です。(1950, 1951, 1953年版は学校読書調査の調査開始以前なので当然ながら載っていない。)(こことここを参照)
ただ問題があって、1988, 1989年版については教育学部の研究室所蔵なのですが、以前(2017年秋ごろ)に訪ねに行ったときは所在不明だと言われてしまいました。ライトノベルの創世期だけに期待していたのですが残念です。現在の状況はどうか分からないので訪ねて行ってみても良いかも知れませんが、行く価値があるかどうかは個人的には微妙な感じがします。
第一期(1954~1979年分(第1~25回))
第1~25回までは『学校読書調査25年』という書籍にまとまっているので容易に分かります。
ただし初期の頃は調査項目が定まってなかったらしく、第一回は小学生と中学生が男女の別のみで掲載されており、1955~1961年(第2~8回)については高校生の調査の具体的なタイトルが載っていません。また1962年は小中高ともに全ての部が未調査です。
第二期(1980~1993年分(第26~39回))
この時期は何とも不憫なことにあんまり良いデータがありません。参考になるのは主催元の毎日新聞が調査年の秋(集計が終わるタイミング+読書の秋という事でしょう)に載せている概要と総括でしょうか(一般向けの読書世論調査の結果も載ってます)。なので『毎日新聞 縮刷版』で頑張って探してみて下さい。
ただ、新聞の欄が狭いせいか各区分に対して上位5位までのタイトルしか載っていません。
第三期(1994年分~(第40回~))
現在まで続くこの期間の調査結果は、共催の(公財)全国学校図書館協議会が刊行している雑誌『学校図書館』で見ることが出来ます。調査年の秋(11月号)です。
データも充実しており、2010年(第56回)までは各区分上位17冊が、2011年(第57回)からは各区分上位20冊以上のタイトルが掲載されています。
補足(他図書館の利用)
第二期(1980~1993年分(第26~39回))について、どうしても諦めきれないので他の図書館から借りることができる資料がないか調べた所、『読書世論調査』について広島市立図書館からの相互貸借が可能なことが分かりました。広島市立図書館の本は広島大学生は利用者カードなしで一回につき5冊まで借りることができます。実際に私は借りることができたのでほぼ確実でしょう。急ぎの調査ではない方はこちらも検討してみて下さい。
まとめ
どの書籍にどの程度載っているかまとめたものを貼っておきます(2019年末時点)。
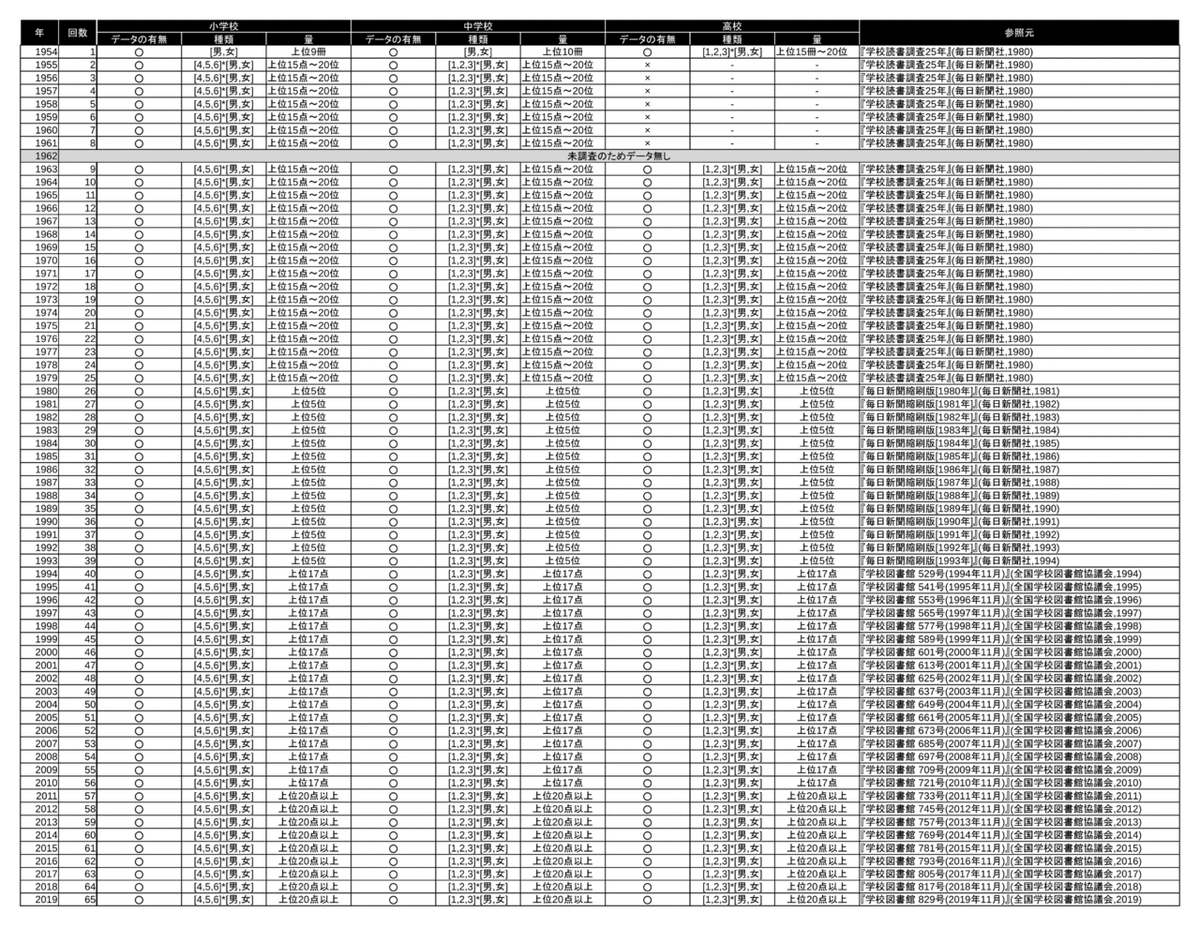
ちなみに中学生が読んだ本でよく出てくる特徴的なものをみると、
1950年代…『怪盗ルパン』『次郎物語』『小公女』『坊ちゃん』など
1960年代…『十五少年漂流記』『シートン動物記』『若草物語』『赤毛のアン』など
1970年代…『シャーロック・ホームズ』『二十四の瞳』『野菊の墓』『伊豆の踊子』など
1980年代…『セーラー服と機関銃』『死者の学園祭』『窓ぎわのトットちゃん』『なんて素敵にジャパネスク』など
1990年代…『ロードス島戦記』『ぼくらの七日間戦争』『もものかんづめ』『創竜伝』など
2000年代…『ハリー・ポッター』『五体不満足』『リアル鬼ごっこ』『恋空』など
2010年代…『謎解きはディナーのあとで』『カゲロウデイズ』『君の名は。』『君の膵臓をたべたい』など
と時代を感じさせ、ライトノベルもちゃんと出ていることが分かります。(恣意的にとりあげた可能性を否定しないので詳しくは自分で調べて下さい。)
ちなみに広島大学図書館所蔵のライトノベルについては項を改めて紹介しようと思っているのでしばらくお待ち下さい。
今回取り上げた書籍(大学図書館へのリンク付き)
・『学校読書調査25年』(毎日新聞社) 中央図書館2階 019.3/M
・『毎日新聞 縮刷版』(毎日新聞社) 中央図書館書庫・雑誌
・雑誌『学校図書館』(全国学校図書館協議会) 中央図書館1階・雑誌コーナー/3階
・『出版指標年報』(全国出版協会出版科学研究所) 中央図書館1階・参考図書/2階
・『読書世論調査』(毎日新聞社) 中央図書館書庫・雑誌 / 教教育学部・教育学 019.3/4
・『コバルト文庫で辿る少女小説変遷史』(嵯峨聖子) 西図書館2階・開架 910.26/Sa-15
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
