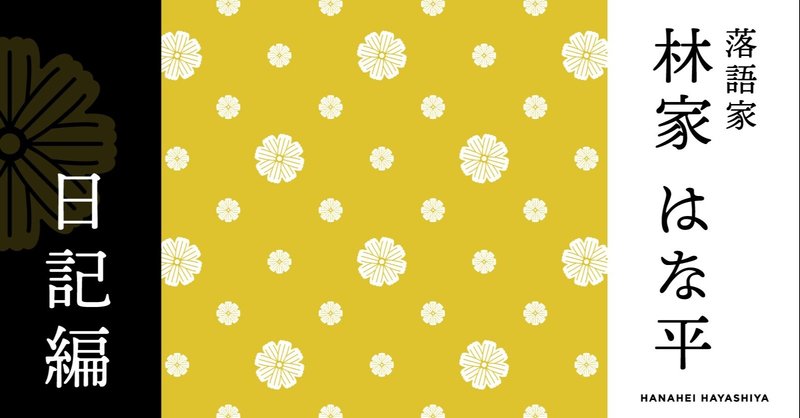
大学の講義を終えて
春学期に城西国際大学で「古典芸能研究」という授業をやらせて頂きました。名前は堅いですが、内容は全部「落語」です。
落語のことについてひたすら12コマ(90分ずつ)話しました。
コロナの影響で、大学に行くことが出来ないので、会議ソフトを使ったリモート授業でした。最初の頃は5月までリモートで、6、7月からは対面になる予定でしたが、5月の終わりくらいの大学の決断で、春学期は全てリモート授業になりました。
結果的にはこの判断は大正解ですね。今の状況ではなかなか授業は難しいです。
本来は15回あった授業を、12回に減らしたので、最後にやりたかった体験してみるというところまでは行きませんでしたが、概ね「落語」というものを理解してもらえたような気がします。
60人くらいの生徒がいるんですが、そのほとんどは落語を知らない(テレビでチラッと見たことがある)子達でしたが、最終的には落語の奥深さを分かってもらえたかと思います。
落語入門的な話は最初の二回くらいで終わって、後はひたすら僕がYouTubeに限定で落語の動画を上げて、それを見てもらって解説をするという流れでした。
落語って、知ると面白いところがいくつもあって、江戸の時間、お金の価値、吉原、芝居噺、怪談噺、人情噺、季節の噺、滑稽噺、小噺、取り上げるとテーマがいくつも出てきます。
毎回学生からの質問も新鮮で、大学生ならではの面白い質問もありました。
学生が疑問に思っている事は、これから落語を教えていく上でとても良い資料になったし、これからの落語にも役立つと思います。
「コロナ後に落語はどうあるべきか?」
という課題を最後に出しましたが、これに対する回答もとても良いものがたくさんありました。こういう質問には正解も不正解もないので、聞いていてワクワクします。
最後にみんなに伝えた事は、「とにかく考えて生きること。」です。考えて生きればこれからどんなことがあっても乗り切っていける。
僕もそうありたいですね。
落語について、また過去の思い出等を書かせて頂いて、落語の世界に少しでも興味を持ってもらえるような記事を目指しております。もしよろしければサポートお願いいたします。
