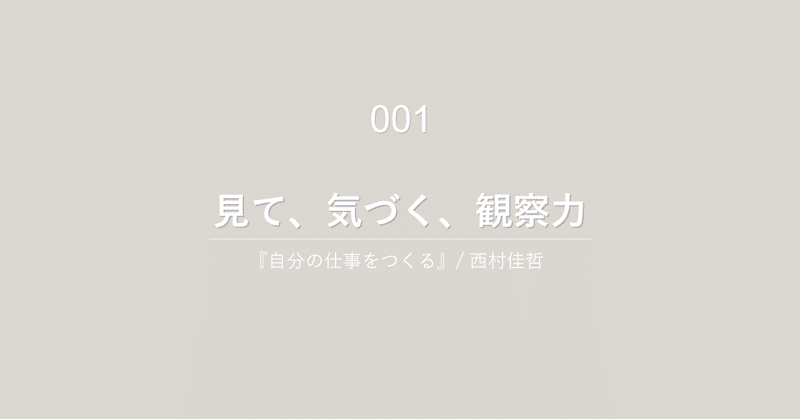
001 見て、気づく、観察力
どうも、シタシマです.昨日初noteを投稿をしたわけですが、さっそく一部の方が見てくださっているようで恐れ多いです.ありがとうございます.
さらに驚いたことに、件のブログがきっかけでnoteを始めたのがぼくだけではなかったということが判明しまして、SNSのすごさを肌で感じました.もしかしたら肩に力入れたほうが良いかもしれませんね.
前置き長いですね、今日から本格的に投稿していきます.
以前、『自分の仕事をつくる』という西村佳哲氏の本を読みました.著者が様々な人の働く現場を取材し、その働き方を探るというものなのですが、その1人目である八木保氏への取材の中で興味深いことが書いてあったので紹介します.
ぼくがその部分を読んで共有したいのは「観察力が創作に直結する」ということです.本書ではイヌイットが雪を示す言葉を100種類も持っているという例が示されていました.イヌイットと日本人のぼくらでは雪に対する感受性が全く異なっており、イヌイットの人々は雪のあらゆる要素を注意深くみて分類しているそうなのです.
ではなんのためにここまで言葉を分ける必要があるのか.それは彼らが環境に適した生活行為を営むために、その環境を見分けることが欠かせなかったからです.ここに、「何かを行うために観察する」という関係が成立します.
実はこれがあらゆる創作活動に言えるのです.すなわち、何かをつくるためには徹底的に対象を観察する必要があるのです.例えばリンゴを描くのに赤色を使う際、それが紫ががっているのか、緑や黄色も交じっているのか、をじっくり見ないと実物に近いリンゴにはなりません.
このように、なにかをつくろうと思ったら徹底的に対象を見て、気づきくことが欠かせないというのがこの本を読んで納得したことです.
著者の西村氏は、本書で
模倣は基本的な上達法だが、そのポイントはまず観察を通したイメージの向上にある.本人の「解像度の高さ」が、その人のアウトプットの質を決める.
と述べています.心にとどめておくべきフレーズだと思いました.
本書では、八木氏のほかにも、象設計集団や柳宗理氏といった様々な方に取材をしており、働き方について色々なことを考えさせてくれます.これから働くぼくにとって大事な1冊です.
今日はこんな感じで終えたいと思います.
ではまた.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
