
第76回はでらCS ヒストリック職工リーグ参加記
初代・職工リーグチャンピオン、はれのちしとどです。
よろしくお願いします。
※本記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。
題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。
©Wizards of the Coast LLC.
はじめに
さて、先日まで私は『ヒストリック職工リーグ』なるオンラインイベントに参加していました。Discordの『はでらMTGサーバー』で開催されたMTGアリーナを使用した対戦会です。
※詳しくは、はでらCSを含む『MOATランキング』を参照されたし。
イベントの内容は、集まった28名の参加者が各4~5名の6ブロックに分かれて、それぞれにて予選の総当たり戦を行った後に、成績優秀者6名による頂上決戦をやろうというもの。
予選・決勝ともに開催期間である2週間のうちに、「調整さん」を用いて他の参加者と予定の合うところを探して自分のペースで戦えばよかったので、「開催が特定の曜日に固定だから、いつも参加できな~い!」といった問題が起こりづらかったり、1日の対戦量も調節が効いたのが大変な利点だと思いました。
逆になかなか予定が合わないと自分だけ過密スケジュールにならざるを得なかったりもするので、自分のスタイルに合うイベント選択も大事。
今回のリーグ戦では、フォーマットに「ヒストリック職工(HistoricArtisan)※」が指定されており、通常の構築戦では味わえないゲーム感を求めて、仲間と練習に励んだ者・独り入念に研究を重ねた者・瞬間の発想にすべてをゆだねた者、様々なプレイヤーが集い、鎬を削ったのでした。
※ヒストリック職工(HistoricArtisan)・・・アンコモンとコモンのみで60枚構築を行うフォーマット。
優勝した
長々と前置きをしましたが、結果を先に申し上げると優勝しました。
冒頭にも書きましたが、改めて。初代・職工リーグチャンピオンです。
なので、この度は使用したデッキ、延いては各採用カードを肴に思い出話に花を咲かせようと思います。そういう回です。
まずはデッキの全容を見よ。

青の呪文を中心に軽量のインスタントを大量投入し、常に除去・打ち消し・ドロー・サイクリングの選択肢があるように振る舞いながら、「墓地のインスタントやソーサリーの枚数だけコストが軽減する」を共通項とした大型生物の展開をするりと狙う。
そう、みなさんご存じの【イゼット・テラー】と呼ばれる型のデッキです。
※他の参加者のデッキは、MTGMELEEの大会ページで公開されているので、こちらも必見。
今回はそこに『エルドレインの森』からの新カード、《豆の木をのぼれ》を採用するためのタッチカラーを行い、継戦能力を得ることを目指しました。見てのとおり、デッキ調整中にタッチ豆の木では済まないてんやわんやの大騒ぎになったのですが、それについては採用カード各位について触れながらお話を致します。
戦績
予選(総当たり)
2-1 vs.黒緑サクリファイス
2-1 vs.黒単バーン
2-1 vs.黒緑フード(トゥック型)
決勝(シングルエリミネーション)
2-1 vs.黒緑ミッドレンジ(動物園型)
2-0 vs.白黒サクリファイス
2-1 vs.黒単アグロ(ナズグル型)
肴

《トレイリアの恐怖》
Pauper※でも愛用している、語るまでもない最強格のクリーチャー。
これと《豆の木をのぼれ》の相性がバツグンに良いのが今回のデッキの発端なので、まさしく勝利の片棒を担いでいる。
※Pauper・・・コモンのみで行う60枚構築戦。
盤面をコントロールするための呪文が、即ちコストの軽減であり、護法や高いタフネスによる耐性も助けて、着地後の対処が非常に困難。コモンのくせに貫禄がありすぎる。
大体1マナで出てくれるし、パワー5なのが良い。4回殴れば20点なので算数が苦手でも、疲れた頭でもダメージ計算が容易である。たすかる。

《かまどの精》
お豆の次元・エルドレインからやってきた、自称・テラー。
このカードがあるから青+赤をベースにしたので次男。
長男と比べると、護法を捨ててサイズを下げた代わりにマナ総量が1だけ軽い。実際、これに何度か助けられたので、この「されど1マナ」が最大の差別点かもしれない。沁みる。
「出来事」の方は、《豆の木》を設置した後であれば無理して使うほどではなく、赤マナが不足している状況では即座に本体を戦列に加える方が大抵の場合は正解だったと思う。手札が土地まみれで最後のリソースがこれなら「出来事」を経由した方が若干美味しい、程度に考えてプレイしていました。
ただ、パワー4なので算数ができなくなる恐れがある。偶数・・・?

《謎めいた海蛇》
三男。アモンケット・リマスターからの刺客。
どんなにがんばっても青マナを2つ要求するのが如何にも末っ子である。
実際、青マナを余計に寝せるという行為は、唱えるに際しての隙も大きくなるし、対戦相手の心理的負担も軽減されるので、Pauper※においても採用枚数を減らされることが多い。今回も2枚まで減らした。
サイズがデカいかわりに除去耐性は皆無であり、アンコモンの除去が跳梁跋扈する職工環境では赤子のように手を捻られ、スペルに囲まれて墓地で寝かせつけられるのが関の山である。バブゥ。
※統率者マスターズで突然コモン収録されてPauperデビューを果たした。
ただし、今回の構築においてはこの2枚採用がデッキ内の流動枠を担っており、個人的にはサイドボードの指針を立てやすくなる良いきっかけになったので、なんだかんだで思い入れのあるカード。

《豆の木をのぼれ》
エルドレインの森から天を貫くトップアンコモン。
テラーにオマケを付けて息切れを防止するのが目的であり、テラーと並んで今回のデッキを構想させたもう片方。
このカードのおかげで、盤面のコントロールから軽くなったクリーチャーを召喚する動きの中に自然なかたちで手札の補充が挟まり、召喚後に攻撃を通すための除去や、追加のクリーチャーを引き込んで一気に攻勢に転じることができる。
また、大型生物のみならず《ロリアンの発見》にも効果が適用されるため、一気に4、5枚のカードを引いて干上がった手札を潤す場面もしばしば。
このドロー性能の高さから、複数枚設置してしまうと逆に手札が溢れたり、ライブラリーアウトを助けてしまうことが危惧されたので、調整中に採用枚数を3つに減らした背景もあります。
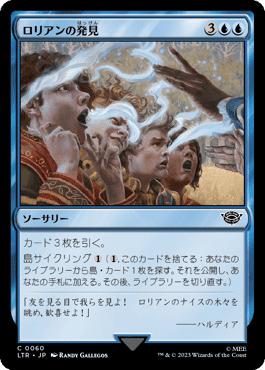
《ロリアンの発見》
こちらも言わずと知れた、『指輪物語』のトップコモン。
サイクル中で唯一の非・クリーチャーであり、島であるカードを探しながら墓地にソーサリーを送り込める。
今回はこれを最大限に活用して、氷雪2色土地にアクセスすることで、適宜黒・赤・緑から必要な色を用意することにしました。もちろん、《冠雪の島》も対象になるのでアンタップインの土地を補充することも可能。
いざ使ってみると、サイクリングすべき場面か否か、どの土地をサーチすべきか、温存してカードを引くべきか、1枚で多くの判断を迫られるカードであり、常にゲームの岐路にある難しい存在に思えてきました。
解決するには、練習量でパターンを身体に覚えさせるしか在らず、私はスパーキー師匠に無限の組手を願い出て、師匠はそれを涼しい顔で承諾したのでした。

《考慮》《選択》
今回のデッキにおいて、私がなにか構えている素振りを見せたら大体この2枚。「打ち消しかも知れない・・・」と一瞬でも対戦相手の脳裏によぎれば勝ちであり、そのロスを用いて有効牌を探しながら、墓地を肥やし、フィニッシャーへ繋ぐ。基本にして全て。
ちなみに両方が同時に手札にある場合は、より墓地にスペルを落とせる可能性がある《考慮》を優先して打ちます。

《消えゆく希望》《霜噛み》
1マナのクリーチャー除去として採用した2種類。
追加コストによって1マナでも高い火力を出すことのできる呪文はいくつか存在していますが、このデッキにはそのコストに充てられるものがないため、氷雪土地を揃えるだけで良い《霜噛み》を採用しています。
ただ、初動を青赤土地のタップインに限定されると、その後に《豆の木》の設置が遅くなるなどのデメリットが発生するため、青緑タップインの際などにおける青1マナでの行動パターンを増やすために《消えゆく希望》をより優先して枚数を取りました。
立ち上がりの色を揃えることで土地のバランスも決まりやすくなり、デッキの安定感が増すなどの効果も狙っています。

《雷猛竜の襲撃》
こちらはゲームの中~終盤で活躍した除去札。
正直、初期の構築では完全に存在を忘れており、やはりイゼットでは巨大生物に対処できないのかと頭を悩ませていたところ、気晴らしにやっていた別のデッキ構築にて発見し、狂喜3くらいした。
使ってみると追放除去なのもズルい。
こんなもんチートだ、チート。シェフを呼べ。

《羅利骨灰》
過去に私は、同『はでらMTGサーバー』で開催された職工イベントにおいて、《オケチラの碑》を利用して盤面をガチャガチャするデッキを披露したことがあります。それでなくても、職工環境には《ザンダーの目覚め》などの厄介極まりない置物がいくつも存在するし、盤面をコントロールするうえで継続的にアドバンテージを得続けるカードの存在など許してはいけない。
なので、メインから割れるようにしました。
どうせ《豆の木》を採用するなら、と甘く見積もったのか、せっかくならキッカーして万能除去になるところまで味わいたい、という心理が働いたのか。気が付いたら黒マナまで出るように調整しており、今思えばデッキがてんやわんやし始めた元凶だと思う。
あ、つよかったです。

《表現の反復》
パイオニアとレガシーの禁止カードが弱いわけないよ。
使っていい環境で、使える色をやるなら、使わない理由なんてない。
3枚掘って2枚選べることによる安定感は健在であり、状況に応じて土地を2枚確保するなどの動きすら可能。2マナのソーサリーであり、土地が置けない&マナが浮かない状況では大したアドバンテージを稼げないため有効に使えるレンジはやや遅めではあるものの、持久力にも爆発力にも繋がるカードパワーがあっては、やはり4枚採用せざるを得なかった。
所感ですが、このカードも《ロリアンの発見》と同じく、打ちどころと確保するカードの理解に練習が必須。

《ガンダルフの制裁》
《雷猛竜の襲撃》と同じ条件下で強くなるクリーチャー除去であり、更に「余剰のダメージは、代わりにそのクリーチャーのコントローラーが受ける」という一撃必殺にもなり得るすばらしい効果を持つ1枚。
如何にテラーを始めとした大型の強力なクリーチャーを展開するとは言え、トークンを主体とするような小粒を並べるデッキ相手では、大量に用意したブロッカーによって毎ターンのアタックを容易にしのがれてしまうと予想し、それを逆手に取って致命傷を与え得ると信じてこのカードの採用へと至ったが、その実、そのような相手は大体これの対象を生け贄に捧げて回避してしまう手段を持っていたのである。
トランプルとは違い、こちらは対象がいなくなればしっかり不適正で立ち消える。当然プレイヤーへのダメージもない。
この一撃でゲームが決まるような最終盤では特に準備は万端であり、今回のマッチングの都合もあると思うが、基本的には3マナ寝かせてソーサリータイミングで打ちたい相手はいないと学びました。
サイド
ここからサイドボードのカードについても触れていきます。
おじさんは話が長いんで、休みやすみどうぞ。

《否認》《呪文貫き》
正直、《ガンダルフの制裁》のかわりにメイン採用で良かった、と後悔するくらいサイドからの採用率も高く、刺さった場面も多かった。
なくてもブラフは成立するけど、あった方がより警戒されるよ。

《エレヒの石》
黒いサクリファイス系のデッキとマッチすることが多く、最多サイドイン賞を獲得してやまない『指輪物語』原産の墓地対策。クリーチャー限定ながらやっていることは《虚空の力線》であり、戦場から墓地に送られることによる誘発もシャットダウンできるので、これ1枚で機能不全に陥るデッキは多い。
かく言う、私の【イゼット・テラー】も《エレヒの石》が持つ第2の能力によって墓地を一掃されてしまうと、大きく展開の速度を落とすことになるため、機を見て割るか、相手に起動したいと思わせてしまうかの駆け引きが重要になりました。
最悪、テラーを7マナで唱えるハメになっても、こちらはただの【イゼット・コントロール】として振る舞ったとも考えられるので、致命的なシステムエラーが発生しない点は救い。

《チェイナーの布告》
いつの間にかアリーナに存在していた「フラッシュバック」付きの布告系除去で、今回は【呪禁オーラ】系のデッキと、自分と同型である【テラー】系のデッキを睨んでサイドに大量投入しました。対処しないといけない生物が多いタイプのデッキに対しても、除去の枚数を稼げるという点で非常に有効でした。
メインボードの《羅利骨灰》が影響してすでに黒マナは出すつもりになっているので、当たり前にサイドに黒いカードを採用していますが、「フラッシュバック」がダブルシンボルであることは忘れがちなので、練習中にはよくプレイングミスを誘発していました。心に刻め。

《自然に帰れ》
エンチャントでガチャガチャするタイプのデッキへの特効薬。命令形なのが良い。帰れ、自然に帰れ。そなたは美しい。
実際、《ザンダーの目覚め》と《秘密の備蓄品》が同時に並べられるチャンプ・ブロックがキツめのマッチングでは早く引きたかったので、採用枚数については再考の余地あり(※引けてない)
【呪禁オーラ】に対しては打ち消し・ドロースペルと併用して、構えていることの違和感を消すことで有効になる場面が増えると思われる。今回は一度も当たっていません。

《ストームケルドの先兵》
サイドボード紹介も最後になるカードは、またしても最新セット・エルドレインの森からの参戦。
ソーサリーであることで唱えるタイミングへのケアが増えますが、本体のクリーチャーが持つ能力によって、これをサイドインしたい置き物系デッキの生成する小粒のチャンプ・ブロッカーども風情ではブロックされない強烈なフィニッシャー性に惹かれて採用しました。
実際に使用してみて、そのフィニッシャー性能は目を見張るものがあり、テラーに加えてこのデカブツにも対処しないといけないのか、という状況は対戦相手の戦意を減退させるのに十分だと感じました。今後の活躍にも期待。
ただし、《チェイナーの布告》と同様に、こちらの本体もダブルシンボルとなっておりますので、採用する際にはデッキのマナベースと十分に相談が必要になります。
おわりに
私にとって今回の『職工リーグ』は、ひさしぶりに「勝つことを見据えてイチからデッキを組み、それに楽しさを覚えていく」という経験になりました。自分が試行錯誤したものが本気でぶつかりあえる相手がいる、というのは幸せですね。
対戦相手のみなさま、この場を作ってくださった葉寺さん、調整に付き合ってくださったエニィ・ターゲットさん、サンドバッグスパーキー師匠、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
