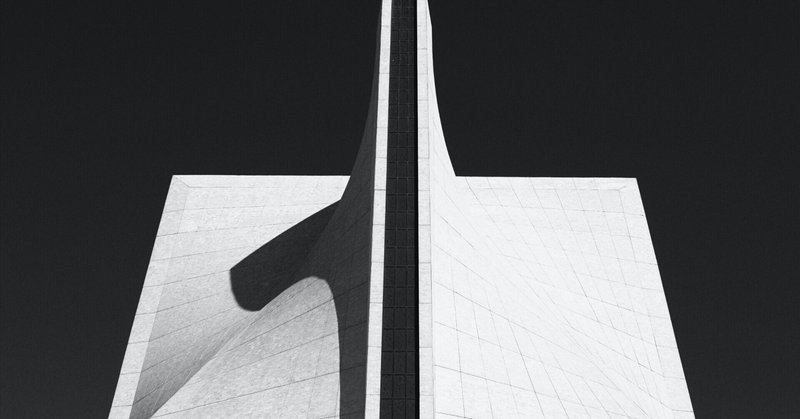
アメリカン・フィクション
2024/3/14
ほめです。
物語を作るということにおいてリアル、とはなんでしょうか。
本作では、皮肉や批判も逆に受け取られて称賛されたり、
一方でありのままでいることが受け入れられなかったりと、
現実で容易に起こり得ることが露悪的に散りばめられています。
その構造をわかりやすく提示するための黒人と白人の比較ですが、
その中で”売れる”ということとやりたいことの差異が大きいモンクが、
頭の中で空想の人物に会話させるだけ、と卑下する作品づくりで苦悩し思いもよらぬ結果を生む流れは、
ラストの展開でレイヤーが変わり、それ自体作品だったというメタの多重構造でした。
すると、今まで見てきた登場人物が途端に役者が演じているだけに思えるのが不思議で、
こうなるのではないかとか、ああなっているのではないか、といった感想そのものが、
君たちの感性に合わせてチューニングされた物語に過ぎないんだよね、お疲れ様でした、
みたいな皮肉を叩きつけられるかのような印象を受けたんですよね。
そうなってくると、もはや流れる音楽、名曲の数々もこういうのが好きなんでしょう?と言われているかのようで、
フラットに見ることができなくなってしまうというあまりにもあまりな作り。
Autumn Leavesが一周回って嫌味に聞こえてしまうのが恐ろしい。
モンクという人自体、白人の感性を馬鹿にしつつも、黒人のことを一番見下しているような人ですし、
歯に衣着せぬ物言いや権威をこき下ろせるチャンスには瞬間的に飛びつくような、
ある意味典型的なヒネた人間であるわけです。
人の気持が理解できないことは名誉でもなんでもないとの指摘通りであり、
フィクションであればキャラクターとして愛せますが、
ノンフィクションでこの人と付き合いたくはない。
そんな彼が嫌味の塊として書いた作品が認められ狂騒を生む様は、
作家の人間性と作品自体にはなんの関係もないということがよく分かります。
作品を見て同一視するべきではないといいますか。
別れがあれば出会いもある。
疎遠だった家族との交流、老いや死、出会いと別れといった人の営みを描く一方で、
面倒な展開でしかなかった小説を巡る悲喜こもごもは、
結局テンプレ通りの分かりやすいオチが喜ばれるんですよというこれまた皮肉。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
