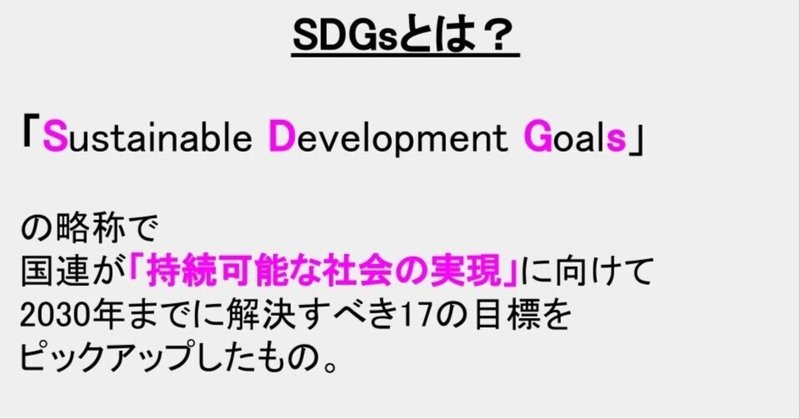
SDGs浸透に建築の木造化・木質化が貢献できる理由
SDGs(エスディージーズ)とは「Sustainable Development Goals」の略称で、国連が持続可能な社会の実現に向けて2030年までに解決すべき17の目標をピックアップしたものです。
SDGsは、世界の共通言語です。ひとりの人間として立場や業種を問わず、「自分にとってのSDGs」を考える時代になりました。
SDGsには正解も手本もありませんので、各企業においては自社で独自のシナリオをつくることが求められています。
このコラムでは、SDGsと建築の木造化・木質化との関連性についてお伝えします。
SDGsと建築の木造化・木質化との関連性

建築業界でも「SDGs」への取り組みが徐々に広がっています。
建築業界が貢献しやすいのは、SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」です。
建築会社としては国の施策を利用しながら、性能の高い建築の進化・普及に取り組み、気候変動対策に積極的に貢献する姿勢が必須です。
各地域の建築会社にとっては、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」も重要です。
これから大きな社会変化を迎える日本にとって、事業を通じて地域の街づくりの持続性に貢献することは、建築会社にとって当たり前の仕事になっていくと予想されます。
SDGs」の目標17には、「陸の豊かさも守ろう」が掲げられています。
そこで具体的に示されているのは、森林の持続的な管理です。建築物の木造化・木質化はそうした目標達成に貢献することができます。
SDGsへの取り組みやビジネスを通した社会貢献の実践や姿勢、企業としてのあり方に共感した個人や法人が、新たな顧客となり、自社を支える人財となっていくことが予想されます。
顧客に対しては他社との差別化、自社の社員に対しては働きがいにつながり、結果として企業の存続にもつながります。
SDGs浸透に伴う建築の木造化・木質化の流れ

SDGsの浸透などを背景に、環境や社会への貢献度が企業価値を左右する時代が訪れています。
日本においても政府のグリーン成長戦略を追い風に、木材活用や省エネなど脱炭素の政策が活発になっています。
温室効果ガス排出量実質ゼロや地域の活性化に向けて、建築界にできることの一つに大規模木造の提案があります。
木造は建築時に炭素排出が少なく、木は炭素を固定し貯蔵する特性があります。
脱炭素社会実現に向けて、大規模木造の普及は推進する要素になります。
持続可能な木材利用を経営戦略に上手に取り組む企業が増えており、自社の事業用の建築物を木造で計画する企業も増えています。
まとめ
脱炭素社会実現のための木造化・木質化普及のポイントは主に下記です。
・気候変動対策に役立つ
・SDGsの一環になる
・健康に配慮できる
木材に触れる機会が減る一方で、森林資源の充実で素材に適した太い木が増えています。
構造材として木材を使うことも大事ですが、インテリアを木質化し、板として木材を使うことで、多くの人々に木の良さを実感してもらう環境づくりも重要です。
特に低層建築物である店舗、事務所、倉庫、幼児施設、高齢者施設等の非住宅建築を、より積極的に木造化を図っていくことが重要になります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
