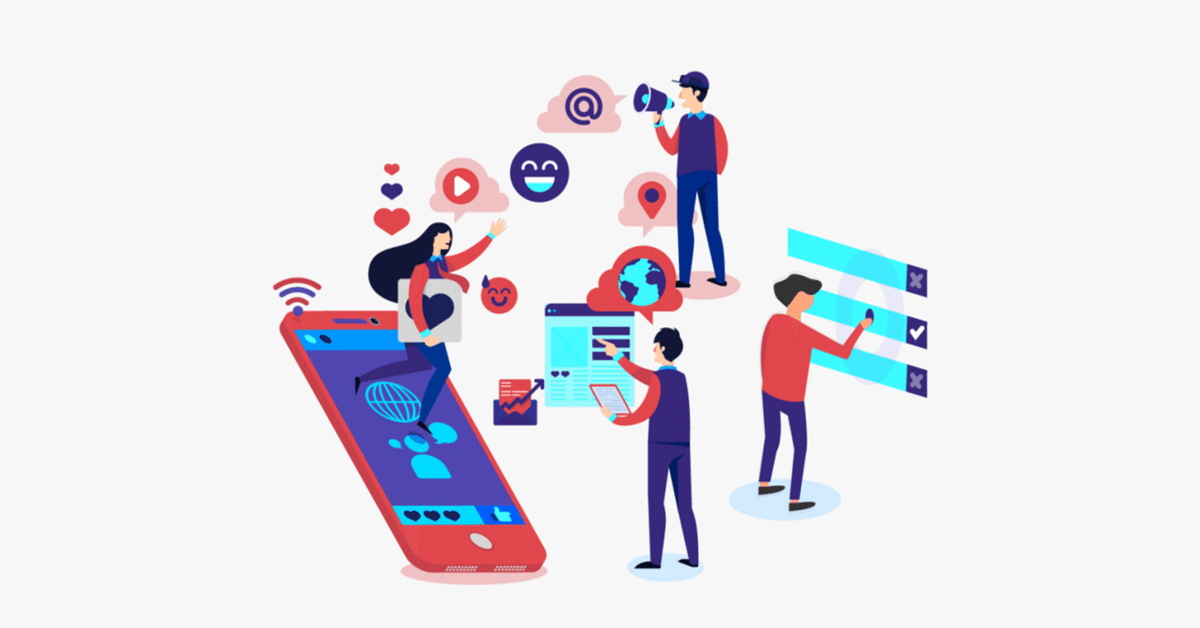
【インターネットと共に生きる。第2回 情報リテラシー論】
はじめまして。かっぱです。
きゅうりが好きなかっぱです。
デザイン系の大学で1年生をしています。
今日からこのブログを通して、僕の通っている大学の情報リテラシー論という授業の、レポートを書いていきたいと思います。
LINEやInstagramといったSNSしか使ったことがなかったので、ちゃんとしたブログを書くのが初めてになるので、緊張しています。自分の言葉で、感じたことなどを素直に書いていけたらと思います。なんだかワクワクしてますよ😊笑。楽しくできたらな〜と思います。これからよろしくお願いします!!🙇♂️
ではでは早速、【情報リテラシー論 第2回】の授業のレポートを書いていきたいと思いますよ。(第1回の授業内容はオリエンテーションだったので、第2回から書いていきます)
第2回のテーマは『インターネット概論と歴史』でした。このテーマを見たときは正直、「ぁぁ、とても難しそうなテーマじゃないか。月曜の最後のコマの授業だし、あたしゃ寝てしまうんではないか。とほほ。😞」と思いましたが、授業をしてくださっているヨコタン先生のお話が面白くて最後まで聞き入っちゃってました!
講義の中で特に印象に残った点を自分の思ったこととかを交えながら紹介していきます!
1. 意外にも最近発展したインターネット
まず、授業を最後まで聞いて思ったのは、インターネットの普及は意外にも最近で、だけど、そのここ十数年のインターネットの普及が自分たちの日常生活の形を大きく変えたということです。自分がこの世界に生まれ落ちたときには、もうすでにインターネットというものがあったから、ネットがなかったり、ほとんど普及してなかった時代のことを考えると不思議な気持ちになります。けどそういう時代があったんですよね!お母さんとお父さんは、ネットが登場する前の世界と、ネットに頼る今の世界、両方を見てるわけだから、「こんな未来、20年前、予想できた?」と聞いてみたら、「1ミリも想像してなかったよ!!日本人のほとんどが板みたいな、ほとんど画面の携帯電話を毎日持ち歩くことになるなんてっ」と言っていて、確かにそうだよなと改めて、ここ十数年の時代の急激な進歩を感じました。インターネットの普及の歴史と、世界と日本のその当時の変化が分かりやすく視覚化されているグラフをヨコタン先生が授業の時スライドで見せてくださったのでここに貼っておきますね!

また、インターネットそのものの誕生も私たちの生活に大きな影響を及ぼしたと思いますが、先ほども言ったように、個人的にはiPhoneをはじめとするスマートフォンの普及がよりインターネットの存在を私たちにとって身近な物にし、さまざまな可能性を広げてくれたと思います。いい意味でも、少しマイナスの意味でも今の私たちはインターネットに依存している部分が大きいように感じます。自分自身もネットがない世界は考えられません笑。今もし突然、全世界のインターネットの利用が停止してしまったらどうなるのでしょうか。世界はいままでにないほどの大混乱を起こすと思います。
2. ネットがあるのは本当に幸せ?
だけれど、その中でも一部の人々にとってはネットが使えないことは何の問題もないかもしれません。世界にはインターネットを利用していない人々もいるのです。

このグラフからわかるように、世界のインターネットの利用者の割合は、6.5割ほど。個人的には7割、8割、行くと思っていたので、想像より少し少なくて驚きました。また世界的に見ると、北米やヨーロッパの普及率は高いのだなと改めて実感しました。逆にアフリカなどの普及率は低い。未だ、電気すら使えていない人々もいるこの世界で、今後、このインターネット普及率がどのように変化していくのか個人的にすごく気になります。同じ時代に、同じ世界に生きているのに、電気すら使わずに生活している人々と、完全にインターネットに浸って生活している人々がいるというのは、改めて考えるとなんだか不思議です。どちらの生活が実際のところ、ほんとうに幸せなんでしょうかね笑。普通に考えたら後者の方が断然幸せなように感じますが、ネットの世界もいいことばかりではなくて、毎日、悲しいニュースも飛び込んでくるこの世の中ですから、もしかしたらネットがない世界の方が良かったのでしょうか。いや、けれども!それでも、やはりインターネットはほんとうに魅力的だし、私たちの可能性を大きく広げてくれました。いやー、考えだすとキリがないですね😇笑。ということで次の話題に行きます。笑
3. いまは、テレビとネットの協力プレーを見せるとき!
次に個人的に授業の中で気になった話題は、テレビのネット敵視についての話題です。

こちらの資料も、授業でヨコタン先生が見せてくださったものなんですが、この図からもわかるように、テレビの利用時間のゴールデンタイムとネットの利用時間のゴールデンタイムが年々重なってきて、テレビとネットの争いが勃発しているということ。今住んでる地域に引っ越してきてもう半年が経ちましたが、僕の友達や先輩の中で、テレビを持ってないという人がいて、そういう人に理由を尋ねると、みたい番組がないからとか、スマホとかパソコン使って、ネットでだいたい見たいもの見れるからと言われます。ほんとにそのとおりですよね笑。だから、テレビはネットと闘うのは難しいから、ネットの力をテレビでも生かして、共存しようとテレビ業界は試みているそうです。たしかに、最近の番組を見ていると、番組の放送に合わせて、Twitterで#〇〇番組をつけてつぶやいてください!とか、番組内で、ネットを使ってリアルタイムで投票とか、YouTubeで、番組のメイキングを公開したりとか、TVerというアプリだったらドラマの見逃し配信をして、さらなる視聴者の獲得に繋げていたりとか、アプリやSNSを存分に活用して番組を盛り上げようとしているように感じます。
テレビはネットと違って伝える情報も不確かなものや不適切なものはなくて、当然私たちのような一般人は制作に関われない。ネットは誰もが発信者になれるけれど、テレビでは難しい。だからこそ、いかに視聴者の人たちが求めている物に寄り添えるか、いかに視聴者の方が求めているものに気づいて、それに応えられるかが大事なような気がします。作る側の人達で一人走りしないで、見る側の人たちと、それこそ、最近ではインスタグラムやTwitterなどで番組公式アカウントを作る様子もよくみられますが、SNSなどで沢山繋がって、番組作りに活かしていったらいいのではないかなと思います。自分はドラマが大好きで、民放ドラマはもちろん、朝ドラ、大河も楽しみに見ているような人なので、是非ともテレビ業界には頑張ってもらいたいです。人ごとみたいになっちゃいますが、自分もSNSなどを使って何か力になれたらなとも思います。
まだまだ第2回の授業の感想で書きたいことは山ほどあったのですが、実は昨日、コロナウイルスのワクチン摂取を受けまして、いま発熱中で体もダルく、このブログの続きを書けそうないので、今回はこの辺りにしたいと思います😭
今回のテーマは「インターネット概論と歴史」でしたが、知ってるようで知らないネットの歴史や概要をたくさん知ることができました。次回の授業も楽しみです!
それではまた〜👋
※途中出てくる画像は、授業をしてくださっているヨコタン先生のスライドのデータを使用させていただいています。
↓授業をしてくださっているヨコタン先生が代表をされてる会社のHPです!興味深い記事がたくさんあるのでぜひ覗いてみてください!
https://www.enspire.co.jp/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
