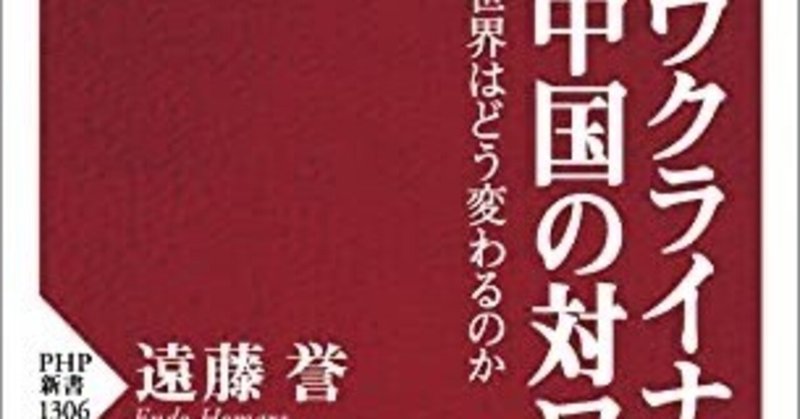
中国はどう動くのか〜遠藤誉「ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略」
かつての私は中国の政治について無知、正直あまり関心がなかった。香港赴任となった後は、そうも言っていられない。日常会話、メディアの報道から、中国の政治に関する話題に接することになる。特に私の赴任した2011年は、翌年に共産党トップの交代を控えたタイミングだった。
そんな時、遠藤誉の書いた「チャイナ・ナイン」という本は、中国政治のメカニズム、中国のトップ、9人の政治局常任委員の今と未来について、分かりやすく論じたもので、大いに参考になった。なお、現在は常任委員7名体制となっており、“チャイナ・セブン“と称される。
その遠藤誉の最新刊「ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略〜世界はどう変わるのか」が、昨日書いた毎日新聞“風知草“で取り上げられており、早速読んでみた。
遠藤氏のこの著書は、こう始まる。<ウクライナに軍事侵攻したブーチンの残忍無比な蛮行は、まだ四歳だった頃にソ連兵に突きつけられたマンドリン(短機関銃)の恐怖を思い起こさせる>。太平洋戦争当時、彼女は中国大陸において関東軍に見捨てられ、ソ連の脅威を体験する。その後、中国共産党軍の流れ弾にあい身障者となり、長春包囲網「チャーズ」の中で地獄を見る。81歳になった彼女は、今回の侵攻を目にし、かつての恐怖が蘇り、PTSDに襲われる。そして、それを克服するために、力を振り絞って書いたのが本書である。
その主題は、中国、習近平がウクライナ戦争にどう対応していこうとするのかである。
まず大前提として、中国とウクライナは<ソ連が崩壊した時点からの「大の仲良し」>であるということ。ウクライナの軍事科学者の多くが、厚遇で中国に招かれた。そのようなウクライナにロシアが武力を行使するということについて、中国は当然にして反対であり(ストレートには言っていないが)、外交的解決を促進すべきという立場である。また、中国は経済的に欧州と近づきたいので、<NATOとは対立したくない>。
一方で、同じ<「アメリカから虐められている陣営」>にいるロシアに対して、経済的には<徹底してロシアを支援する>。そして、これを通じて中国にとってのエネルギー安全保障問題の改善、非ドル経済圏の拡大を目論んでいる。これを総称して、遠藤氏は「軍令軽熱」戦略と称している。
ウクライナ問題に関わらず、中国が仕掛けているのは武力による戦争ではなく、経済戦争である。その意味では、いずれウクライナの復興問題が浮上するはずなので、中国としてはここに入り込みたい。
従って、中国の台湾への軍事侵攻などあり得ないし、中国にとって何のメリットもない。ただし、台湾が独立を宣言したり、アメリカを始めとした西側諸国が、<「台湾は合法的に中国の一部」>という、そもそもニクソン元米大統領が作った「国際秩序」を壊すような動きは、中国にとってのレッドラインである。
なお、本書の後半は、ウクライナ問題におけるアメリカ、とりわけバイデン大統領の責任、そしてどう転んでも得をするアメリカの貪欲さを問うている。彼女の指摘には異論もあるだろうが、「国際政治エンターテイメント」を読んでいるような気分にもなる。
遠藤氏は理学博士でもあることから、本書も極めてロジカルに書かれており、現在の問題点を理解する為の良書だと思う。
この本を読み、周辺各国の国益のために利用・蹂躙され続けてきたウクライナの不幸な歴史は、今も続いているように思えた。
遠藤氏は、本書をこう結んでいる。
<ウクライナの民に栄光を!>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
