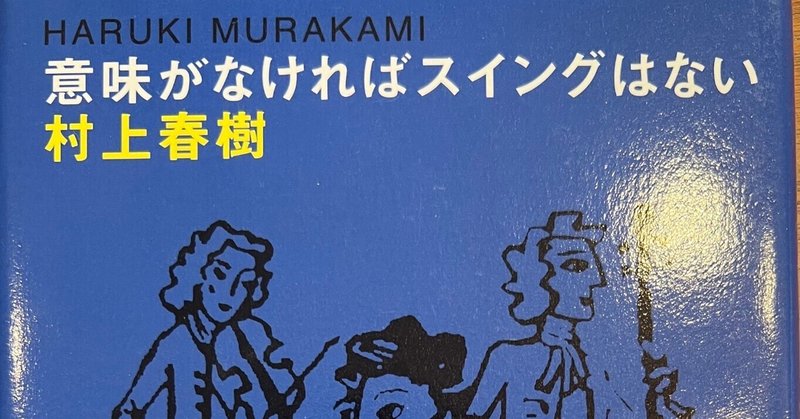
ウィントン・マルサリスの芸術(その2)〜村上春樹さんの分析
(承前)
村上春樹の「意味がなければスイングはない」である。2003年から2005年にかけて書かれた、音楽関連の文章である。その中の一つの章のタイトルは、結構衝撃的、“ウィントン・マルサリスの音楽はなぜ(どのように)退屈なのか?“である。
1990年代初めの数年間、村上さんはアメリカ東海岸のプリンストン大学に滞在する。そこで、マルサリスのスモール・グループによるコンサートが開催されることになり、村上さんは演奏を心待ちにしていた。ところが、コンサートの前日、通りかかりの猫を撫でていたら、猫に噛まれてしまう。当地では、狂犬病や破傷風が大きな問題になっており、村上さんは救急病院に連れていかれ、<馬に打つようなぶっとい注射>を何本も打たれ、コンサートどころではなくなってしまう。
その後、マルサリスはJazz at Lincoln Center Orchestra(JLCO)のコンサートをプリンストンで開き、村上さんは無事に聴きに行くことができる。村上さんは、<このオーケストラは基本的にけっこう気に入っている>、<ただ、何度も繰り返してこのオーケストラの音楽を聴きたいかというと、正直なところあまりそういう気持ちにはなれない>、そしてJLCOの音楽には、<頭のいい大学院生がすらすらと書き上げた学術論文みたいなところがある>と書いている。
村上さんは、マルサリスのことが嫌いではないし、<彼の音楽がジャズにとってのひとつの突破口になるのではないかという期待>を抱きながらも、あれほどの才能とセンスの持ち主の音楽が、<どうしてこれほどまで退屈でなくてはならないのか>、<どうしてスリリングであってはならないのか>について検証している。
その理由として、村上さんはマルサリスの持つ<生真面目さ、口数の多さ、自信過剰、コントロール好き、お勉強好き>といった性向を挙げている。
このエッセイを読むと、村上さんの指摘は、前回書いたコンサートが表現したある種の完璧さにつながっているように思える。構成にすきがなく、不満を抱かせる部分がない。それがジャズという音楽の持つ力を削いでいるのだろうか?
村上春樹は、マルサリスが<もっとも大きな可能性を持った、同時代のジャズ・ミュージシャンであることは間違いない>とし、その潜在能力は大いに評価している。<彼は自分の魂の地下室に、自らの意志で意図的に降りていくことはできないけれど、何かの加減で非意図的にそこにふとたどり着くことはある>と書き、これからも彼の音楽を聴き続けるとする。
そして、<滋養のある、真に新しい音楽をこの人がいつか作り上げてくれればいいのだが、と祈っている>。
上記の通り、この文章が書かれてから20年程度の時間が経っている。今のマルサリスを村上春樹はどう見ているのだろう。
私は、ウィントン・マルサリスの音楽を分析する力はない。ただ、サントリーホールでの演奏は、“芸術“と言えるようなものであり、それはとても楽しかった。
村上さんが指摘したマルサリスの本質はあまり変わっていないようにも思える。それでも、私にとっては、決して“退屈“な音楽ではなかった

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
