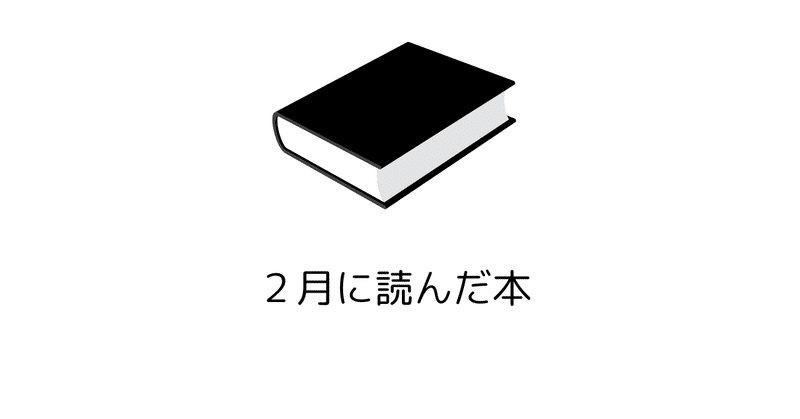
2月に読んだ本
※Amazonのリンクを載せていますがアフィリエイトはやってません。
理論社の『世界ショートセレクションシリーズ』
から、チェーホフ、トルストイ、カフカを読んだ。図書館の児童本コーナーにあった。
ヨシタケシンスケさんの絵がとてもかわいい~。子どもも手にとりやすいと思う。1話ごとに扉絵があるのもうれしい。
少年少女達はカフカやチェーホフを読んで何を感じるんだろうか。
山崎努『柔らかな犀の角』
俳優の山崎努さんの読書日記。
こんなに本を読む人だったのか。
文章は自動的に山崎努の声で脳内再生される。
紹介されていた武田泰淳『めまいのする散歩』を買った。
ハン・ジョンウォン『詩と散策』
古今東西の詩を紹介しながら、散歩や、心の内の散策について書かれたエッセイ。雪の降る日のような静謐な文章がとてもよかった。好きだと思った。
河出書房新社『自転車に乗って』
自転車について書かれたものを集めたアンソロジー。
夏目漱石と萩原朔太郎の『自転車日記』が面白かった。
萩原朔太郎の
一月十五日 既に全く熟練し、市中を縦横に乗走し得。
歩行して数時間を要する遠路を、 わずか一時間にして走り、しかもほとんど疲労を知らず。
天下にかくのごとき爽快事あらんや。
今日、地図と磁石を携えて近県の町に遠乗りす。
途中甘味に飢え、路傍の汁粉屋に入りて休息す。
という日記がいい。
というか汁粉屋がいい。行きたい。自転車に乗って。5km以上走ったことないけど。
ヴェルナー・ヘルツォーク『氷上旅日記』
一九七四年の十一月下旬に、友人がパリから電話をかけてきて、ロッテ・アイスナーが重病だ、おそらく助からないだろう、といった。
ぼくはいってやった、そんなことがあってたまるか(中略)そしてまっすぐパリに向かった、ぼくが自分の足で歩いていけば、あのひとは助かるんだ、と固く信じて。
重病の友人のロッテ・アイスナーに会いに、ミュンヘンからパリからまで600km以上歩いた映画監督、ヴェルナー・ヘルツォークの旅行記。
600km以上歩くってどんな感じだろう。
足、痛くなるだろうな〜と思う。
実際、足が痛むとよく書いてある。
何km歩いたとか、あと何kmだとか、そういうことはあまり書かれない。
書かれているのは少しの事実(足痛いとか)と幻想、夢想的な散文詩のようなもの。
旧版の帯には「幻視行」と書かれていた。
日記からシームレスに幻想の世界に発展していくので、書かれているのが事実なのか虚構なのかだんだんわからなくなってくる。
しかし、ヘルツォークがアイスナーのために600キロ歩いてパリまで辿り着いたということはまぎれもない事実だ。
ロッテ・アイスナーはこの8年後(8年生きた)
「私にかけられた死んではいけないというを呪縛を解いてもらえないか」
とヘルツォークに頼んだという。
ヘルツォークは了承し、アイスナーは8日後に亡くなった。
一度は生きてほしいと強く願った相手にそうする(呪縛を解く)ことは簡単ではないはずだ。想像もつかないほど。でもヘルツォークは今回もやり遂げた。アイスナーは救われたと思う。
レベッカ・ソルニット『歩くことの精神史』
第一章「岬をたどりながら」の文章がとても素晴らしかった。最後までこんなに素敵だったらどうしようと心配になるくらい。
歩行のリズムは思考のリズムのようなものを産む。風景を通過するにつれ連なってゆく思惟の移ろいを歩行は反響させ、その移ろいを促してゆく。
(中略)考えることは何かをつくることではなく、むしろ空間を旅することなのだと。そう考えると、歩くことの歴史には、具現化された思考の歴史という側面があることがわかる。
第二章の「時速3マイルの精神」には、哲学者達の引用が多くある。
前提とされる知識の足りてなさにぼんやりする。
ルソーは歩くことに深く結びついた作家であるらしい。
キェルケゴールには友達がいなかったとか。親近感。
「庭園を歩み出でて」
「ウィリアム・ワーズワースの脚」が面白かった。
ワーズワースと彼の仲間は、
徒歩の旅をそれまでとは違う新しいものへ変えたといわれてきた。
それはただ歩くことを目的に、風景にわけいる愉しみのために歩く 人びとの系譜の礎となり、多くの実りをもたらした。
歩くということを文化的活動として取り入れ、美的な経験として受け入れたのはこのロマン派の第一世代だったとはよくいわれることだ。
ワーズワース以前に街道を歩く者が少なかったことは疑いない。
やむを得ず徒歩で移動する者は少なくなかったが、楽しみとする者はほとんどいなかった。
ワーズワース以前は一部の位の高い人々が作られた庭園を見て回ることが、「歩くこと」の楽しみだったという。
ワーズワースは風景を楽しむために歩くことの親!
興味深いのが、ワーズワースの妹のドロシーもワーズワースにくっついて野山を20km、30kmと歩いていること。雨の日も風の日も。元気!
引用される日記が本当に楽しそうでいい。
「ウォーキングクラブと大地を巡る闘争」
ウォーキングクラブに興味がないし、どうかな…と思っていたのに、読んでいたらどんどん面白くなってきた。こういうことがあるから読書はあつい。
自転車で、全然注目されてなかったCTの選手が勝つみたいな。全く違う。
「未踏の山と巡りゆく峰」
山!この章が好きだ。
「ただ純粋に山に登り、高みからの眺望を楽しんだ初めての人物」といわれている詩人のペトラルカが登ったその山が、モンヴァントゥなのもなんかうれしい。ツール・ドフランスなどの自転車レースでよく出てくる山だ。
なんとなく出てくる予感がしていた富士山も出てきた。
「パリ」
「1840年ごろにはパサージュ(アーケード街みたいなところ?)の散歩にカメを連れてゆくことが流行した」
とヴァルター・ベンヤミンが綴っている。
「遊歩者はカメに歩調を合わせることを好んだ。カメに行きたい方向があるときはその歩み慮って足を勧めたものだった」。
カメ〜🐢
(しかし、ベンヤミンの著書以外にカメの散歩が流行っていたことを記したものはないらしい…。)
「作家ジェラール・ド・ネルヴァルがシルクのリボンにつないだオマール海老を連れて散歩していたことはよく知られるが」
全然知らなかった。海老〜🦐
書くとは想像力の大地に新しい小径を刻み、あるいは、通い慣れた道で新しい発見を指し示すことなのだ。
そして読むとは著者を導きにしてその地平を旅してゆくこと。
手中のガイドは常に正し いとも信用できるとも限らない。
けれどもどこかに連れていってくれる、ということだけは期待していい。
作者のいうように、読むことが旅なら、ちょっと長めの、でもたのしい旅だった。たまに寄り道したりして。
単純に散歩に行きたくなった!
山とか川とか、雪の中とか桜並木とかに。
昔の人が歩きながら考えたことに思いを馳せたりしながら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
