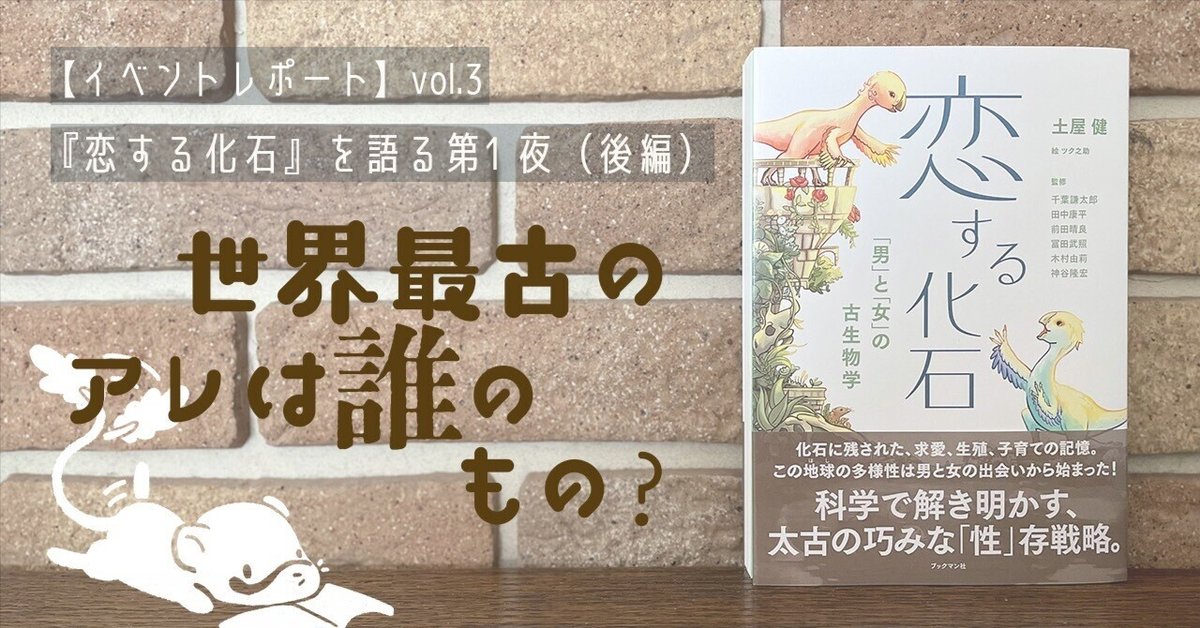
【イベントレポ】世界最古のアレは誰のもの? #『恋する化石』 を語る第1夜(後編)
2021年12月、『恋する化石 ―「男」と「女」の古生物学―』の刊行を記念して行われたオンラインイベントに、著者の土屋健さんとイラストレーターのツク之助さんが登壇された。
古生物の花形といえば恐竜? アンモナイト? いやいや、介形虫だ! という宣言のもと、後半は一般向けの古生物トークとしては異例の介形虫祭と化し、ついにはグッズ展開の要望まで!?
#『恋する化石』 を語る第1夜(前編・中編)に引き続き、トークイベントの内容を一部編集してお届けします。
〜〜〜🎙〜〜〜
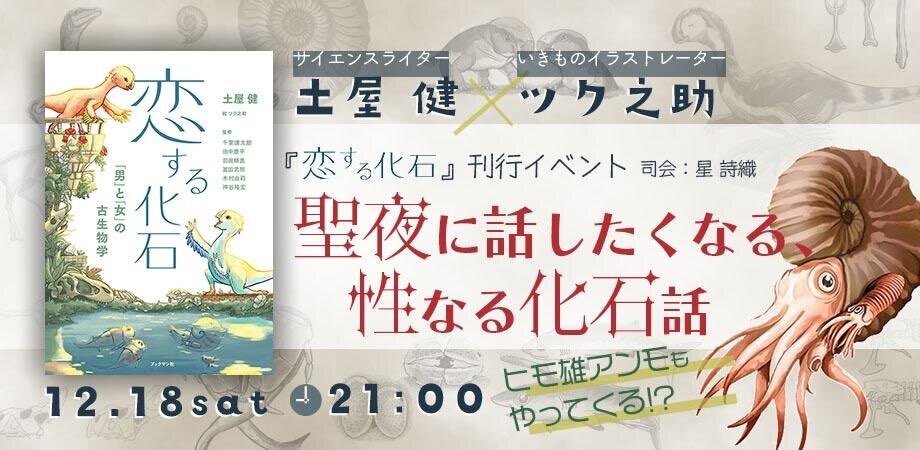
ヒトは例外
――次は、我々に身近な哺乳類の章です。ここでのポイントももちろん「ペニス」ですか?
土屋:「ペニス」です。哺乳類の中でも我々ヒトは例外なのでピンとこないかもしれませんが、多くの哺乳類のペニスには陰茎骨と呼ばれる骨があります。これが化石に残るんですね。おもしろいのは、我々はここに骨がなくても何も困らないじゃないですか。でも持っているやつがいるってことは何らかの役割がある。じゃあ陰茎骨ってなんなの?ってところですね。
――あと、哺乳類ならではのものとして、もう一つミルクの話にも触れていますね。
土屋:哺乳類はその名の通り哺乳する動物で、ミルクは子育てに欠かせません。ではそのミルクの起源、授乳の起源は?という話ですね。これについては、監修の木村由莉さんからこんなネタがあるよと教えていただいたものです。
――ヒトは例外という言葉がありましたが、このミルクについても例外なこととして、ヒトは他の動物のミルクも飲むと。これは確かにそうだなと思って。
土屋:私自身も、木村さんに指摘されて目から鱗でした。ヒトはいつから他の動物のミルクを飲むようになったのか。要は酪農の起源ということですが、そのあたりも科学の視点から迫っています。
――木村先生といえば、イラストの監修の方でも、ツク之助さんと熱いやり取りがあったとか。
ツク之助:特にジュラマイア(Juramaia)! ジュラ紀にいたネズミのような小さな動物で、授乳シーンを描いたのですが、吻部の形状とか、赤ちゃんの配置とか、すごく細かい要望が描いては飛んでくるという感じで、ずっと高速ラリーを続けているような(笑)。すっごく楽しかったです。これだけでおそらく2時間くらい語れてしまうのですが、どうしましょう(笑)。
――次回に取っておきますか! みなさん、この話は次回です。次回もぜひご参加ください。
世界最古のオス
――そして、最後を飾るのが介形虫ですね。先ほども、古生物の性を語るならまず介形虫からというお話がありました。そもそも、なぜこの分野の研究で介形虫が注目されているのでしょうか。
土屋:多くの恐竜は現在の地球にいない生き物なので、違う特徴が見つかってもそれがオスとメスの違いを表しているのか簡単には判断できないのですが、介形虫は今もいるので、今いる介形虫のオスの特徴、メスの特徴を、そのまま化石の中に探すことができる。あと介形虫は非常に小さいので、殻の形そのままの姿で、しかも数もたくさん見つかるというのも特徴です。
――確かに、恐竜は見つかっている化石の数も少ないし、さらに完全体で見つかることがないから、性的二型を判断するのが難しいというお話でしたね。それに比べて、介形虫は完全な姿で見つかり、数も豊富。そして現生にもいるので確かな情報も得やすい。サンプルとなる母数が多いと。
土屋:そうそう。母数が多ければその平均値が取りやすくて、イレギュラーなものはそこから弾かれる。例えば、我々人間の中には大柄な女性や小柄な男性ももちろんいるけれど、データをたくさん集めれば、全体として男性の平均身長はこのくらい、女性の平均身長はこのくらいで、男性の方が大きいという特徴があるのがわかりますよね。
――あと、世界最古のオスも介形虫から見つかっているということですが、これは少し事情が異なるそうですね。
土屋:コリンボサトン(Colymbosathon)ですね。この個体は、オスの物的証拠であるペニスが確認されているんです。介形虫のペニスは軟組織なので本来は化石に残らないんですけど、ここの産地は特殊で、軟体部の鋳型が残されていた。それが現生の介形虫のペニスとそっくりだったのでオスと判断されました。
――ちなみにこのコリンボサトンという名前の意味が、「泳ぐ大きなペニス」。
土屋:メスは見つかっていないのですが、もし見つかったら、そのメスも「泳ぐ大きなペニス」と呼ばれることになります(笑)。
やっぱり介形虫
――恐竜から介形虫まで幅広く、古生物の性について語っていただきましたが、イラストを描くにあたってはどの章が一番難しかったですか?
ツク之助:やっぱり介形虫ですね。先ほどのコリンボサトンと、あとメスの貴重な化石としてニムファテリナ(Nymphatelina)という種を描いたのですが、最初は化石のスケッチを書いてくださいって言われたんです。化石のCTスキャン画像が送られてきまして。でも、化石なので変形しているし、このままだとわかりづらい。なので、現生のように復元してもいいですか?って聞いたらOKをいただいて。よし!介形虫を復元させてもらえるぞ、と(笑)。
――惚れ込んだ介形虫ですもんね。
ツク之助:もう、嬉しくて。ただ、介形虫の知識が全くないところからスタートしているのと、あと非常に部位が多く、同定するために必要なポイントがたくさんあるので、本当に難しかったです。でも、その分すごく楽しかったですね。
――お二人の話から、この本の肝が介形虫にあることがよくわかりました(笑)。
土屋:グッズメーカーの方が見ていたら、ぜひ介形虫のアクセサリーとか、ぬいぐるみとか、枕とか作ってもらいたいです。
――いいですね、介形虫のYES/NO枕とか。
知るワクワクを味わって
――最後に、この本の「ここを読んで!」というところを改めてお聞かせください。
土屋:もちろん人類の進歩を促す科学技術みたいなサイエンスもすごく重要なんですけど、楽しいサイエンス、エンターテインメントのサイエンスがあってもいいじゃんっていうのが、自分の中の大元の部分にありまして、この本は、その一つの着地点になったのかなと思います。別に陰茎骨の使い方がわかったところで明日から生活が便利になるわけじゃないし、介形虫の交尾姿勢を知ったところでご飯が食べられるわけじゃないんですけど、その謎を紐解いていく過程とか、新しい何かを知ることでワクワクする、その楽しさを味わってもらいたいです。
――土屋さんの本は本書に限らず、いろいろな論文を引用されて、その難しい論文の内容をすごくキャッチーにわかりやすく書いていらっしゃる印象があります。論文というと「新種の恐竜の発見」とか、そういう派手なものを浮かべてしまうのですが、それこそ性的二型の研究をずっと続けていらっしゃる方とかがいて、そういった地道な研究が、古生物の復元をよりリアルな説得力あるものにしているのだなというのを、本書を読んですごく思いました。
土屋:おっしゃったように、私が書く一文の背景には、ものすごく多くの研究者による研究成果があって、その論文自体にも、いろいろな論文が引用されていたりする。そこを感じてくださったのはすごく嬉しいですね。
――ツク之助さんも、最後に一言いただけますか。
ツク之助:この本にイラストを描かせてもらえて嬉しかったですし、作業は苦しみましたが、でもとても楽しかったです。とにかく全編通してすごくおもしろい本なので、絵も楽しみつつ、読んでもらえたら嬉しいです。
*本記事は、2021年12月18日に開催されたオンラインイベント「『恋する化石』刊行イベント 〜聖夜に話したくなる、性なる化石話〜」の内容をもとに作成しています。
(聞き手:星詩織 / 編集:藤本淳子)
→#『恋する化石』を語る第1夜(前編)へ戻る
→#『恋する化石』を語る第1夜(中編)へ戻る
profile
土屋健
サイエンスライター。オフィス ジオパレオント代表。日本地質学会員。日本古生物学会員。日本文藝家協会員。埼玉県出身。金沢大学大学院自然科学研究科で修士(理学)を取得(専門は、地質学、古生物学)。その後、科学雑誌 『Newton』の編集記者、部長代理を経て、現職。愛犬たちと散歩・昼寝を日課とする。2019年にサイエンスライターとして史上初となる日本古生物学会貢献賞を受賞。近著に『地球生命 水際の興亡史』(技術評論社)など。
ツク之助
いきものイラストレーター。爬虫類や古生物を中心に生物全般の復元画や商品デザインを描く。著書に絵本『とかげくんのしっぽ』、『フトアゴちゃんのパーティー』(共にイースト・プレス)。イラストを担当した書籍に、『イモリとヤモリ どこがちがうか、わかる?』(新樹社)、『マンボウのひみつ』(岩波ジュニア新書)、『小学館 はじめての国語辞典』(小学館)、『恐竜・古生物ビフォーアフター』(イースト・プレス)など。爬虫類のカプセルトイシリーズ(バンダイ)も展開。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
