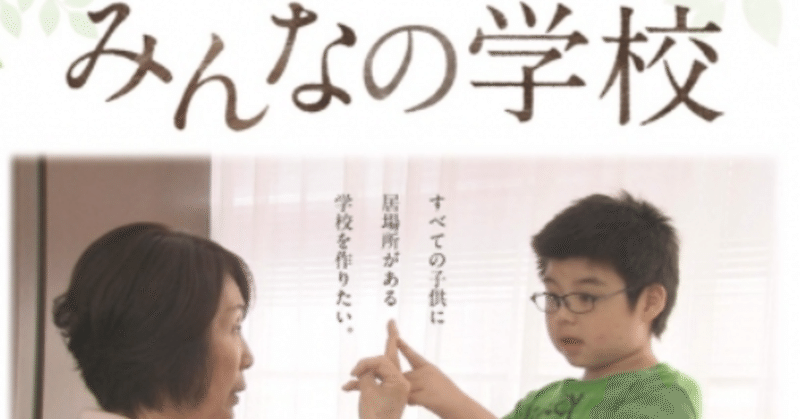
妻が良ければオールオッケー!!
こんにちは!ベストファーザー賞教師部門受賞予定のジョージです!
先日、大阪で木村泰子さんとお会いすることができました。
木村泰子さんといえば映画「みんなの学校」の「校長」として有名ですが、
今回は「母親」としての泰子さんに『幸せな育児』についてお話をしてまいりました。
それでもやっぱりお互い教育者なので、家庭の育児と学校の教育の共通点もたくさん見つかりました。
その中で一番印象に残ったのは「奥さんがよければオールオッケーやで!」というお言葉でした。
オンラインではなかなか聞けない泰子さんの育児について学んだことを下記にまとめます
育児って辛いの?
子どものためより妻のため
正論が伝わるわけではない
やっぱり育児でも伴走者
1. 育児って辛いの?
ワンオペ育児とかネグレクトとか、育児の暗いニュースをよく耳にします。
育児は大変っていうイメージが強くなってしまいますが、
そんな事はありません!
楽しいことや気づくこと、感動することもたくさんあります。
育児を辛くしているのは「世間の声」です。
「母親はこうあるべきだ」「親としてこうしないといけない」
アップデートされていない先入観が育児を辛くしています。
さらに、育児のネガティブなことはよくニュースになってしまいます。
これはアメリカの企業Asher & Lyricが実施した「子育てしやすい国ランキング2020 (The Best Countries For Raising A Family In 2020) 」です。
この項目で幸福度、養育費、子どもと過ごす時間の3つで日本は最低のF評価となってしまいました。

そんな育児のネガティブ要素をなくすたに、泰子さんから学んだのは
「育児の視点を変える」ことです!
育児って子どもと一緒に何かをするだけではないんです!
2. 子どものためより妻のため
近年では「イクメン」や「男性育児休暇」など父親が子どもに関わる場面が注目されだしました。
しかし、しかし父親が子供に対してできることは意外と少ないものです。
実際には何をしていいのか分からない場面がたくさんあります。
ミルクの適正温度、夜泣きの対応、授乳間隔…時々無力を感じてしまいます。
そんなときは「子どもの世話をする」ことよりも
「母親の力になる」ことに焦点を当ててみてください!
乳幼児に対してはとてもデリケートな対応が必要ですが、それ以外の家事などは父親でもなんとかなります。
おむつのまとめ買い、おむつ用ごみ袋の入れ替え、ベビーバスやベビーベットの準備、乳児用石鹸の補充、etc…父親ならではの役割もたくさんあります
子どもと直接関わらない「間接的育児」はたくさんあります。
この考え方のベースは
「何をしたら妻が楽になるか」
妻のことを考えて、妻との対話を通して、最適解を導くプロセスが育児を楽しむコツだと思います。
3. 分かっているけどできないこと
「もっとこうすればいいのに…」
そんな場面をみるとついつい口を出してしまいます。
「自分だったらこうするよ?!」
正論を伝えて修正を加えようとしまいますが、すんなり伝わらないことがあります。
むしろ対立が生まれてしまいます。
「わかってるよ!わかってるんだけど…」
口論になったり、妻が落ち込んでしまう時もあります。
我が家の事例です。
イヤイヤ期の子どものオムツをママが替えようとすると嫌がって逃げ回ってしました。
しかし、ジョージパパが変えようとするとすんなりとオムツを替えられました。
ママの役に立てたぜ!
って思って報告をすると、浮かない顔してお礼を言われました。
「なぜ???」と思って聞いてみると
「私のときは変えさせてくれなかったのになんでジョージパパの時だけ…」と思ってしまったようです。
もちろん、ママからすればオムツを替えることが最優先だとはわかっているです。
それでも「なんでママの言うことは聞いてくれないの?」と思ってしまうようです。
「ママだから甘えてるんだよ!」とか
「オムツ替えられたんだからそれでいいじゃん!」とか、
冷静に考えることはできません。
余裕のない時期なんです。
生活習慣が大きく変わって、睡眠時間が削られ、予想外のことがたくさん起きているんです。
まだまだ親になって数年。落ち着いて対応できなくて当たり前です。
正しい言葉を使うことより、相手に伝わる方法を考えることは教育とも似ています。
4. 育児の主役は父親じゃない
「イクメン」や「男性育児休暇」など、育児をする男性が注目されますが
やっぱり育児の主役は母親です。
母親なくして育児はうまくいきません。
この理屈は育児を経験したから気づけることです。
つまり当事者になるということです!
実際に育児現場にどっぷり入り込んでみてください。
子どもの寝顔を見ているだけで癒されます。
夜泣きの頻度には驚かされます。
父親には授乳はできません。
父親の育児は褒められても母親だと褒められません。
このような気づきや疑問がたくさん生まれます。
やってみたからわかることがたくさんあります。
その時に泰子さんに教えていただいた
「奥さんが幸せならオールオッケーやで!!」
この言葉がストンと腑に落ちました!
父親がたまにオムツを換えられても、
その後の母親のオムツ交換が辛くなるのであれば育児を楽しめません。
母親の感情を優先するためにオムツを替えないということでもありません。
大切なことは「夫婦の対話」だと思います。
保育士をしている教え子に「オムツを替えるくらいなんて育児のほんの一部ですよ」と教えてもらったことがあります。
「オムツ替えたよ!」ではなく
「いつも替えてくれてありがと!」というマインドセットを持ち続けたいです。
「育児の視点を変える」ことは
「育児の主役は母親」と考えることだと思います。
これは「学校の主語は子ども」という泰子さんの言葉と似ています。
次回は「学校教育と家庭育児の共通点」についてお伝えします。
教師が育児をやったらこんなにも楽しめるんだっていうポイントをお伝えします!
「教育を本気で語る会」ではtwitter, Instagram, spotifyでも発信しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
