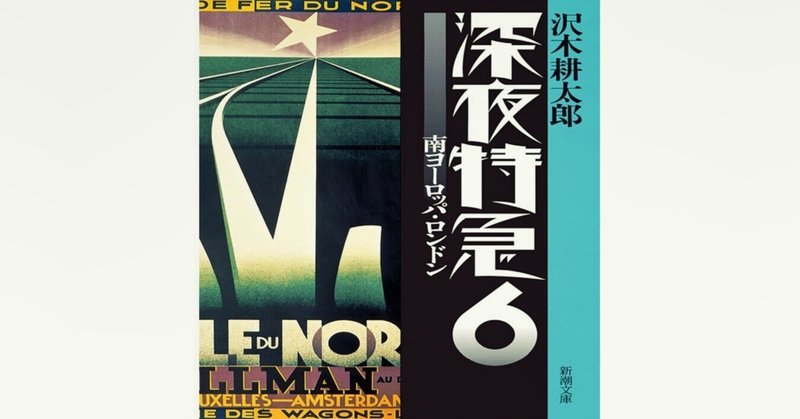
『虐待児の詩』 新潮文庫の一冊
「深夜特急(6) 南ヨーロッパ・ロンドン」
この旅は、どこで何が起こるか予測のつかない放浪とふれあいの旅であり、お膳立てされた観光などではない。つまり実際の目的はロンドンへ辿り着くことなどではなかったのだ。
自らの進むべき道を試行錯誤していた、当時26歳の著者にとってはきっと自分自身を見つける旅だったのではないだろうか。
なんとなくサグレスの岬に茶(CHA)を飲みに行ってみたくなった。
ただ、なんとなく・・・。
著者も小田実の「何でも見てやろう」を読んで、そんなふうに思ったのだろうか・・・。
著者が言うように、旅も人生のようなものなのかもしれない。
まだ旅慣れてないときは、何事も要領を得ない代わりに、観るもの触れるもの新鮮な体験として蓄積されていくだろうが、旅慣れてくると要領は得て来るだろうが、パターン化されたものになってくるだろう。
以前に、感動したり衝撃的だった街へ再び訪れたところで、たとえ街そのものは何も変わっていなくても自分自身は変化しているのだ。
そんなことに気付いてくると、今度はきっと自分自身の旅を振り返って感慨にふけったりするのだろう。
考えてみれば生きて行くということは、「生命」という大陸を人間という乗り物に乗って、「時間」という決して後戻りできない道を「死」という街を目指して、ただひたすら旅を続けているだけなのかも知れない。
しかし、この道は一本道ではない。
目的地はどの人も皆「死」という街だが、そこに辿り着くまでの経路は無数にあり、どの道を選ぶかという選択権は我々自身に与えられている。
私は、明るい光のさす方向へ進んで行くことにしよう。
「劇的紀行 深夜特急」という1996年から98年にかけてテレビで放送されたものがDVDで出ていた。
「沢木耕太郎原作の大ベストセラー『深夜特急』。その2年に及ぶユーラシア大陸横断大旅行を完全映像化した作品。」と解説が書いてあった。
著者が放浪していた年代とは随分変わっているのだろうが、どんな人たちが住む、どんな所を旅したのかが観てみたくて買ってみた。
作品自体は、タイトルや解説どおり完全映像化ではなく、しいて言えば沢木耕太郎の「深夜特急」を読んだ現在(1996年)の青年(大沢たかお)がその旅を真似て同じように放浪したといった感じなので、「深夜特急」がそのまま映像化されたと思って見ると期待はずれになってしまう。
著者が放浪した当時のままのノンフィクションが観たいというなら、絶対、観ない方がいいだろう。
しかし、私のように、「いったい著者はどんな人たちが住む、どんな所を旅したのだろう」と思って見る分には結構良いのではなかろうか。
ドラマ仕立ての部分にはさして感動もしなかったが、種々雑多な人々の営みを追いかけていると、心の奥が揺さぶられる思いがした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
