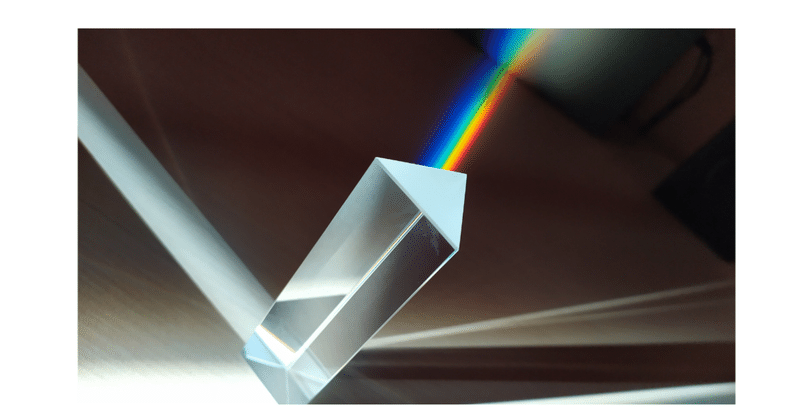
学校って不思議
旅行計画時、商品購入時、画像や口コミ・価格を見て念入りに検討し、 期待に沿わない場合、批判か二度と買わない厳しい目を持つ私たち
でも、なぜか対象が学校となると、偏差値や有名度が重要ファクターとなり、購入後も商品が(不適切な表現だったらごめんなさい)対価に見合わなかったり期待を大きく下回っても「我慢」する。 それがいつも不思議で仕方なかった。
原細胞でしかなかった存在を胎内でヒトのカタチにまで育て、母乳という母の血を与えて(母乳ではなくても同様に貴重です)夜も眠れず片時も自分の時間を持てず、それでも愛おしいと育てた我が子が一日の大半を過ごす学校という場の選択になると、私たちはなぜこうもぞんざいになり、検討や吟味という手法を放棄してしまうのだろう。
「卒業資格」「修了証書」をもらうために学校には盾突かないと白旗を挙げているのだろうか。何か口を出すと「モンスターペアレント」と呼ばれ子どもが不利益を被ることを恐れているのだろうか。
以前読んだ本で(すみません、探したけれど確認できなくて)、子どもたちが30人集まれば、保護者が先生を探してきて学校を作れるという国の制度を(アメリカだったか北欧だったか)知った時、感激した。
本来は勉強ってとっても楽しいものだから、『子どもたちの目が輝くような学校』を作りたいと思い色々調べたときに、「一条校」じゃないと学校として認可されず、そのためには莫大な資金が必要で、とても教育に対する熱い思いだけじゃ実現できないと思い知った。地域により風習や伝統、生活習慣も異なるのに、全国一律同教育をしなければならないことにも違和感がずっとあった。高校の校長をしたときに、他校の校長が「クラスによって単元の進度が違うんですよ!」とお怒りだった様子を見て訝しく思った。私はクラスによって理解度も異なるから生徒たちがわかるように指導するためには進度が異なって当然だろうと思っていたのだが「試験範囲がずれてしまう」とのこと。先生たちの負担増は理解するが、誰のための教育なんだろう?
塾だったら、支払う対価に応じた教育サービスを得られているか?と保護者は常に比較検討する。でも学校は違うようだ。
学校って生徒たちに対して優しく丁寧に指導してくれる先生ももちろんいるが、威圧的な先生も少なからずいるなぁという印象がある。もちろん教育指導上必要な場面もあるのかもしれない。でも、その言い方、学校の門を出て外で他人に言えますか?って思ったことが何度かある。
明治時代に作られた今の学校スタイルは、西欧列強に追いつくために「右向け」と命令されたら何も考えず「右を向く」富国強兵用の人間を大量に作ることを目的としたそうで、残念ながら、その後あまり変わっていないと言われている。(大正時代に一時期良い教育が展開されたが、戦争と戦後のアメリカ統治でそれに戻ることはなかったそうだ)。
これだけ、AIやグローバル化、多様化と子どもを取り巻く社会は大きく変化し、子どもたちはパソコンを駆使し世界中の情報を難なく入手する術を大人以上に獲得しているのに、旧態依然の学校は外の社会との時間のずれ、まるでアインシュタインの時空のゆがみの中にいるかのように感じる。
学校に違和感を感じ、学校に行きたくない、行くことを拒否する子どもたちがいることを私は不思議に思わない。だから、学校に行かないという選択に対してマイナスの印象で語る風潮を変えられないだろうか。「行くか行かないか?」の二者択一ではなく、複数選択肢があり、自分に合った学びができるような教育制度を作れたらと思う。政府がピンバッジを作り言葉だけが上滑りしている「多様化」ではなく、異なる価値観に合わせた選択肢が当然に存在する社会=真の意味での多様化。
多様化については、また語りたいことが多々あるので、後日書こうと思う。
今の学校制度下で不登校、登校拒否、学校に行かないと決める勇者たちがいるのは、さもありなんと思う。資源のない日本が今後も国として存在していくには、私たちはもっと学校というものをよく見て考えて検討しなければならないのではないだろうか。海外の学生、特に大学生は本当に驚異的なほど勉強している。大学入学をゴールに設定している大半の日本の学生たちでは全く歯牙にもかからない、その事実を知るべきだと思う。
海外で懸命に勉強している若者が言っていた「日本にずっと住んでいる人は、日本を先進国だと思って他国を遅れてると勘違いしているけど、外に出ればわかる、かなりの点で今や日本は後進国だよ。」
日本にはもちろん良い点も多々あると思うが、ガラパゴス化していると指摘されていることも承知しておかねばならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
