
【短編】養蜂者
久助の右腕は徐々に3つに裂け、順を追って左手も同じように裂けた。裂けた腕はそれぞれ膨らみ、筋肉が構成されていく。久助は筋肉が裂ける激痛にもだえ苦しみ、ついには気を失った。
目が覚めると久助は鏡で見るために体を起こそうとしたが、いつもよりも上体が重い。やっとの思いで起き上がり鏡を見ると、両腕にそれぞれ3本ずつ立派な腕が生えていた。数は増えたが、長さは前より短くなった。一本一本の腕は筋肉粒々であり、まるでおとぎ話に出てくる金太郎のようだった。この腕を見て上体が重かった理由を久助は理解した。明らかに、いや、異常なほど筋量が増えている。
そこで久助は自分がねじれるほど空腹であると気が付いた。それもそのはずだ。一晩にしてこのような腕を6本(以前は皆と同じ2本である)作り上げたのだから。しかし、久助の寝ぼけた頭は急速に状況を理解しようとし始めた。
久助は困った。こんなもの他の人に見られたら、異形として殺されてしまうに違いない。久助の姿はどこからどう見ても魑魅魍魎の類であった。
久助はその腕を半纏の中に隠し、そそくさと山へ向かったのだ。誰にも鉢合わせないことを祈りながら。
「きっとこれはあやつらの復讐だ」
◇◇◇
久助は今年で18歳になる。幼い頃から学業に優れ身体能力もすこぶる高く、将来を大変期待され、田舎より東京の高等学校へ出してもらった。久助は優れた才能の数々に比べ、精神は幼稚であった。自分より弱き者のことはとことん見下し、強き者にはうまく取り入った。なんせこの久助、悪知恵はすこぶる働く。彼の悪事を報告しようとも、久助はそれをうまく隠し通した。
そんな久助の趣味は昆虫標本である。暇な時間が出来ると彼はすぐに寮を出て、虫を捕まえに行った。虫を捕まえると久助はそれを水に浸す。呼吸の出来なくなった虫たちがもがく様子を久助はまじまじと観察し、悦に浸った。命を握る感覚は久助を絶頂たらしめた。
そして、動かなくなった虫はハンカチに包み持ち帰る。そして窓枠に置き、一晩の間、乾燥させる。そして、体の隅まで水分を飛ばした虫のはらわたを丁寧に抜き取る。ここが最も集中力を要する。ここで失敗するとまた家を出て捕まえに行かなくてはならない。その後、乾燥させはらわたを抜き取った虫を針でコルクに固定し、保存する。
寮の久助の部屋は昆虫の標本で覆われていた。久助にはお気に入りの虫がいる。それは蜂、特にクマ蜂が彼のお気に入りであった。クマ蜂は蜂の中でもおとなしく、警戒心が薄い。かつ、でかい体に見合わぬ小さな羽を必死に動かし必死に飛んでいる姿は久助に耳をなめられたかのような刺激を感じさせた。
クマ蜂を見つけると久助はそれを地の果てまで追いかけ続けた。クマ蜂は基本的に群れることが無い。見つけたら捕まえなければ次の獲物にいつ出会えるのかわからない。久助にとってクマ蜂は入手困難な西洋の甘味のようなものだったのである。
クマ蜂を捕まえると久助はいつもよりも念入りにいたぶる。水に浸し、動きが鈍くなったら水から出す。これを繰り返すのだ。生かさず、殺さず、絶妙に。それでも徐々に溶けていく小さな命に久助は限りない幸福感を覚えた。
そのうち、久助はいたぶるだけに飽き足らず、羽毛のある体をなめたり、ついには食すようになった。口の中でもがく足が上顎の感覚の敏感なところに当たる。その時、久助は自慰では得られない興奮を覚えた。
◇◇◇
山まで逃げてきた久助の足は皮がむけ、ふくらはぎが痙攣した。ついには立っていられなくなり、地面に座り込んでしまった。上半身が重く、その分の負担は全て下半身へと集中していた。腕とは対照的に、脚はいつもより細くなっているように感じた。久助は6本の腕を使い、這うように進んだ。少し進んだところに小さな沢があった。中を覗くとイワナが数匹見えたので、久助は必死にそれを捕まえ、そのままかぶりついた。それほどまでに空腹だったのだ。
イワナを5匹ほど食し、ようやく落ち着いた久助は沢に足を浸しながら休息した。すると、足の人差し指と中指の間が少し裂けているように見えた。水に浸した足は歪み、良くは見えない。焦った久助は足を引き上げると、確かに指と指の間に少しの裂けめがある。また今朝のような痛みに襲われるのかと久助は戦々恐々としたが、しばらくたってもその裂け目が広がる様子は無かった。恐らく、必死に走っているうちにどこかにひっかけてケガをしただけだろうと久助は胸を名でおろした。
一息ついた久助は足が使えず、腕が多いこの状況をどのように打開しようかと考え始めた。腕に関しては二本だけ外に出して、他の腕は自分を抱きしめるようにしていれば服の下に隠せる。問題はその後である。いつまで隠し通せるのだろうか。田舎に逃げ帰ったとしても皆にバレるのは時間の問題だ。どうにかしてもとに戻る方法を考えなければならない。
久助は賢い頭を必死に働かせたが、どうにも良案が浮かばなかった。そんなことをしているとすぐに日が暮れてしまった。時期はすでに春だが、夜はかなり冷える。久助は冷水に浸して感覚の無くなった足を引き上げ、腕を使って移動し始めた。腕は疲れる様子が無く、まるで元からついていたかのように自在に動いた。そのようにして歩いて(実際には這っているのだが)いるとまた、先程のような沢があり、その近くには木の根に覆われた大きな岩を見つけた。そこには空洞があり、人が一人寝泊まりするには申し分のない空間であった。木の根に覆われているおかげで雨風もしのげそうである。久助はそこを打開策が浮かぶまでの住まいとすることにした。地面は腐葉土のおかげで柔らかく、久助はそのまま眠りについた。
朝目覚めると久助は下半身に違和感を感じた。そして脚を見るとそれは4本になっていた。恐らくだが、沢に長い間浸していたことと山に来るまでに負った傷等で痛みが限りなく軽減されたのだ。しかし、腕とは違い、筋量が増えているようには思えなかった。それぞれの脚は細く、筋量は変わらず数だけ増えた感じである。試しにそのうちの二本だけで立ち上がろうとしてみたがうまくいかない。膝から崩れ落ちてしまった。それぞれの足を支えるように他の足を使わなければまともに歩くことはむずかしかった。
異変はそれだけではない。久助は自分の脚さえも異形になってしまったことを嘆きながら沢に行くと途方もない恐怖に襲われた。イワナだ。昨日は何ともなかったはずだが、今日はイワナがたまらなく怖い。水中を泳ぐイワナのひれが動くたびに、久助の体は硬直した。
久助は逃げるように住まいに戻った。自分の身に何が起こったのかわからず、それでもなお変化し続ける体に久助の賢いはずの頭脳は全くもって対応できなかった。久助は外に出ることに恐怖を感じ、その場でうずくまり時が解決してくれることを願った。しかし、動かないからと言って腹が減らないわけではない。久助はまたも耐えられぬほどの空腹に襲われやむを得ず食料を探しに外に出た。
しかし、イワナを除き、食べられそうなものはどこにも無かった。落胆し、もはやここで命を絶ってしまうことを考えた時、どこからか何とも言えぬ良い香りがした。甘味のようだが少し違う。例えるならば、すき焼きのような、砂糖と醤油の深くて甘い匂いであった。その匂いがする方に向かうと、その匂いの正体は一体に咲くツツジであることが分かった。久助は必死にツツジをすすった。不思議なことに量はほとんどないにもかかわらず、大変満たされた気分であった。
腹が満たされた久助は今度は足で歩き出した。通常の速度で歩くためには一つ一つの足にしっかりと力を込め地面を蹴り、普段の2倍の力を入れる必要があった。
久助はそれからしばらくのあいだ、自分の住まいである洞穴からそのツツジまでを往復する毎日を過ごした。絶え間なく足を使う訓練をしたおかげで、疲れることには変わりはないが4本の足を使い通常の速度で歩けるようになった。
そんな生活を続けてひと月が経った。その頃には久助の体は短いが柔らかい体毛で覆われ、目は白目が消え、黒目のみとなった。口からも歯が抜け落ち、その代わりに舌が筒状になり、蜜を吸うことだけに特化した。
久助は変化していく自分の体に絶望しながらも、頭が働いているうちには希望があると自身に言い聞かせ正気を保っていた。久助の見た目はどこからどう見ても異形のものであった。
そんなある日いつものようにツツジを取りに行くと、どこかに引き寄せられるような感覚を覚えた。大量のツツジを抱えて家に帰ろうと歩き出したが、体は意に反して住まいの反対方向へと向かっていった。
久助は混乱した。この一ヶ月、体の変化はあったものの自身の体の制御が効かなくなったことはなかったからだ。気がつくと久助はある小屋の前に立っていた。その小屋は猟師が物置として使っているものらしい。しかし、久助が引き付けられたのはその棟についている大きな蜂の巣であった。
久助が巣の前に立ち尽くしていると、そこからクマ蜂が出てきて次々に久助のかかえるツツジから蜜を持っていこうとした。
「まて、それは俺のものだ、返せ!」
久助はそう叫びながら蜂を振り払おうとしたが、蜂はそれを避けながら蜜を掠め取っていく。怒った久助は屋根を登り、蜂の巣をはたき落とそうと両腕を振り上げた。
しかしその時、一発の銃声が響き、久助は叫び声を上げながら屋根から落ちた。この小屋の主である猟師が帰ってきたようだった。この猟師の一発は久助の右肩を撃ち抜いた。久助はこの猟師に自分が人間であると弁明しようとしたが言葉がうまく出てこない。焦った久助は降参の意を示すように右手を挙げながら近づいたが、これが良くなかった。
猟師の打った二発目の球は無慈悲にも久助の頭を貫き、久助は呻き声をあげ、その後絶命した。久助が最後のひとときに感じたのは人間に戻れなかった悔しさや、無慈悲さではなく、先ほどまで粉々に砕いてやる腹づもりであった蜂の巣の安否であった。
◇◇◇
皮肉にもこの猟師は行方のわからなくなった久助の捜索隊の1人であった。その後、破れた久助の衣服があの洞穴から発見され、久助は森で鬼に襲われ喰われたとされた。この久助を撃ち殺した猟師は鬼殺しの英雄として村中で讃えられ、久助の家族から多額の報酬をもらったそうだ。
回収された久助の体は寺で厄祓いの末、火葬された。祟りを恐れた村人たちはツツジ畑に久助の遺体を燃やした際に残った灰を埋め、そこに新たに桜の苗を植え、供養した。
その桜は長い時間をかけ6本の太い枝を生やした。毎年春になるとクマ蜂がやってきてその枝の下に大きな巣を作るという。人々は畏怖の念を込めその桜を「養蜂桜」と呼び、6本腕の鬼の話を語り継いだ。
蜂を食った男は重たい桜の下でいつまでも蜂を支え、蜂に食われ続けている。
縦書き版
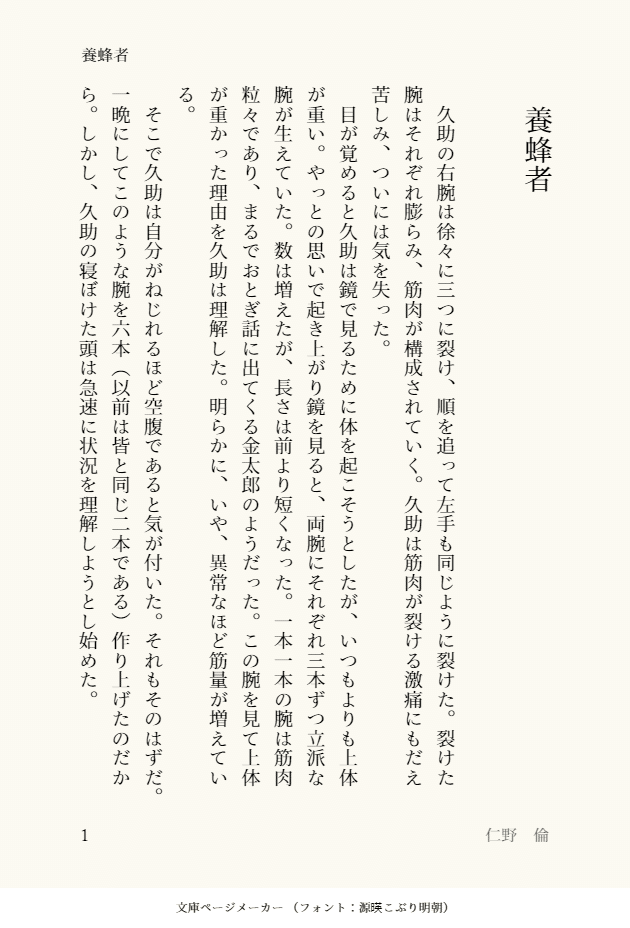







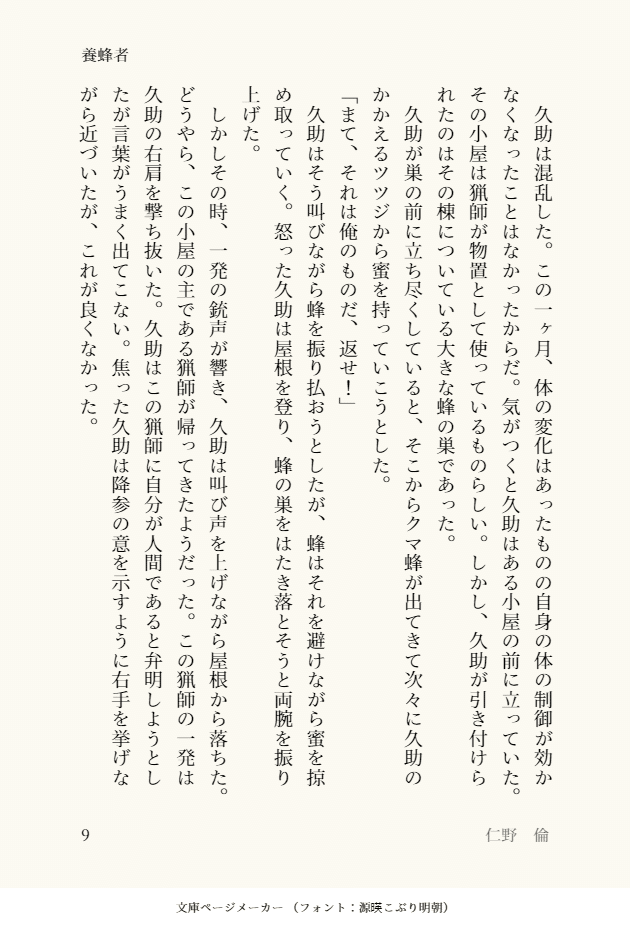


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
