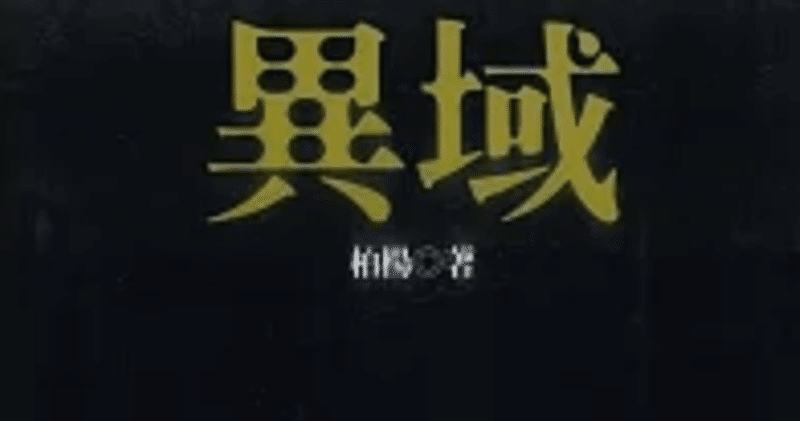
異域、孤軍
30年前、結婚して台北の石牌に住んでいた頃、書店で「異域」というタイトルの本を見かけました。このシンプルなタイトルに惹かれ手に取ってみたところ、国民党軍が雲南から国境を超えてミャンマーに入り、その地で共産中国に対しての反抗を続けたという物語であることを知りました。
泰北の末裔
28歳の時に台北の設計事務所で仕事をしていた時に、この事務所の代表建築師に専属の運転手がいました。彼は身なりは普通の台湾人と同じでしたが、言葉に少し訛りがありました。同僚の話から彼は、タイの泰北から移住してきた人であると知りました。
その時は、この泰北というところが中華民国にとってどの様な意味を持っているのか全く知らず、この運転手の家庭の背景についても考えが及ばず、単にタイから移民としてやってきた華僑なのだろうと理解していました。
後から、この人物は正にこの「異域」の舞台となっている泰北から移ってきた国民党の軍隊の末裔なのだろうと気がつきました。その様な特殊な背景を待つ人間に対し、建築師が仕事のチャンスを与えていたわけですね。この建築師は客家の出身でしたが、国民党政権や国民党軍に何らかのシンパシーを持っていたのでしょう。そう言えば,この建築師は後に中国大陸に活躍の場を広げていました。
柏楊の小説「異域」
「異域」というこの本は、厳密には小説です。架空の主人公鄧克保の視点から、中央から見捨てられた様な形になりながらも、ミャンマーに根拠地を構え中国共産党軍に対峙している雲南人民反共志願軍第三軍、第五軍の状況を描いています。恐らくこの人物は柏楊そのものなのでしょう。しかし、彼の経験としてそのまま描写するわけにはいかなかった。そのために小説の形で発表されたのだと思います。
「異域」では、この部隊のいるミャンマー、連絡将校として送られるタイ、そして台湾を舞台に話が進みます。
印象的なのは、それぞれの場所における、戦争に対する温度感の違いです。ミャンマーでは戦闘の最前線で、中国への反撃、ミャンマー軍からの攻撃に対する対応など、戦いに満ちた日常の生活が描かれます。国民党の残存部隊を上げて戦闘に対する臨戦体制が整っています。悲惨な生活を強いられているわけです。
これがタイに行くと、戦争の匂いは残るのですが、戦場ではありません。タイが連合国の兵站拠点となっており、アメリカ軍と中華民国軍が情報交換などを行いますが、実際の戦闘は行われません。後方支援の場なわけです。
そして、同じ時代の台湾では戦争はほとんど忘れ去られている様な状況です。中華民国の国防軍としては、このミャンマーの軍隊のことはもちろん把握しており、彼らに対する支援を行っていますが、一般国民の意識としては、既に平和を謳歌しているわけです。
この小説が台湾でベストセラーになったのは、この様な軍隊が、発表された時点では現存しており、中華民国の同胞が、遠く離れたミャンマーの山林、タイの北部で悲惨な生活を続けていることを、詳細に知らしめたからでしょう。
翻って考えてみると、それまでこの軍隊のことは中華民国としては、あまり公にはしておらず、知る人ぞ知るといった存在だったのでしょう。そのため、小説として発表されたものであるにも関わらず、或いは小説であったからこそ、人々の心に訴える強い力を持っていたのかもしれません。
孤軍
この軍隊は別名"孤軍"とも呼ばれ、国共内戦で国民党軍が敗れ、蒋介石が台湾に移った後、実に30年に渡りミャンマーからタイ北部に割拠し、戦闘を続けていました。日本にはこの様な戦闘部隊はいなかったので、直感的には理解しづらいところがありますが、比較的似ているのは小野田正一さんの様な状況でしょうか。小野田さんは全くの個人,1人で異郷での戦争を続けたわけですが、これが一群の戦闘部隊がそのままミャンマーの地に居座り、共産中国に対する抵抗活動,戦闘を続けたわけです。
この中華民国の軍隊がミャンマーと中国の国境地帯で30年に渡り武力闘争を行い続けたということに、僕はずっと合点がいきませんでした。台湾から遠くに離れた軍隊にどのように補給をしていたのだろうかとか、ミャンマーの国はどうしてこの様な軍隊が自国にいることを許したのだろうとか、たくさんの疑問が残ります。日本の軍隊がガダルカナルやインパールの戦いで悲惨な敗戦を迎えたのは、補給ルートが伸び切り、武器も食糧も底をつき、そもそも戦闘どころではなくなってしまっているからです。
それと比べると、この孤軍が異郷で長い年月に渡って存在し続け、戦闘行動を行っていたということには、この様な日本軍の戦闘の常識では理解できない要因があるはずです。
一つは、単純に中華民国のこの軍隊が強かったからなのだそうです。これは、台湾の友人から聞いた話ですが、とにかくミャンマーの軍隊では中華民国の軍隊に歯が立たなかった。
ミャンマーというのは今でも、近代国家になりきれていない部分があります。特に山岳地域に入ると、少数民族の半独立状態の様になっていて、中央の統制もきいていない。中国との国境に近い山岳地域では特にその様な状況で、近代的な軍隊で国境を守るのとは程遠い状態であるわけです。
そのために、中華民国の敗残部隊と言ってもよい軍隊がこの山中に逃げ込んできても、ミャンマーはそれを自力で追い払うことができなかったそうです。
この、軍事力の差というのは、日本軍と中国軍の間でも明らかなわけですが、中国軍とミャンマー軍の間でも同じように隔絶しているわけです。僕はこの軍事的能力の違いというのは、近代化のバロメーターのようなもので、科学技術というハードウェアを行使する部分と、それを組織だって運営するソフトウェアの部分の両輪を伴っているのだと考えています。
その点で、中国国民党とミャンマーの間には明らかな軍事力の違いがあったわけです。
もう一つは、この中華民国の軍隊には少なからず、雲南の少数民族が加わっていたことです。
中華民国の軍隊は、中国の中央部から追われ雲南に逃げ込み、最終的にはそこからも追い払われることになります。この敗走の過程で中華民国軍は兵力の補充を現地で行います。そうすると、この軍隊には最終的に少なからず、雲南の少数民族の若者を取り込んでいました。
彼らは、ミャンマーと中国の国境の中国側に住んでいたわけです。それなので、国境のミャンマー側に住むことに違和感がなかった。それどころか、この人たちは、最終的に台湾に移るかタイに留まるかという選択を迫られた際に、タイに残ることを選んでいる人も多いのだそうです。だから、ミャンマーの山林の中でも自立して生活する能力があったわけですね。
このような理由で、中華民国中央からの補給が限られている状況下で、孤軍は存在し続けました。
最終的には、外交関係を通じて中華民国に対して軍隊の撤収が要求され、この指示に基づいて孤軍は解散します。一部は台湾に移り、一部はタイに留まることを選びます。
僕は歌手のテレサ・テンが亡くなったのが、タイの北部チェンマイであることと、泰北に残った国民党の軍隊の間に何らかの関係があるのではないかと考えていますが、詳しいことは分かりません。
香港の映画「異域」
この小説はベストセラーになり、香港で映画化されました。それも、第一部と第二部の二部作になっています。主演は劉德華、アンディー・ラウです。
この作品が何故香港で映画となることになったのか、その経緯はよく分かりません。この時代の香港は中国から逃げてきた人達が多く、この異域の物語にシンパシーを感じていたのかもしれません。
ビジュアル化されたこの孤軍の物語は、真実とは異なっている、誇張された部分も多いでしょう。しかし、このような歴史があるのだということを人々に知らしめる大きな影響力があったと思います。今はネットにアップロードされているので,この作品を簡単に見ることもできます。
孤軍の歴史と台湾
この物語は、台湾にいると過去の歴史ではないと感じることがあります。去年この孤軍の歴史を紹介する記念館がオープンしています。国民党の歴史としては、この孤軍の物語は栄光ある一章となっているわけです。
台湾にある雲南料理の店を見ると、この店のオーナーはこの時代の孤軍と共に台湾にやってきた,雲南の人々の末裔なのだろうかと想像してしまいます。
このように、人々のつながりが今でもあることは、歴史が現在とつながっているということでしょう。
僕はこの孤軍の物語は中華民国の歴史における大切なエピソードの一つであると考えています。日本人にはあまり知られていない物語ですので、紹介してみました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
