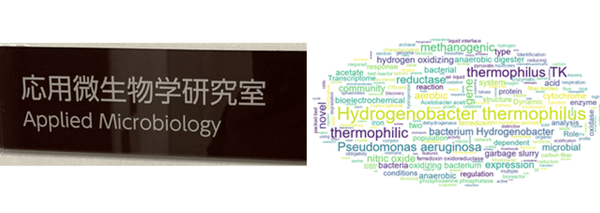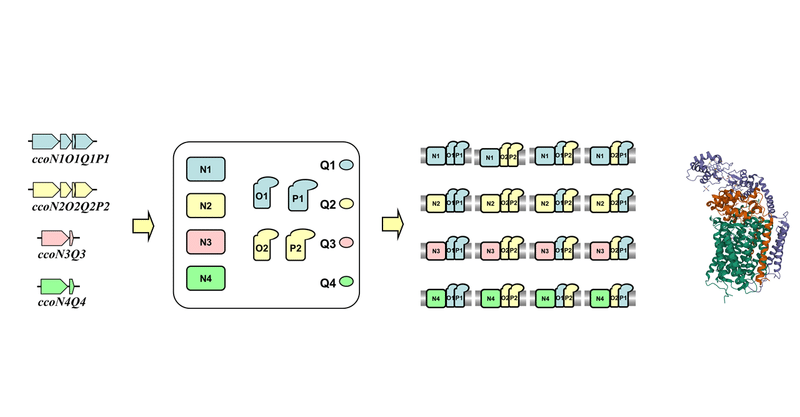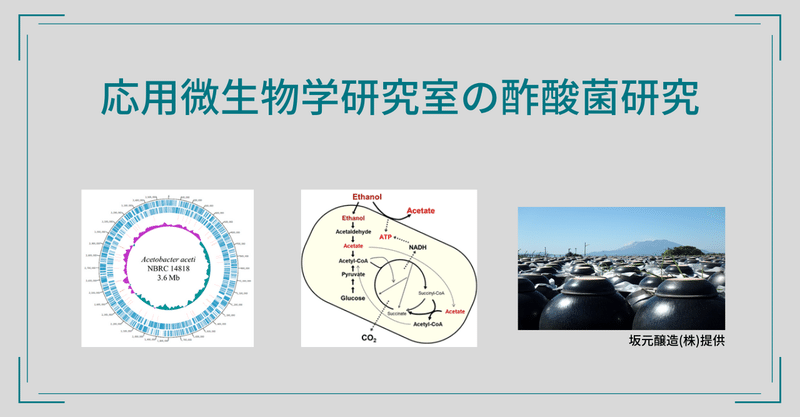最近の記事
二酸化炭素(CO2)を直接利用する微生物によるバイオものづくりの促進事業を開始 ~ 8機関が共同でNEDOグリーンイノベーション基金事業に参画 ~
採択された課題がプレスリリースされました。 二酸化炭素(CO2)を直接利用する微生物によるバイオものづくりの促進事業を開始 | バイオテクノロジー | 製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp) NITE(ナイト)[独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長:長谷川 史彦、所在地:東京都渋谷区西原]、国立大学法人 東京大学[総長:藤井 輝夫、所在地:東京都文京区本郷]、国立大学法人 京都大学[総長:湊 長博、所在地:京都府京都市左京区吉田本町]、国立大学法人 茨城大学[

水素細菌Hydrogenovibrio marinus MH-110において低CO2条件で高親和性Rubisco遺伝子の発現を制御する調節因子の同定
論文情報 Regulation of the high-specificity Rubisco genes by the third CbbR-type regulator in a hydrogen-oxidizing bacterium Hydrogenovibrio marinus. Toyoda, K., et al., J. Biosci. Bioeng., 134, 496-500 (2022). 水素細菌Hydrogenovibrio marinus MH-1