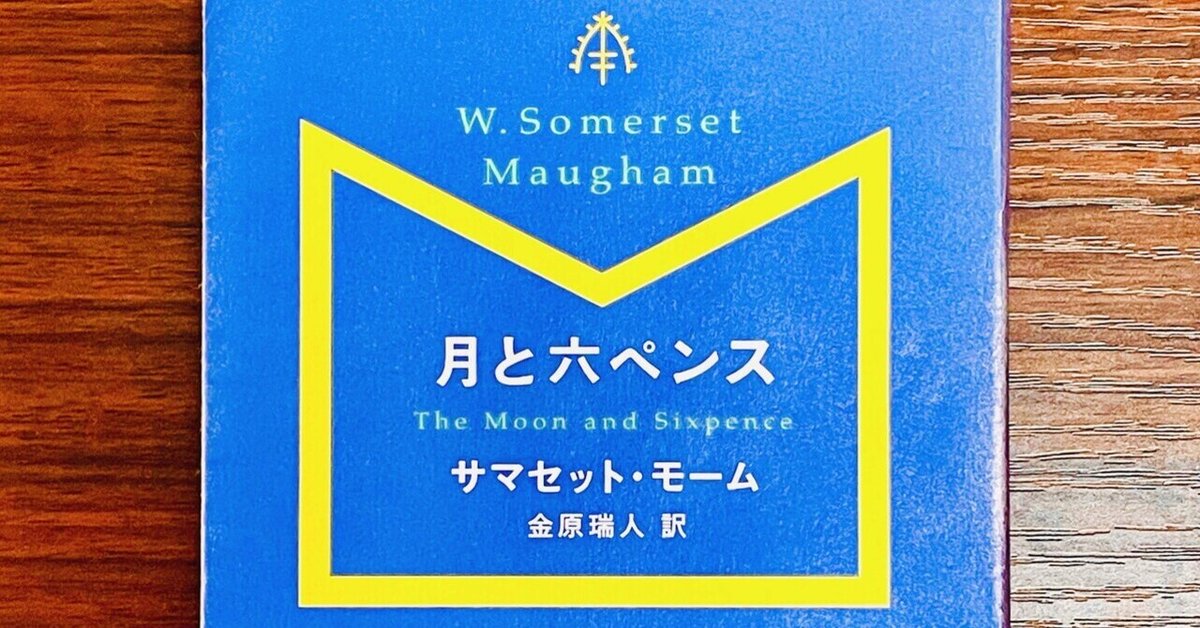
Hirotomusicと読書 第10回 「月と6ペンス」サマセット・モーム
この作品は自分の芸術に対する考え方に大きな影響を与えてくれた作品。
主人公のチャールズ・ストリックランドはある日、突然、これまで幸せに暮らしていたイギリスでの家族との生活を捨て、画家として生きるためにパリへ向かう。
彼はそこから芸術の情熱に取り憑かれ、生涯をかけて自分の表現したい芸術を追求する。
彼はそのために家族を捨て、財産を捨て、時には友人の家庭まで壊してしまう。
私はそんな彼を人としては尊敬はしない。
しかし、この作品を読むと最高の芸術のためには、自分の全てを捧げ、自分のエゴや虚栄心をかなぐり捨てなくてはならないことが分かる。
彼は最期、終の棲家となるタヒチでハンセン病にかかり、盲目にもなるが、自宅の壁に自分の追い求める芸術の集大成となる作品を描き上げる。そして、彼はタヒチで結婚した妻に遺言として、自分の死後、この絵を家と共に燃やすことを命じ、燃やさせてしまう。
彼は亡くなってから、画家として大きな評価を得るが、彼のその最高傑作を見たものは彼のタヒチの家族と彼の主治医のみである。彼はこのように全く名声を求めず、ただ自分の表現したい芸術を表現しきって死んでいった。
ここに私は芸術の真髄があるのではないかと考える。
最後にこの作品を読むと、真の芸術家は自分の芸術と引き換えに自分の幸せを放棄しなければならないのかという問いが生まれる。
私は18歳でこの作品を初めて読んだ時、そのまま幸せを捨てて、芸術を追い求めなければならないのではないかと考えた。
しかし、今は違う。私はこの作品を今、改めて読み返し、こんな風に考えた。ストリックランドになかったものは信仰ではなかったかと。
こんなことを読んでいる時にふと思った矢先に、生前、タヒチに移り住んだストリックランドと共に過ごしたフランス人のブリュノ船長がこんなセリフに出会った。
「信仰です。信仰がなければ、わたしたちは途方に暮れていたでしょう」
このブリュノ船長は法定代理人のミスでいきなり無一文になってしまったことから、全く不毛の地であった島を友人からお金を借りて買い、そこの土地を夫婦二人三脚で耕し、農園を作り上げ、再び成功を収めた人物である。このセリフは語り手の作家がこの成功はブリュノ船長と妻の揺るぎない意志と強い精神の証と彼に述べた時に、彼はそれともう一つあると言い、語り手の作家に告げた言葉である。
私は作者のモームがこのブリュノ船長を作中に登場させたのはこのセリフを言わせたかったからであると思う。
ある人が「優れた宗教のあるところ、必ず偉大な文化、芸術が生まれる」という言葉を残している。
芸術を追い求めることは、世界の真理を解き明かそうとすることなのかもしれない。
だから、芸術家の人生は厳しいものなのであろう。
しかし、その荒波の中を正しい方向に、そして勇敢に進ませてくれるものが信仰であると私は思う。
