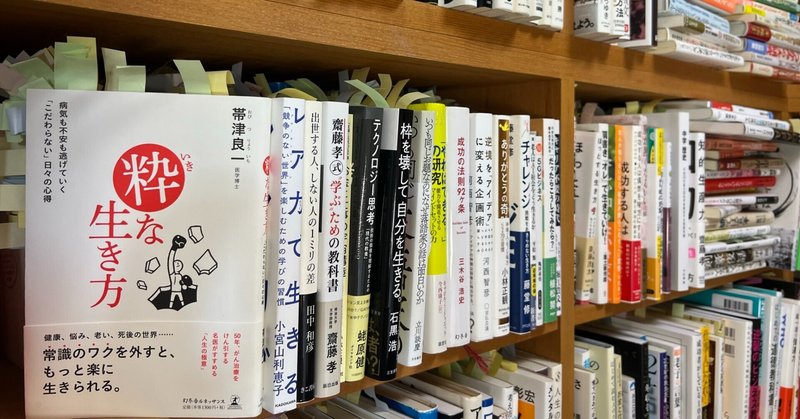
長生きするヒトはどこが違うか?
今日のおすすめの一冊は、帯津(おびつ)良一氏の『粋(いき)な生き方』(幻冬舎ルネッサンス)です。その中から「自然治癒力を高めるには」という題でブログを書きました。
本書の中に「長生きするヒトはどこが違うか?」という興味深い文章がありました。
長生きしたいですか? と聞くと、ほとんどの人がYESと答えます。でも、長生きの中には年を取ることも含まれていて、いろいろなところに不具合が出てきて不自由なことを背負うことですよと言うと、そうではなくて、人のやっかいにならずに長生きして、ぽっくりと死にたいと言います。
そんな都合のいいように物事が運ぶと思いますかと聞くと、そのために、酒もあまり飲まないようにして、たばこもやめて、毎朝、散歩をしています、と答えます。実際は、いくら節制しても病気になる人はなるし、不摂生な生き方をしていて元気に生きている人もいるわけです。
『長生きするヒトはどこが違うか?』(春秋社)という本があります。アメリカの老化を専門とする二人の生理学者が書いたものです。いろいろと長生きする方法が書かれているのですが、最後の「長生きするヒトはどこが違うか?」という結論では、「違うところ なんかない」で締められているのです。 これには笑えるというか、拍手を送りたくなりました。
昔から、たくさんの人が長寿の方法を求めてきて、いまだに見つからないのだから、そんなものはないと考えたほうがいいでしょう。 その本には、著者である二人の学者が「長生きの方法」について、どういう考えをもっているかが書かれていました。それがまた私好みで、ここでも拍手を送りたくなりました。
人間、長生きするためには節制をしなければならないと思われているが、七〇歳を過ぎたら、いつも節制しないで、週に一回は悪食をしたほうがいいと書かれているのです。七五歳になったら週に二回は悪食。だんだんと健康的ではない生活を増やしていくのがいいという、なかなか粋な考えが披露されていました。
あれを食べちゃいけないとか、これはからだに悪いとか、そんなことを考えて生きるのは窮屈です。私は、凛として老いることをおすすめしていますが、私が見る 限り、すてきに年を重ねている人は、食べたいだけ食べ、飲みたいだけ飲んでいます。
残念ながら、そういう人は少なくて、私は、せっかく七〇歳とか八○歳まで生 きたのだから、そのご褒美として少しずつ羽目を外して、もっと自由になればいいのに と思えてなりません。
先日、講演会に行ったら、昔の知り合いが聴きに来てくれました。終わったあと、 少し世間話をしたのですが、そのとき、「ところで、本当に休肝日はなくていいのかい?」と質問されました。彼とは同い年で、よく飲みました。酒の好きな男です。
私は、「休肝日なんか必要ない!」と、彼に返答しました。この年になって休肝日云々と言っているようではいけません。とても凛として老いることはできません。 いくら健康に気をつけて生きていても、交通事故や災害で死ぬかもしれません。 あまり、健康、健康と言っているのは、私には、魅力的には見えません。
志を果たすには健康はとても大切なことです。でも、志を果たせずに倒れたとしても、それはそれでいいじゃないですか。本当にいのちがけでやっていたことなら、必ず、だれかがその志を引き継いでくれるものです。あっちの世界から、自分が蒔いた種が、 どんなふうに育っていくのか見ているのも、またおつなものです。
帯津先生は、「理想を持って、死ぬまで進み続けて、志半ばで倒れるのが、かっこいい」といいます。成就するもよし、成就しなくてもまたよし、ということです。倒れるときは前のめりに倒れればいい、と。
山本常朝の「葉隠」の中にこんな一節があります。
人間の一生は誠にわずかの事なり。好いた事をして暮らすべきなり。夢の間の世の中に、好かぬ事ばかりして、苦しみて暮らすは愚かな事なり。
我々は人生の後半生になると、どうしても守りに入り、「あれをしてはダメ、これはやらない」と節制したり、自己規制も多くなります。そして、結局、新しいことへの挑戦をしなくなります。
粋に、好いたことして、長生きできたら素敵です。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
