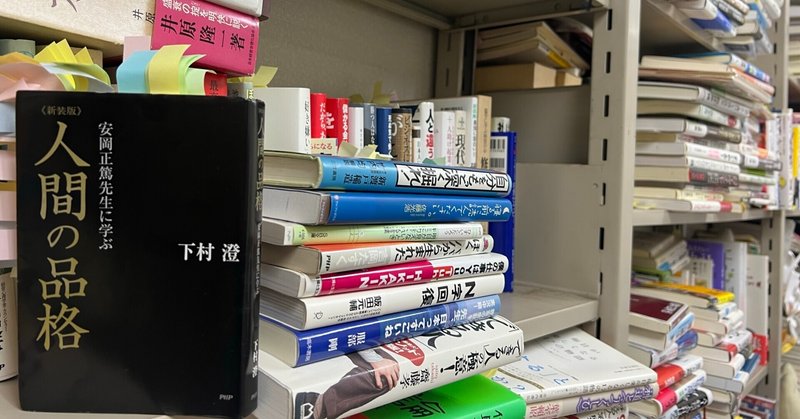
安岡正篤先生のお金に対する考え方
今日のおすすめの一冊は、下村澄氏の『人間の品格』(PHP)です。その中から「魅力は後ろ姿ににじむ」という題でブログを書きました。
本書の中に「安岡正篤先生の金に対する考え方」という心に響く一節がありました。
安岡正篤先生という人は自分の金銭については無頓着だったが、金銭について無原則だったかというと、決してそうではない。きちっとした金銭哲学をもっていて、折に触れて金に対し、とるべき態度を説かれていた。
たとえば、こんなふうである。「明治維新の人物たちはその不羈(ふき)奔放(ほんぼう)さから贅沢(ぜいたく)はしたが、金を蓄えることはしなかった。没してみればいずれも清貧だったといわれる。しかし本人自身貧乏だと思っていたわけではない。金というものは蓄えるものではなく、使うものだと思っていたにすぎない」
明治維新の人物たち…坂本竜馬にしろ高杉晋作にしろ、金があると確かに贅沢をしている。ことに高杉晋作がそうだった。ただし、彼は私腹をこやすためには一文も使っていないことを、誰もが知っていた。事実、彼は高杉家の家計を豊かにするためにはさっぱり貢献していない。そして誰もが、彼は国を救うという高い志のために東奔西走していることをよく知っていたからである。
高い志…明治維新の人物たちを何よりも豊かにしていたのは、これである。だから、自分が金銭的に貧しいとは思わなかった。というより、金銭的に豊かか貧しいかなどは意識になかったのである。
明治政府の大物となった人物たちも、さしたる蓄財はしていない。まあ、政府の高官となったのだからそれなりの収入はあり、私生活も豊かになっている。その一端をうかがわせるのは目白の椿山荘である。広大な敷地につくられた庭園は山形有朋の屋敷跡なのである。だが、内情はそれほど豊かだったわけではない。
その証拠に椿山荘は山形有朋の死後しばらくして人手に渡っている。一般庶民から見ればそれなりの財を残したとはいえ、いま開発途上国の権力者に見られるような蓄財ぶりからはほど遠い。清貧は明治維新の人物たちの特徴といえる。そして、それがまた彼らの人間的魅力の重要な部分になっている。
安岡先生の贅沢はタカが知れている。さしずめ酒を飲むことだけが贅沢で、ほかは眼中になかったといっていい。悠然と杯を口に運び、それだけで満ち足りる。そういう安岡先生は誰より豊かに見えた。高い学識と深い思想が安岡先生を何よりも豊かにしていたのである。
安岡正篤先生の金に対する考え方の基本は、金は使うためにある、というところにあった。まさにそのとおりである。金はいくら蓄えたからといって、それだけではなんの価値も持たない。使われてこそ、初めて価値を発揮するのである。
金を使うなら、その価値を充分に発揮できるような使い方をしなければいけない。金の価値を充分に発揮させる使い方とは、金を使うことによってその人の魅力が増すような使い方である。
安岡正篤先生はこう喝破されていた。「金と人というものを運命学的に見れば、金を蓄えるべき人間と、蓄えてはいけない人間とがある。政治家や事業家は後者に属する。政治家や事業家が金を蓄えるようになったら、それは彼ら自身の堕落であり、飛躍的業績などは望み得べくもない」
そういえば、バブル経済がはじけて以後、金にからんで社会的な立場を失う政治家や実業家が続出している。その中には実に人間的魅力に溢れ、失脚させるのは惜しい人物もいる。だが、金がからんでいるだけに取り返しがつかない。
どんなに実績があり、また人間的魅力に溢れていようとも、金にからんでの齟齬はそれらを一挙に台無しにしてしまう。金とはそういう力があるものなのだ。これらの金がらみの齟齬の実態を解きほぐしてみると、そもそもは金を蓄えようとしたことにきっかけがある、とわかる。
金を蓄えてはいけない、ということではないのです。私腹を肥やしてはいけない、ということです。老後や病気や不慮の災害にあったときのための正当な蓄えは誰にとっても必要だからです。
私腹を肥やすとは、公の地位や立場を利用して、自分の欲のために財産をふやす、ということです。公私混同という、公のことに自分の我欲や私情を持ち込むことこそ品性に欠けることはありません。
公平で、私的な感情や利益を交えないことを「公平無私」の態度といいますが、我々は常日頃、公平無私の気持ちで日々過ごしたいものです。
今日のブログはことらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
